 一時
一時 寒風稍々強し 旧暦2月大14日
寒風稍々強し 旧暦2月大14日
新聞報道では大阪城梅林満開だが、もう終わりに近い、大勢の人だったが16時過ぎると寒い所為か人影はまばらに











剪定作業に
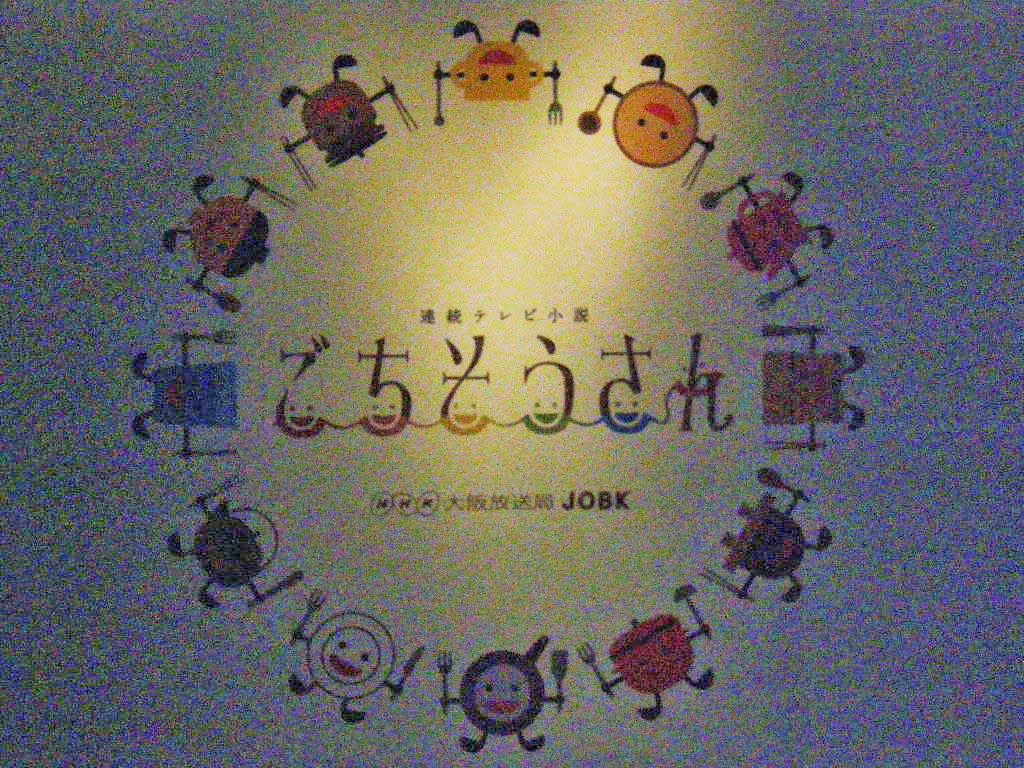
*次回 連続ドラマ〝ごちそうさん〟展示セットを紹介
 一時
一時 寒風稍々強し 旧暦2月大14日
寒風稍々強し 旧暦2月大14日
新聞報道では大阪城梅林満開だが、もう終わりに近い、大勢の人だったが16時過ぎると寒い所為か人影はまばらに











剪定作業に
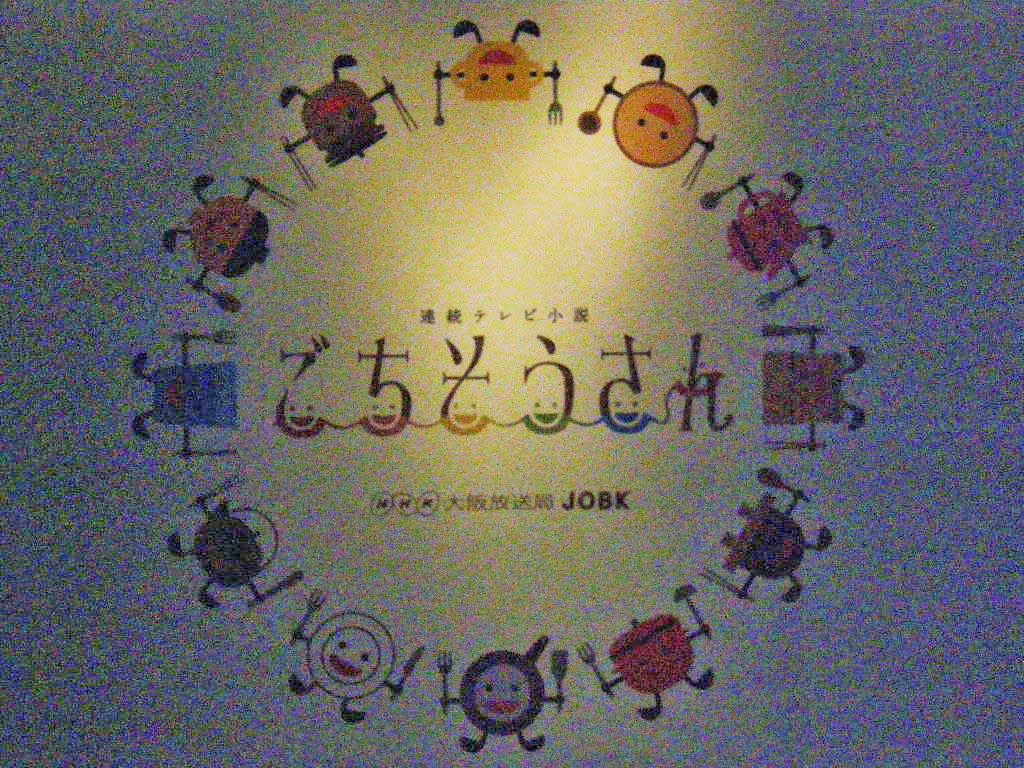
*次回 連続ドラマ〝ごちそうさん〟展示セットを紹介
 時々
時々 日中稍々暖かくなる 旧暦2月大11日 東日本大震災から3年目
日中稍々暖かくなる 旧暦2月大11日 東日本大震災から3年目
震災・津波と原発事故からの復旧・復興は遅々として進まない、それでも原発は再稼働さす政府の方針、政治屋は次の選挙のことだけ考え、日本の将来を考えていない。政治家ならば将来を考えるが不幸にも今の日本に政治家はいない。
出でよ田中正造のような井戸塀代議士よ!!! 敢えて暴言を吐く、原発事故が各地で発生、そこで初めて政治屋も気が付くかも知れない?が、時既に遅し。一蓮托生は御免蒙りたい。
↑毎年咲かす我家の水仙 打上川治水緑地の水仙ロード
打上川治水緑地の水仙ロード
毎年3月末頃から桜並木のトンネルになる

 旧暦2月大8日
旧暦2月大8日
土曜日のせいか大勢の人で見づらいほどの賑わい
川瀬巴水は明治16(1883)年、東京市芝区露月町(現在の港区新橋5丁目)の生まれ。幼い頃から絵を好み、画家を志したが本格的な修業の開始は遅く、鏑木清方への入門を果した後のこと。すでに27歳になっていた。
転機が訪れたのは大正7(1918)年。同門の伊東深水が手がけた連作≪近江八景≫を見て木版画の魅力に打たれ、版元・渡邊庄三郎と組み、塩原に取材した三部作を翌年発表。写生に基づく温雅な下絵が清新な木版画となり、好評をもって迎えられた。以後旅にでてはスケッチをし、東京に戻っては版画を作るという暮らしを、病で世を去る昭和32(1957)年まで続けた。
巴水の旅は日本全国に及び、名所旧跡も選び、多くはかつて日本のどこにでもあった風景。四季や時刻の表情を大切にし、またしばしば土地に暮らす人々を点景として織り交ぜながら、おぼろ月の、わきたつ入道雲の、そぼふる雨の、しんしん雪の降る風景を、あくことなく描き続けた。生涯に残した木版画は600点を超える。旅の印象を抒情的に描くその作風から、「昭和の広重」とも称えられた。
本展は、渡邊庄三郎の孫である渡邊章一郎氏の全面的な協力を得て開催され、その良質な渡邊版を惜しみなくご出品、巴水の生の感興を伝える写生帖や原画類をあわせて展示し、 旅先での足取りや版画制作の過程も浮き彫りにした。
大阪展の後「京都高島屋グランドホール」で 9月25日(木)~10月6日(月)開催される。


会場外に展示されていた「木版画オリジナル額装品」
↓「木版画オリジナル額装品」の数点をコラージュとしてまとめる

 のち
のち 日中温暖 旧暦2月大4日
日中温暖 旧暦2月大4日
大阪・船場・旧家の雛飾りと昔の写真展
 芝川ビル
芝川ビル
大阪市中央区にある歴史的建造物として有名。 京阪電車や地下鉄「淀屋橋駅」から徒歩約5分
1927(昭和2年)の竣工。設計は渋谷五郎(基本・構造設計)と本間乙彦(意匠設計)。施主の芝川家は江戸時代、唐物貿易の豪商として知られ、4代目当主・芝川又四郎は関東大震災から火事・地震に強い建物を建てることを決心。竜山石を用いたマヤ・インカ文明を思わせる装飾が施されている。
戦前まで、芝蘭社家政学園という花嫁学校で、現在はテナントビルになっていて数店と事務所などが入っている。
4階まであるがエレベーターは無く階段は狭く年配者や足の不自由な人は乗降に不便。
年配の女性が多かったが、次々と訪れる人の列が途絶えず賑わっていた






 屋上
屋上
夏には、ここがビヤガーデンとして利用されることもある
 一時
一時 寒さ戻る・週半ばより更に寒くなるとの予報 旧暦2月大3日
寒さ戻る・週半ばより更に寒くなるとの予報 旧暦2月大3日
あかりをつけましょ ぼんぼりに
お花をあげましょ 桃の花
五人ばやしの 笛太鼓
今日はたのしい ひな祭り  会場入口の雛飾り
会場入口の雛飾り
〝春浅く 昔を偲ぶ 顔と顔〟
昨日は昔を懐かしむ会が宝塚でありました、会場の庭景色です



 一時
一時 温暖 旧暦2月大朔
温暖 旧暦2月大朔 
 弁天池
弁天池
 こんもりした樹は槇
こんもりした樹は槇
 山桃
山桃 榧(カヤ)
榧(カヤ)

「米つき場」西の大木 樹齢数百年ものだろうセメントで補強されている