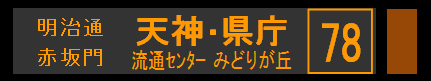(つづき)
「西鉄大橋駅」バス停における「63番」の側面表示。
「博多ふ頭←住吉←美野島南公園前←塩原橋」
という表示になっている。
住吉と博多ふ頭の間で「天神」を経由するのだが、日赤通り経由の「62番」「49番」などと比較して遠回りであることから、敢えて「天神」を表記していない(と考えられる)。
まあ、「62番」も「49番」も、「大橋駅から電車に乗る」ことに比べたら「遠回り」なのだけど…。
起点の「博多ふ頭」は維持しつつも、途中の経由地(渡辺通一丁目・那の川経由→キャナル・博多駅経由→渡辺通一丁目・住吉四丁目経由)や終点(扇町~博多駅方面→大橋駅)が時代とともに変化し、地味な路線ながら話題には事欠かない「63番」。
この勢いで(?)、竹下駅西口に乗り入れそうな予感もするのだが、どうでしょうか…。
(つづく)
「西鉄大橋駅」バス停における「63番」の側面表示。
「博多ふ頭←住吉←美野島南公園前←塩原橋」
という表示になっている。
住吉と博多ふ頭の間で「天神」を経由するのだが、日赤通り経由の「62番」「49番」などと比較して遠回りであることから、敢えて「天神」を表記していない(と考えられる)。
まあ、「62番」も「49番」も、「大橋駅から電車に乗る」ことに比べたら「遠回り」なのだけど…。
起点の「博多ふ頭」は維持しつつも、途中の経由地(渡辺通一丁目・那の川経由→キャナル・博多駅経由→渡辺通一丁目・住吉四丁目経由)や終点(扇町~博多駅方面→大橋駅)が時代とともに変化し、地味な路線ながら話題には事欠かない「63番」。
この勢いで(?)、竹下駅西口に乗り入れそうな予感もするのだが、どうでしょうか…。
(つづく)