
(つづき)
「博多ふ頭~博多ふ頭入口~対馬小路~市民会館前~天神北~天神大丸前~天神一丁目~キャナルシティ博多前~駅前三丁目~博多駅~駅前四丁目~東領団地~アサヒビール前~竹下~井尻一丁目~井尻駅入口~井尻六ツ角~精華女子短大前~寿町二丁目~JR南福岡駅~雑餉隈営業所」を走る「46番」の天神地区における側面表示。
博多駅から雑餉隈営業所に向かうルートは複数あり、かつ、「46番」が雑餉隈営業所まで行くようになったのはつい最近(今年3月23日)で、博多駅から雑餉隈へのメインルートでもないことから(雑餉隈まで延長される前は井尻六ツ角が終点)、「博多駅→雑餉隈営業所」という表示ではやや不親切に見える(前面の行先表示も、行先部分の上に大文字で博多駅、下に雑餉隈営となっている)。
“博多駅から先の利用者は常連客なので「46」という番号で判断できるだろうから、天神地区においては、博多駅までの利用者に対してわかりやすい表示にすることを主眼に置こう”という考えもわからないではないのだが、せめて「竹下」と、できれば「井尻」はどうにかして入れてほしい気はする。
なお「46番」の郊外部は、「井尻六ツ角」までの運行となるさらに前は、「~放送所前~昇町~上白水~現人橋~道善~那珂川営業所」まで運行されており(一時期は「天神山行き」もあり)、そしてさらにその前は、もっと郊外の「大山」まで運行されていたそうだ。
都心部についても、「博多ふ頭」が始発となる前は「天神」や「那の津四丁目」を基点としていた(なお、当初は国体道路経由ではなく昭和通り経由で、天神郵便局前から出ていたようだ)。
郊外部と都心部での変化はあるものの、「駅前四丁目~竹下~井尻」間については、私がバスに興味を持ってから既に30年以上が経つが、その間ずっと固定されており、この区間に「46番」以外のバスが通ったこともないと思われ、都市部にありながら、距離的にも期間的にも、路線がずっと固定されている。
このことを以前書いた際、ひろしさんから「担当営業所はちょこちょこ変わりましたけどね。」というコメントをいただいた。
たしかに、現在は「雑餉隈営業所」が担当しているが(←私が担当営業所とか車両のことについてほとんど興味がないため、違っていたらごめんなさい)、福岡の「1番」や大野城の「12番」などとともにKassyさんから提供していただいた平成9年の「46番」の時刻表では担当は「高速営業所」となっているし、「那珂川営業所」が担当していたこともあったと思う。
「46番」が長年あまり変わらないのは、「46番」には「営業所への帰属意識」というものがあまり強くなく、各営業所とも、「46番」という路線を「持っている」というよりは「預かっている」くらいの心もちなので、あまり大きく変えることには気持ちが向かわないのかもしれない。
そう考えると、井尻六ツ角から雑餉隈営業所までの延長というのは、かなり画期的なことといえるのかもしれない。
今後さらに、以前提案したルート変更や竹下駅への「46番」以外の路線の乗り入れなどが行われることはあるだろうか…。
(つづく)
「博多ふ頭~博多ふ頭入口~対馬小路~市民会館前~天神北~天神大丸前~天神一丁目~キャナルシティ博多前~駅前三丁目~博多駅~駅前四丁目~東領団地~アサヒビール前~竹下~井尻一丁目~井尻駅入口~井尻六ツ角~精華女子短大前~寿町二丁目~JR南福岡駅~雑餉隈営業所」を走る「46番」の天神地区における側面表示。
博多駅から雑餉隈営業所に向かうルートは複数あり、かつ、「46番」が雑餉隈営業所まで行くようになったのはつい最近(今年3月23日)で、博多駅から雑餉隈へのメインルートでもないことから(雑餉隈まで延長される前は井尻六ツ角が終点)、「博多駅→雑餉隈営業所」という表示ではやや不親切に見える(前面の行先表示も、行先部分の上に大文字で博多駅、下に雑餉隈営となっている)。
“博多駅から先の利用者は常連客なので「46」という番号で判断できるだろうから、天神地区においては、博多駅までの利用者に対してわかりやすい表示にすることを主眼に置こう”という考えもわからないではないのだが、せめて「竹下」と、できれば「井尻」はどうにかして入れてほしい気はする。
なお「46番」の郊外部は、「井尻六ツ角」までの運行となるさらに前は、「~放送所前~昇町~上白水~現人橋~道善~那珂川営業所」まで運行されており(一時期は「天神山行き」もあり)、そしてさらにその前は、もっと郊外の「大山」まで運行されていたそうだ。
都心部についても、「博多ふ頭」が始発となる前は「天神」や「那の津四丁目」を基点としていた(なお、当初は国体道路経由ではなく昭和通り経由で、天神郵便局前から出ていたようだ)。
郊外部と都心部での変化はあるものの、「駅前四丁目~竹下~井尻」間については、私がバスに興味を持ってから既に30年以上が経つが、その間ずっと固定されており、この区間に「46番」以外のバスが通ったこともないと思われ、都市部にありながら、距離的にも期間的にも、路線がずっと固定されている。
このことを以前書いた際、ひろしさんから「担当営業所はちょこちょこ変わりましたけどね。」というコメントをいただいた。
たしかに、現在は「雑餉隈営業所」が担当しているが(←私が担当営業所とか車両のことについてほとんど興味がないため、違っていたらごめんなさい)、福岡の「1番」や大野城の「12番」などとともにKassyさんから提供していただいた平成9年の「46番」の時刻表では担当は「高速営業所」となっているし、「那珂川営業所」が担当していたこともあったと思う。
「46番」が長年あまり変わらないのは、「46番」には「営業所への帰属意識」というものがあまり強くなく、各営業所とも、「46番」という路線を「持っている」というよりは「預かっている」くらいの心もちなので、あまり大きく変えることには気持ちが向かわないのかもしれない。
そう考えると、井尻六ツ角から雑餉隈営業所までの延長というのは、かなり画期的なことといえるのかもしれない。
今後さらに、以前提案したルート変更や竹下駅への「46番」以外の路線の乗り入れなどが行われることはあるだろうか…。
(つづく)














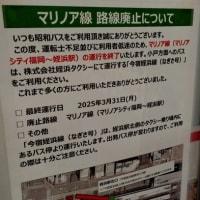





もうこれは、4つの枠ではどうにもならない状況ですね。
フィルム幕式であった場合でも、雑餉隈まで行く分に関しては、65番のように6行は必要ですし…。
強引に4つの枠に収め、しかも上記のような事態を解決させるなら…
3つ目を「博多駅・竹下」、4つ目を「井尻・雑餉隈」とでもするしかないかも…?
44・45・46番とも、ルートは違うにしても、結局は駅南地区は何らかの形で通る訳で、特に「竹下」は絶対はずしてはならないでしょう。
>博多駅から先の利用者は常連客なので
これを「大前提」としてもらっては、非常連の人にとっては大変困りものであり、このような考え方は厳に控えるべきですよね。
>担当営業所はちょこちょこ変わりました
確かにこう書かせてただきました。
しかし、担当営業所が頻繁に変わるというのは、かなり珍しい話なんですよね。
そういうことを考えると、46番は雑餉隈営業所まで延伸した(といっても、その「延伸区間」は通常回送ルートとして用いられているんですがね)のを機に、そろそろ雑餉隈担当で落ち着いてもらいたいです。
文中でのご紹介、ありがとうございますm(_ _)m
郊外方面に別媒体の公共交通がない場合を除き、都心部天神から郊外へ向けて走る路線の中で、郊外エリアで駅などに接続しない[46]系統は少し珍しい感じもします。南エリアでは大橋駅・井尻駅・南福岡駅と豊富にあるにもかかわらず、この系統(の雑餉隈延伸前)はかすりもしませんでした(かすっても井尻駅入口だけ?)。あんなに鉄道線にまとわりつくように走っているのに(笑)。
そんな片足立ちの状態が続いていましたが、雑餉隈延伸によって南福岡に着地したという印象では、ようやく両足でしっかりと立てるようになったかと親心の気分でいなくもないです(^ ^)
LEDですが、現状4枠しかないので、以前soramameさんが文章にされておられるように「系統番号や案内放送から経由地やルートは判断してちょ」と言っているように思えますね。幕時代にも経由地表記がすべて、主要地点を示す赤(マゼンタ)だったということもあり、妥協してこうなったというよりは、「何とかしてくれぇ」という製作側の悲鳴が聞こえてきそうです。
>44・45・46番とも、ルートは違うにしても、結局は駅南地区は何らかの形で通る訳で、特に「竹下」は絶対はずしてはならないでしょう。
たしかに。
どういう表示にしろ(上部に「46 キャナルシティ経由」と入れるとか?)、やはり「竹下」は要りますよね。
>>博多駅から先の利用者は常連客なので
>これを「大前提」としてもらっては、非常連の人にとっては大変困りものであり、このような考え方は厳に控えるべきですよね。
私も同感です。
例えば25番や54-1番とか、9番の能古渡船場行きのように、他に速く行ける選択肢があり、始発から終点までを乗り通すことが合理的でない場合には詳しく入れる必要はないと思いますが、天神から竹下方面に行くバスは46番しかない訳ですからね。
Kassyさん、こんにちは。
>そんな片足立ちの状態が続いていましたが、雑餉隈延伸によって南福岡に着地したという印象では、ようやく両足でしっかりと立てるようになったかと親心の気分でいなくもないです(^ ^)
たしかに。
一方で、JR竹下駅を通る唯一の路線という面もあり、親心としては複雑です(ただ、駅前にあっても停留所名は単に「竹下」ですが)。
南福岡に着地したとはいいつつ、着地するのは平日のみであり、このへんも親心としては、またまた複雑だったりします(笑)。
昭和50年代に東京に接し、東京でバスが駅と駅とを結ぶように路線を延ばし、鉄道のあくまでわき役として走っているのを見て、福岡もそうなればよいのに、と思ったものですが、本当にそのようになってくると、以前のほうがよかったのに、とも思うものです。
あの頃、バスは駅のそばを走ってはいても、「~駅」または「~駅前」という停留所名はつけていなかったものです。
かすかな記憶をたどっても、思い出す「~駅」バス停は、「博多駅」のほかは、「南福岡駅前」、「井尻駅」(45番)、「春日原駅」、できたばかりの「下大利駅」、「筑紫駅」、「小笹駅前」以遠の筑肥線の駅、「吉塚駅前」、「箱崎駅前」、「土井駅」、「貝塚駅」、くらいかな。
「竹下」のように、駅のすぐそばにバス停があっても、「~駅」と名乗らない「平尾」、「朝倉街道」、また、「西鉄二日市」、「国鉄二日市」のようにどうみても駅を示しているとしか思えない停留所名でも「駅」とつけない例などあり、バスが鉄道従属ではない、というたしかなアイデンティティを示していました。(停留所名は今でも同じですが。また、西鉄多々良、国鉄多々良と対比させるとおもしろいかも)
その特徴も近年になって崩れ、急速に「東京化」してきているように思えます。理由の一つには、国鉄がJRになって利便性がアップし、乗り換え客のことを考えざるを得ない状況になったこともあると思います。
他の多くの地方都市は、ほとんどが、「バスに乗って都心まで」というパターンで、鉄道との乗り換えを考えた路線にはなっていませんね。
>郊外で鉄道駅と接続しないのは、福岡のバス路線の特徴で、長い目でみた場合、むしろ近年になって鉄道駅との接続を意識しだしたように思います。でも基本は、電車は電車、汽車は汽車、そしてバスはバス、として独立に都心へ向かうという動きだと思います。
たしかに。
東京と福岡では、鉄道の線路の「密度」も、都心と住宅地との距離も、大きく違いますからね。
東京のように「密度」が濃ければ、駅と駅を結ぶことのメリットは大きいと思うのですが、福岡で、例えば姪浜駅と橋本駅を結ぶバスをたくさん走らせたとしても、実際はあまり利用されないのかもしれません。
>「竹下」のように、駅のすぐそばにバス停があっても、「~駅」と名乗らない「平尾」、「朝倉街道」、また、「西鉄二日市」、「国鉄二日市」のようにどうみても駅を示しているとしか思えない停留所名でも「駅」とつけない例などあり、バスが鉄道従属ではない、というたしかなアイデンティティを示していました。(停留所名は今でも同じですが。また、西鉄多々良、国鉄多々良と対比させるとおもしろいかも)
「竹下」は、もともと駅とは道一本隔てていたので「駅」という印象があまりなかったのも要因かもしれませんね。
46番のように線路に概ね並行して走るのではなく、垂直方向に走る路線(西は塩原や大橋、東は東那珂や板付など)がもしあれば「駅」としての「竹下」がもっと際立つのでしょうが、実際は、西の那珂川と東の福岡空港の存在で、垂直方向の広がりがあまり期待できないのかもしれません。
「西鉄多々良」は健在で、「国鉄多々良」は今は単に「多々良」になっています。
「西鉄」が付くバス停はたくさんありますが、駅でも営業所でもターミナルでも西鉄関連施設(ストア、自動車学校、工場…)でもないのに「西鉄」を冠している「西鉄多々良」は、かなり存在感があります。
>その特徴も近年になって崩れ、急速に「東京化」してきているように思えます。理由の一つには、国鉄がJRになって利便性がアップし、乗り換え客のことを考えざるを得ない状況になったこともあると思います。
>他の多くの地方都市は、ほとんどが、「バスに乗って都心まで」というパターンで、鉄道との乗り換えを考えた路線にはなっていませんね。
郊外の駅と住宅地を結ぶ路線が単独で成り立つためには、“ベッドタウン”“衛星都市”を擁するような一定規模以上の都市でないと難しいということでしょうか。