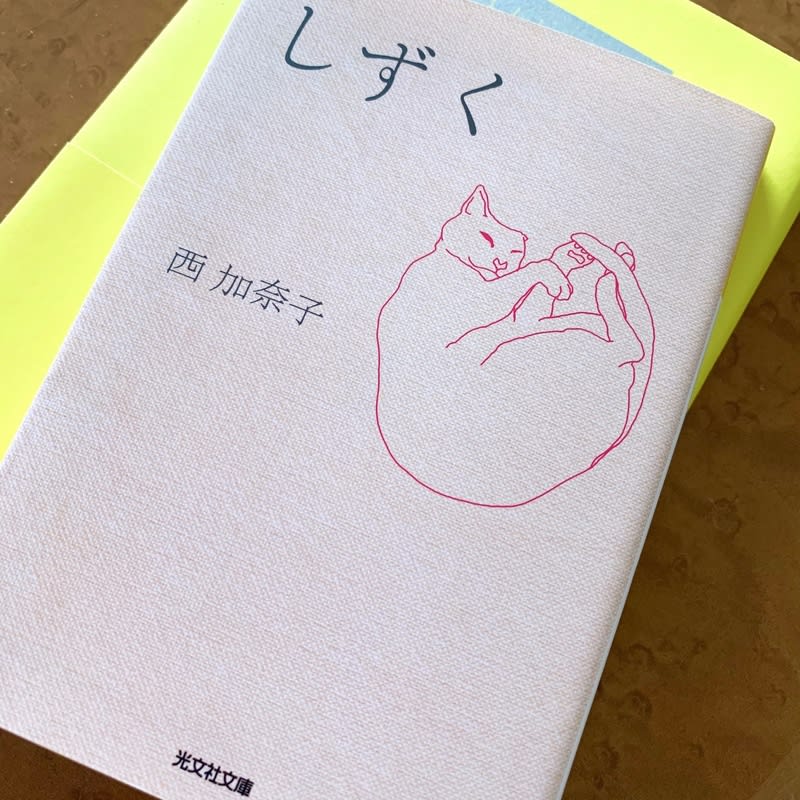11月のある日、昼休みを長めにもらって久保田万太郎の短編を伊丹の蕎麦屋で聴いた。
三島の金閣寺と同時に読売文学賞を受賞した『三の酉』
30分くらいの短編の朗読やリーディングは疲れなくてよく味わえてとてもいいな。

最初に美味しいお蕎麦としらす丼のセットをいただきます。
日本酒が飲みたくなるけど、午後にまた仕事に戻るので我慢。
それから二階に移動して照明を落とした部屋で
男女一人ずつのリーディング形式の舞台を楽しみました。
男の方は、蕎麦屋へ向かう道でお見かけして印象的なダンディな殿方だなと思って
記憶に残ってたその人で、ああやっぱり役者さんって雰囲気があるよねぇと思った。
女性は華奢できれいな着物の方で、とても涼やかな声をされてる。
複数でのリーディング形式の舞台を初めて聴いたけど、すごく良くて気に入りました。
お話は毎年11月の酉の日に開催される酉の市を楽しみにしている芸者と
そのなじみ客との会話で進みます。
酉の市は12日ごとにあるので三の酉まである年もあり、
これはそれについての会話劇で、ラストのオチは想像できたけど
暖かいような物悲しいようなお話でした。
作者の久保田万太郎が、三島由紀夫の金閣寺と同時受賞で読売文学賞を取った作品ですが
読売文学賞の小説部門は、室生犀星、佐藤春夫、井伏鱒二、大岡昇平などがいますね。
「金閣寺」に比べると、いつか古典になっていくようなタイプの作品ではなく
自分の生まれ育った浅草を舞台にした小説ばかりの、今は読まれなくなった作家のようです。
作家自身の人生も、あまり幸せじゃなかったみたいだけど
女性に関しては結構ひどい男だったっぽくてちょっと自業自得に感じます。笑
彼の句をふたつ置いておきます。
わが胸にすむ人ひとり冬の梅
湯豆腐やいのちのはてのうすあかり
三島の金閣寺と同時に読売文学賞を受賞した『三の酉』
30分くらいの短編の朗読やリーディングは疲れなくてよく味わえてとてもいいな。

最初に美味しいお蕎麦としらす丼のセットをいただきます。
日本酒が飲みたくなるけど、午後にまた仕事に戻るので我慢。
それから二階に移動して照明を落とした部屋で
男女一人ずつのリーディング形式の舞台を楽しみました。
男の方は、蕎麦屋へ向かう道でお見かけして印象的なダンディな殿方だなと思って
記憶に残ってたその人で、ああやっぱり役者さんって雰囲気があるよねぇと思った。
女性は華奢できれいな着物の方で、とても涼やかな声をされてる。
複数でのリーディング形式の舞台を初めて聴いたけど、すごく良くて気に入りました。
お話は毎年11月の酉の日に開催される酉の市を楽しみにしている芸者と
そのなじみ客との会話で進みます。
酉の市は12日ごとにあるので三の酉まである年もあり、
これはそれについての会話劇で、ラストのオチは想像できたけど
暖かいような物悲しいようなお話でした。
作者の久保田万太郎が、三島由紀夫の金閣寺と同時受賞で読売文学賞を取った作品ですが
読売文学賞の小説部門は、室生犀星、佐藤春夫、井伏鱒二、大岡昇平などがいますね。
「金閣寺」に比べると、いつか古典になっていくようなタイプの作品ではなく
自分の生まれ育った浅草を舞台にした小説ばかりの、今は読まれなくなった作家のようです。
作家自身の人生も、あまり幸せじゃなかったみたいだけど
女性に関しては結構ひどい男だったっぽくてちょっと自業自得に感じます。笑
彼の句をふたつ置いておきます。
わが胸にすむ人ひとり冬の梅
湯豆腐やいのちのはてのうすあかり