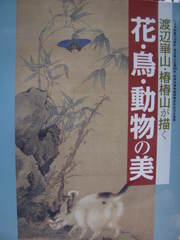谷文晁が、自分が見た作品や風景、器物をスケッチし、縮図冊として保管し、後に作画の参考としているように、崋山も多くの縮図冊を作成し、それを保管し、作画の参考にしています。崋山の縮図冊としては、「客坐録」や「客坐掌記」などが知られていますが、それに目を通してみると、崋山がさまざまな作品を模写し、また日常生活や旅先等で興味・関心を抱いたものを、丹念に記録しスケッチしていることがわかります。その興味・関心の範囲は実に幅広い。たとえば「客坐録」の「天保二年八月全楽堂」を紐解いてみると、花鳥や人物のスケッチ以外に、農民の農作業風景が描かれており、崋山はそれぞれの農機具なども克明にスケッチしています。これなどを見ると、崋山は農民たちの農作業風景よりも、むしろ彼らが使っている農機具そのものに興味関心を持ってスケッチしていると思われるほどです。「運派塚 三尻村」というスケッチがあることを考えると、これらの農作業風景や農機具等のスケッチ類は、崋山が藩祖の旧領調査のために訪れた、武州中山道熊谷宿近くの三ヶ尻村あるいはその近辺で描かれたものではないかと推測することができます。 . . . 本文を読む
サントリー美術館で開催された『生誕250周年 谷文晁』展を観て感じたことは、文晃の画業が一つの枠にはまらぬ多彩さを持っていることでした。「序章」に「様式のカオス」とありましたが、「南画」とひとくくりできぬ、多彩さと多能さにあふれた画家であると思われました。たとえば、「ファン・ロイエン筆花鳥図模写」、「仏涅槃図」、「文晁夫妻影像」、「海鶴蟠桃図」、「公余探勝図巻」、「熊野舟行図巻」、「石山寺縁起絵巻」、「木村蒹葭堂像」など。それらを支えていたのは日頃の丹念なスケッチであり、それをまとめたスケッチ帖であったことは、「画学斎過眼図藁」(ががくさいかがんずこう)や「画学斎図藁」であり、「縮図帖」等の展示物で知ることができました。この文晁の真摯な作画姿勢は、崋山や椿椿山(つばきちんざん)にも受け継がれていきます。崋山は多くの縮図冊を残しており、鈴木利昌さんによると、よく知られているものだけでも約10冊ほどが知られているという。また、晩年、田原池ノ原の屋敷には、自分の背丈と同じくらい高く積み上げることができるほどの縮図冊を保存していたという話も伝えられているとのこと。椿山についても、「過眼掌記」や「琢華堂画録」「水墨花卉画冊」などの縮図冊が残されており、日頃、目にした花鳥や風景、絵画作品などを丹念にスケッチしていたことがわかります。観察(写実)を徹底すること、また画技を高めることに余念がなかったということです。 . . . 本文を読む
田原市博物館副館長の鈴木利昌さんの「崋山・椿山の写実表現」によれば、日本では、「花鳥画」という呼び方は、「動物画を含み」、花と鳥に限定せず、花卉(かき)、草木、虫、魚などありとあらゆる生物を対象として、組み合わせられるものであり、また爬虫類(はちゅうるい)や両生類なども、「ありとあらゆる生物」の中に含まれているという。細密描法を主とし、写実的表現の花鳥画は、享保16年(1731年)に長崎へやってきた沈南蘋(しんなんぴん・生没年未詳)によってもたらされて一大ブームを巻き起こし、鶴亭(1722~1785)や宋紫石(1715~1786)によって関西と江戸にもたらされ、全国的に広がりを見せていった、とのこと。8代将軍吉宗の治世のもと、西洋の大量の情報がもたらされると、身分に関わらず人々はこぞって動植物の生態の観察や、飼育・栽培に熱中。そのような博物学の流行を背景に画家たちもあらゆる動植物へ眼を向けていくことになった、という。東洋的な「沈南蘋流花鳥画体」の影響を受けた画家たちの中から、徹底的な観察を行うことによって対象をあるがままに捉えようとする(迫真性の追求)画家たちが登場してくる。鈴木さんは、その一派が「谷文晁からはじまる一派である」と指摘する。崋山が、谷文晃(あるいはその画塾「写山楼」の世界)のもとで画家として育ったことはまず間違いない。そこで薫陶を受け、培われた崋山の基本的な作画姿勢は、肖像画にも、風景画にも、そして花鳥画にも、生涯にわたって一貫されたものであると私は考えています。 . . . 本文を読む
渡辺崋山が生まれたのは寛政5年(1793年)で、三河国田原藩士の子として江戸に生まれています。椿椿山(つばきちんざん)が生まれたのは享和元年(1801年)で、やはり江戸に生まれ、父と同じく幕府槍組同心を勤めています。二人とも江戸生まれの江戸育ち、すなわち「江戸っ子」ということになる。この椿椿山は長沼流兵学を修め、俳諧や笙(しょう)にも長じ、煎茶(せんちゃ)への造詣も深かったという。画は、はじめ金子金陵に学び、金陵没後は同門の渡辺崋山に入門。また谷文晁にも学んでいます。崋山よりも8歳年下。温和で忠義に篤く、崋山に深く信頼されたという。門人には、渡辺小華(しょうか・1836~1887)や野口幽谷(1827~1898)などがいるが、この渡辺小華という人は崋山の二男。小華は弘化4年(1847年)、13歳の時に田原から江戸に出て椿椿山の画塾である琢華堂に入門し、椿山の指導によって花鳥画の技法を習得したという。この崋山・椿山をはじめとし、その影響を受けた画家たちの系譜を「崋椿系」といい、椿山以降、その代表的な作風は「花鳥画」とされているという。 . . . 本文を読む
愛知県の田原市博物館では、「田原市制施行10周年・渡辺崋山生誕220年・田原市博物館開館20年」を記念して、9月14日~10月14日の期間、「渡辺崋山・椿椿山が描く 花・鳥・動物の美」というテーマで企画展が開催されました。そのポスターを夏休みにある図書館で見掛け、これは行ってみなければ、と思っていました。せっかく田原市まで行くならば、日帰りはもったいないので、田原市中央図書館をはじめとして周辺の施設にも立ち寄ってみたいと思い、いつもはたいてい日帰りですが、この取材旅行はビジネスホテルに泊まり(まだ残暑が厳しいので)、余裕のある1泊2日の行程をとることにしました。以下、その報告です。 . . . 本文を読む
「道」には、進むべき道(方向性)というものもある。「これからの日本や世界の進むべき道」といった使い方。私は、今回の取材旅行で、茨城県北部から青森県種差海岸までの東北地方太平洋岸の被災地(といってもその海岸線から見ればごく一部に過ぎませんが)の取材旅行をひとまず終えましたが、その地域それぞれの被災の状況は、その土地の形状、震源地からの方角、海流の向きなど、さまざまな要因によってまちまちであるということをまず知りました。たとえば仙台平野の海岸部である荒浜地区(若林区荒浜)と、三陸リアス式海岸の田老地区(宮古市田老)を比較しても、それは明らかでした。高い津波が押し寄せても、すぐに逃げることができる山が近くにあるかないかでも、犠牲者の数には大きな違いがあることを知りました。また津波で亡くなった人たちの多くが高齢者であることは、どの地域においても共通することでした(これはつい先日の伊豆大島元町における土石流被害においても同様でした)。地震や津波が発生した時間帯(午後2時46分からそれ以後の数時間)によることもありますが、「少子高齢化地域」を巨大津波は直撃したのです。あれから2年5ヶ月を経過して、復旧なり復興なりがまがりなりに進んでいるその度合いとしては、私が見た限りでは、岩手県が比較的速く(道路や鉄道、集団移転先の造営など)、その次が宮城県で、福島県が最も遅れていると思われました。福島県沿岸部はやはり東京電力福島第1原発事故の放射能汚染が、瓦礫処理一つをとってみても復興の足を大きく引っ張っています。福島第1原発の事故は、当初から東日本大地震による災害対策の大きな障害(いや、東日本大震災における最も深刻な災害事故であった)となっているものであり、もちろん、私もその放射能汚染警戒地域には立ち入ることはできませんでした。押し寄せてくる津波の高さや形状が、場所によって千差万別であるように、被災地の復興のあり方も千差万別であると思われますが、全体の方向性としては共通したものがあるべきです。それはやはり将来的な脱原発の方向性であり、少子高齢化社会であっても持続可能な地域社会の構築です。これからの東北地方の復興のあり方は、今後の日本や世界のあり方(あるべき道=方向性)をまるごと問うものである、と私には思われました。 . . . 本文を読む
古来、道を描いた画家は多い。風景画の中には多く道がある。広重の『東海道五十三次』がまさにそうだし、五雲亭貞秀や川瀬巴水の浮世絵にも多く道が描かれる。渡辺崋山の風景画にも多く道が描かれますが、特に道が描かれたものとして印象的なのは、『四州真景図』の「二巻」中の「釜原」という作品。この画中の二人の人物(親子)が歩く道は「木下(きおろし)街道」であり、馬が草を食む周囲の草原は、現在の千葉県鎌ヶ谷市近辺の野原であり、当時、関東郡代の管轄下にあった「中野牧(なかのまき)」(牧=放牧場)。崋山は市川から鎌ヶ谷へと向かう途中で、この絵(下地であるスケッチ)を描いています。この絵ののびやかさは、種差海岸の風景に通じるものがある。さらに東山魁夷が『道』という作品を描いたこの種差海岸一帯の芝原は、かつては馬の放牧場であったところであり、昭和30年代頃までの写真を見てみると、この芝原に馬がいて、観光客が馬と戯れている姿が写されています。東山魁夷が種差海岸をスケッチした絵(『道』のもととなる絵)にも、放牧場の中を走る道と、その周辺の牧草地で草を食む馬や、道の先にある葦毛崎の灯台などが描かれていたのが、後に馬や柵や灯台などが捨象されて、あの『道』という作品が生まれたのです。東山魁夷が住んでいた住まいのほんそばを走っていた木下(きおろし)街道は、そのような広々とした馬の放牧場の中を突っ切っていた道であり、東山魁夷は、その木下街道の風景を、バスの窓からか、あるいは歩きながら、見たことがあるのではないかと私は推測しています。古来、「道」は人の行き交う道であり、物資が流通する道であり、そして文化文物が伝播する道でもある。そして「道」は、人生の道でもある。東山魁夷の『道』は、それらすべてを含んだ道を、具体物を捨象して、抽象化した道であるように思われます。夏の早朝の道ということもあってか、それは希望や明るさへと通ずるような新鮮さと力強さを見せています。 . . . 本文を読む
千葉県市川市に市川市立東山魁夷記念館があり、私は2011年の2月にそこに立ち寄っています。洋風のペンションのような建物で、八角形の塔を伴っていました。そこを目指して訪れたわけではなく、東京の小名木川から、行徳を経て、利根川の木下河岸(きおろしがし)跡まで陸路を歩いた時(もちろん一度ではなく何度かに分けて)、成田街道から左折して木下街道(県道市川印西線)に入り、坂道をのぼってしばらくしていきなり現れたのがそのペンション風の建物であったのです。「ここに、東山魁夷の記念館があったのか」と、当初は意外に思いましたが、受付の方から、「ここは東山魁夷先生のお住まいがあったところの近くなんですよ」と言われて、合点がいったことを思い出します。つまり東山魁夷のお住まいは、木下(きおろし)街道に沿ったところにあり、東山魁夷にとって木下街道はきわめて身近な生活の「道」であったということになります。かつてこの木下街道は、利根川の木下河岸から陸揚げされた物資が江戸へと運ばれた道であり、また江戸の物資が木下河岸へと運ばれた道であり、その木下河岸は利根川河口の銚子を経て、海上交通により東北地方と繋がっていたことはすでに見てきたところです。東関東地方や東北地方の物資が馬の背で行徳まで運ばれていったのです(行徳からは新川や小名木川、日本橋川を経て江戸日本橋まで運ばれる)。ちなみに渡辺崋山は、日本橋から日本橋川や小名木川などを経て行徳まで行き、成田街道→木下街道を経て、利根川の水上交通を利用して銚子まで赴いています(「四州真景」の旅」)。木下(きおろし)街道のそばに住んでいた東山魁夷は、もちろんそのような重要性を持った木下街道の歴史についてはなにがしかの知識を持っていたと思われるし、また東山魁夷にとってその木下街道はきわめて身近な生活の道であったから、私はあの「道」という作品を観た時、それは木下街道のどこかを描いたものかと思ったほどです。しかし、実はそうではなくて、それは青森県の太平洋に面する種差海岸近くのある道をもとに描いたものであることを知りました。しかし私には、あの「道」には、東山魁夷にとってきわめて身近であった木下(きおろし)街道に対する思いも、なにがしか含まれているのではないかと思われるのです。 . . . 本文を読む
板谷英紀さんの『賢治と岩手を歩く』(岩手日報社)によれば、宮沢賢治が田野畑村の羅賀から宮古行きの発動機船に乗ったのは、大正14年(1925年)の1月上旬のことであったらしい。鵜の巣断崖や浄土ヶ浜などのある三陸海岸を右手に見て宮古港に入り、夜零時発の釜石行きの三陸汽船に乗船。翌日昼前に釜石に入港しました。叔父岩田磯吉を天神町に訪ねるためでした。叔父の家に入る前に、賢治は釜石の映画館に立ち寄り、映画(活動写真)を観たらしい。賢治はどういう映画を観たのだろう。用事を終えた賢治は、仙人峠を越えて花巻へと戻っています。賢治は、それよりもずっと前の大正6年(1917年)の夏にも、釜石から、大槌・山田を経て宮古へと三陸海岸を旅行しています。これは東海岸視察団の一行(36名)に加わって出掛けたもの。花巻の鳥谷ヶ崎駅から岩手軽便鉄道に乗り、徒歩で仙人峠を越え、大橋からふたたび軽便鉄道に乗って釜石に到着しています。釜石では捕鯨会社や溶鉱炉などを見学し、宮古では岡田製糸工場・昆布工場・公会堂・測候所などを見学しています。さらに水産学校の岩手丸に乗って浄土ヶ浜に遊んでいます。おそらく釜石から宮古への移動は三陸汽船による船の利用であったと思われます。それから8年後、賢治は宮古から釜石へと向かい、釜石から仙人峠を越えて花巻へと戻っているのですが、それは全部徒歩ではなくて、大正6年の時と同様に軽便鉄道を利用するものであったのでしょう。 . . . 本文を読む
高山文彦さんの「『三陸海岸大津波』を歩く」によると、吉村昭さんが田野畑村島越(しまのこし)を最初に訪れた頃は、旅館も民宿もなく、吉村さんが泊めてもらったのは島越の漁師の番屋であったという。島越の隣に羅賀という集落がありますが、そこで吉村さんが定宿としていたのは「本家旅館」。この旅館は高台にあり、また石垣で土台を守っていたために、石垣まで津波は襲ってきたものの、建物は無事であったとのこと。しかし、そこから下の家々は全滅していたという。吉村さんが三陸海岸大津波について講演したところは、羅賀の海岸にある、第三セクターが運営する「ホテル羅賀荘」で、鉄筋コンクリート10階建ての白い建物。500人を収容することができる施設でしたが、海岸べりの防潮堤を目の前にして、高い崖を背にして建っていることから、ホテルの4階部分まで津波に襲われたという。このホテルの社長であったのが早野仙平氏であり、この早野氏は昭和40年(1965年)の初当選以来8期にわたって田野畑村の村長をつとめた人。吉村さんを標高50メートルはある中村丹蔵さん(明治38年の大津波を体験した生存者の一人)の家に案内してくれたのは、当時村長になったばかりのこの早野仙平氏(当時35歳)でした。吉村さんは、自分が講演をしている10階建てのこのホテルが、後に4階部分まで津波の被害を受けるという事態を、想定していただろうか。 . . . 本文を読む
「三 チリ地震津波」の最後は「津波との戦い」。吉村さんはまず指摘する。「津波は、今後も三陸沿岸を襲い、その都度災害をあたえるにちがいない。」 「しかし」と吉村さんは、田老町の取り組みを例に出す。田老町は明治29年(1896年)に死者1859名、昭和8年(1933年)に911名と、2度の津波来襲時にそれぞれ最大の被害を受けた被災地であったが、町の人々はその津波被害防止のために積極的な姿勢をとり、巨大な防潮堤を建設し、その防潮堤の存在によって昭和35年(1960年)のチリ津波の時には死者もなく家屋の被害もなかったこと。さらに田老町は、広い避難道路を建設し、避難所や防潮林、警報器などの設備も完備し、町を挙げての避難訓練も毎年3月3日に実施していること。そのような田老町の津波対策を例に挙げて、吉村さんは、「他の市町村でもこれに準じた同じような対策が立てられているから」、たとえ大きな津波が来ても「被害はかなり軽減されるに違いない」とやや楽観的な見方を示しつつも、田野畑村羅賀の中村丹蔵さんの証言から、大津波によっては「海水は高さ10メートルほどの防潮堤を越すことはまちがいない」と指摘するのを忘れない。つまり田老町に見られるような頑丈で巨大な防潮堤であったとしても、巨大津波が生ずれば、その津波はその巨大防潮堤を軽々と越えて内陸部に流入し、被害をもたらすことが十分にありうるのだ、と吉村さんは断言していたのです。吉村さんは平成11年(1999年)、田野畑村の羅賀の「ホテル羅賀荘」で「災害と日本人-津波は必ずやってくる」という題で講演をしています。そこでも吉村さんは地元羅賀の中村丹蔵さんの証言を紹介しています。10数メートルの防潮堤を軽く越えてしまうような巨大津波(そしてそれをも含めた自然災害など)は「必ずやってくる」のだから、それへの対策は(想定の範囲外に置いてしまって、あとで「想定外だった」と言い訳をするようなことはせずに)しっかりと怠らずにやっておくべきだ、というのが吉村昭さんが最も「伝えたかったこと」であったと私は考えています。 . . . 本文を読む
「二 昭和八年の津波」の次は、「三 チリ地震津波」です。 最初は「のっこ、のっことやって来た」というもの。この津波は、昭和35年(1960年)5月23日に南米チリの中部沖合で発生した大地震によって起こった津波が、日本の太平洋沿岸に押し寄せてきたもの。押し寄せてきたのは5月24日の未明。岩手県下の死者は61名。そのうち52名は大船渡市における死者でした。その津波の押し寄せ方は、明治29年、昭和8年の津波とは全く異なっており、それは過去の津波のように高々とそびえ立って突き進んでくるものではなく、海面がふくれ上がってゆっくりと襲来するものでした。ある漁師は、それを「海水がふくれ上って、のっこのっことやって来た」と証言しましたが、吉村さんの「のっこ、のっことやって来た」という題は、その漁師の印象的な表現に由来する。「のっこ、のっことやって来た」の次が「予知」。ここで、吉村さんは、チリ地震が発生してのをキャッチしながら、その後十分な観測をせず、三陸沿岸をはじめ日本の太平洋沿岸に積極的な事前警告を行わなかった気象庁に対して、「世の批判を受けてもやむを得なかったのだ」と厳しい指摘をしています。このチリ地震による大津波については、私は幼少時に見た新聞記事として記憶に留めています。昭和35年といえば、私が小学校1年生の時であり、津波被災地の現場の上空写真や現場写真を新聞で見た記憶があります。私が東北仙台に住んでいた時に、盛岡から宮古へと向かい三陸海岸を見てみようと思ったのは、もしかしたらそのチリ地震による津波被災の記憶があったからかも知れません。子ども心に、はるか離れた南米チリで発生した地震による津波が、太平洋を伝わって日本の太平洋沿岸に押し寄せ、多くの犠牲者が発生したいうことが、かなりの驚きであったのだと思います。 . . . 本文を読む
「昭和八年の津波」の最後は「救援」です。津波が発生した同年3月3日と、その後数日の三陸地方の気温は零下7.8度~17.1度という厳しさであり、積雪が海岸を覆い、さらに雪もちらつくという状態であったという。強い地震で飛び起きた人々の多くが、地震がおさまるとまた布団にもぐりこんだのはその厳しい寒さにありました。赤沼山に逃げた人々がそこで見たものは、焚火がたかれていることであり、逃げてきた人々は厳しい寒さの中、それで暖をとったのです。「深夜、着る物も着ずに飛び出した生存者たちは寒気にふるえ、多くの凍死者」も出るありさまでした。そのような「寒気と飢えで呻吟していた」被災民に対して、救援活動が展開されました。当時は陸軍や海軍があり、陸軍ではただちに派遣部隊を編成し、トラックと徒歩による強行軍によって被災地へ急行し、海軍の場合は、大湊要港部や横須賀鎮守府などの駆逐艦が、釜石・宮古等の三陸海岸の港へと急行したという。岩手県の石黒知事が、被災当日、全県民に対して告諭を発表していますが、その中で注目されるのは、「時恰(あたか)モ郷土将兵ハ、熱河掃匪ノ為尽忠報国ノ至誠」を遂行している時だから、「希(ねがわ)クハ忠勇ナル出動将兵ヲシテ、後顧ノ憂ナカラシムルニ努メラルベシ」と結んでいること。当時は満州事変の最中であり、三陸海岸からも多くの青壮年たちが満州へと出征していたということについては、「住民」のところで吉村さんが指摘しているところ。郷土将兵が満州で尽忠報国の行動を遂行しているのだから、彼らに後顧の憂いをさせないためにも被災民もがんばれとの叱咤激励の仕方です。しかし救援物資の輸送は、内陸部からの道が狭いことや積雪のため、さらに地震や津波によって海岸沿いの道路が破壊されていたことによって、なかなかはかどらないという状況でした。三陸海岸各地への物資輸送は海上から行うのが最も適していましたが、岸近くで物資輸送を行わなければならない小舟のほとんどが流失したり破壊されたりしていて、意のままにはなりませんでした。住居については、家を失った被災民のためにまず急造バラックが建設され、さらにその後、個人用住宅も続々と新築されていきました。津波被災を避けるために高所移転が進められていきましたが、年月が経って津波の記憶が薄れるにつれて、逆戻りする傾向があった、と吉村さんは記しています。 . . . 本文を読む
「住民」の次は、「子供の眼」。ここに私が田老第一中学校の校舎(敷地)の左手に見た山である赤沼山が出て来ます。吉村さんは次のように記しています。「村民は、村の背後にある赤沼山をはじめとした高地に逃げた。が、道路はきわめてせまく押し合いへし合いしたため動きはおそかった。その人々に、津波は秒速一六〇メートルという恐るべき速度でのしかかってきたのだ。」 ここで吉村さんは、津波を経験した田老尋常高等小学校の作文をいくつか紹介しているのですが、その作文の中にも赤沼山が出て来ます。「お父うさんが弟をせおって、私は、くらい道をはせ、ようよう赤沼山にのぼると、よしさんたちは、もうたき火をしていました。」(尋三 川戸キチ)「笹にとっきながら赤沼山のお稲荷さんの所まで行くと、みんながもっと登って行くので、私達もはなれないように、ぎっしり手をとって人の後について山のてっぺんまで上って火をたいてあたりました。」(尋六 牧野アイ) 八人家族のうち、自分を除いて七名の家族を亡くして孤児となった牧野アイさんは、叔父の家、宮古町、北海道の根室と親戚の家を転々とした後、十九歳の年にふたたび田老に戻り、翌年、やはり津波で両親、姉、兄を失った、教員の男性と結婚しました。吉村さんはそのアイさん夫婦と会って話を聞いています。一部がここに収録されている作文は、田老尋常高等小学校の先生たちの指導でまとめられたものであり、同校生徒164名、2名の教員の死に対する鎮魂文でもある、と吉村さんは記しています。 . . . 本文を読む
次の「住民」は、昭和8年(1933年)の大津波を経験した人たちの記録。最初の岩手県気仙郡唐丹村本郷の鈴木善一さんの記録で興味深いのは、波間に漂っていた人々が、お互いに「満州の兵隊を思い出せ、これ位で死ぬものか」と励まし合っていたという証言です。当時は満州事変の最中であり、三陸海岸からも多くの青壮年たちが出征していたからである。同じく本郷村の体験記録が紹介されていますが、これは、古老たちが「こういう晴天には、津波は来ないものだ」と自信ありげに語っていたということの証言。種市村宿戸の上岡谷たまさんの場合は、一家6人のうちたまさんを除いて全てが亡くなっています。吉村昭さんは、ノートを手にメモをしながら三陸海岸を歩き回り、37年前の昭和8年の津波の生々しい記憶をもつ多くの人たちに出会いました。その中に岩手県下閉伊郡田野畑村島ノ越に住む畠山ハルという方がいました。昭和8年の津波当時ハルさんは14歳。「津波だあ!」との声にハルさんは飛び起き、そして30mほど離れた裏山へと走りました。後方でバリバリと家が壊れる音がしたので瞬間的に振り向いたところ、2階建ての家の屋根の上方に、白い水しぶきをあげた黒々とした波が、ノッと突き出ていたという。その証言を受けて、吉村さんは、「その話をきいただけでも、津波の怖しさがよく分るような気がした」と記しています。 . . . 本文を読む