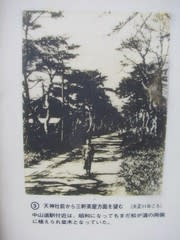崋山が生田万と別れて上尾宿を出ようとしたところ、従僕の弥助が足を痛めて一歩も歩くことができない状態になり、やむなく弥助に持たせていた行李(こうり)と笈(おい)を連れの高木梧庵と交互に担いで行くことになりました。しかしその荷物が肩のあたりに食い込んで痛くなり、崋山自身も一歩も踏み出せないような状態になる。そのよう状況であるのに雨は降ってくるし夜が更けて行く手も見分けがたい状態となる。かろうじて桶川宿に着いたのは夜戌(いぬ)の時ほど(午後8時頃)のことでした。桶川宿で人足を借りて行李を持たせることにして出立。人の往来はなく、雨はいよいよ激しくなる。人家で蓑と笠を借り歩いていくものの疲労は極度に達する。ようやく鴻巣宿の「穀屋次郎兵衛かた」に到着したのは夜の10時過ぎのことであったと思われる。板橋宿の茶店で落ち合う約束であった岩本家の使用人吉兵衛がすでに到着していて、崋山が旅籠に到着したことを知って驚いて出迎えます。崋山は直ちに酒を命じますが、酒の肴が良くなかったので卵を5つ購入して食べました。一日50kmほどの行程は、崋山であってもやはり相当にこたえたことがわかります。上尾宿で、「疲れてしまったからここで泊まる」と言って崋山の誘いを断った生田万は、賢明であったと言うべきでしょう。可哀そうなのは、重い行李と笈を背負って、足の痛いのを我慢しつつ、必死に崋山や梧庵のあとを上尾宿まで付いてきた従僕の弥助でした。 . . . 本文を読む
嘉陵は、桶川宿から中山道を戻り、上尾宿を過ぎ大宮宿に至ったところで、足も疲れてしまったので戻り馬に乗りました。今まで私は嘉陵は帰途もずっと歩いたものと思いこんでいましたが、大宮宿から馬に乗っていたのです。ではどこまで馬に乗ったのか。はっきりとは記してありませんが、おそらく蕨宿までであるようで、そこの「中村や作兵衛」という茶屋に立ち寄って夕飯を摂り、戸田の渡しを日が暮れるまでに越えようと走るように歩き、元蕨村の縄手の人家があるところで振り返ってみると、秩父連山の上に浅間山が見え、その東に妙義山も榛名山もくっきりと見えました。傍らにいた人に聞いたところ、「いかにもあれは浅間山、これは妙義山」と答えます。今朝、ここを通過した時はまだ暗かったから、ここから浅間山が見えることも知らないで通り過ぎたけれども、桶川で見た浅間山の風景よりもこちらの方が勝っていることを考えると、桶川まで行ったのは馬鹿らしいようにも思われたけれども、思い返してみれば、あそこまで行って浅間山を確かめたからこそ、帰りにはここから見えるかも知れないと思って道を急いだのであり、またここでも晴れていたからこそ遠くの山が見えたのであって、曇っていたり霞がかかっていたならば見えるはずはなかったのであると、心に満足を覚えながら嘉陵は戸田の堤に上がって、黄昏(たそがれ)を過ぎる頃に荒川を渡し舟で越えたのです。大宮宿から蕨宿まではおよそ10.5km。その間を馬に乗ったから、その距離を全行程から差し引いても1日で約80kmを歩いたことになります。板橋宿に着いたのが午後6時頃。還暦を迎えた嘉陵にとって長距離歩行の疲れはさすがに足にきて歩みはのろくなり、帰宅したのはそれから3時間後の午後8時過ぎのことでした。 . . . 本文を読む
嘉陵は、茶菓子屋の主人の話を頼みに中山道をさらに進み、桶川宿の入口右手の畑の中に教えられた通りに不動堂があったので、畑の細道に入ってその不動堂の不動尊を拝しました。しかしここの畑からは日光山や赤城山などが木々の間から見えたものの、浅間山の方角は木々に遮られて見えない。そこで不動堂の縁に腰掛けていた男に尋ねてみると、「浅間山は桶川宿の西裏の畑の中から見えますよ」ということだったので、桶川宿に入って二丁(200m余)ばかりの石橋のところから左折して五、六丁(600m前後)ほど進んだ畑の中から北の空を見渡してみたところ、まゆ墨のようにあわあわと見える山がある。それがどうも浅間山らしいと思ったものの確信が持てないので、遠くで畑を耕している男を見付けて、畔(くろ)を伝って近寄り尋ねてみると、その男は、「あれが確かに浅間山です。今日はとりわけよく晴れたのですが、あまりにのどかで霞んでいるため噴煙ははっきりと見えません。今朝ははっきりと噴煙が見えていたのですが」などと言って、妙義山や榛名山なども教えてくれました。やっと念願を果たした嘉陵は、未(ひつじ)の刻(午後2時頃)ばかりであったため、そこから急いで帰途に就きました。ここに出てくる「不動堂」というのは、南蔵院という明治初年に廃寺となったお寺の不動堂であったらしい。雑木林の中に広がっていた畑は、この地で栽培されていた「紅花」の畑であったのだろうか、それとも「紫根(しこん)」の畑であったのだろうか。不動堂の縁に腰掛けていた男も、桶川宿の西側で畑を耕していた男も、桶川宿近辺の百姓であったと思われる。嘉陵は「紅花」については触れていませんが、「紫根」については触れています。「六貫目を以(もって)一苞とし江戸に送ると云(いへ)り、もの染るのみにあらず、薬物にも入」。「紅花」や「紫根」といった商品作物の栽培から、桶川宿やその近辺も「江戸地廻経済圏」の中に組み込まれていた地域であったことがわかります。 . . . 本文を読む
崋山が上尾宿を通過したのは、この『毛武游記』の時が初めてではない。そのことを知ったのは『板橋区史通史編上巻』に目を通していた時でした。それによると文政2年(1819年)、もと田原藩藩医であった加藤曳尾庵(えいびあん)が板橋の平尾宿に移り住みますが、その年の5月27日、崋山は「石戸宿」というところへ向かう途中、曳尾庵宅に立ち寄り、翌28日にはその「石戸宿」より戻って曳尾庵宅に2泊したというのです(P676)。つまり文政2年5月27日、崋山は板橋宿を通って「石戸宿」というところに向かったのですが、『通史編』には、崋山がなぜ「石戸宿」に向かったのかは記されていませんでした。気になってネット等で調べてみると、その時の崋山の目的は、「石戸」の「蒲ザクラ」を描くことであったことを知りました。現在の北本市には「石戸宿」というところがあり、そこには「日本五大桜」の一つである「石戸蒲ザクラ」があります。その推定樹齢はおよそ800年。その根もとには源範頼の墓と言われる石塔があるという。この源範頼は、源頼朝の異母弟であり、「蒲冠者(かばのかじゃ)と呼ばれたことから、その石塔があるところに咲く桜は「蒲ザクラ」と言われてきたとのこと。この崋山が描いた「石戸蒲ザクラ」が挿絵として掲載されているのが、滝沢馬琴の『玄同放言』という随筆集(3巻6冊)であり、その後編は文政3年(1820年)に発行されています。文政2年の5月、崋山はその「石戸蒲ザクラ」を描くために、わざわざ江戸から中山道を歩いて上尾宿を通過し、おそらく桶川宿から左に折れて石戸宿へと向かいました。崋山にとって中山道桶川宿まではすでに歩いたことのある道であったのです。 . . . 本文を読む
板橋宿から浦和宿までは14.4kmほど。歩けば3時間ほど。板橋宿から上尾宿までは27.3kmほど。歩けば5時間ちょっと。板橋宿を崋山が出立したのは、正午前後と考えられる(崋山は「飲飯の料弐百五十弐文」を茶店に支払っています)から、崋山が浦和宿に至ったのは午後3時頃。上尾宿に至ったのは、途中「月よみの社」(調神社)に立ち寄ったりしているから午後6時前後ということになります。崋山が生田万と別れたのはどこの宿であっただろうか。崋山の文章は次の通り。「上尾この道いと遠して日暮たり。万に我やどるかたまで来てひとよを語あかさばやと申せしかど、いとつかれにつかれたれバとて、此駅にやどかる」。普通に考えれば「此駅」とは上尾宿ということになりますが、『渡辺崋山集』には「此駅」は「浦和駅」となっています。しかし先ほど推測したように、浦和駅を二人が通過したのは午後3時頃であって、まだまだ日暮れには時間があります。二人は大宮宿氷川神社の黒々とした参道を右手に見て、そこから2時間近くを上尾宿まで歩きましたが、そこまでですっかり日が暮れてしまったことと疲労のために、生田万は崋山の誘いを断って上尾宿で泊まることにした、と考える方がやはり自然であるでしょう。上尾宿で名残りを惜しんで万と別れた崋山が桶川宿に至ったのは「夜戌の時過程」(午後8時過ぎ)。宿泊を予定(予約)していた鴻巣宿に到着したのは、桶川宿から鴻巣宿まで7.2kmほどであることを考えると、午後10時近くであったと考えられます。 . . . 本文を読む
「宮原」や「吉野原」といった地名からうかがえるように、この上尾宿近辺の中山道界隈は、見渡す限りの原っぱや雑木林が広がっていた地域であったものと思われます。その間に農家や農村が散在し、広大な畑などが開かれていたのでしょう。大宮宿の周辺も、嘉陵の描いた絵図からわかるように同様でした。その平地(台地)からは、空気が澄み切った天気のよい日には、西方向はるかかなたに富士山の秀峰がくっきりと見えたはずだし、また上州の山々や、また遠く浅間山なども北方に見えたはずです。その広大な平地からやや突き出た古墳や富士塚といった築山(つきやま)の上からは、背の高い建物が周辺に密集する現在の状況とは違って、かつては周囲の山々を見晴るかすことができました。中でも人々にとって印象的であったのは富士山の姿でした。特に雪をかぶって白く輝く独立峰の富士山は、それを見るものに神々しさを感じさせました。その富士山への人々の信仰は、富士浅間信仰として古来あったものと思われますが、その長い信仰の蓄積の上に、幕末になって人々の間に急速に広がったのが「富士講」でした。加茂神社周辺の「富士塚」を見ただけでも、この埼玉県にはかなりの数の「富士塚」があるものと推測されました。「富士塚」があるということは、その「富士塚」を築いた「富士講」の人々がその地域にいたということであり、その地域に「富士講」があったということは、その人々が富士山へと向かう「富士道」が各地にあったということです。富士詣でが大山詣でとセットされている場合(実際そういうケースが多いのですが)、その「富士道」は「大山道」でもあったわけです。嘉陵が記す「富士浅間」を祀る「小高い山」とは、「富士塚」であるように思われますが、見晴らしが効かず、日が差し込まないほどに樹木が鬱蒼としていたことを考えると、もしかしたら古来からの富士浅間信仰にもとづいた石祠か神社のある「小高い丘」であったのかも知れず、それはもしかしたら円墳などの古墳を利用したものであったのかも知れない。周囲はだだっ広い平地であったから、その「浅間様」は中山道を行く者からは目立つものであり、その上に登れば周囲が見渡せると嘉陵が考えたのも、無理なからぬことでした。 . . . 本文を読む
嘉陵が上尾宿に至ったのは巳の刻(午前10時)過ぎ頃。さらに中山道を進んで行くと、道の西側に富士浅間(せんげん)を祀る小高い丘があり、そこに登れば北の空が見えるだろうとそれに登ったところ、木立が繁っていて日差しが当たらないほどであり、北の方を見晴らすことはできませんでした。つまり、その日見ようと思っていた浅間山を、その小高い丘の上からは見ることができなかったのです。落胆もあって歩き疲れた嘉陵は、道筋の茶菓子を売る店に腰掛けて休憩かたがた、その店の主人に尋ねてみたところ、北の空を見晴るかすことができるところは、もう少し進んで、桶川宿の入口の右手、不動堂のある畑あたりで、そこからは北の山々が少しは見えるとのこと。そこで嘉陵はその主人の言葉をたよりに桶川宿の入口付近まで歩いてみることにしました。この嘉陵の文からも、このあたりの中山道の界隈には、「富士浅間」を祀る「小高き丘」、つまり「富士塚」らしきものがあったことがわかります。 . . . 本文を読む
前月は上尾まで歩きましたが、埼玉新都市交通伊奈線加茂宮(かものみや)駅近くでバイパスに入ってしまい、旧中山道から外れてしまったため、今月はJR高崎線の宮原駅で下車し、上尾や桶川を通過して鴻巣まで歩きました。『江戸近郊道しるべ』の著者村尾嘉陵は、江戸から桶川宿の入口まで中山道を歩いてこの日のうちに江戸まで戻り、崋山は江戸から1日で鴻巣宿まで歩きました。崋山は1日で52km以上を歩き、そして嘉陵は、往復で単純計算をしてもなんと90km近くを歩いています。大宮の氷川神社の長い参道も往復しているから、少なくとも90kmは歩いているのではないか。嘉陵は午前4時半頃に自宅を出発し午後8時過ぎに帰宅しています。計算すると時速6kmほどで15時間歩いていることになります。崋山も健脚ですがその時の年齢はまだ39歳(数え)。しかし嘉陵はその時還暦を迎えていたと思われるから60歳の高齢者でした。そのことを考えると驚くべき健脚です。今の私たちから考えると「驚くべき健脚」ですが、むかしの人々(成人男性)はいざとなれば1日でそれぐらいの距離は歩き続けることができたのでしょうか。以下、鴻巣までの取材報告です。 . . . 本文を読む
津波が到達した標高線に咲く桜は、全通した東日本の沿岸部を走る鉄道に沿った歩行者専用道路から眺めるのが望ましい、としましたが、それは全国から訪れた人々が一番利用しやすいからです。もちろん列車の窓から眺めることも出来るのですが、空気や風を感じ、季節の香りや生活の匂いを感じ、復興していく「まち」の景観や人々の暮らしをしっかりと眺めるのには、ゆっくりと歩くのが一番です。かつての旅人が行き交う街道筋には、人々の足を止めさせ人々をもてなすためのさまざまな装置がありました。宿場や街道沿いに住む人々によって丹念込めて育てられた樹木や草花などが街道筋に彩りを添えていたのも、それは街道を行き交う人々をもてなすものでした。旅人はそれらの装置で旅の疲れを癒され、街道筋の人々も旅人をもてなすことにより生活の糧を得るとともに、旅行く人々との関わり(コミュニケーション)を楽しんだのです。茶屋も旅籠も、その装置の一部でした。人々が歩く街道筋には、旅人をもてなし、疲れを癒すための装置が、街道筋の人々によって緊密に構成され保全され続けていたのであり、それが全体として歴史的景観を形づくっていたのです。しかし、それらの道が急速に車優先の道になり、また幅広のバイパスが出来ていくことによって、もてなしもてなされることによって形作られてきた歴史的景観は、急速な勢いで消滅していったのです。道を歩くことを復権させること。歩くことによって得られるものを復権させること。安心して安全に歩ける道を取り戻すこと。その道を仲立ちにした人々の関わり(コミュニケーション)を復活させること。「被災地にミニ東京を造ってはならない」とは建築家の伊東豊雄さんの言でしたが、私もそのように思います。被災地を走る鉄道に沿って歩行者専用道路を造ることの意味を、思いつくままにいくつか列挙してみます。 . . . 本文を読む
まず一つの取り組みとしては、被災地の巨大津波が押し寄せた最上部のところに(それは海抜20m前後の地域によってかなり幅のある標高線になるだろう)、亡くなった人たちや行方不明者の慰霊(鎮魂)のための桜の木を一本一本植樹していくというのはどうだろう。植樹していくのは犠牲者の身内の人であったり、友人や知り合いの人であったりと、被災地の人たちです。その桜の木は、あの漁師の方の話にあったように単なる慰霊のためのものではなく、津波警報が出されたらまずは一目散にそこへと避難していく目印となるものです。明治29年(1896年)の三陸海岸を襲った巨大津波は、ジャバ島に起きた巨大津波に次ぐ世界第2位の大規模なものであったという。公式記録によると10mから24.4mと言われているというけれども、実際には海面から50mのところもあったという。この巨大津波によって、岩手県の気仙郡、上閉伊郡、下閉伊郡、九戸郡、この四郡の人口が約10万3千名であったところが、実にその22%が死亡していると、『三陸海岸大津波』の著者である吉村昭さんは述べています。では、その明治29年の三陸海岸大津波の記憶はしっかりと継承されていたかというと、結果的に見るとそうとは言えず、年月の経過とともに風化してしまったといっていい。それが端的に現れたのが東京電力福島第1原子力発電所の事故でした。冷却水を循環させる装置の電源がすべて喪失するという致命的事態(冷却水喪失事故)は、その電源が巨大津波にのみ込まれたことによるものであり、それは「想定外」でも何でもなく、明治29年の巨大津波の高さを想定に入れていれば、十分に予測可能なものでした。何も貞観地震の巨大津波まで遡らなくとも、わずか115年前に起こっていたことなのです。 . . . 本文を読む
『毎日新聞』3月11日(日)に別刷りで、東日本大地震でこれまでに死亡が確認された人たちの名前が居住地別に掲載されていました(各都道府県警が1年間に発表した犠牲者名簿を基にしたもの)。この別刷りの2面から7面にはびっしりと犠牲者の名前と年齢が記されていました。年齢は「昨年3月11日時点」のものであり、これを見るとやはり高齢者が圧倒的に多いことに否応なく気づかされますが、また一方で乳幼児の「0」とか「1」とか「2」といった痛ましい数字も目に入ってきます。もちろん児童生徒や若い人たち、また働き盛りの人たちの死亡者名も見られます。この名簿の中には行方不明者は当然のことながら含まれていません。3月11日のテレビ報道では、被災地の各所において慰霊や供養をする多くの人々や復興に向けて動き出した人々の姿が映し出されましたが、その中でもとくに私の印象に残ったのは、ある漁師の方が中心になって行っていた、津波が到達したところに桜の苗木を植える取り組みでした。その方は抱いた男の子に、「津波がきたら桜の木があるところまで逃げるんだよ。そこまで逃げれば大丈夫だから」といったことを話しかけていました。「ああ、桜か!」と私はその場面を見て、膝を打つような気持ちになりました。以下、それについての私の一つの「夢想」を記します。 . . . 本文を読む
一つの仮想を設定してみたい。全国各地に原発が造られていった時に、東京湾岸部にも、原発が何基か造られていったとする。そして1年前の3月11日に、巨大地震と巨大津波による東京電力福島第1原発の事故が発生し、水素爆発による放射性物質によって広範囲の地域が汚染されるという事態が引き起こされる。静岡県御前崎の浜岡原発は、その立地上の危険性から稼働停止が命ぜられましたが、それは東京を中心とする首都圏の安全の確保を第一にはかるためのものでした。ということは、もし東京湾岸部に原発があったとしたら、東京直下型の巨大地震が発生した場合を想定して、福島原発のあの生々しい事故の深刻さから、浜岡原発と同様に即座に稼働停止命令が政府によって出されたはずです。では、福島第1原発の原子炉内の冷却水の温度が安定したことによって「収束」宣言が出され、また今後他の原発についてはストレステストなどで徹底的な安全性を確保していくという方向性が出されたところで、東京湾岸部の原発も含めた上で、その「再稼働を先頭に立って推進する」などといったことを時の総理大臣が宣言することができただろうか。東京を中心とする首都圏には、福島や福井とは比べものにならないくらいの人口が密集し、首都としてのさまざまな国家的機関や大企業の本店が一極集中し、そして皇居が存在しているのです。ここで巨大地震が発生し、それにともなう巨大津波が押し寄せ、浦安や潮来のような液状化現象が生じ、そしてあの福島のような原発事故が発生したとしたら、それによる被害や影響はそれこそ「想定外」のものとなることでしょう。東京湾岸部およびその周辺の人々は、その「東京原発」の再稼働をおそらく絶対に認めないはずです。政府もおそらくそうでしょう。この一つの仮想から考えられることは、国は国民全体の生活の安全・安心をはかることよりも、国の中心的な機能を守り、日本経済の発展ないし安定を第一にはかろうとしているということです。より一層の経済の発展こそが国民を豊かにし、国民全員の福祉充実をもたらすという思想はすでに破たんが明らかであるのに、その幻想にしがみついている人たちがいる。かつて「経済」とは「経世済民」の謂いではなかったか。 . . . 本文を読む
「東日本大震災」は、東日本の広範囲な海岸線に押し寄せた巨大津波による甚大な被害に加えて、福島第1原子力発電所の事故とそれによる広範囲な放射能汚染が復興への取り組みの大きな足かせとなり、今後もずっとなり続けるであろうという意味において人類史上未曽有の大災害である、という認識から出発しなければ、この大震災で亡くなった人たちや行方不明になった人たちへの慰霊・供養につながらず、また今後生きていく人々(避難している人たちや私たちも含めて)がどう生きていくかの教訓とはならない、としましたが、それは言い過ぎでしょうか。巨大津波によってのみこまれていった身近な人々や生まれ育った土地の瓦礫と化した風景を前に、生き残った人々が、亡くなった人たちと会話を重ねつつ、亡くなった人たちのためにも「ちゃんと生きよう」とした時に、その歩み出そうという足を大きく引っ張るような力となったのは、あの安全であったはずの原発事故ではなかったか。放射能汚染が広範囲にわたり、それによる風評被害もさまざまな分野に及んでいます。発生した膨大な瓦礫の最終処理済みが6%でしかなく、復興・復旧に向けての大きな障害となっているという事態は、これは放射能汚染への恐怖と不安によるものであって、もし、あの原発事故がなかったならば、復興・復旧はもっとスピーディーに進められたはずです。東日本の被災地全体の復興・復旧への大きな足かせになり、被災地の人々が希求する「将来の見通し」がなかなか持てない状況を生み出した大きな要因は、あの原発事故が発生したことであり、そしてそれによって引き起こされた広範囲の放射能汚染の恐怖である(それへの対応は今後ずっと続いていく)という認識を、まずしっかりおさえて、自然災害はまた起きるかも知れないけれども(その対策は「減災」という方向でいろいろと考えられ、実行されていくことでしょう)、原発事故が自然災害等で起きてしまった時のその被害の甚大さ、その影響の大きさを考えた時、「脱原発」という方向性を、あの人類史上未曽有の大災害を経験した日本という国が選択していくのは当然のことである、と私は考えます。そして、それに向けての生き方やライフスタイル、コミュニティー空間のあり方(「まちづくり」を含めて)などを一人一人が考えて生きていくことが、「3月11日」「被災者」を「忘れない」ということではないか、と考えます。 . . . 本文を読む
今朝の新聞(『毎日新聞』)に目を通すと、東日本大震災1年の関連記事とともに、警察庁がまとめた死者・行方不明、復興庁がまとめた避難者数が29面の右下に小さく出ています。それによると死者数は1万5854名、行方不明は3167名、避難者は34万3935人となっています。また1面には「不明者9割死亡届」とあり、岩手・宮城・福島3県で今なお計3151人に上る行方不明者がおり、その9割の2860人の死亡届が受理されている(9日現在)ことが記されています。死者・行方不明者の県別内訳を見てみると、そのほとんどは岩手・宮城・福島の3県に集中しており、巨大津波による死者・行方不明者が圧倒的に多かったことを示しています。しかも2月末時点での不明者の69%は60代以上であるという。避難者34万3935人の地域別内訳は記してありませんが、おそらくこの数の中には福島第1原発事故による放射能汚染による避難者数が多数含まれていることでしょう。1年前の3月11日に発生した巨大地震にともなって押し寄せた巨大津波は、高齢者の割合の多い地域に押し寄せて多くの犠牲者を生み、またこの巨大地震や巨大津波は、東京電力福島第1原発事故を引き起こして、その事故がこれだけ多くの避難者を1年後になっても残している大きな要因となっていることを示唆しています。その避難者数に占める高齢者の割合も、死者や行方不明者のそれと同様に高いものであると思われる。復興・復旧を阻む膨大な量の瓦礫の処理が一向に進まないのは、原発事故による広域にわたった放射能汚染およびその恐怖が足かせとなっているからであり、この「東日本大震災」の特異さを示しています。確かに、想像を絶するような巨大津波に東日本の海岸線一帯が広範囲にわたって襲われ、壊滅的な被害を受けたという点において、震災処理に向けての取り組みは厳しいものがありました。しかし、福島第1原発事故とそれによる放射能汚染があらゆる面でその取り組みの大きな足かせになり、現在も、そしてこれからも大きな足かせになり続けていくだろうという意味において、この「東日本大震災」は人類史上「未曾有の大災害」であると言わざるをえず、その認識から出発しなければ、高齢者や幼い子どもたちを含む多くの死者や行方不明者の慰霊や供養にはつながらず、またこれからをどう生きるかの教訓ともなりえないと私は考えています。 . . . 本文を読む