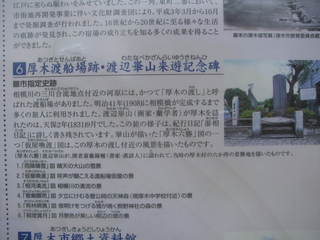9月24日(陰暦)の朝、卯刻頃(午前6時頃)に崋山は目を覚まし、まず日記を記しています。日記を記しているうちに夜は明け、「万年屋」に泊まっている客の煙管(きせる)をはたく音やくしゃみをする声、カラカラと井戸の水を汲み上げる音やお膳で食器があたって鳴る音などが聞こえてきます。まもなく下女が梅干しを添えた土瓶を持ってきて茶を入れてくれたりして、旅先にいるという気分に浸っていると、やがて斎藤鐘助がやって来て「先生、六勝図はできましたか」と問うてくる。崋山は昨日描いたスケッチをもとに「厚木六勝図」をすらすらと描き上げました。厚木の資産家である清田半兵衛、厚木村の名主である中野新兵衛、知人でたまたま厚木の伯母の家に滞在していた浅田文治郎などもやって来る。また「厚木ノ侠客」である駿河屋彦八も、また唐沢蘭斎などもやって来る。駿河屋彦八に崋山は質問をし、それに彦八がどう答えたかはすでに触れたところ。唐沢蘭斎もまたその席で烏山藩の支配のあり方についてふたたび不満をぶちまけたようだ。みんなで昼食を終えた後、出立しようとする崋山が万年屋の主人平兵衛に一昨日から費やした酒肴の代金を払おうとすると、平兵衛は受け取ろうとしない。そこで崋山は梧庵と相談し、酒肴代といろいろ世話をしてくれたお礼として黄金一両と白銀一両を投げるようにして平兵衛に渡して出発しました。唐沢蘭斎は、二人を中津川を対岸の金田村へと渡る「金田の渡し」まで見送ってくれました。その金田村から「厚木の渡し」で河原口村へと渡って、そこから右折して二人は東海道藤沢宿へと向かったようです。そして25日の朝、藤沢宿の旅籠を出立した二人は、江ノ島、鎌倉、金谷村の大明寺を経由して浦賀に赴き、浦賀での用を済ませてから江戸へと帰途に就いたのです。 . . . 本文を読む
2泊3日のの厚木宿滞在で、崋山の記憶に残ったのは、水上交通・陸上交通の要衝地としてのその繁栄や賑わいと、それにも関わらずその地を領する烏山藩の政治に対する不満や反発が人々の間に鬱積している現実であったでしょう。その不満や反発を崋山に語ったのは、23日に斎藤鐘助とともに崋山を桐辺堤へと案内した厚木宿の医者唐沢蘭斎であり、そして24日に崋山の人物を確かめにやってきた「厚木ノ侠客」駿河屋彦八でした。彦八は「今の殿様は民を慈しむ心は全くなく、隙をうかがって厳しく御用金を取り立てようとするばかり。いっそ殿様を取り替えた方がいいと思っている」と言い、蘭斎も「厚木は天領(幕府領)になれば上々、旗本領になってもその方がましだ」と言う。崋山はその二人の言を聞いて「愕然」としています。崋山は彦八に対して、儒教的な道徳観念からその考え方の非をとなえていますが、現実の長い生活体験から出てきている彼らの不満や反発を、通り一遍の言論で封じ込めることがとうてい無理であることは十分に感じたはずです。このような領民の不満や反発の鬱積が、自分の属する田原藩の領内で生じたらどうするか。いや、生じさせないようにするためにはどうすればよいか。さらに、このような不満や反発が各地に広がっているとしたら(つまりもし全国的なものになっているとしたら)、為政者はそれにどう対処すればよいのか。崋山はそのようなことにまで思いを致したかも知れない。庶民の赤裸々な不満・反発の吐露に接して、崋山はあるべき政治のあり方を模索していきます。その一つの契機となったのが厚木宿での唐沢蘭斎や駿河屋彦八らとの出会いであったでしょう。 . . . 本文を読む
斎藤鐘助(撫松)が撰んだ「厚木六勝」の題はみな五文字でしたが、崋山はそれは雅(みやび)ではないとして四文字に変えました。では鐘助が考えた五文字の「厚木六勝」はどういうものであったかというと、「雨降山晴雪」・「仮屋戸喚渡」・「相模川清流」・「菅公祠驟雨」・「熊野森暁鴉」・「桐辺堤賞月」というものでした。このうち「桐辺堤」からは、他の五勝をすべて見張るかすことができたことが、崋山の日記からわかります。私は崋山が六勝それぞれの地に赴いて、それをスケッチしていたと思い込んでいましたが、日記をしっかり読んで見ると、崋山が唐沢蘭斎と斎藤鐘助に誘われて赴いたところは、途中「熊野森」に立ち寄っているものの、実は「桐辺堤」であり、崋山はそこでスケッチした後に「万年屋」に戻っています。崋山の厚木村における行動範囲は決して広いものではなく、厚木宿からその南方一里ほどにあった桐辺堤までの範囲(大山街道沿い)であったことがわかります。崋山が厚木宿(「万年屋」)を出立したのは、駿河屋彦八らが訪れた9月24日(陰暦)の午後(昼食後)のことでした。崋山と梧庵は、もう大山街道を大山方向へと進むことはなく、「厚木の渡し」で相模川を渡って(なぜか「金田の渡し」で中津川を渡っています)、河原口村で右折して東海道藤沢宿へと向かう道を歩んで行きました。崋山と梧庵が厚木宿「万年屋」に滞在したのは、9月22日の夕方から24日のお昼頃までのことで、2泊3日の短い滞留であったことになります。 . . . 本文を読む
斎藤鐘助が撰んだ「厚木六勝」とは、「雨降晴雪」・「仮屋喚渡」・「相河清流」・「菅廟驟雨」・「熊林暁鴉」・「桐堤賞月」の六景(もともとは五文字であったのを崋山が四文字に直したもの)。鐘助と蘭斎が崋山を誘った場所は「桐辺堤」であり、六勝のうちの「桐堤賞月」がそれに該当する。月景色が美しいところであったのでしょう。厚木の町の長さは十八丁(約1.8km)。そのうち上(つまり北側)の三、四丁は大きな商店が軒を並べていて賑やかだが、それから下つかた(つまり南側)は人の行き来もまれであると崋山は記しています。崋山らは旅籠「万年屋」がある天王町から南へと進み、宿の外れにある大きな森へと至りますが、これが熊野森。そのさらに南にあったのが「桐辺堤」でした。堤の長さは八、九丁(800~900m)ほど。文政年間における築堤工事の時に完成したらしい。竹や草が生い茂っていて、新たに造られたものとは思われないほど。この堤を境に、右側(つまり西側)には田んぼが見渡す限り広がり、左側(つまり西側)には清らかに流れる相模川の水面が広がる。水上にはただ烏が飛び交っているのを見るのみである。崋山はそのようすをスケッチしています(「写真す」)。この堤からは熊野森の全体を見ることができるし、雨降山(大山)も田んぼの向こうに手に取るばかりに見ることができる。天神の森は青田の中にこんもりとあるのが見え、江戸の三囲(みめぐり)神社を彷彿とさせる。ここからは厚木の渡し(河原口村と厚木村を結ぶ渡し船)の様子も見え、そこは先日、自分が相模川を渡ったところで、河原には粗末な小屋が見える。つまりこの堤からは、「厚木六勝」の全てを見ることができ、そこからの六つの景色を崋山はその地点でスケッチしました。唐沢蘭斎が語ったものと思われる相模川の水害は、烏山藩の堤防新築工事に対する批判を伴ったものでしたが、その文政年間に新築されたという堤防は「桐辺堤」を含むものであったでしょう。おそらく「桐辺堤」を歩いた時に、唐沢蘭斎が崋山に語った内容であったものと思われます。崋山は一緒に堤を歩いている時に、そしておそらく堤からの眺めをスケッチしている時に、蘭斎が語る内容をしっかりと聞いていたのです。 . . . 本文を読む
天保2年(1831年)の9月22日(陰暦)の夜から翌23日にかけて、厚木宿天王町の旅籠「万年屋」で開かれた宴会の途中、崋山は気持ちよく酔っ払ってそのまま寝てしまいます。ふと目を覚ましたのが寅刻過ぎ(午前5時頃か)と思われる頃。夜着が掛けられており、枕も敷いてある。崋山は起き上がって行燈を点け、昨日聞いたことや見たことを日記に細々と書きつけているうちに、夜は白々とあけてきました。この「昨日聞いたことや見たこと」というのは、下鶴間宿の旅籠「まんじゅう屋」を出て大山街道の赤坂から左折する道へと入り、小園村の大川家を訪ねて「お銀さま」と会い、それから厚木宿の「万年屋」に入って宴会を開いたところまでのことでしょう。「お銀さま」との25年ぶりの再会についての細々としたことは、この23日の早朝に書いたことになります。崋山が起きているのを察して「万年屋」は茶と梅干を出しました。崋山は日記を書き終え、出された茶と梅干で一息入れると、口をすすぎ髪に櫛を入れました。それから朝飯をとりました。朝飯の内容は、味噌汁とご飯ととうふ、そして鰹(お刺身か)。味噌汁は大根が入ったもの。味噌は白みそ。甘味が少々あるものの、味はそれほどよくはなかったようです。朝飯を食べ終えた崋山は、「万年屋」に泊まった大川清蔵(「お銀さま」=「まち」の夫)と、いろいろと話をしています。「我がこゝろ様をはなし、清蔵がこゝろの程を聞く。吾心安し」と崋山は記しており、崋山の満足の行くように話はまとまったことがわかります。その清蔵は、昼飯を食べてから小園村へと帰っていきました。唐沢蘭斎がふたたび崋山に会いにやってきたのは、この23日の昼食後、つまり午後のことであったでしょう。「万年屋」の亭主平兵衛が紙を持ち出して崋山に絵を求めたのですが、その絵の素晴らしさに感嘆した蘭斎は、斎藤鐘助(撫松)を呼び寄せたものと思われる。斎藤鐘助は、かねて「厚木六勝」を選んでいて、その絵を描いてくれる人を望んでいました。蘭斎と鐘助は、「ぜひこれから厚木六勝を見に行きましょう」と崋山を誘いました。もちろん崋山に「厚木六勝」の絵を描いてもらうため。二人が崋山を誘って目指した先は、「桐辺堤」というところでした。 . . . 本文を読む
崋山が描いた「客舎酔舞図」という素描画が『游相日記』にある。ここに描かれている人物は、左端中央から時計回りに、唐沢蘭斎の娘・唐沢蘭斎・斎藤鐘助・薬屋常蔵・内田屋佐吉(「庄吉」の誤り)・万年屋主人(古郡平兵衛)・高木梧庵・崋山・小園村の大川清蔵の9人。座の真ん中(万年屋主人の前)には、大きな魚やお刺身のようなものが置かれた台か敷布のようなものが畳にじかに置かれています。崋山は、「吸もの(小鯛) さしミ 鉢肴(年魚) 鉢肴(アイナメ)」「平(アンカケトウフ) 平(湯ドウフ)」と、この宴会で出された料理をメモしています。「平(アンカケトウフ)」と「平(湯ドウフ)」は、唐沢蘭斎と内田屋佐吉が注文して差し入れたもの。「客舎酔舞図」に描かれた料理は、万年屋主人が出した宴会料理であり、まぐろか何か大きな魚をお刺身にしたものと、鮎やアイナメの焼き魚(鉢皿に並べたもの)であったようです。描かれてはいませんが、もちろんご飯(お椀)や酒(銚子やおちょこ)も出されていたことでしょう。この夜、目薬屋常蔵と唐沢蘭斎の娘(12歳)は三味線を弾き、内田屋庄吉は富士田仙蔵という者に習ったという長唄(ながうた)を歌い、高木梧庵と唐沢蘭斎は酔って踊り、そして崋山自身もまた扇を持って舞い踊りました。「夜明るまで歌ひつ舞(まい)つ、予をなぐさむ」「人々笑フ」と崋山は記しています。おそらくこの夜は、難しい話などは抜きにして、三味線や長唄を楽しみ、それに合わせての踊りや舞いをみんなで楽しんだのでしょう。小園村の清蔵は、膝頭を露わにして正座し、かしこまりながらこの風流人たちの宴会を物珍しげに眺め、楽しんでいたことでしょう。この「客舎酔舞図」においても、崋山はすでに「酔臥」しています。小園村を訪ねて「お銀さま」に25年ぶりに会えた、実り多い長い一日の疲れもどっと出てきたに違いない。「お銀さま」の消息を知るという任務を果たした開放感もあったことでしょう。心地よい疲れの中で、いつのまにか崋山はそのまま寝入ってしまい、清蔵を除いて他の客たちが帰って行ったこともまったく知りませんでした。 . . . 本文を読む
斎藤利鐘(鐘助)は、崋山に、厚木は今は愛甲郡に属しているが、文禄慶長の頃は中郡に属していたことや、今は「アイコウ」と呼ぶけれども、昔は「アカ」と称していたのを、今は「ナカ」と誤っているのだといったことを語っています。厚木について、さらに崋山は詳しく記していますが、これも斎藤利鐘から聞いたことだろうか、それとも唐沢蘭斎から聞いたことだろうか。その内容は以下の通り。「厚木村は、東は相模川が境となっており、西は恩名村、北は金田村、南は岡田村と境を接している。およそ縦二十町余、横は三十町余。烏山藩の分領であり納める年貢は1800石余。陣屋は牛頭天王社のそばにある。年4回役人が交代している。烏山藩領に属している村は、用田・中野・岡田・厚木・半原・田名・大島・片瀬・腰越・鎌倉・山崎などおよそ36ヶ村で、おおよそ1万石。烏山藩の支配は過酷であり、人々はみな怨みや怒りを抱いているようだ。最近、糠(ぬか)や干鰯(ほしか)などの仲買人10家を決めて運上金を取るようになり、また御用金を命じて人々から絞り取っている。一挙に2000両を差し出したのは厚木村のみである。大変な負担であるが、それだけの御用金を差し出すことが出来たということは、厚木村の経済力を示すものでもある。厚木の豪商は溝呂木彦右衛門(「孫右衛門」の誤り)と高部満兵衛(「源兵衛」の誤り)。二人とも呉服をもともとの生業(なりわい)としている。相模川の渡船料も少なくはなく、それはみな溝呂木家に納められているという。烏山藩の分領で富豪第一は栗原村の大谷弥市という者でおよそ18万両の財産があるとのこと。是に次ぐ者は用田村の伊東彦右衛門、一ノ宮の日野屋新太郎であるとのこと。」 崋山は斎藤利鐘と唐沢蘭斎の二人は頗る学問があり、この二人に匹敵するような者は他にはいないと記しています。厚木村や烏山藩政について崋山に詳しく語ることができたのは、宴会に集まって来た者の中では、斎藤利鐘と唐沢蘭斎二人だけであり、特に烏山藩政に対して批判的であったのは唐沢蘭斎であったことを考えれば、烏山藩による運上金や御用金の取り立てのことについて崋山に語ったのは、唐沢蘭斎ではなかったかと考えられます。 . . . 本文を読む
崋山の『游相日記』の厚木宿のところで出てくる人物たちが住んでいた場所や営んでいた店の場所については、金子勤さんの『大山道今昔 渡辺崋山の「游相日記』から』(神奈川新聞社)に詳しい。「江戸時代の厚木宿大山道の見取図」というもので、P210~211に掲載されています。厚木の渡船場近くに住む溝呂木孫右衛門は、渡船権(渡船料の半分を取る)を持つ厚木の旧家で溝呂木の総本家。呉服の他に塩や肥料(干鰯〔ほしか〕)も商っていました。烏山藩(からすやま)大久保氏より三十人扶持を与えられ、苗字帯刀を許されて役人格に取り立てられていました。屋号は「山九」。溝呂木宗兵衛(金物屋宗兵衛)は「山九溝呂木」の分家で通称「金物角九」と呼ばれていました。崋山が宿泊させてもらおうと、小林蓮堂の紹介状を持って訪ねたところが、乞食絵師がやってきたと思われてすげなく扱われたところ。街道の西側に店があったようです。高部源兵衛は天王町東側に間口八間の呉服・太物の店を開いていた厚木宿でも屈指の豪商。崋山が描いた厚木上町の商店図は、鈴村茂さんの『厚木の商人』によるとこの高部源兵衛の店ではないかとのこと。内田屋庄吉は、万年屋の真向いで筆墨紙などを商い「紙内田」または「ヤマ久」と呼ばれていました。駿河屋彦八は大住郡酒井村の名主で、博奕(ばくち)の親分。厚木村の下宿を中心として多くの子分を持っていました。本姓は「石井」。中宿に二号を置いて「駿河屋」という料理屋を営んでいたという。この見取図に記載されている「駿河屋」とは、その料理屋のこと。現在の旧街道と小田急線が交わるあたりにそのお店はあったようです。斎藤鐘助(かねすけ)もこのあたりに住んでいました。崋山に「厚木六勝」の絵を描いてくれるように依頼した人物。長男七三郎は初代の厚木町長になりました。唐沢蘭斎は武蔵国二宮(現在の東京都あきるの市)出身の人で医者。12歳の娘は三味線が得意でした。この見取図には「厚木六勝」も示されています。鐘助と蘭斎が崋山を誘って万年屋から向かったところは「桐辺堤」で、その箇所には「桐堤賞月」と記されています。ここからは「厚木六勝」がパノラマのように一望することができ、『厚木街道いまむかし』の大矢邦夫さんによると、「厚木六勝」の構図はこの桐辺堤の付近から厚木の町方、つまり北の方を眺めてまとめたものではないかとのことです。 . . . 本文を読む
フェリーチェ・ベアトの幕末期の厚木宿を写した古写真については、鈴村茂さんの『厚木の商人』が詳しい。それによれば、この写真は南から北を向かって写したもので、前方の樹木は天王社(現在の厚木神社)の森ではなく、東町北方の堤防の西にある稲荷社の樹木。この稲荷社は、角にあった内田勘兵衛家とその付近の稲荷講中が祀ったもの。渡船場があった頃には、河原からこの稲荷社の前を回って宿の北端に入ったとのこと。道路中央に写されている用水路は「前堀」と言われ、厚木用水を横町(現在の元町)の西端から取り、横町の町並み東側の家の前を通し、上町(現在の東町)で大通り(大山街道)中央を通して町並みに沿って南に流れ、下町(現在の旭町)の最勝寺南で右折して厚木用水に流入していました。「火の見やぐら」の下の石灯籠は秋葉様の石灯籠。毎夜点火して横町に曲がる人々の足元を照らしたとのこと。その石灯籠の周辺には多数の馬がたむろしているが、それは人馬継立用の馬であり、厚木宿では常時25頭の馬が用意されていたという。写されたのは、日影から考えて午後になってから。場所は、現在の東町の伊藤荒物店の前あたりであると鈴村さんは推測しています。中央やや右側にある店には「江州彦根 生製牛肉漬」「江州肉」「薬種」の看板があり、この店は酒を主体に、牛肉や薬を商う店であったらしいと鈴村さんは指摘してます。つまりこの写真は、フェリーチェ・ベアトが、幕末のある日の午後に大山街道上から北に向かって厚木宿の上宿を写したもの。後のページに宮ケ瀬村の古写真が出てくることを考えれば、横浜から避暑地である宮ケ瀬村へ馬に乗って赴く途中に撮影したものではないかと考えられます。 . . . 本文を読む
厚木宿の繁栄が「相模川ノ利」すなわちその舟運に由来することを指摘した崋山は、その相模川の甚だしい「害」、すなわち水害の深刻さについてもしっかりと触れています。4、50年ほど前の天明三年(1783年)の頃、雨が連日降り続いて相模川が氾濫し、水没した田んぼや流失した人家が数え切れないほどの大水害が発生したことがありました。幸いに一気に押し寄せた氾濫ではなかったので、溺死者は生まれなかったというが、記憶に残る大水害であったらしい。文政年間の初め、烏山藩によって治水工事が展開され、莫大な経費をかけて10里(約40km)ほどの新しい堤防がわずか1年で完成しました。その翌年に長雨が続いたことがあったが、人々は完成した立派な堤があるので安心しきっていました。ところが、その新しい堤はしっかりと固められていなかったために、激しい濁流によってたちまち決壊。濁流は人家を押し流し、溺死者が多数発生しました。田んぼもまたその氾濫のために荒れ果ててしまったものが多かったという。以上のことを崋山は誰から聞いたのだろうか。そのすぐ後の記述から、これはどうも医者の唐沢蘭斎から聞いたことであるらしいことがわかります。唐沢蘭斎は、烏山藩による治水工事のやり方に対して強い不満を持っていました。相模川の新堤が決壊した後、村人たちは協力してその補強工事をしたのですが、その堅固さは藩によって行ったものよりもずっとしっかりしたものでした。蘭斎は、もし藩が村長に資金を与え、村人たちに堤の新築をやらせていたなら、大水害は発生しなかったばかりか、それにかけた莫大な費用も半分に済んだはずだと崋山に話しています。鈴村茂さんの『厚木の商人(県央商業史)』(神奈川情報社)によれば、厚木宿は相模川の自然堤防上に構成された集落であり、その自然堤防は、厚木・岡田・酒井・戸田を経て平塚近くまで延びていました。その自然堤防の西側は相模川によって出来た沖積平野であり、水田地帯が広がっていました。相模川の堤防が決壊すれば、自然堤防上の集落が流失し、そしてまたその西側の広大な水田が洪水に覆われて多大な被害が生じることになりました。このあたりを治める烏山藩としても、相模川の治水には無関心ではいられなかったのです。 . . . 本文を読む
鈴村茂さんの『道しるべを追って 厚木の街道』(県央史談会 厚木支部)という本がある。それによれば厚木市内を通っている街道としては、①矢倉沢往還(大山街道)②八王子道③津久井道④大山道⑤甲州道⑥丹沢山道⑦巡見道⑧丹沢御林(おはやし)道などを挙げることができます。「八王子道」というのは、平塚-岡田村-厚木村-上依知村-当麻村-八王子のルートであり、崋山が「平塚道」とした街道。「津久井道」は、「中依知村-三増(みませ)峠-長竹村というルート。「大山道」は、上依知村-川入村-荻野村-岡津古久村-西富岡村というルート。「甲州道」は、岡田村-厚木村-妻田村-荻野村-半原村-長竹村というルートで、『新編相模国風土記稿』の厚木の「渡船場ノ図」では、小鮎川に沿って延びていた土手道がそれにあたります。おそらく半原村の鍛冶屋で猟師でもあった孫兵衛が歩いた道。「丹沢山道」というのは、厚木村-飯山村-煤ヶ谷村-丹沢山中というもので、「丹沢御林(おはやし)道」といって江川代官所手代の山見廻りのルートでもありました。「巡見道」とは、石田村-愛甲村-下荻野村-甲州道-田代村-三増村(津久井道)というルートで、幕府の巡見使が見廻りをする道でした。崋山は、「矢倉沢往還」「平塚道(八王子道)」「甲州道」と三つの主要道路を挙げていましたが、それ以外にも厚木を通過したり、厚木を始点とする街道があったわけで、水上交通(相模川水運)の拠点であるとともに陸上交通の拠点でもあったことがよくわかります。厚木周辺地域の農村からの年貢米は、この厚木の河岸場から船(高瀬船)に積み込まれ、須賀湊で積み替えられて、海路江戸へと運ばれたものと思われます。 . . . 本文を読む
崋山は、厚木が繁盛している理由として、相模川水運の拠点であることと陸上交通の拠点であることの二つを挙げています。相模川水運について崋山が記しているところについてはすでに触れました。では、陸上交通の拠点である点についてはどのように記しているだろうか。原文は次の通り。「凡地過客多モノハ、八王子ヨリ(八王子布帛紬絹ヲ出盛)ハ平塚道、江戸ヨリハ大山、矢倉沢、信ノ諏訪、甲州、荻野、諸道、故ニ客舎モ又盛ナリ。酒肴ノ便、居ナガラニシテ八珍ヲ可致。」 八王子から平塚の間を「平塚道」が走っていて、それが厚木を通っていること。江戸からは大山道(矢倉沢往還)が延びていて、やはり厚木を通っていること。信州の下諏訪から甲州街道・津久井街道を経由して、半原・荻野方面から厚木へと入ってくる道があること。この三つの道の結節点であることから、厚木宿の旅籠は多数の旅客で賑わっており、酒肴一つをとってみても山海の珍味がいながらにして味わえるところであることを崋山は記しています。このうち厚木から甲州方面へと延びていく道については、『新編相模国風土記稿』の厚木の「渡船場ノ図」において、小鮎川に沿って延びているあの土手道がそうであったわけですが、この道は地元においては「甲州道」(甲州へと延びている道)と言われており、荻野→半原→三ヶ木などを経由して甲州街道の与瀬宿へ合流していました(途中で、道志川沿いに甲州へと入って行く道〔道志みち〕もありました)。崋山が荏田宿で出会った半原村の孫兵衛は、この「甲州道」を利用して半原村から厚木へ出て、それから大山街道を江戸へと向かっていく途中であったのでしょう。 . . . 本文を読む
相模川の、厚木河岸より上流に目を転じて見たい。手元に『津久井の古地図』という冊子がありますが、それによると津久井の太井村には幕府が設けた荒川番所がありました。津久井街道が相模川を渡る地点に「荒川の渡し」があり、その街道の脇に荒川番所(代官所の出先機関)があったのです。この荒川番所は、主に相模川を船や筏(いかだ)で運ばれる炭・薪(まき)・材木・板などり品物へ、金額の五分一の運上金(雑税)を課し、荷主から徴収した役所であり、寛文4年(1664年)頃に設けられ、明治6年(1873年)まで置かれました。太井村は相模川と津久井街道(往還)の交差する地点に位置し、物資流通や交通の拠点でした。太井村荒川に住んでいた角田(つのだ)六郎兵衛家の屋敷図を見てみると、左の石垣の脇には薪置場や炭置場が描かれており、これは同家が薪や炭を扱っていたためと思われる、と同書には記されています。また塩店と注記された建物もあり、塩も販売していたようである、とも記されています。江戸時代の津久井地方は、「実際は豊富な林産品に支えられ、活発に商業活動をするような農民が住んだところ」であり、「商取引を通じて外の世界と密接に結びつい」ていたのです。炭・薪・材木・板・塩・その他の日用品などが相模川の水運によって運ばれ、その商取引によって「外の世界」と密接に結びついていたということですが、その「外の世界」とは、上流の甲州や信州であり、下流の厚木河岸や須賀湊、そして大消費地の江戸や房総半島であったでしょう。 . . . 本文を読む