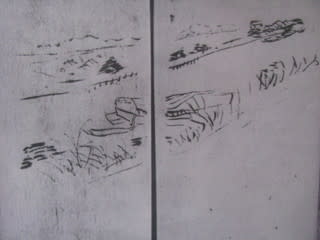第5図は、大きな川に架かる長い木橋と、その橋の左側の土手筋にある家並みが描かれたもの。よく見ると左詰(おそらく南詰)の西側土手には、頂きに木の板状のものが何本も突き立った盛り土のようなものがあり、その左奥にはお寺の山門のようなものとお寺の本堂のようなものなどが建っています。その日の行程から考えれば、この幅の広い大きな川は豊川であり、赤坂宿・御油方面から東海道を歩いて豊川を渡る長い橋と言えば吉田大橋であるということになります。吉田大橋の左側に描かれた道が東海道であり、この吉田大橋を渡ると、すぐに左折して川沿いをしばらく歩くことになります(そのまま東海道を進めば御油宿や赤坂宿、藤川宿を経て岡崎城下へ至ります)。従ってここは藤川宿方面から東海道を歩いてくれば、豊川に架かる吉田大橋を渡り切ったところ(南詰)ということになり、豊川の土手沿いを中心にあった吉田船町の家並みと、川幅の広い豊川に架かる吉田大橋、およびその川向こうに見える本宮山の山並みを描いた絵であるということになります。では吉田大橋の南詰からやや西側(豊川の下流側)へ入ったところにあるお寺はどこかと言えば、それは浄土宗の橋本山龍運寺であるということになり、この絵の左端に描かれた建物は、龍運寺の山門や本堂などであるということになります。かつて吉田大橋南詰の西側の土手上には、板状のものが何本もその頂きに突き立った盛り土のようなものがあったことが、崋山の絵からわかるのですが、これが一体何であったのかは今のところよくわかりません。 . . . 本文を読む
「本宮山」「小吉田」と記されている風景スケッチは、どのあたりからの風景を描いたものだろうか。「本宮山」というのは、東三河で一番高い山で標高789m。三河国一宮の砥鹿(とが)神社の奥宮として東三河の人々の信仰の対象でした。「三河富士」の名前で呼ばれることもあり、歩いているといろいろなところから見える山です。崋山は吉良吉田から藤川宿を経て吉田(豊橋)に至る道中で、各所からこの本宮山を、北方向に望見しているはずです。この風景スケッチの左端の下には小さな橋と人家があり、東海道はその橋から右側画面下へと延びているようです。その向こうは山の麓まで田園が広がり、その広がりの向こうに本宮山がそびえています。赤坂宿、御油宿を出て豊川に架かる吉田大橋に至るまでの沿道風景であることは確かです。本宮山全体が北方向に大きく見えてくるのは、現在の「白鳥跨線橋」(名鉄名古屋本線を国道1号が越える橋)のあたりから。「白鳥5西」交差点から国道1号から県道496号が分岐しますが、これが旧東海道。そこから豊川に至る前にある川は佐奈川、善光寺川、豊川放水路。豊川放水路は新しく造られた川であるから、佐奈川か善光寺川が、この風景スケッチに描かれた橋の下を流れる川であるかもしれない。「小吉田」というのは、どこかわからない。御油宿と吉田宿の中間には「伊奈村立場茶屋」(加藤家・俗称「茶屋本陣」)があり、そこは現在「伊奈町茶屋」という地名になっています。またもう少し豊川寄りに「宿」という地名もあります。おおよその推測としては、佐奈川から善光寺川あたりまでの東海道から、広々とした水田の向こう側に見える本宮山を描いたもの、と言うことができると思います。 . . . 本文を読む
「長沢」、「萩」と記してある風景スケッチはどのあたりを描いたものだろうか。岡崎市から豊川市に入ると、北方向に京ケ峰という山があり、その南麓が長沢町で、その長沢町の東側に萩町があります。このスケッチに描かれる中央やや左側の山は京ケ峰であり、右側奥に描かれる山は額堂山であるかも知れない。中央の丘の向こう側には東海道と宿場らしきものが描かれており、その丘の両側にその家並みが続いていることがわかります。高札場のようなものも描かれており、この宿場らしき家並みは、位置的に見て赤坂宿ではないかと絞られてきます。この絵で最大のポイントとなるのは、中央の小山の頂きに建てられている四角い石碑のようなもの。私は赤坂宿でそのような場所を探してみましたが見つけることはできませんでした。ただ気になったのは、関川神社(かつては弁財天)の境内にあった芭蕉句碑で、現在のものは明治になって再建されたものですが、旧碑は宝暦元年(1751年)に建立されたものであるという。崋山は、伊良湖村でも藤川宿でも芭蕉の句碑に立ち寄っており、芭蕉の俳句や芭蕉句碑については若い時から関心を持っていました。このスケッチに描かれた石碑のある小山は、東海道の南側にあり、崋山はこのスケッチをその小山の南側から北(北々西)方向を眺めて描いています。つまり東海道からわざわざ外れた地点から、石碑のある小山を中心に赤坂宿らしき家並みを描いているわけで、そこまでわざわざ寄り道をしたというからには、よほどこの石碑に関心を持っていたと言わなければなりません。つまりこの小山の頂きにある石碑は、宝暦年間に建てられたという芭蕉句碑ではないか、という推測が成り立ってきます。しかし現在の関川神社境内には、そのような小山はありません。旧碑は別のところに立っていたのではないか。それは赤坂宿を見下ろし、遠く京ケ峰や額堂山などを見晴るかすことができる小高い丘の上にあり(もし私の推測が正しければ)、その場所を崋山はスケッチしたのではないか。では現在の石碑、そして旧碑に刻まれている芭蕉の句とは何かと言えば、「夏の月 御油より出でて 赤坂や」でした。芭蕉が詠んだ句の「夏の月」が見える赤坂宿の高台に、赤坂宿およびその周辺の俳諧仲間が宝暦元年(1751年)に建てた芭蕉句碑(旧碑)を、崋山は赤坂宿とともに描いたのではないか、と私は考えています。 . . . 本文を読む
八ツ面山から藤川宿に至るまでの吉良道沿道の風景スケッチはどのあたりを描いたものだろうか。八ツ面山から「高須北」交差点あたりまでは、沿道に崋山のスケッチに見るような右へとせり上がっていくような山(丘陵)はなく、上地町あたりからようやく行く手前方に丘陵のような山が見えてきました。吉良道は「総合学習センター前」で団地の中を右折し、その丘陵の中の峠道を越えて馬頭や「下北野尻」交差点へと至るのですが、その峠道へと入って行く手前の風景が、崋山の風景スケッチに似ていると思われました。現在は吉良道は直線道路となっており、その両側は住宅団地になっています。ここの峠道は、かつては塩俵や米俵などを背に載せた馬が往来した道であったでしょう。このあたりがそうだと断言はできませんが、可能性の高いところだと思いました。崋山がなぜこの風景に興趣を感じてスケッチしたのかは、現在の風景からはよくわかりませんでした。 . . . 本文を読む
八ツ面山あたりから藤川宿を経て吉田宿(現豊橋市)に至るまでの道筋で崋山が描いた風景スケッチ5図のうち、第2図である、右端に石垣と木戸らしきものが描かれた図の場所は、今回実際に歩いてみて、比較的すぐに分かりました。これは東海道藤川宿の「棒鼻」を描いたもの。藤川宿の「棒鼻」は、「西棒鼻」と「東棒鼻」がありましたが、これは右端の家並み奥に見える小山から、「東棒鼻」(江戸側)を描いたものであることがわかります。藤川宿の「東棒鼻」を出てしばらくのところから、振り返って描いたもの。「宿囲石垣」(しゅくがこいいしがき)のある部分が「棒鼻」であり、この奥に見える家並みが藤川宿。この少し先で東海道は右へと直角に曲がり、しばらく進んで左へと直角に曲がります。中央の茅葺きの大きな家は、宿場入口にあったという茶屋であるのかも知れない。これが藤川宿の東棒鼻を描いたものであるとなると、第1図の風景画は、おそらく八ツ面山あたりから藤川宿までの沿道(吉良道)のどこかの風景を描いたものと推測が成り立ってきます。 . . . 本文を読む
西尾城下に崋山一行は宿泊したらしい、という推測を私はしています。その推測から考えると、芸妓3人を描いた絵は西尾城下の旅籠での情景であるということになります。つまり崋山一行は旅籠に芸妓3人を呼んで宴会をし、その時に興に乗って芸妓を描いたものであり、この絵は西尾城下の旅籠で描かれたもの、ということになります。その当否はさておいて、八ツ面山あたりから東海道藤川宿を経て吉田宿(現豊橋市)に至るまでに、崋山は風景画を5図描いています。第1図は、左手前に道がカーブしながら奥へと延び、集落へと入っています。その集落の背後から右側にかけて樹木の繁った丘陵が連なっています。第2図は、真ん中に人家があり、その人家の連なりが右端奥へと続いています。その集落の入口には両側に石垣を伴った木戸のようなものがあります。第3図は、上に「長沢」・「萩」と記され、手前の小山のてっぺんに四角い石碑のようなものがあり、その小山の右手下に街道とその街道両側に連なる人家が描かれています。お堂や高札のような施設も描かれています。第4図は、「本宮山」・「小吉田」と記されています。北方向に見える「本宮山」を描いたもの。左下の人家があるところに「小吉田」と記されています。第5図は、川に架かる長い橋と、その手前(左側)の人家の集まりとお寺のような建物を描いたもの。それぞれ道筋のどこからの風景を描いたものなのかが考察の対象となります。 . . . 本文を読む
八ツ面山は男山(標高67.4m)と女山(標高39m)からなり、男山では古くから「雲母」(うんも、きら、きららとも読む)の採掘が盛んに行われ、かつては朝廷にも献上され、また江戸時代においては西尾藩の専売品にもなっていたという。雲母を採掘した坑道はかつては多数あったが、事故等により、現在は一本だけが保存されているとのこと。久麻久神社には立ち寄りましたが、その雲母坑は山の上の方にあったのかも知れません。八ツ面山は「雲母山」「吉良山」とも言われ、久麻久一族が雲母の採掘を行っていたらしい。雲母は古くは婦人病や頭痛の医薬として用いられ、江戸時代には屏風や襖の装飾材料とし使われたということですが、「雲母摺り(きらずり)」というのがあって、料紙装飾や浮世絵版画の技法の一つであったという。浮世絵版画の場合、版木に糊(のり)や膠(にかわ)をつけて紙に摺り、その上に雲母の粉をふるいかけて、乾いた後に残りの粉を払い落とすというもの。版画の技法の雲母摺りは、金粉や銀粉をまぶしたようなきれいな背景が表現でき、写楽や歌麿を特徴づけるものであるとのこと。崋山も、この「雲母摺り」については画家として当然知っていたものと思われます。その雲母が西尾藩の専売品であり、八ツ面山はその産出地であり、また「吉良」の地名は「雲母」(きら、きらら)から来ているということも知った可能性は十分にあるのですが、日記には、「八面」の山のスケッチはあっても、雲母に関する記述は何もありません。この西尾藩の専売品(特産物)である雲母は、平坂道(へいさかみち)を平坂湊へと運ばれ、そこから船で江戸へと運ばれたと思われますが、その流通等については今のところよくわかりません。 . . . 本文を読む
「吉良道」は、吉田~萩原~雑役免~上横須賀~木田~寺嶋~黄金堤~善明~駒場~貝吹~高須北~上地~馬頭~蓑川~藤川というコース。一方「平坂道」(へいさかみち)は、平坂~熊味~江原橋~駒場~平原~須美~桐山~深溝~蒲郡というコース。「吉良道」と「平坂道」は駒場で交差することになります。「平坂道」の終点は平坂湊であり、ここは西三河各藩の年貢米の積み出し港でした。また平坂湊は木綿の積み出し港でもありました。平坂廻船や高浜廻船は田原藩の廻米御用を行っていたから、平坂の廻船問屋や高浜の廻船問屋は、田原藩と深い関係があったものと思われます。また三河国から江戸への木綿は、平坂湊からの積船しか認められておらず、それ以外は白子に回送し、白子から江戸に送られたという(以上、「十八世紀の平坂湊・大浜湊と三河の廻船」曲田浩和〔『愛知県史研究 第9号』所収〕による)から、平坂湊は年貢米および木綿の積み出し港として極めて重要な港であったことがわかります。「八ツ面山」は、この平坂道の熊味と江原の間の北側に位置し、崋山が描いた「八面」というスケッチにおける山の形状により、崋山が八ツ面山南側の平坂道を歩いたことは確実であり、なぜ、崋山一行が吉良道から西へと外れて、八ツ面山の南側を通過した(遠回りした)のか、その理由はよくわかりません。『三河の街道と宿場』大林淳男・日下英之(郷土出版社)によれば、この八ツ面山では雲母(きらら)が採掘されており、それは西尾藩の専売品であったという。「吉良」は「雲母の庄」から来ているらしいことは、前に触れたことがあります。西尾城下から東海道藤川宿まではおよそ五里の道程。5時間はかかることになり、八ツ面山付近を午後5時頃に通過したとすれば、ここから藤川宿へ向かうことは断念せざるを得なかったでしょう。 . . . 本文を読む
華蔵寺のある岡山と茶臼山、そして横須賀畷(なわて)をまとめて描いた風景画(素描画)の次に出てくるお寺(?)の門前と思われる町のスケッチがどこのものであるか、今のところ私には確定できていません。もしかしたらお城の門前であるのかも知れない。このあたりの近くにあるお城と言えば、西尾城ということになります。となると、崋山は今まで歩いて来た吉良(きら)道を外れて、西尾城下に足を踏み入れたということも考えられます。次のスケッチは「八面」と記されているように「八ツ面(やつおもて)山」を描いたもの。八面山がこのように見える場所はというと、現在の「八ツ面南」交差点のあたりであり、ここは岡崎へと至る県道319号と、安城と蒲郡を結ぶ県道43号が交差するところ。この県道43号はこのあたりでは「平坂道」と重なっており、華蔵寺を出た崋山は吉良道を北進して駒場で左折して平坂道へと入り、八ツ面山の南側を通過した可能性が出て来ます。この道をさらに西へ進むと西尾城下に入ることになり、行程的なことから考えると藤川宿へその日の明るいうちに至ることは困難であり、西尾城下で崋山一行が宿泊した可能性も出てきます。華蔵寺を出た後、吉良道をたどってそのまま藤川宿へ至ったのではないということが、この八ツ面山のスケッチから断定することができるのです。 . . . 本文を読む
吉良上野介義央(よしひさ)が領内巡回の際に乗ったとされる馬は「吉良の赤馬」と言われて郷土玩具にもなっているのですが、農耕用の赤毛の馬であったらしい。吉良地方は「饗庭塩」の生産地であり、この塩は岡崎に運ばれて八丁味噌(はっちょうみそ)に使われたり、中馬(ちゅうま)街道を経て信州に運ばれて漬物に使われたりしました。この塩はどのように運ばれたのかを考えると、馬で運ばれたり、船で運ばれたりしたものと思われます。矢崎川筋の吉田湊には馬で塩が運ばれてきて、船に積載されて各地に運ばれたであろうし、吉良道は馬による塩の運送に使われたものと考えられます。また田んぼで生産された米についても、船や馬が利用されたはずですが、「饗庭塩」の運送面のことや流通面のことは、今のところ私にはよくわかっていません。矢作(やはぎ)川は信州へと物資が運ばれる際に、また信州から物資が運ばれる際に利用された河川であり、中馬街道は、陸路、それらの物資を馬で運ぶ際に利用された街道でした。足助(あすけ)の塩問屋では、「饗庭塩」と瀬戸内海産の塩が混ぜ合わせられ、「足助塩」として信州地方や周辺各地で流通したということですが、そのあたりについても具体的に知りたいと思っています。 . . . 本文を読む
崋山のスケッチには、「東山正緒南甫的流 帝網窟 沙羅樹下八十二歳老網書 慧鶴 白隠」と記されています。また和尚像が描かれていますが、これは頭注によると、華蔵寺開山の月船和尚の像であるということであり、肖像画(頂相)を見て崋山が写し取ったものと考えられます。「白隠」(白隠慧鶴)については、頭注に「江戸時代中期の禅僧、三島竜沢寺開山」と記されています。またもう一枚のスケッチには「華蔵世界 三岳」と記されています。頭注によると、これは華蔵寺中門の扁額であり、「華蔵世界」とは「蓮華蔵世界」の略であるとのこと。「三岳」とは、江戸時代中期の南画家池大雅の号であるという。崋山がこの扁額と題額をわざわざ写し取ったのは、一方に「三岳」と記され、一方に「白隠慧鶴」と記されていた(つまり扁額は池大雅が書いたもので、題額は白隠が書いたもの)からであるでしょう。白隠慧鶴(はくいんえかく・1686~1769)は臨済宗中興の祖といわれる禅僧であり、「達磨図」など禅画をよくした人物。池大雅(1723~1776)は与謝蕪村とともに文人画(南画)の大成者とされる人物。崋山はその二人とも、絵を通してよく知っていたものと思われます。 . . . 本文を読む
崋山のスケッチのように、茶臼山と華蔵寺のある岡山と、その手前にある横須賀畷が、このような位置合いで見える場所はあるかというと、直線道路をやや外れたところや華蔵寺前の道(岡山の南麓を通っている道)を歩いて確かめてみましたが、そういう場所はありませんでした。「華蔵寺」と記されているあたりの小高い山が「岡山」であり、その背後に聳え立っている山が「茶臼山」ですが、実際は「茶臼山」はこれほど大きく聳え立ってはおらず、「岡山」の背後ではなく、「岡山」のやや右側、奥の方になだらかな稜線を見せている山です。スケッチのように「岡山」と「茶臼山」は重なってはおらず、左と右に並んでいます(茶臼山は東方向やや離れたところにあり、標高は291mの山)。岡山は標高としては50m(私の目視による推測)ほどの低い山です。従ってこのスケッチは、「真景画」ではなく、茶臼山と、華蔵寺のある岡山と、その南方に広がる田んぼ、そしてその田んぼの中を走る横須賀畷を、一つにまとめて描き込んだもの、と推定することができます。実際その場所で描いたというよりも、あとで風景を思い出して描いたものであるのかも知れません。崋山のスケッチ(風景画)には、ままそういうものがあることをおさえておく必要があることを教えてくれる一枚です。 . . . 本文を読む
『渡辺崋山集 第2巻』のP283には、崋山のスケッチである「(五輪塔)華蔵寺殿円山成公大居士」が掲載されています。頭注によれば、これは「東条吉良持広の養子高安。永禄一二年駿河藪田村(藤枝市)で死去、墓は華蔵寺(吉良町岡山)」とあって、この五輪塔は東条吉良義安のお墓であり、その所在地は吉良の岡山にある華蔵寺であることがわかります。これをスケッチしたということは、崋山がこの華蔵寺に立ち寄り、このお墓(五輪塔)の前に立ったことを示しています。このお墓(五輪塔)が現在でも残っているのか、華蔵寺のどのあたりにあるのか、そのまわりはどうなっているのか、といったことに興味をそそられました。この華蔵寺には吉良氏代々のお墓があるということを聞いており、あの赤穂浪士で知られる吉良上野介義央(よしひさ・元禄15年=1702年に殺害される)のお墓は、どういうものなのかと言ったことも気になりました。なぜ、崋山は有名な吉良義央のお墓をスケッチせずに、それ以前の吉良義安(永禄12年=1569年没)のお墓をスケッチしたのかも気になるところです。 . . . 本文を読む
幡豆海岸の矢崎川河口を少し入った吉田湊と佐久島との、船による人や物の往来は活発であったと思われますが、それについての具体的なことが記された資料は見つかりませんでした。幡豆海岸から佐久島は目と鼻の先であり、幡豆海岸から見れば、三河湾の中央に横長に浮かんでいる島です。矢作(やはぎ)川河口部の平坂湊や大浜湊、また渥美半島の古田湊(崋山一行はそこから船で佐久島へと向かいました)とも船の往来が活発にあったはずですが、それに関する資料も見つけることはできませんでした。「十八世紀の平坂湊・大浜湊と三河の廻船」曲田浩和(『愛知県史研究 第9号』所収)には、「田原藩の廻米は、高浜船・平坂船が請け負う以前は、篠島・佐久島の船が行っていることがわかって」いる、という記述がありました。ということは、佐久島の弁財船は田原藩の年貢米を江戸に運んでいたことがあったということであり、田原藩と佐久島とは全く無縁ではなかったことになります。田原藩の年貢米はどのように運ばれたのか。先ほどの記述によれば、高浜船や平坂船が請け負っていたということになりますが、その実態については今のところ、私にはよくわかっていません。 . . . 本文を読む
崋山の「塩」に関する記述は、「正念寺、塩神祖コノハタノ故事」と「塩ハ一反にて廿両ほどアガル」の記述だけ。「正念寺」は佐久島(東村)の浄土宗のお寺で、佐久島には古代の塩田遺跡があり、塩の生産が行われていたことがありました。崋山が訪れた天保年間に塩作りが行われていたかどうかはわからない。吉良地方の幡豆海岸では、江戸時代から昭和期(昭和40年代)まで「饗庭塩」と言われる塩が生産されており(矢崎川河口部西側の「本浜塩田跡地碑」に見られるように)、その「饗庭塩」は岡崎の八丁味噌製造や信州の漬物生産に使われていました。崋山が記す「塩ハ一反にて廿両ほどアガル」とは、おそらく吉良地方の「饗庭塩」について触れているものと思われ、吉良あたりにおいて土地の誰かからその情報を得たものと思われます。崋山が「塩」という吉良地方の特産物(「一反にて廿両ほどアガル」)に関心を寄せたことは確かなことであるでしょう。 . . . 本文を読む