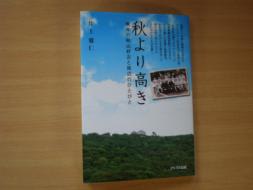子どもの頃の記憶も交えながら、あれこれと書いてみます。よって多少の誤りがあるかも知れ
ませんので、ご了承ください。


松山城は小高い山の上にあります。山の名前は「勝山」ですが、松山人はこの山を「城山」、
あるいは親しみを込めて「お城山」と呼んでいます。
松山城は別名「勝山城」、時には「金亀(きんき)城」といいます。金亀城のいわれは、かつて
二の丸付近の池に金の亀が住んでいたという伝説に由来しています。城は、豊臣秀吉の家臣、
賤ケ岳の七本槍の一人「加藤嘉明」が築城、その後落雷で焼失しますが、江戸時代に復元され、
江戸時代から現存する数少ない木造の城として貴重な存在です。


加藤嘉明の後、しばらくしてから徳川の松平家(後に旧姓の久松に改姓)が藩主となり、幕末、
明治に至ります。
明治になり、城山の南麓に旧藩主久松定謨は別邸としてフランス風洋館「萬翠荘」を建てました。
「萬翠荘」、かつてはフランス料理のレストランでしたが、今は美術館になっています。
小学生のとき城山で遊んでいて、菊花展を開催中の「萬翠荘」の敷地内に迷い込んだことがあ
ります。


秋山兄弟の生家には、石碑とその碑文の要約が建てられています。
父・久敬が家を建て、兄弟はここで生まれ育ったこと、兄の好古は陸軍大将を退役後ここに住み、
北豫中学(現在の松山北高校)の校長として教育に尽くしたことが記されています。
私にとっての松山北高校は、部活(バレーボール)の良きライバルチームでした。


生家は四部屋しかない、質素な作りです。


兄の好古は二十代後半、旧藩主久松定謨の依頼により陸軍を休職して、久松定謨の輔導役とし
てフランスに留学したそうです。明治になっても、旧藩主の意に従わなくてはならなかったようです。
私が子どもの頃はずっと、愛媛県知事は久松定武でした。当時大人は時々、知事のことを「お殿
さま」と言っていました。調べてみると、久松定謨の子・定武が1951年から1971年まで県知事
をしていました。
弟の真之は日露戦争の日本海海戦で、村上水軍の戦法を参考に作戦を立て、また、開戦前の
電文「本日天気晴朗ナレドモ浪高シ」を起草しています。
私の両親は瀬戸内海の島の生まれのため、たぶん祖先は村上水軍と思われます。私は小学生
時代、運動会のマイクのテストで友人と一緒に「本日天気晴朗ナレドモ浪高シ」と言ていたことを記
憶しています。これが真之の起草文であることを知ったのは、小説・坂の上の雲を読んでからです。
秋山兄弟は軍人として戦争に参加はしたものの、平和を希求していたことが小説の中でよく分か
ります。兄の好古は、人生の最初と最期を教育に携わっています。弟の真之は戦争の悲惨さに
遭遇して、「軍人を辞めたい」と言っていたそうです。
好古は幼少の頃、藩校・明教館で学んでいます。明教館は明治になって松山中学に引き継がれ、
ここで真之と友人・正岡子規は学んでいます。松山中学は現在、私の母校の松山東高校になって
います。その敷地内に、明教館の建物がいまも現存しています。私が高校生のときは、部活の大
きな大会前には明教館の畳の上に座って、高名な方の話を聞いて試合に臨んでいました。悲しい
かな、その話の中身は全く記憶に残っていません。
松山東高校の敷地内には、明治の作家・夏目漱石が歩いたという石畳もあります。そう、漱石の
小説「坊ちゃん」の学校は当時の松山中学、今の松山東高校なのです。
故郷の先人たちが苦労を苦労とも思わず明治を明るく生き、日本のある部分の第一人者として
活躍した足跡を、ほんの少しだけ辿ることができた帰省でした。