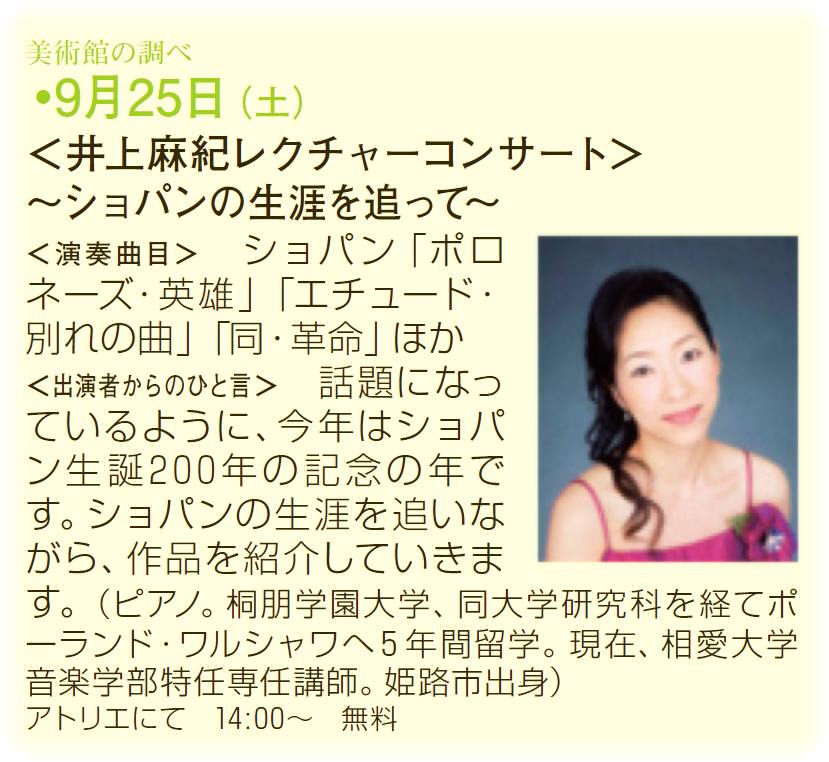街を往く(其の十一) 徳島市で賀川豊彦についての講演会を聞いて
高松、坂出市へと足をのばす
藤井新造
少し旧聞になるが、3月に鳴門市賀川豊彦記念館創立10周年の記念行事として≪賀川豊彦と友愛革命≫と題した講演会が徳島市であり、知人に誘われでかけて行った。
ここでも書いたことがあるが、人に誘われると時間があれば拒むことなく気軽に参加するのが私の習い性になっている。
今回も講演会の題名に魅力があり、賀川についての知識が少ない私は彼の業績を知るいい機会と思い誘いにのった。これも最近自分で本を読むより、人の話を聞いたり、テレビを見て理解しようと安易な気持によりかかる姿勢が一層強くなったせいである。その原因の一つとして活字を何時間も読む根気がなくなったせいかもしれない。
それはそれとして、講師の小林正弥氏(千葉大学教授)についても彼の著作を読むことなく、講演の題名にひかれて参加した。と言うのは、賀川が唱えた「友愛」について講師より何程かの知識が得られると期待したからである。
もともと、私は労働運動と生活協同組合という狭い領域のなかでの仕事しか知らず限定された範囲内での活動であり、主として「実践」で、理論書は多く読んでいない。だから賀川については、1921年当時の川崎三菱造船の争議の指導者であったこと、又神戸の貧民街でのキリスト教の伝道活動をしていたこと、それに我国の農民運動の初期の指導者であったこと、それだけでなく日本の生協活動の組織者であった――特にコープ神戸の生みの親であることをわずかの本を読んで知っていたのみであった。
個人的なことを言えば、今から約35年前に東京の中野綜合病院を訪れた時、この病院を賀川が設立したことを聞いて感心させられたことがあった。(この病院は生活協同病院として法人として、昭和の初期に設立される。)
彼の活動範囲の広さと深さに比し、何かしら彼についての評価が私の中では低かった。
このことは、『賀川豊彦』(隅谷三喜男著・岩波文庫)の本でも指摘されているので、あながち私だけでないことがわかり安堵したが、それにしても彼の著作類を読まないで、勝手に彼の業績を低く、評価していたのだから、その罪は大きい。
さて、当日の小林氏による講演の内容については長時間の話なので、当日配布された「談話」(レジメ)を少し長くなるが引用させてもらい参考にして戴くことにする。
「賀川が、このような実践的活動(『死線を越えて』の作家・小説家そして労働運動、農民運動、協同組合運動、キリスト教福音運動での活躍)に立ち上がった動機は『愛』であり、このような愛は社会的には友愛として表現されることが多いのです。友愛は自由・平等とともにフランス革命の3原理のひとつです。賀川は、この愛を基礎にして、新しい経済学や協同組合を基礎にする経済のビジョン、そして平和のビジョンを提起しました。私たちは、先人である賀川から、彼の実践やこのような理想を学ぶことができます。」
そして、「『友愛革命』は、今日の日本に求められている政治的・社会的な構造変化にとって基軸となる精神の革命を指しています。私は、これがフランス革命に匹敵する世界史的意義をもつ新しい世界を拓くものであり、それが日本において段階的に展開してゆくと考えています」としめくくっている。このことを当日1時間30分にわたり聞かされた。
講義の内容を理解するため、徳島から帰り次第、前述の隅谷さんの本を読みかえした。勿論、小林さんの文庫本にも眼を通した。
賀川の膨大な全集(24巻)を読むには、今の私には時間的にも困難であるからである。
尚、当日講演会の会場はほぼ満席で約200名の出席者があった。講演会が終り、レセプションには、徳島県知事をはじめ各界(農協、生協、全労済etc.)多方面からの参加で盛況をきわめた1日であった。
同席していた労働運動、全労済で活躍された先輩のKさんは、賀川の思想と活動の影響を受けた人、又彼の功績を讃える人が、このように沢山集まっていたことに深く感じ入っていた。
Kさんは、神戸の賀川豊彦記念館の運営に長らく携わっていた筈であったが、そのことを聞くのを忘れていた。
一昨年、日本福祉医療生協連合会(前身は日生協医療部会)によって、賀川の生涯を綴った映画が製作された。その映画が、尼崎でも上映(自主上映)されたので、映画好きの私はさっそく観に行ったが、私の感想として映画化が成功した作品とは思われなかった。
コープ神戸と賀川との関係は上述した通りであるが、このコープは三木市に同生協の役・職員の研修施設「協同学苑」を今から15年程前に設立した。私も二度宿泊した経験があるが、少し交通の便が悪い難点があるが、研修施設としては申し分ない立派な建物である。
別棟にイギリスの「生協」の発祥地である「ロッチディール公正開拓組合」の記念館を模した建物があり、イギリス・日本の「生協」運動の歴史を紹介し、賀川についての著作類も展示していて参考資料も多い。
「生協にかかわる役・職員は一度は訪問した方がいいのでないかと思う。
今日「生協」のあり方、将来について様々な厳しい意見があるが、そのことについては『世界』(2012年11月号)で特集しているので参考にされるといいと思います。
<この項、次号に続く>