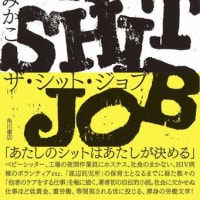大島真寿美『ピエタ』(ポプラ社、2011年)
ヴィヴァルディが孤児たちに音楽教育を施し、自分の作品を演奏させていたことで有名なピエタ慈善員院の女性たちとヴィヴァルディゆかりの人たちを主人公にした小説。
私はなぜかヴィヴァルディは1720年代からすでにヴェネチアを離れていたと思い込んでいたのだが、そうではなくて、1741年にウィーンでなくなる直前まで、ヴェネチアにいて、ピエタとかかわりがあったようだ。おそらく1711年出版の『調和の霊感』とか1725年出版の『和声と創意への試み』以降は、あまり有名なものがないので、ヴェネチアを離れてしまったと思い込んでいた。
ヴィヴァルディといえばもう『四季』というくらいに有名になってしまっているので、ヴィヴァルディは同じ曲にちょっと変化をつけて次々出しているだけというような悪罵に近いことを言う人もいるようだが、あれだけ次々と曲を生みだす創意というのはやはり大変なものなのだと思う。
この小説はヴィヴァルディ本人が直接出てくることはないけれども、彼の弟子であったピエタの女性たちを通して彼の生き方が描き出されるところが興味深い。そのなかには、1740年に神聖ローマの皇帝カール6世が死んだことに端を発するオーストリア継承戦争の話も出てくる。オーストリアやオランダにたいしてフランスが継承権を要求して戦争を仕掛けたのだが、ヴェネチアは交通の要衝として、様々な情報の集まるところとしても重視されており、ちょうどこの小説の舞台となっている時期1743年から44年にかけて、フランス大使の秘書としてルソーがヴェネチアに赴任していた。彼の『告白』にはこの戦争の渦中にあるヴェネチアでの情報戦の様子が簡単ではあるが記述されている。
またヴィヴァルディの『四季』は1725年に出版された直後から、フランスでも大変な人気で、フランスの宮廷でもよく演奏されていた。シェドヴィルが当時の流行を反映してミュゼットなどの楽器用に編曲したりしたのが有名だが、上記のルソーも「春」をフルート独奏用に編曲している。これのCDもあるから、ちょっとは知られているのかもしれない。「ルソー編曲ヴィヴァルディの春」とか難波薫「フルート・レヴォリューション」がある。
これだけ有名な作曲家なのに、伝記となると、この人が挙げている参考文献でも、1970年のマルク・パンシェルルとかロラン・ド・カンデとか、せいぜい近いところで1981年のトールバットというのは、ひどすぎないだろうか? あれからもっと研究も進んでフランスやイタリアではあれこれ文献が出ているのだから、翻訳したら、売れるとおもうけどな。
 | ピエタ |
| 大島真寿美 | |
| ポプラ社 |
私はなぜかヴィヴァルディは1720年代からすでにヴェネチアを離れていたと思い込んでいたのだが、そうではなくて、1741年にウィーンでなくなる直前まで、ヴェネチアにいて、ピエタとかかわりがあったようだ。おそらく1711年出版の『調和の霊感』とか1725年出版の『和声と創意への試み』以降は、あまり有名なものがないので、ヴェネチアを離れてしまったと思い込んでいた。
ヴィヴァルディといえばもう『四季』というくらいに有名になってしまっているので、ヴィヴァルディは同じ曲にちょっと変化をつけて次々出しているだけというような悪罵に近いことを言う人もいるようだが、あれだけ次々と曲を生みだす創意というのはやはり大変なものなのだと思う。
この小説はヴィヴァルディ本人が直接出てくることはないけれども、彼の弟子であったピエタの女性たちを通して彼の生き方が描き出されるところが興味深い。そのなかには、1740年に神聖ローマの皇帝カール6世が死んだことに端を発するオーストリア継承戦争の話も出てくる。オーストリアやオランダにたいしてフランスが継承権を要求して戦争を仕掛けたのだが、ヴェネチアは交通の要衝として、様々な情報の集まるところとしても重視されており、ちょうどこの小説の舞台となっている時期1743年から44年にかけて、フランス大使の秘書としてルソーがヴェネチアに赴任していた。彼の『告白』にはこの戦争の渦中にあるヴェネチアでの情報戦の様子が簡単ではあるが記述されている。
またヴィヴァルディの『四季』は1725年に出版された直後から、フランスでも大変な人気で、フランスの宮廷でもよく演奏されていた。シェドヴィルが当時の流行を反映してミュゼットなどの楽器用に編曲したりしたのが有名だが、上記のルソーも「春」をフルート独奏用に編曲している。これのCDもあるから、ちょっとは知られているのかもしれない。「ルソー編曲ヴィヴァルディの春」とか難波薫「フルート・レヴォリューション」がある。
これだけ有名な作曲家なのに、伝記となると、この人が挙げている参考文献でも、1970年のマルク・パンシェルルとかロラン・ド・カンデとか、せいぜい近いところで1981年のトールバットというのは、ひどすぎないだろうか? あれからもっと研究も進んでフランスやイタリアではあれこれ文献が出ているのだから、翻訳したら、売れるとおもうけどな。