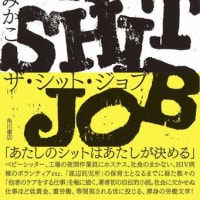アゴタ・クリストフ『第三の嘘』(早川書房、1992年)
 A「この小説、面白かった。」
A「この小説、面白かった。」
B「そう? でもじつはこれはこういうことだったんだよ。知ってた?」
A「うそ! もしそれを知っていたら、もっと面白かっただろうね。」
私はこういう会話はありだと思う。しかし、
C「あーあ、この小説、わけ分らん。ぜんぜん面白くない。」
D「そう? でもじつはこれはこういうことだったんだよ。知ってた?」
C「うそ! もしそれを知っていたら、面白かっただろうね。」
こんな会話はありえないと思う。つまりなんの説明もなしに面白く思えなかったけど、人から説明を聞いて(解説を読んで)面白くなる、なんてことはありえない。それは小説が面白いのではなく、人の話(解説)が面白いということにすぎないからだ。
『第三の嘘』は後者のケースである。まず、『悪童日記』『ふたりの証拠』とで三部作になっているという話自体が人を馬鹿にしている。しかも同じ三部作と言っても、それぞれ独立に読んでも面白いというのなら話は別だが、『悪童日記』を読んでいなければ、『ふたりの証拠』も『第三の嘘』も話が分らない。というか『第三の嘘』は前二作を読んでいても、チンプンカンプンで、もうめまいがしてきそうなほど訳が分らない。訳者の堀茂樹は解説で「本書を前二作と対照して注意深く読まれる読者には」と書いているが、注意深く読むことを要求するなと言いたいし、もし注意深く読んだ結果としていったいなにが浮かび上がってくるのかと言っても、なにもない。
リュカやクラウスの不幸はいったいどこから由来していたのか? 『第三の嘘』を読む限りでは、両親と双子のリュカとクラウスが幸せに暮らしていたところに、父親が妻と双子を捨てて、アントニアという女のところに行こうとしたことで発狂した妻がピストルで夫を殺したうえに双子の一人のリュカの脊柱に障害を負わせてしまったことが原因であるようにしか読めない。そこには『悪童日記』にあったようなナチスドイツの侵略も戦後にソ連による侵略支配もまったく影を落としていない、というか関係ない出来事として描かれている。
いったい訳者が絶賛する理由がいったいどこにあるのか、私にはさっぱり分らない。『悪童日記』はたしかに面白かった。それはすでに書いたから繰り返さないが、その面白さは、『第三の嘘』の解説に転載されている浅野素女さんによる作者へのインタビューで作者が語っている意図がそのまま実現されていることから来ている。つまり「何食わぬスタイルで人間世界の現実をきびしく暴く辛らつかつ残酷な情景もしくは寸劇を、一貫性のある形でいくつも連続させる」ことを目指し、そのために「語り手――単一の”ぼくら”という意識において一体化している双子の兄弟――が、あらゆる主観性を、あるいは少なくとも、感じやすさのあらゆる痕跡を、情け容赦なく強引に排除し去った小説」を書こうという意図が実現されているから面白かったということなのだ。
しかし残りの二作は、いったい何を書こうとしてるのか、なぜこんな形式をとっているのかもまったく伝わってこないし、物語そのものとしても、どこがいったい「驚愕」なのかと言いたくなるような、陳腐な世界でしかなく、それは解説からもまったく理解できない。
訳者の堀茂樹は第三作の『第三の嘘』で三部作が完結したということになっているが、完結してはないという疑問を感じており、作家の佐藤亜紀が同じことを言っているとか、フランスでもそうした評判が立っているとして、なんか鬼の首でも取ったようなことを書いているが、だからどうだというのだ。
 A「この小説、面白かった。」
A「この小説、面白かった。」B「そう? でもじつはこれはこういうことだったんだよ。知ってた?」
A「うそ! もしそれを知っていたら、もっと面白かっただろうね。」
私はこういう会話はありだと思う。しかし、
C「あーあ、この小説、わけ分らん。ぜんぜん面白くない。」
D「そう? でもじつはこれはこういうことだったんだよ。知ってた?」
C「うそ! もしそれを知っていたら、面白かっただろうね。」
こんな会話はありえないと思う。つまりなんの説明もなしに面白く思えなかったけど、人から説明を聞いて(解説を読んで)面白くなる、なんてことはありえない。それは小説が面白いのではなく、人の話(解説)が面白いということにすぎないからだ。
『第三の嘘』は後者のケースである。まず、『悪童日記』『ふたりの証拠』とで三部作になっているという話自体が人を馬鹿にしている。しかも同じ三部作と言っても、それぞれ独立に読んでも面白いというのなら話は別だが、『悪童日記』を読んでいなければ、『ふたりの証拠』も『第三の嘘』も話が分らない。というか『第三の嘘』は前二作を読んでいても、チンプンカンプンで、もうめまいがしてきそうなほど訳が分らない。訳者の堀茂樹は解説で「本書を前二作と対照して注意深く読まれる読者には」と書いているが、注意深く読むことを要求するなと言いたいし、もし注意深く読んだ結果としていったいなにが浮かび上がってくるのかと言っても、なにもない。
リュカやクラウスの不幸はいったいどこから由来していたのか? 『第三の嘘』を読む限りでは、両親と双子のリュカとクラウスが幸せに暮らしていたところに、父親が妻と双子を捨てて、アントニアという女のところに行こうとしたことで発狂した妻がピストルで夫を殺したうえに双子の一人のリュカの脊柱に障害を負わせてしまったことが原因であるようにしか読めない。そこには『悪童日記』にあったようなナチスドイツの侵略も戦後にソ連による侵略支配もまったく影を落としていない、というか関係ない出来事として描かれている。
いったい訳者が絶賛する理由がいったいどこにあるのか、私にはさっぱり分らない。『悪童日記』はたしかに面白かった。それはすでに書いたから繰り返さないが、その面白さは、『第三の嘘』の解説に転載されている浅野素女さんによる作者へのインタビューで作者が語っている意図がそのまま実現されていることから来ている。つまり「何食わぬスタイルで人間世界の現実をきびしく暴く辛らつかつ残酷な情景もしくは寸劇を、一貫性のある形でいくつも連続させる」ことを目指し、そのために「語り手――単一の”ぼくら”という意識において一体化している双子の兄弟――が、あらゆる主観性を、あるいは少なくとも、感じやすさのあらゆる痕跡を、情け容赦なく強引に排除し去った小説」を書こうという意図が実現されているから面白かったということなのだ。
しかし残りの二作は、いったい何を書こうとしてるのか、なぜこんな形式をとっているのかもまったく伝わってこないし、物語そのものとしても、どこがいったい「驚愕」なのかと言いたくなるような、陳腐な世界でしかなく、それは解説からもまったく理解できない。
訳者の堀茂樹は第三作の『第三の嘘』で三部作が完結したということになっているが、完結してはないという疑問を感じており、作家の佐藤亜紀が同じことを言っているとか、フランスでもそうした評判が立っているとして、なんか鬼の首でも取ったようなことを書いているが、だからどうだというのだ。