Cypora Petitjean-Cerf, Le Corps de Liane, Editions Stock, 2007.
シポラ・プティジャン=セール『リアーヌの体』(ストック書店、2007年)
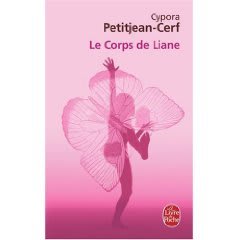
前回読んだサミラ・ベリルの自伝のすざまじく荒れた生活とはうって変わって、ほとんどたいした変化もないように見える同じ12才前後の少女とその家庭や友だちといった狭い生活圏での日常を描いた小説なのだが、なんだかクスッと笑える場面が満載で、面白かった。
一応主人公はリアーヌという少女。パリに住んでいて、小説の冒頭では小学校のCM1、つまり日本で言う小学4年生にあたる。ただしフランスの小学校は5年生まで。彼女は授業中に内容がわかっていてもなかなか発言する勇気がなくて、面談の結果、CM1を留年してしまう。フランスの小学校・中学校には成績が悪いと留年の制度がある。五年生になったクラスでロズリンというブロンドの美人の女の子と友達になる。リアーヌの胸はぺちゃんこなのに、この子の胸は大人のように大きかったからだ。(ずっと後になって、そのことをリアーヌがロズリンに言うのだが、ロズリンはそれを聞いてがっかりする。)
リアーヌの親は母親のクリティーヌだけ。父親はまだ赤ちゃんの頃に蒸発した。母子家庭だ。ロズリンも母子家庭だが、最近母親が男を作り、二人の間に赤ちゃんができる。クリスタルという女の子。ロズリンは中学生になってジャン=リュックというサン・ドニに住んでいるボーイフレンドができる。17歳でケーキ屋で修行中の身だが、彼の修行が終わったら、ロズリンも中学三年生に進級しないで学校を辞めて、結婚するつもりだという。フランスの中学は4年制。15歳までが義務教育で、学力的に進級が無理な場合は、その時点で学校を辞める子も多い。
リアーヌのクラスにはアシュラフという真面目な男の子がいる。彼の家は中学の正門のすぐ向かいで、ハッサンというお父さんが食料品店をやっている。お母さんはガニアで、何もしないお母さんだ。お父さんは店の中から、いつも学校の前を見張っている。息子は学校が終わるとまっすぐ家に帰る。どうもお母さんの血をひいたようで、真面目なわりには勉強ができない。真面目に宿題をしているのだが、何を勉強しているのかよく分かっていないのだ。
リアーヌにはユゲットというブルターニュ住んでいるおばあちゃんがいる。毎年夏のバカンスにはカンペールの近くのおばあちゃんの家で過ごす。このユゲットも子どもができたら男に捨てられたくちで、二代続いて子どもができたら男に捨てられた。
リアーヌが中学2年生になった年、突然母のクリティーヌが寝込んでしまう。仕事にも行かない、家事もしない、食事もしないという状態になってしまう。しかたがないのでエヴァという家政婦を雇うことになる。彼女にはアルメルという女の子がいるのだが、この子がまた悪い。エヴァは家政婦と言ってもまともな家政婦ではなく、掃除をさせれば、飾ってある花瓶を割るし、ホコリは残ったままだしで、家政婦を雇ったわりには家は片付かない。
埒が明かないので、ついにブルターニュからユゲットが上京してきて家の世話をすることになる。すこし経つとパリでの生活にもなれてきて、いつもバスに乗って行っているリュクサンブール公園に車で行きたいと思うようになり、自動車学校に通いだす。ちょうどジャン=リュックがもっている白いルノー5を売りたいと思っていたので、免許を取ったら、ユゲットがそれを買うことに。
ロズリンはちょっと蓮っ葉な感じの子なのだが、何もしない母親の代わりに家事をしたり夜鳴きをする妹の世話をしたりする子で、人の気持ちが分かる優しい子なのだ。勉強はできないのだが。
リアーヌの14才の誕生日パーティに呼ばれてすごく喜んでいたが、すこし前に死産したアシュラフの叔母さんのラミアは来なかったほうがいいかも、ロズリンが妹を連れてきていたので、赤ちゃんを見て泣いていたからだと言う。そんな優しい子だ。
1985年6月ロズリンは職業リセに進学し、リアーヌは中学3年生(中学は4年生まである)に進級する。ロズリンの妹(まだ赤ちゃん)は母親が育児放棄をしていたので、ユゲットが面倒を見ていたのだが、ロズリンのママが世話をしたいと言い出し、ユゲットの元を離れることになる。ユゲットはその日から泣き続け、何もしなくなる。代わりにクリスティーヌがおきだして、家事をするようになった。「今からでも子どもを作るのは遅すぎるかしら」と尋ねる。
パリ生活も6ヶ月になるころ、ユゲットはそろそろブルターニュに帰りたくなる。バカンスを機会に、ジャン=リュックから買い受けたルノー5に乗って、ブルターニュに帰る。
この小説を読むと、人生は分からない、なにかあらかじめ決められた方向性や意味があるわけでもなくて、何がどうなるのか分からないものだ、でも(だからではなく)、生きていれば楽しいのじゃないかな、と思わせてくれる。けっして誰一人として幸せではない。リアーヌは毎日吐き気に悩まされ、いつ公衆の面前で吐いてしまうかと怖れているし、ロズリンは何もしない母親の代わりに家政婦みたいなことをしている。
でも人生はこうでなければならないとか、自己実現だとか、そういう肩肘をはらないで生きていけたらいいじゃないと思わせてくれるところがこの小説にはある。なぜか女ばかりの小説だけど、それも意図してのことだろう。
説明文と会話文とが交互にできくるが、どの会話もちょっと可笑しくて面白い。
トローヌの市でジャン=リュックと知り合ったというロズリンが彼の住んでいるサン・ドニまで行くから一緒に行こうと誘われる。リアーヌは母のクリスティーヌに言ってもいいかと確認する。
「ママ、土曜日の3時にボーイフレンドに会いに行くロズリンについて行ってもいい?」「ボーイフレンドですって?どんな?」
「ジャン=リュックよ」とリアーヌは絶望的になってため息をついた。「17歳。ケーキ屋。行ってもいい?」
「ええ」
「いいの?でもジャンティイまでなのよ!」
クリスティーヌは肩をすくめた。
「それで?」
リアーヌは足を引きずりながらリビングを出た。(p.45-46)

もうブルターニュに帰るとユゲットお祖母ちゃんが言い出したころ。その頃、ロズリンは母親が家事と育児を放棄していたので、リアーヌの家に寝泊りしていた。
「お祖母ちゃんが私に何をくれたと思う?」とリアーヌは灯りを消すまえにたずねた。
「プレゼント?」
「ちがう。お金よ。私に200フランくれたの。」
「まぁ!たくさんじゃない!あんたお金持ちね!」とロズリンは叫んで、足をばたばたさせた。
「待ってよ。それで全部じゃないの。こう言ったの。ロズリンと分けなさいねって。」
「うそでしょ?ロズリンと分けなさいってそう言ったの?」
「ええ。うそじゃないわ。これはあなたたち二人のものだから、セフォラに行って欲しいものを買いなさいって。」
「おお、ちくしょう!」
「なによ?」
「なんでもないわ、ちくしょう!」
「なによ、ちくしょうって?」
「ユゲットお祖母ちゃんって私の妹のほうがかわいいはずよ。でもお母さんが妹を取っちゃたし、反対に私を選んでくれても何も難しいことはないのよね。お祖母ちゃんって私を養子にしたいのかしら?」
「できないわ。あなた孤児じゃないもの。」
「ちぇ、そうね。運がないわ」(p.140-141)
作者のシポラ・プティジャン=セールについては1974年生まれということ以外には何も分からない。
 音楽家を目指す高校生が高校の文化祭での発表や演奏会に向けた練習の中で成長していく過程を描いた青春小説ってやつでしょう。
音楽家を目指す高校生が高校の文化祭での発表や演奏会に向けた練習の中で成長していく過程を描いた青春小説ってやつでしょう。 音楽家を目指す高校生が高校の文化祭での発表や演奏会に向けた練習の中で成長していく過程を描いた青春小説ってやつでしょう。
音楽家を目指す高校生が高校の文化祭での発表や演奏会に向けた練習の中で成長していく過程を描いた青春小説ってやつでしょう。









 漢方医学を専門とする大学の先生であり、みずからクリニックを開いている医者ではあるが、もともと歴史が好きだったこともあり、たくさんの茶道家が膝を痛めてクリニックを訪れることから、正座に関心をもち、一冊の本をまとめたということのようだ。
漢方医学を専門とする大学の先生であり、みずからクリニックを開いている医者ではあるが、もともと歴史が好きだったこともあり、たくさんの茶道家が膝を痛めてクリニックを訪れることから、正座に関心をもち、一冊の本をまとめたということのようだ。 古筆学の大家小松茂美の研究者としての半生を描いた評伝なのだが、古筆学という学問自体が私にはよく分からない―いわゆる日本の古い文学的作品を扱う国文学とどう違うのかよく分からないという意味で―のだが、小松茂美という人のすごさは、もう感嘆に値するというほかない。
古筆学の大家小松茂美の研究者としての半生を描いた評伝なのだが、古筆学という学問自体が私にはよく分からない―いわゆる日本の古い文学的作品を扱う国文学とどう違うのかよく分からないという意味で―のだが、小松茂美という人のすごさは、もう感嘆に値するというほかない。 「アカペラ」
「アカペラ」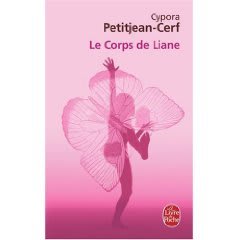 前回読んだサミラ・ベリルの自伝のすざまじく荒れた生活とはうって変わって、ほとんどたいした変化もないように見える同じ12才前後の少女とその家庭や友だちといった狭い生活圏での日常を描いた小説なのだが、なんだかクスッと笑える場面が満載で、面白かった。
前回読んだサミラ・ベリルの自伝のすざまじく荒れた生活とはうって変わって、ほとんどたいした変化もないように見える同じ12才前後の少女とその家庭や友だちといった狭い生活圏での日常を描いた小説なのだが、なんだかクスッと笑える場面が満載で、面白かった。 もうブルターニュに帰るとユゲットお祖母ちゃんが言い出したころ。その頃、ロズリンは母親が家事と育児を放棄していたので、リアーヌの家に寝泊りしていた。
もうブルターニュに帰るとユゲットお祖母ちゃんが言い出したころ。その頃、ロズリンは母親が家事と育児を放棄していたので、リアーヌの家に寝泊りしていた。 自分の身体の調子をたずねながらの自転車乗りなので、なかなか思うに任せない。今日は天気がいいので、以前断念した吉野行きを決行することに。とにかく帰りは輪行なので、気楽のはずが。
自分の身体の調子をたずねながらの自転車乗りなので、なかなか思うに任せない。今日は天気がいいので、以前断念した吉野行きを決行することに。とにかく帰りは輪行なので、気楽のはずが。 14才のときに集団による暴力、レイプ、輪姦に三度もあい、その精神的後遺症に苦しみ続け、やっと25才でこの本を書くことでそれから自分の解放することができた女性のドキュメントである。
14才のときに集団による暴力、レイプ、輪姦に三度もあい、その精神的後遺症に苦しみ続け、やっと25才でこの本を書くことでそれから自分の解放することができた女性のドキュメントである。 これまた久しぶりの岩湧の森だ。出発が9時40分くらいになったので、あまり遠くにも行けない、ということで、ここに。
これまた久しぶりの岩湧の森だ。出発が9時40分くらいになったので、あまり遠くにも行けない、ということで、ここに。 寺のそばに四季彩館というガイドセンターみたいな建物があるので、なんか飲み物とか食べ物はないのかなと思って行ってみたが、なにもなかった。外はデッキになっており、見晴らしがよく、PLの塔などが見える。別荘としてなら最高だなと思う。
寺のそばに四季彩館というガイドセンターみたいな建物があるので、なんか飲み物とか食べ物はないのかなと思って行ってみたが、なにもなかった。外はデッキになっており、見晴らしがよく、PLの塔などが見える。別荘としてなら最高だなと思う。 医者の家長(という言い方がまさにまだフランスで活きていた時代の話なので)を中心とした大人数家族の末っ子のファニーの視点から見た父ルイ・デルヴァスや母親、兄弟姉妹の旧弊な世界を描いたもの。
医者の家長(という言い方がまさにまだフランスで活きていた時代の話なので)を中心とした大人数家族の末っ子のファニーの視点から見た父ルイ・デルヴァスや母親、兄弟姉妹の旧弊な世界を描いたもの。



