ミシュレ『フランス史V(18世紀ヴェルサイユの時代)』(藤原書店、2011年)
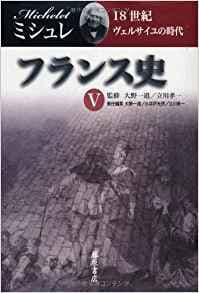 歴史の記述というのは、フランス語では単純過去形といって、事実が自らをそのまま語っているかのような「客観的」な叙述の形式がある。ミシュレの『フランス史』はまさにその対極にあるような、語り手の個性むき出しの叙述だ。
歴史の記述というのは、フランス語では単純過去形といって、事実が自らをそのまま語っているかのような「客観的」な叙述の形式がある。ミシュレの『フランス史』はまさにその対極にあるような、語り手の個性むき出しの叙述だ。
こういう叙述が好きな人には大いに受けるのだろうが、客観的な記述を好む私としては、なんとも読みにくいことこの上ない。とは言ってもこの時期を扱った日本語の本があまりないので、大雑把な感じにせよ、概略をつかみたいと思って、読んでみたのだが、意外と面白かった。
ただ登場人物が多すぎて(もちろん翻訳なので、適宜注の形で簡単な説明が付いているとはいえ)、訳がわからない。ダルジャンソンなんて、親のダルジャンソンから、けっこう悪い長男のダルジャンソンから、わりと良い奴の次男のダルジャンソンまで三人も登場してくる。
ローのシステム崩壊の過程について、そこはやはりたぶん素人だし、19世紀の本だから、現在の研究の到達ということから見たら、不十分な記述が多い。
私が知りたいのは時代の雰囲気のようなものだが、それはなんだかつかめたような気がする。
それにしても、いったい誰がこんな本を読むんだろう。
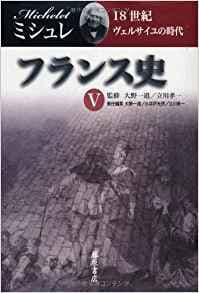 歴史の記述というのは、フランス語では単純過去形といって、事実が自らをそのまま語っているかのような「客観的」な叙述の形式がある。ミシュレの『フランス史』はまさにその対極にあるような、語り手の個性むき出しの叙述だ。
歴史の記述というのは、フランス語では単純過去形といって、事実が自らをそのまま語っているかのような「客観的」な叙述の形式がある。ミシュレの『フランス史』はまさにその対極にあるような、語り手の個性むき出しの叙述だ。こういう叙述が好きな人には大いに受けるのだろうが、客観的な記述を好む私としては、なんとも読みにくいことこの上ない。とは言ってもこの時期を扱った日本語の本があまりないので、大雑把な感じにせよ、概略をつかみたいと思って、読んでみたのだが、意外と面白かった。
ただ登場人物が多すぎて(もちろん翻訳なので、適宜注の形で簡単な説明が付いているとはいえ)、訳がわからない。ダルジャンソンなんて、親のダルジャンソンから、けっこう悪い長男のダルジャンソンから、わりと良い奴の次男のダルジャンソンまで三人も登場してくる。
ローのシステム崩壊の過程について、そこはやはりたぶん素人だし、19世紀の本だから、現在の研究の到達ということから見たら、不十分な記述が多い。
私が知りたいのは時代の雰囲気のようなものだが、それはなんだかつかめたような気がする。
それにしても、いったい誰がこんな本を読むんだろう。










 河内長野のマイタウンオペラを鑑賞するようになってかなりの年月がたつが、初めてのフランス語オペラだと思う。以前、感想を書く用紙に、フランス語オペラもやってほしいと書いたのが反映されたのだろうか。(そんなことはないだろうけど)
河内長野のマイタウンオペラを鑑賞するようになってかなりの年月がたつが、初めてのフランス語オペラだと思う。以前、感想を書く用紙に、フランス語オペラもやってほしいと書いたのが反映されたのだろうか。(そんなことはないだろうけど) 17世紀・18世紀のフランスの啓蒙思想に関する逸話とか著者の雑学などを、旅、戦争、サロンという三つの主題を中心に披露したもの。
17世紀・18世紀のフランスの啓蒙思想に関する逸話とか著者の雑学などを、旅、戦争、サロンという三つの主題を中心に披露したもの。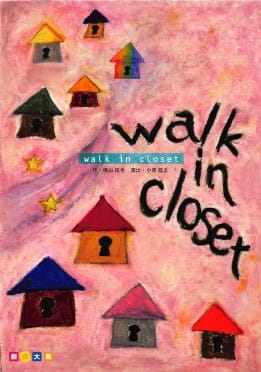 同性愛を家族にカミングアウトするという問題を主題にした作品。
同性愛を家族にカミングアウトするという問題を主題にした作品。 サン=テグジュペリの『星の王子さま』は2005年に独占的出版権が切れて、それまで岩波書店の内藤濯訳だけだったのが、続々と翻訳本が出版された。この時点で13本もあったという。内藤濯訳の誤訳を中心に、これらの後継翻訳本のすべての誤訳を検討して、書いたのが、この本だということだ。
サン=テグジュペリの『星の王子さま』は2005年に独占的出版権が切れて、それまで岩波書店の内藤濯訳だけだったのが、続々と翻訳本が出版された。この時点で13本もあったという。内藤濯訳の誤訳を中心に、これらの後継翻訳本のすべての誤訳を検討して、書いたのが、この本だということだ。



