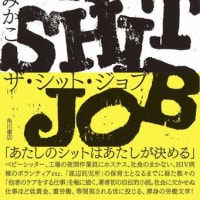岡田晴恵『コロナの夜明け』(KADOKAWA、2022年)

 2020年と2021年の私のブログは政府・厚労省・東京都や大阪府などコロナ対策のいい加減さに対する怒りに満ちている。
2020年と2021年の私のブログは政府・厚労省・東京都や大阪府などコロナ対策のいい加減さに対する怒りに満ちている。
クルーズ船ダイヤモンド・プリンセスでのコロナ感染の対策のお粗末さから、日本のコロナ対策の行末は見えていたようなものだが、一番の問題はPCR検査抑制、国民皆保険制度があるにもかかわらず、感染して発症しても医療を拒否される・たどり着けない状態に国民を置いた医療放棄政策だと言える。
PCR検査抑制は、「たくさん検査をしてたくさん陽性者が出れば医療が逼迫する」これが政府・専門家会議の言い分であり、橋下徹や木村盛世らがこれをテレビで盛んに代弁した。橋下徹なんかPCR検査抑制を言いながら、自分が発熱すると真っ先にPCR検査を受けていたくせに!絶対に許さない。
この小説を読むと、たしかに最初は保健所関係でPCR検査のできる数が少なかったこともあって、PCR検査そのものが間に合わない状態だったようだが、もともと大学などの研究機関にはPCR検査の機器もあれば、それを使用できるスタッフもたくさんいたし、その後、自動で検査できる機器もできたし、検査そのものも1時間で、30分で、とだんだんと進歩していった(それもこれも日本のメーカーが必死に開発したのだ)にもかかわらず、厚労省・専門家会議は一切これを使用する指示を出さず、最後までPCR検査抑制の態度であった。
いったい誰が感染者なのかわからないからみんな疑心暗鬼になる。未だに多くに日本人がマスクを取らないの(そのもそ誰もいない屋外でもマスクをしている老人などを見ると厚労省・専門家会議の愚策に腸が煮えくり返る)は、PCR検査そのものにもたどり着けない・医療にたどり着けないという現実を知っているから、絶対に感染したくないと思っているからだろう。
PCR検査を「誰でも・どこでも・いつでも」できるようにしておけば、陽性判定が出た人は自主的に自宅待機をする(もちろん家族に感染しないような生活の仕方が必要だが)、症状が出たら、医療機関に相談して、必要な医療を受けるということができるから、医療が逼迫することはないし、ロックダウンなどする必要もなく、通常の経済活動を回すことで、飲食店なんかが潰れたりすることもなかっただろうに。
それにしてもこの著者のような人がいたこと、そして宇都宮市のインターパーク呼吸器内科の倉持仁さんのように、厚労省がすべきことを率先して(ある意味で命と財産をなげうって)自分の医院でPCR検査も中等症以上の患者も医療する、そのために臨時の施設を作るような人がいたことは、唯一の救いだ。
この本のアマゾンのサイトへはこちらをクリニック
最後に、専門家会議、なんなのあれは?専門家でもない人たちがコロナの現実も国民の現実も見ないで、政府に都合のいいことばかり発言していたことを、東京大学の児玉龍彦さんが批判している次のYoutubeを参考に添付しておく。これは2時間くらいの長尺の一部だが、全部を見ても興味深い。

クルーズ船ダイヤモンド・プリンセスでのコロナ感染の対策のお粗末さから、日本のコロナ対策の行末は見えていたようなものだが、一番の問題はPCR検査抑制、国民皆保険制度があるにもかかわらず、感染して発症しても医療を拒否される・たどり着けない状態に国民を置いた医療放棄政策だと言える。
PCR検査抑制は、「たくさん検査をしてたくさん陽性者が出れば医療が逼迫する」これが政府・専門家会議の言い分であり、橋下徹や木村盛世らがこれをテレビで盛んに代弁した。橋下徹なんかPCR検査抑制を言いながら、自分が発熱すると真っ先にPCR検査を受けていたくせに!絶対に許さない。
この小説を読むと、たしかに最初は保健所関係でPCR検査のできる数が少なかったこともあって、PCR検査そのものが間に合わない状態だったようだが、もともと大学などの研究機関にはPCR検査の機器もあれば、それを使用できるスタッフもたくさんいたし、その後、自動で検査できる機器もできたし、検査そのものも1時間で、30分で、とだんだんと進歩していった(それもこれも日本のメーカーが必死に開発したのだ)にもかかわらず、厚労省・専門家会議は一切これを使用する指示を出さず、最後までPCR検査抑制の態度であった。
いったい誰が感染者なのかわからないからみんな疑心暗鬼になる。未だに多くに日本人がマスクを取らないの(そのもそ誰もいない屋外でもマスクをしている老人などを見ると厚労省・専門家会議の愚策に腸が煮えくり返る)は、PCR検査そのものにもたどり着けない・医療にたどり着けないという現実を知っているから、絶対に感染したくないと思っているからだろう。
PCR検査を「誰でも・どこでも・いつでも」できるようにしておけば、陽性判定が出た人は自主的に自宅待機をする(もちろん家族に感染しないような生活の仕方が必要だが)、症状が出たら、医療機関に相談して、必要な医療を受けるということができるから、医療が逼迫することはないし、ロックダウンなどする必要もなく、通常の経済活動を回すことで、飲食店なんかが潰れたりすることもなかっただろうに。
それにしてもこの著者のような人がいたこと、そして宇都宮市のインターパーク呼吸器内科の倉持仁さんのように、厚労省がすべきことを率先して(ある意味で命と財産をなげうって)自分の医院でPCR検査も中等症以上の患者も医療する、そのために臨時の施設を作るような人がいたことは、唯一の救いだ。
この本のアマゾンのサイトへはこちらをクリニック
最後に、専門家会議、なんなのあれは?専門家でもない人たちがコロナの現実も国民の現実も見ないで、政府に都合のいいことばかり発言していたことを、東京大学の児玉龍彦さんが批判している次のYoutubeを参考に添付しておく。これは2時間くらいの長尺の一部だが、全部を見ても興味深い。