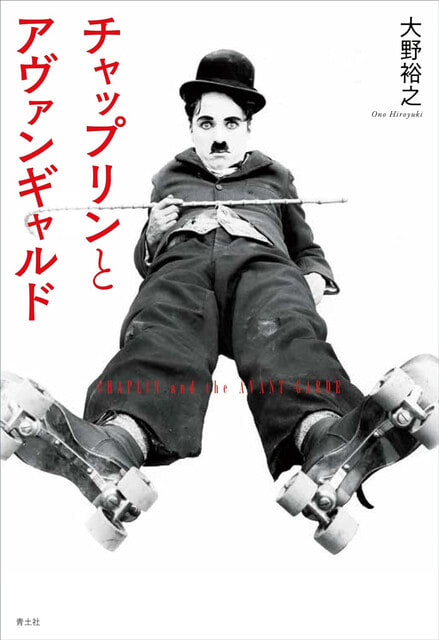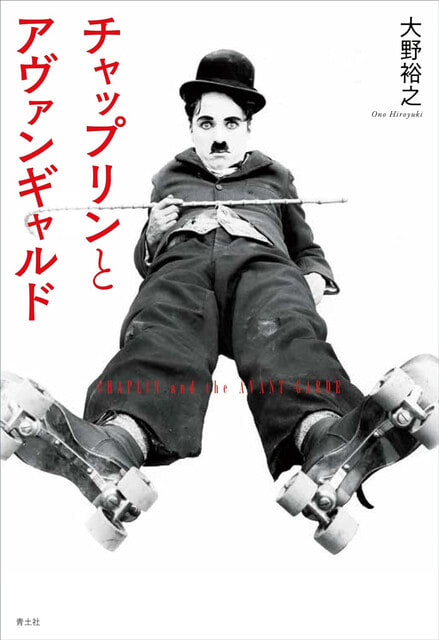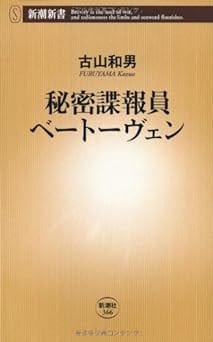岩田弘三『アルバイトの誕生』(平凡社新書、2021年)


興味深い本だった。それこそこの本が指摘するように、多くの学生がアルバイトをするようになった現今では、誰でもアルバイトについて語ることができる。
私の場合は、大学生のころは、夏休みに阪急デパートでアルバイトをしたのと、家庭教師のアルバイトだった。夏休みの阪急デパートでのアルバイトはいい経験をした。大学生協で「日本文学初版本復刻セット」なるものを10万円近くで買った私は、これの支払いのために夏休みにはアルバイトとすることにした。ちょうど同じ下宿の学生が阪急デパートのアルバイトに応募するというので、私も一緒に応募したら、うまく採用されて、江坂にある配送センターのワイシャツと靴下の部門に配属になった。
一人だけ若い社員の人がいて、彼の下に私のようなアルバイトが4人くらい。梅田の本店から発注表がくるとそれをもとに、ワイシャツとか靴下を包装して配送表を張って、コンベアで送り出す。
ところが時期的にお中元の品物がメインになるのだが、お中元にワイシャツとか靴下を贈る人はあまりいない。それで少ししか伝票が来ない。暇で暇で…、隣の洗剤コーナーとは大違い(こちらはフル稼働、それに洗剤って重い)。それで社員のお兄さんの提案で浜寺のプールに遊びに行ったこともあった。
そして7月末日までの契約だったが、たぶん4人もアルバイトはいらないということになったのだろう。私だけが梅田の本店の売り場に配属替えになった。きれいな女性社員たちと働けるようになって、緊張していたのを思い出す。もちろん売り場には女子大生のアルバイトたちもいて…、最後の日にその一人から告られる、なんてこともあった。(今から思えば、この一年は私のモテキだった。)
この夏のアルバイトで稼いだお金は、予定どおり「復刻本セット」の支払いに使われ、残りは、サークルの友人たちと信州に旅行に行く費用で消えた。
二年生の夏休みはアルバイトどころではなかった。私は一年生の後期試験でボロボロと単位を落として四年間で卒業するのが怪しくなったので、本気でフランス語を勉強しないといけないと気を引き締めて、夏休みは田舎に帰って、それこそねじり鉢巻でフランス語の勉強をした。三年生と四年生の夏休みは何をしていたのかさえ思い出せない。
アルバイトはこれ以外には家庭教師のアルバイトをしていた。まぁこれは週一なのでたいしたことはない。相手は中学三年生、つまり受験生で、私は中学の勉強はよくできたので、一生懸命に教えたら、この子も成績が上がって、志望校に入学できた。お母さんが喜んでくれて、他の子の家庭教師へとつながった。
同級生でアルバイトをしている学生はけっこういたと思うが、なかでも夜間の学校や保育園の警備員のアルバイトをして、そのバイト代で学費も生活費もまかなっているやつがいた。立派だなと感心したものだ。
私の場合は三万円の仕送りでひと月を暮らしていたので、週一程度のアルバイトでちょっとだけお小遣いが入ればいいくらいに思っていた。(授業料十数万円は親に出してもらっていた)。
しかし今の学生は、学費からして文系で100万近く、理系なら100万を超える。そして東京や大阪のような大都市に送り出せば、家賃が10万近く、生活費だって5・6万円はいるだろう。だからせめて生活費くらいは自分で作りたいとおもってアルバイトに精を出す学生も多いだろう。
それと決定的に違うのは、私らの時代には、専門以外の授業はほとんどでなかったが、今の学生は親から100万程度の学費を出してもらっているという思いがあるから、授業もすべてこまめに出席している。そういうことをしながら、その上でアルバイトをしているのだから、たいしたものだ。
そういう意味では、コロナ禍でアルバイトが減ったり、ウェブ授業で、レポート提出が毎週あったりすようになったのは、痛手だったのではないだろうか。
この本のアマゾンのサイトへはこちらをクリック