佐伯一麦『還れぬ家』(2013年、新潮社)

 認知症が始まった父親と、彼を取りまく母親や「私」や妻の日常を父親の死まで描いた私小説。
認知症が始まった父親と、彼を取りまく母親や「私」や妻の日常を父親の死まで描いた私小説。
昨日の『朝日新聞』のなんでも相談室みたいなコーナーに50歳代の女性がこんな内容の投稿をしていた。自分の母親は認知症で、娘である私のことも孫のこともわからなくなり、たぶん自分自身のこともわからなくなっているのではないか、そんな母親にやっと面会できたが、そんなふうになった祖母を見て、娘が「こんなになってまで生きていたくない」と言ったのでショックを受けて、「そんなことを言うものではない」と諌めたが、心のなかでは自分も同じことを考えていた。どうしたらいいのだろうか、というものだった。
回答者の姜尚中は、人間の命は自分で決めることができない、人生をまっとうするのが人間としての努めだから、みたいなことを答えていたが、この小説でも描かれているような悲惨な老後を果たしてまっとうしなければならないのかどうか、そもそもそんなことももうわからなくなってしまっているのに。
本当に尊厳死というものを真面目に検討しなければならない時代になっていると思う。つまりそのための法的な整備をしなければならないという意味だ。一番厄介なのは、認知症によって、まったく判断ができなくなってしまった場合だろう。そうなる前に自分の意思表示をしておくにしても、そこで指示された状態が今の状態だと判断するのは他人になるからだ。
これから十年先・二十年先の日本は、病院や施設に入ることができなくて、自宅でのたうち回って死ぬという人が続出することになるのではないか。まぁ自分ひとりのことなら、それもいいかと思うが、やはり身内がそういう事態になるのは、つらいだろう。
すでに人口の三分の一が65歳以上。ピラミッド型どころか、寸胴鍋型の人口配分になっている。最近では、身内が惜しんでくれるうちに、早く死ぬのが一番いいという考えになってきた。
この本のアマゾンのサイトへはこちらをクリック

昨日の『朝日新聞』のなんでも相談室みたいなコーナーに50歳代の女性がこんな内容の投稿をしていた。自分の母親は認知症で、娘である私のことも孫のこともわからなくなり、たぶん自分自身のこともわからなくなっているのではないか、そんな母親にやっと面会できたが、そんなふうになった祖母を見て、娘が「こんなになってまで生きていたくない」と言ったのでショックを受けて、「そんなことを言うものではない」と諌めたが、心のなかでは自分も同じことを考えていた。どうしたらいいのだろうか、というものだった。
回答者の姜尚中は、人間の命は自分で決めることができない、人生をまっとうするのが人間としての努めだから、みたいなことを答えていたが、この小説でも描かれているような悲惨な老後を果たしてまっとうしなければならないのかどうか、そもそもそんなことももうわからなくなってしまっているのに。
本当に尊厳死というものを真面目に検討しなければならない時代になっていると思う。つまりそのための法的な整備をしなければならないという意味だ。一番厄介なのは、認知症によって、まったく判断ができなくなってしまった場合だろう。そうなる前に自分の意思表示をしておくにしても、そこで指示された状態が今の状態だと判断するのは他人になるからだ。
これから十年先・二十年先の日本は、病院や施設に入ることができなくて、自宅でのたうち回って死ぬという人が続出することになるのではないか。まぁ自分ひとりのことなら、それもいいかと思うが、やはり身内がそういう事態になるのは、つらいだろう。
すでに人口の三分の一が65歳以上。ピラミッド型どころか、寸胴鍋型の人口配分になっている。最近では、身内が惜しんでくれるうちに、早く死ぬのが一番いいという考えになってきた。
この本のアマゾンのサイトへはこちらをクリック















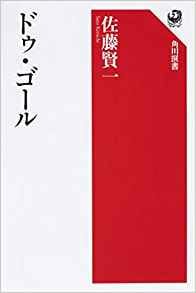 パリ北部の国際空港にも名前がついているシャルル・ド・ゴールについての評伝である。
パリ北部の国際空港にも名前がついているシャルル・ド・ゴールについての評伝である。
 パリのさる占い女がジャンヌ=アントワネットが国王の愛妾になると占ったという逸話から始まって1764年に死去するまでを描いた小説である。小説だから読みやすい。読みやすい上に、もともと西洋史学を大学院で勉強し、ほとんどの小説をフランス物で書いてきた著者(小説『フランス革命』なんてのもあるくらいだから)にしてみれば、資料を渉猟するのも、お手の物だろう。きちんとした下調べのもとに描かれているから安心して読める。
パリのさる占い女がジャンヌ=アントワネットが国王の愛妾になると占ったという逸話から始まって1764年に死去するまでを描いた小説である。小説だから読みやすい。読みやすい上に、もともと西洋史学を大学院で勉強し、ほとんどの小説をフランス物で書いてきた著者(小説『フランス革命』なんてのもあるくらいだから)にしてみれば、資料を渉猟するのも、お手の物だろう。きちんとした下調べのもとに描かれているから安心して読める。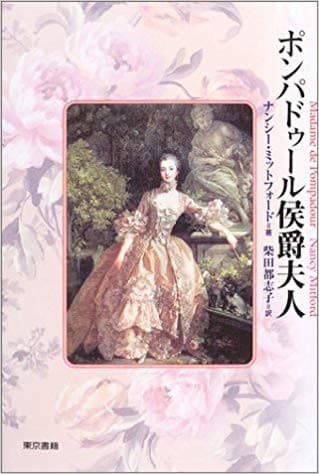 翻訳は2003年の出版だが、原書は1954年の出版である。2000年頃から、ポンパドゥール夫人に関する著作が増えてきていることを思うと、早すぎた著作と言えるかもしれないが、第二次大戦後にパリに移住したとのことで、フランスの資料を相当に調べた上での著作だと思われる。
翻訳は2003年の出版だが、原書は1954年の出版である。2000年頃から、ポンパドゥール夫人に関する著作が増えてきていることを思うと、早すぎた著作と言えるかもしれないが、第二次大戦後にパリに移住したとのことで、フランスの資料を相当に調べた上での著作だと思われる。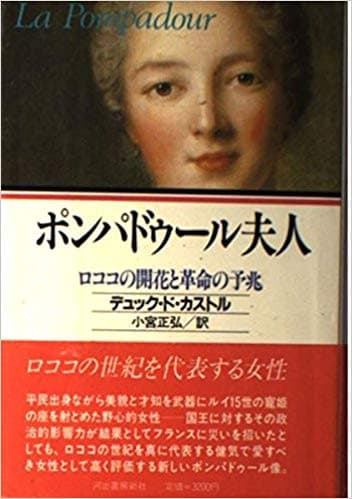 これはフランス人の歴史学者による評伝である。非常に細かい所まで記述されている。ポンパドゥール夫人と同時代人で、日記や回想録を書いた人々(バルビエ、リュイーヌ公爵、ダルジャンソン侯爵)の著者は当然用いられており、随所にその抜粋が織り込まれているので、資料集として手元に置いておくのもいい。
これはフランス人の歴史学者による評伝である。非常に細かい所まで記述されている。ポンパドゥール夫人と同時代人で、日記や回想録を書いた人々(バルビエ、リュイーヌ公爵、ダルジャンソン侯爵)の著者は当然用いられており、随所にその抜粋が織り込まれているので、資料集として手元に置いておくのもいい。 このだけは以前読んだことがあって、このブログでも感想を書いている。これも非常によく出来た本で、どうでもいいようなゴシップが書いてない分、必要最小限のことが書かれている。著名な芸術家たちからダンス、朗唱、歌などの教育を受けて優れた才能を見せたことや「小部屋劇場」のことなどもそうである。
このだけは以前読んだことがあって、このブログでも感想を書いている。これも非常によく出来た本で、どうでもいいようなゴシップが書いてない分、必要最小限のことが書かれている。著名な芸術家たちからダンス、朗唱、歌などの教育を受けて優れた才能を見せたことや「小部屋劇場」のことなどもそうである。 1720年代から30年代にかけて人気の絶頂にあったアントニオ・ヴィヴァルディも、1730年代末になると隆盛してきたナポリ派の音楽に押されて凋落し、多額の借金を踏み倒すほどになっていた。そして1740年に状況を挽回するためにウィーンに出かけるも、支援者を見つけることができず、当地で病死することになる。
1720年代から30年代にかけて人気の絶頂にあったアントニオ・ヴィヴァルディも、1730年代末になると隆盛してきたナポリ派の音楽に押されて凋落し、多額の借金を踏み倒すほどになっていた。そして1740年に状況を挽回するためにウィーンに出かけるも、支援者を見つけることができず、当地で病死することになる。 篠田節子の小説で最初に読んだのが『カノン』だったと思う。だから篠田節子というと音楽家の狂気みたいなものをサイコ調に書く作家というイメージがある。今回読んだのは短篇集なので、ちょっと趣が違うが「秋の花火」と「ソリスト」がこうした系列にあたる。
篠田節子の小説で最初に読んだのが『カノン』だったと思う。だから篠田節子というと音楽家の狂気みたいなものをサイコ調に書く作家というイメージがある。今回読んだのは短篇集なので、ちょっと趣が違うが「秋の花火」と「ソリスト」がこうした系列にあたる。