高見沢俊彦『音叉』(文藝春秋、2018年)

 バンドのアルフィーのメンバー高見沢俊彦が初めて書いた小説ということで新聞などで知っていたのだが、たまたま図書館の返却コーナーにあったので読んでみた。
バンドのアルフィーのメンバー高見沢俊彦が初めて書いた小説ということで新聞などで知っていたのだが、たまたま図書館の返却コーナーにあったので読んでみた。
とにかく文章が読みやすい。本人の実際に経験したことを回想風にそのまま書いたせいなのか、もともと文才があるせいなのか、読みやすい。
しかも書かれている時代が私の学生時代とほぼ同じということもあって、時代の雰囲気がよく分かる。もちろん私にはこれほどの女性遍歴はまったくないので、その辺のことを差し引いても、「私にも書けるんじゃないか」という気にさせるような、いい小説だ。
実際アルフィーも74年くらいにデビューしてから、メリーアンがヒットする80年の初頭まではたいへんな苦労をしたらしいが、その後はずっと一線を走っている。
とは言っても私は彼らにはまったく関心がなかったのだが、この5・6年くらい前からBS7チャンネル(テレビ東京か?)で「あの年あの曲」とかいう番組があって、曲のアナウンサーの隣に出ていたのが、アルフィーの坂崎幸之助と高見沢俊彦だった。とくに坂崎幸之助はもうあらゆるフォークソングを知っているのではないかというくらい、つねにギターを抱えていて、ちょこっと弾いて歌ってみせるので、気に入った。
この頃には高見沢俊彦はもう長髪の宝塚女子って雰囲気で、面白い人だなくらいだったのだが、新聞で『音叉』という小説を書いたのを知って、多才だなと感心したものだ。
とにかく音楽業界の一線をこれほど長期に走っているバンドも少ないので、これからも活躍してほしいし、高見沢俊彦の他の小説も読んでみようかなと思っている。
『音叉』のアマゾンのコーナーへはこちらをクリック

とにかく文章が読みやすい。本人の実際に経験したことを回想風にそのまま書いたせいなのか、もともと文才があるせいなのか、読みやすい。
しかも書かれている時代が私の学生時代とほぼ同じということもあって、時代の雰囲気がよく分かる。もちろん私にはこれほどの女性遍歴はまったくないので、その辺のことを差し引いても、「私にも書けるんじゃないか」という気にさせるような、いい小説だ。
実際アルフィーも74年くらいにデビューしてから、メリーアンがヒットする80年の初頭まではたいへんな苦労をしたらしいが、その後はずっと一線を走っている。
とは言っても私は彼らにはまったく関心がなかったのだが、この5・6年くらい前からBS7チャンネル(テレビ東京か?)で「あの年あの曲」とかいう番組があって、曲のアナウンサーの隣に出ていたのが、アルフィーの坂崎幸之助と高見沢俊彦だった。とくに坂崎幸之助はもうあらゆるフォークソングを知っているのではないかというくらい、つねにギターを抱えていて、ちょこっと弾いて歌ってみせるので、気に入った。
この頃には高見沢俊彦はもう長髪の宝塚女子って雰囲気で、面白い人だなくらいだったのだが、新聞で『音叉』という小説を書いたのを知って、多才だなと感心したものだ。
とにかく音楽業界の一線をこれほど長期に走っているバンドも少ないので、これからも活躍してほしいし、高見沢俊彦の他の小説も読んでみようかなと思っている。
『音叉』のアマゾンのコーナーへはこちらをクリック












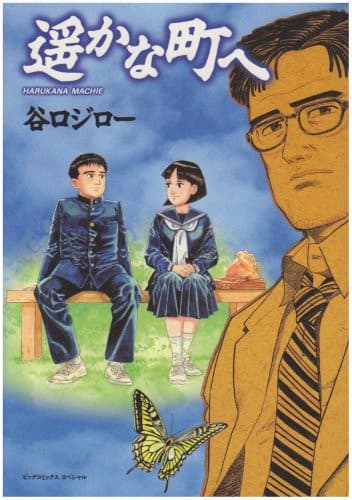 東京でデザイン会社を営む中原博史は48才、妻と二人の娘がいる。京都に出張した帰りの日、疲れからか東京行きの新幹線のかわりに、自分の故郷の倉吉行きの「スーパーはくと」に乗っているのに気づく。
東京でデザイン会社を営む中原博史は48才、妻と二人の娘がいる。京都に出張した帰りの日、疲れからか東京行きの新幹線のかわりに、自分の故郷の倉吉行きの「スーパーはくと」に乗っているのに気づく。 平成23年度の芥川賞を受賞した作品である。図書館に返却に行ったら、見つけた。ちょっと出だしを読んでみると、すーと頭に入ってくる。こなれたいい文章だったので、借りてきた。私は小説については、出だしを読んでみて、すーと頭に入ってこないようなものは、まず読み続けることはしない。
平成23年度の芥川賞を受賞した作品である。図書館に返却に行ったら、見つけた。ちょっと出だしを読んでみると、すーと頭に入ってくる。こなれたいい文章だったので、借りてきた。私は小説については、出だしを読んでみて、すーと頭に入ってこないようなものは、まず読み続けることはしない。 FUJI XEROXが発行しているGRAPHICATIONという雑誌がある。GRAPHICATIONというのはGraphic communicationをもとにした合成語で、イメージによって情報を伝達する方法を総称した言葉らしい。
FUJI XEROXが発行しているGRAPHICATIONという雑誌がある。GRAPHICATIONというのはGraphic communicationをもとにした合成語で、イメージによって情報を伝達する方法を総称した言葉らしい。 ロードバイクでも見ごたえもあるし、やりがいもあるのは、やはりヒルクライムだと思う。たとえばツール・ド・フランスのデュエーズ峠への登りでもうみんなが疲れきって意識朦朧状態で上がっている側を、まるで平地を走るみたいに、ダンシングでぐいぐいと追い越していくランス・アームストロングの姿やマルコ・パンターニのつるつる頭姿は、本当にかっこいい。
ロードバイクでも見ごたえもあるし、やりがいもあるのは、やはりヒルクライムだと思う。たとえばツール・ド・フランスのデュエーズ峠への登りでもうみんなが疲れきって意識朦朧状態で上がっている側を、まるで平地を走るみたいに、ダンシングでぐいぐいと追い越していくランス・アームストロングの姿やマルコ・パンターニのつるつる頭姿は、本当にかっこいい。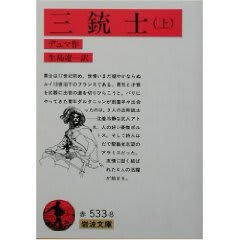 佐藤賢一の『褐色の文豪』を読んだことで、またデュマにたいする興味がわいて『三銃士』を読んでみた。以前読んだのは子どもの頃に子ども向けにリライトしたものだったので、原作を翻訳したものはこれが初めて。もっと波乱万丈の出来事が次から次へとでて来るのかと思ったら、意外にそうでもなかった。
佐藤賢一の『褐色の文豪』を読んだことで、またデュマにたいする興味がわいて『三銃士』を読んでみた。以前読んだのは子どもの頃に子ども向けにリライトしたものだったので、原作を翻訳したものはこれが初めて。もっと波乱万丈の出来事が次から次へとでて来るのかと思ったら、意外にそうでもなかった。 田中英光なんていってもほとんど知る人などいない、忘れられた作家だろう。1913年東京生まれで、早稲田大学在学中に1932年のロサンゼルス・オリンピックにボート(エイト)選手として出場したが、予選で敗退した。大学を卒業して横浜ゴムに就職し、日本統治時代に京城と呼ばれていた現在のソウルに派遣され、そこで朝鮮人文学者との交友が生まれる。1940年、ロサンゼルス・オリンピックに出場したときの経験をモチーフにして書いた『オリンポスの果実』を文学界に発表し第7回池谷信三郎賞を受賞する。終戦前に静岡に引き上げ、終戦後太宰治の自殺に衝撃を受けて薬物中毒になり、49年に太宰の墓前で、睡眠薬服用の上、手首を切り自殺した。太宰に師事し彼と同じように同棲をしたり薬物中毒になったりして「無頼派」と呼ばれる。
田中英光なんていってもほとんど知る人などいない、忘れられた作家だろう。1913年東京生まれで、早稲田大学在学中に1932年のロサンゼルス・オリンピックにボート(エイト)選手として出場したが、予選で敗退した。大学を卒業して横浜ゴムに就職し、日本統治時代に京城と呼ばれていた現在のソウルに派遣され、そこで朝鮮人文学者との交友が生まれる。1940年、ロサンゼルス・オリンピックに出場したときの経験をモチーフにして書いた『オリンポスの果実』を文学界に発表し第7回池谷信三郎賞を受賞する。終戦前に静岡に引き上げ、終戦後太宰治の自殺に衝撃を受けて薬物中毒になり、49年に太宰の墓前で、睡眠薬服用の上、手首を切り自殺した。太宰に師事し彼と同じように同棲をしたり薬物中毒になったりして「無頼派」と呼ばれる。 北朝鮮による100ドル紙幣偽造とそれを追うアメリカのシークレットサービスや日本の政府関係者のスパイ映画もどきのやりとりを、日本で稀有なインテリジェンスの人といわれる、元NHKワシントン特派員の手嶋龍一が小説化したもの。「わが国に初めて誕生したインテリジェンス小説」と書かれている。解説も、少し前に対談をした相手の、佐藤優が書いている。
北朝鮮による100ドル紙幣偽造とそれを追うアメリカのシークレットサービスや日本の政府関係者のスパイ映画もどきのやりとりを、日本で稀有なインテリジェンスの人といわれる、元NHKワシントン特派員の手嶋龍一が小説化したもの。「わが国に初めて誕生したインテリジェンス小説」と書かれている。解説も、少し前に対談をした相手の、佐藤優が書いている。