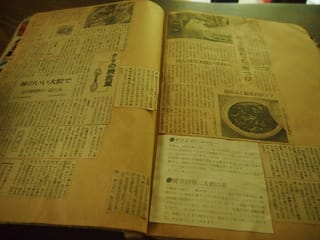昨日は、どんぐり工房の毎月定例の草木染め講習会でした。前夜から雨が降り続き、各地ではその前からゲリラ豪雨の被害が起きていたので、開催できるか心配でしたが、朝は小降りになったので、一安心。早朝起きて、敷地内の垣根を覆っているクズの茎葉を採取しました。
そのクズの葉と茎を刻んで、アルカリ水で煮出しました。アルカリ水で煮出すと、緑っぽい色が引き出されるのです。
この日の参加者は6名と小学生のお子さんふたり。全員豊田市街地から来て下さいました。

雨のため、クズしか採取できなかったので、もう一種類の染め草には、どんぐり工房の冷凍庫にしまってあったマリーゴールドを使いました。
小学二年生のMくん、1学年下の妹が夏休みの工作として提出する予定のバンダナを洗っています。マリーゴールドを染めるのは久々ですが、やはり、この花から生まれる黄色は鮮やかです。

クズの茎葉で染めた布を撮るのを忘れました。1,2番液で渋い緑系の色、3,4番液で、薄いながら冴えた緑色が生まれました。

ほかに、鍋に残ったマリーゴールドといっしょにタマネギの皮を入れて煮出し、金茶色も作りました。参加者のお一人が友人に頼まれて持ってきたワンピースを、この液の中に入れて染めてみました。はげかかったベージュの色が、若干濃い目の茶色に変わり、もうしばらく着られそうな服に変身しました。たぶんきっと喜んでもらえることでしょう。
さて、どんぐり工房の定例の講習会、来月8月はお休みです。次回は、9月22日(日)。詳しくは豊田市広報やどんぐり工房のHPをご覧ください。
そのクズの葉と茎を刻んで、アルカリ水で煮出しました。アルカリ水で煮出すと、緑っぽい色が引き出されるのです。
この日の参加者は6名と小学生のお子さんふたり。全員豊田市街地から来て下さいました。

雨のため、クズしか採取できなかったので、もう一種類の染め草には、どんぐり工房の冷凍庫にしまってあったマリーゴールドを使いました。
小学二年生のMくん、1学年下の妹が夏休みの工作として提出する予定のバンダナを洗っています。マリーゴールドを染めるのは久々ですが、やはり、この花から生まれる黄色は鮮やかです。

クズの茎葉で染めた布を撮るのを忘れました。1,2番液で渋い緑系の色、3,4番液で、薄いながら冴えた緑色が生まれました。

ほかに、鍋に残ったマリーゴールドといっしょにタマネギの皮を入れて煮出し、金茶色も作りました。参加者のお一人が友人に頼まれて持ってきたワンピースを、この液の中に入れて染めてみました。はげかかったベージュの色が、若干濃い目の茶色に変わり、もうしばらく着られそうな服に変身しました。たぶんきっと喜んでもらえることでしょう。
さて、どんぐり工房の定例の講習会、来月8月はお休みです。次回は、9月22日(日)。詳しくは豊田市広報やどんぐり工房のHPをご覧ください。