2月5日、足助交流館で開かれた車座ミーティングに参加しました。タイトルは「いなかをいなからしく磨き上げる」。豊田市内の都市部と山間部のコーディネート役として活動しているおいでんさんそんセンターの主催です。
このイベントは、数年前から毎年開かれているのですが、参加したのは今年が初めて。参加した理由は、基調講演の登壇者・石見銀山生活文化研究所の松場登美氏の話を聞きたかったからです。
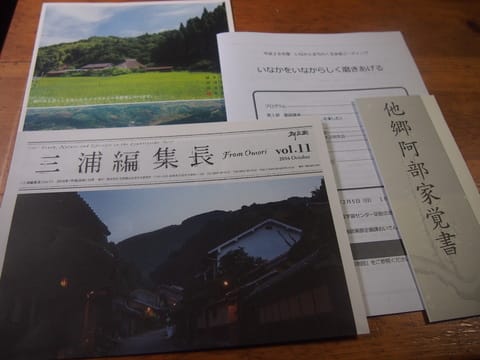
松場さんはアパレルメーカー・群言堂の代表。人口500人のかつて栄えた銀山の街なかに、会社を持ち、古民家を何軒も再生して、宿泊施設や店舗などとして利用しています。
群言堂の洋服は、足助の街中の本屋・マンリン書店で見たことがあります。質のいい生地を、着やすくしかもおしゃれに仕立てた服が並んでいました。わたし好みです。ほしかったけれど、おしゃれにお金をかける習慣のない私には即決する勇気がなく、そのままになっていました。
松場さんが講師ときいておもったのは、行政や地域の力を借りる前に、魅力的な個人や個店や企業があれば人は集まり、経済は豊かになり、地域は自然に活性化するだろう、とぼんやりこれまで私が思っていたことを、まさに体現している方のおひとりではなかろうかということです。
で、やはりそうでした。
彼女はいろいろ興味深い話をなさいましたが、なかでもわたしが共感した言葉はこれ。「一企業が地域のレベルを上げることはできる」
一企業が経済的に地域を豊かにすることは、日本中あちこちでやっています。私がすんでいる豊田市はまさにそう。もともと挙母町という町名だったのを、トヨタ自動車が移転したのにともない、名前まで変えてしまった。いまやたぶん、日本屈指の豊かな市だと思います。
でも、松場さんが言うのは、少し違います。「金銭も精神も両方を豊かに」し、「継続させるのが目標だ」とおっしゃいます。会社の方針は、100のうち、「文化に51かけ、経済に49かける」と決めているそうです。企業のメセナもさかんですが、それともちがう。なん百年も前の朽ちかけた古民家を再生し続けているのも、その方針から。そして、家を改築するだけではなく、そこに人がすんで家を生き返らせるのが目的だそう。
そのうちの一軒で、宿泊施設になっている「他郷阿部家」(宿泊施設)の写真が講演中何枚も紹介されました。「今の家は建てた直後が一番いい。でも昔の家はだんだんいい家になる」と、友人がいいましたが、まさにそのとおり、ちゃんと建てられた家は、住むほどに美しくなるのだなと思いました。
500人の小さな集落に、彼女の会社の社員は90人。それもほとんどよそから移住してきた20代30代の若い人たち。いまは、服だけでなく、種々の生活用品の開発にも取りくんでいるそうですが、それもみな、松場さんと若い社員たちの闊達なコミュニケーションによって生まれたようです。

午後は分科会に分かれて、話題提供者の話を聞き、ミーティング。わたしが出席したのは、スモールビジネス研究会。話題提供者の一人は、奥三河Three trees+のメンバーの三木和子さんでした。和子さんも、ほかのふたり~東栄町でdanonというシエアハウスを始めた金城愛さん、旭地区で農家民宿ちんちゃん亭を経営している鈴木桂子さん~も、移住に至るいきさつ、移住後の生活、家族のこと、仕事のこと、近隣との付き合いなどについて気負うことなく紹介。紹介の仕方がしっかりしていて、感心しました。
その後は、席の近い人たち数名とミーティング。
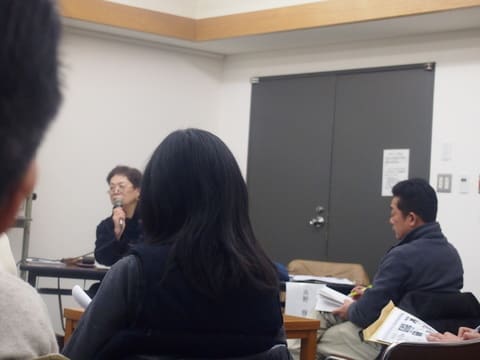
たまたま、移住者と都市住民と地元住民が車座になった形だったので、普段は聞けない意見が聞かれ、勉強になりました。
松場さんは私と同世代。わたしが田舎暮らしにあこがれ始めたころ、人里離れた銀山跡地の集落に移住しました。それからほぼ30年。当時は、あえて田舎を選ぶなど、よほどの事情があるか、相当酔狂な奴に違いないと思われていました。ところがいまや、田舎暮らしは、若い世代の結構な割合の人たちを魅了するくらしかたになっているのだとか。やっと話の合う人たちに出会うチャンスが増えるようになったな、と思うこの頃です。
このイベントは、数年前から毎年開かれているのですが、参加したのは今年が初めて。参加した理由は、基調講演の登壇者・石見銀山生活文化研究所の松場登美氏の話を聞きたかったからです。
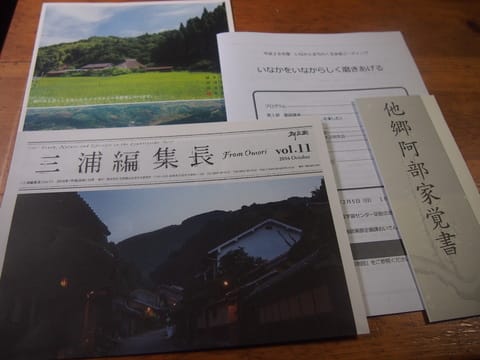
松場さんはアパレルメーカー・群言堂の代表。人口500人のかつて栄えた銀山の街なかに、会社を持ち、古民家を何軒も再生して、宿泊施設や店舗などとして利用しています。
群言堂の洋服は、足助の街中の本屋・マンリン書店で見たことがあります。質のいい生地を、着やすくしかもおしゃれに仕立てた服が並んでいました。わたし好みです。ほしかったけれど、おしゃれにお金をかける習慣のない私には即決する勇気がなく、そのままになっていました。
松場さんが講師ときいておもったのは、行政や地域の力を借りる前に、魅力的な個人や個店や企業があれば人は集まり、経済は豊かになり、地域は自然に活性化するだろう、とぼんやりこれまで私が思っていたことを、まさに体現している方のおひとりではなかろうかということです。
で、やはりそうでした。
彼女はいろいろ興味深い話をなさいましたが、なかでもわたしが共感した言葉はこれ。「一企業が地域のレベルを上げることはできる」
一企業が経済的に地域を豊かにすることは、日本中あちこちでやっています。私がすんでいる豊田市はまさにそう。もともと挙母町という町名だったのを、トヨタ自動車が移転したのにともない、名前まで変えてしまった。いまやたぶん、日本屈指の豊かな市だと思います。
でも、松場さんが言うのは、少し違います。「金銭も精神も両方を豊かに」し、「継続させるのが目標だ」とおっしゃいます。会社の方針は、100のうち、「文化に51かけ、経済に49かける」と決めているそうです。企業のメセナもさかんですが、それともちがう。なん百年も前の朽ちかけた古民家を再生し続けているのも、その方針から。そして、家を改築するだけではなく、そこに人がすんで家を生き返らせるのが目的だそう。
そのうちの一軒で、宿泊施設になっている「他郷阿部家」(宿泊施設)の写真が講演中何枚も紹介されました。「今の家は建てた直後が一番いい。でも昔の家はだんだんいい家になる」と、友人がいいましたが、まさにそのとおり、ちゃんと建てられた家は、住むほどに美しくなるのだなと思いました。
500人の小さな集落に、彼女の会社の社員は90人。それもほとんどよそから移住してきた20代30代の若い人たち。いまは、服だけでなく、種々の生活用品の開発にも取りくんでいるそうですが、それもみな、松場さんと若い社員たちの闊達なコミュニケーションによって生まれたようです。

午後は分科会に分かれて、話題提供者の話を聞き、ミーティング。わたしが出席したのは、スモールビジネス研究会。話題提供者の一人は、奥三河Three trees+のメンバーの三木和子さんでした。和子さんも、ほかのふたり~東栄町でdanonというシエアハウスを始めた金城愛さん、旭地区で農家民宿ちんちゃん亭を経営している鈴木桂子さん~も、移住に至るいきさつ、移住後の生活、家族のこと、仕事のこと、近隣との付き合いなどについて気負うことなく紹介。紹介の仕方がしっかりしていて、感心しました。
その後は、席の近い人たち数名とミーティング。
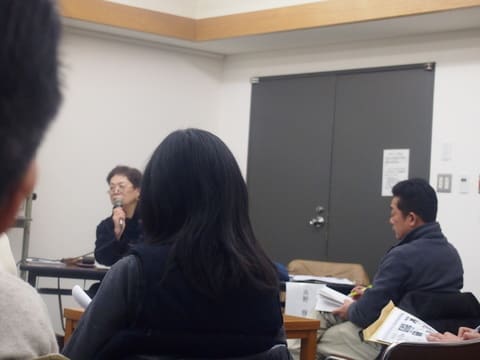
たまたま、移住者と都市住民と地元住民が車座になった形だったので、普段は聞けない意見が聞かれ、勉強になりました。
松場さんは私と同世代。わたしが田舎暮らしにあこがれ始めたころ、人里離れた銀山跡地の集落に移住しました。それからほぼ30年。当時は、あえて田舎を選ぶなど、よほどの事情があるか、相当酔狂な奴に違いないと思われていました。ところがいまや、田舎暮らしは、若い世代の結構な割合の人たちを魅了するくらしかたになっているのだとか。やっと話の合う人たちに出会うチャンスが増えるようになったな、と思うこの頃です。
















