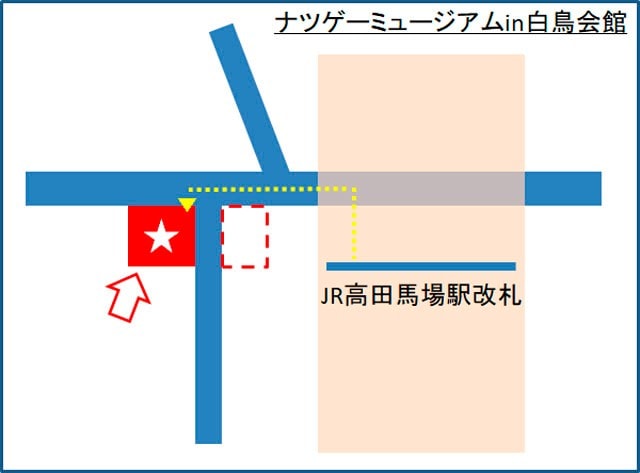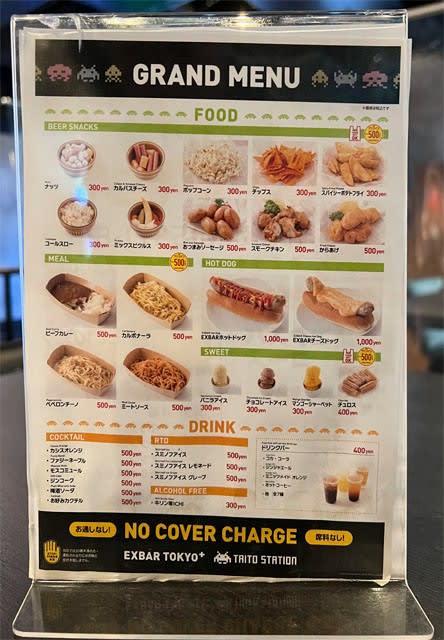大阪は阿倍野区文の里に、60年代(もしくはもっと古い)のコインマシンが遊べる「エレメカ研究所」があることを知ったのは、今から3年ほど前のことでした。これはいずれ訪れなければと思いつつも、何しろ東京からではそう気軽に行けるものでもなく、もたもたしている間にコロナ禍による「ステイホーム」が始まって、ますます行くチャンスが遠のいてしまいました。
文の里での「エレメカ研究所」は入場料制で運営して「博物館」を謳い、風俗営業(風俗第5号営業=ゲーセン)の許可を取らずに営業していたのですが、警察はこれを認めず、そして当時の所在地は風俗店の営業許可が下りない地域であったため、閉鎖のやむなきに至ったのが昨年の初めころでした。
警察がどんな経緯でエレメカ研究所を把握し、どのように接触してきて、どんなやり取りがなされたかには興味が惹かれますが、何にせよ、無許可営業で引っ張られるまでには至らなかったのは不幸中の幸いでした。
文の里閉鎖後もオーナーは不屈の精神で北区中崎西に移転先を見つけ、苦労の末に風俗営業の許可も取って再オープンにこぎつけたのが昨年(2022年)の暮れでした。オーナーの頑張りには大きな賛辞を贈りたいと思います。
SNSで再開を知ったワタシは、3年前のように逡巡ばかりしていては結局行かずに終わってしまうと一念発起して、遂に先月念願の訪問を果たしてまいりましたので、今回から何回かに分けてその時の記録を残しておこうと思います。
**************************
新大阪に到着したのが午前11時半頃。最寄り駅は谷町線中崎町とあったので梅田駅で乗り換えるルートを考えていたところ、SNSで「新大阪からなら、梅田駅の手前の中津駅から徒歩だと乗換えもなく早い」とアドバイスくださる方がいたので、それに従って現地に到着したのが12時15分頃でした。

エレメカ研究所の入り口。開店間もない時間だが、早くも中に数人の姿が見える。
店頭には場内での遊び方や看板、それにオバQのキディライドと、かつてキディライドのトップだったと思しきパンダの置物があります。

店頭の様子4枚。①場内での遊び方の説明と、手指消毒用アルコール。コロナ禍はまだ収まっていないのだ。 ②文の里時代から看板となっているオバQのキディライド。 ③エレメカ研究所の看板。 ④かつてキディライドの乗用部分だったと思しき部分。中村製作所(後のナムコ)が1973年にリリースした「ささぶねパンダ」と似る部分があるが形が異なる。謎。
オバQのキディライドは、文の里の頃からエレメカ研究所の看板として店頭に設置されていました。体重70㎏まで利用可能とのことです。キディライドの乗用部分と思しき部分は地面に固定されておらず、ワタシが滞在中に女子が一人、乗ろうとしてバランスを崩していました。もしかすると危険かもしれないので、固定するなり「乗らないでください」の注意書きを添えるなりした方が良いのではないかと思いました。
入り口の掲示にある通り、エレメカ研究所では硬貨(現金)とメダルを併用した運営が行われています。メダルは10円ゲーム用と100円ゲーム用の2種類があり、10円ゲーム用のメダルはメダル貸出機がありますが、100円ゲーム用のメダルは遊戯料金が100円のゲームのプライズとして払い出される以外には入手できません。
機械によっては硬貨とメダル共通の投入口を持つものもありますが、殆どの機械は現金の投入口の他にメダルの投入口を取り付ける改造が施してあります。今回は設置されている機種の中から、シングルロケ向けの、いわゆる「駄菓子屋ゲーム」と呼ばれるタイプを主としてまとめておきます。
店頭には表通りに向けて4機種が設置されていました。

店頭を飾る4機種。①タッチ! アクション(こまや 1980-81?) ②カエルのうた(こまや 1990) ③山のぼりゲーム(こまや 1981) ④ロボリング(阪急工芸 1972)
過去記事「初期の国産フリッパー・ピンボール機:こまや製作所製の2機種」でも述べましたが、こまやは安易な模倣に走ることなく、創意工夫に溢れた味のある機械を数多く作ったと思います。
店内はゲーム機の配置によって二つの通路が作られています。

入り口から見て左と右それぞれの通路。左の通路の壁側には接客カウンター、右の通路の壁沿いには比較的大型の機械が並ぶ。

駄菓子屋ゲームその1。①キャッチボール(メーカー不明、1998*) ②名称不明(メーカー、製造年不明) ③ロボット(KアンドU商会、1979) ④パイパイ45(メーカー、製造年不明) (*は、斯界では有名な「駄菓子屋ゲーム博物館」のウェブサイトによる情報)(③ロボットのメーカーと発売年が判明につき修正・23/4/10)

駄菓子屋ゲームその2。①森のゆうびんやさん(メーカー、製造年不明) ②キセノン(サミー工業、1983-84) ③スーパーカーズ(メーカー、製造年不明) ④スーパーカーズ(メーカー、製造年不明)

駄菓子屋ゲームその3。①日米対抗試合 (トークエレクトロニクス、製造年不明) ②W・ATTACK (メーカー、製造年不明) ③Super Flight (三共、製造年不明) ④アイスホッケー (メーカー、製造年不明)
「駄菓子屋ゲーム」は、業界紙誌で紹介されたり広告が掲載される例が少なく、またワタシ自身も駄菓子屋ゲームにはあまり馴染んでこなかったため記憶に残る機械は数えるほどしかありません。そのためメーカー名や製造年どころか本来の名称すら不明のものさえあります(上記画像「駄菓子屋ゲームその2」の③と④などはその好例)。もし、上記画像に見える機械のうちメーカーや製造年をご存じの方がいらっしゃいましたら、コメント欄などでぜひともご教示いただけますようお願い申し上げます。
(つづく)