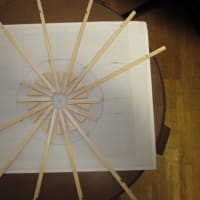巻第5「秋歌下」のトップ
249 吹くからに秋の草木のしをるれば むべ山風をあらしといふらむ
これさだのみこの家の歌合のうた
文屋やすひで
これさだのみこ=是貞親王、58代光考天皇(55才即位、58才没)の第二皇子
歌合=歌の品評会。入選するかしないかは、収入や出世に直結する、真剣勝負。
上の歌の次も、文屋やすひでの作。
250 草も木も色かはれども わたつうみの浪の花にぞ秋なかりける
これら2首の解釈は次。
・ 風が吹くたびに草木が萎れていきますが、この山風をあらし(荒ラシ)と(一般に)言うことは納得です。
・ (秋になると)草木は色を変えますが、海の浪(シラナミか?)は(いつも同じ色で、)秋を感じさせません。
西暦800年代の末期、文屋康秀は歌詠みとして有名であったらしい。実際、古今和歌集には、上以外に3首採録されているし、小野小町からの返歌も(名前つきで)載っている。
しかし、不思議なことに、わざわざ名指しをしている古今集の序での評価は、かんばしいものではない。
いわく「言葉はたくみにて、そのさま身におはず。いはば、商人(アキヒト)のよき衣(キヌ)たらんがごとし」(言葉使いは上手だけれども、それが人品の格と一致しない。例えれば、(利に敏い)商人が上等な服を着ているようなものだ)
のちの世に六歌仙と名付けられた6人すべての評価が、この文屋康秀同様、古今和歌集の序ではかんばしくないのです。
なぜなのでしょうか?
今のところ、梅原猛の考察に魅かれているのですが、もうすこし時間をかけて考えようと思います。
249 吹くからに秋の草木のしをるれば むべ山風をあらしといふらむ
これさだのみこの家の歌合のうた
文屋やすひで
これさだのみこ=是貞親王、58代光考天皇(55才即位、58才没)の第二皇子
歌合=歌の品評会。入選するかしないかは、収入や出世に直結する、真剣勝負。
上の歌の次も、文屋やすひでの作。
250 草も木も色かはれども わたつうみの浪の花にぞ秋なかりける
これら2首の解釈は次。
・ 風が吹くたびに草木が萎れていきますが、この山風をあらし(荒ラシ)と(一般に)言うことは納得です。
・ (秋になると)草木は色を変えますが、海の浪(シラナミか?)は(いつも同じ色で、)秋を感じさせません。
西暦800年代の末期、文屋康秀は歌詠みとして有名であったらしい。実際、古今和歌集には、上以外に3首採録されているし、小野小町からの返歌も(名前つきで)載っている。
しかし、不思議なことに、わざわざ名指しをしている古今集の序での評価は、かんばしいものではない。
いわく「言葉はたくみにて、そのさま身におはず。いはば、商人(アキヒト)のよき衣(キヌ)たらんがごとし」(言葉使いは上手だけれども、それが人品の格と一致しない。例えれば、(利に敏い)商人が上等な服を着ているようなものだ)
のちの世に六歌仙と名付けられた6人すべての評価が、この文屋康秀同様、古今和歌集の序ではかんばしくないのです。
なぜなのでしょうか?
今のところ、梅原猛の考察に魅かれているのですが、もうすこし時間をかけて考えようと思います。