人気小説家の桐野夏生さんの新作小説「デンジャラス」をやっと読み終えました。
この新作小説「デンジャラス」は、文豪の谷崎潤一郎の第二次大戦直後の作家活動を支えた女系家族の物語です。
この小説「デンジャラス」は2017年6月10日に中央公論新社が発行されました。価格は1600円プラス消費税です。
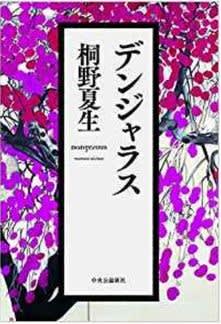
実は、一度は軽く眼を通したのですが、細部が分からない気がして、何回か読み返しました。
この小説の冒頭は、谷崎潤一郎が昭和26年(1951年)に詠んだ短歌から始まります。最愛の女性たちに囲まれた、君臨する主人として満足した私生活を送っていました。
その短歌は「つまいもうと娘花嫁われを囲むセンカン亭の夜のまどゐ哉」です。この“センカン亭”は、旧字の漢字なので、表示できません。
この短歌が詠まれた昭和26年(1951年)は、谷崎潤一郎が書いた小説「細雪」(ささめゆき)がヒット作となり、文化勲章を受章した時です。
第二次大戦時中は軟弱な女系家族の生活内容という中身から発禁扱いだった小説「細雪」が戦後になると読まれて、谷崎潤一郎が“文豪”と呼ばれ始めた時期でした。
この短歌の「つま」とは三番目の妻となった松子のことです。そして、「いもうと」とは松子のすぐ下の妹の重子(しげこ)を指しています。
「娘」とは、三番目の妻となった松子の連れ子の美恵子(みえこ)を指しています。「花嫁」とは、松子の連れ子の清一の嫁になった千萬子(ちまこ)を指しています。
この小説は、「いもうと」の重子の視点で描かれています。松子や重子は、小説「細雪」に描かれた四姉妹のモデルといわれています。そして、重子は「細雪」に描かれた三女の「雪子」のモデルとみなされています。
当時の谷崎潤一郎は血縁関係がない妻の親族の女性に囲まれた理想的な女系家庭をつくり、満足して暮らしていました。
この小説の後半部では、売れっ子小説家になり、多額の原稿料などが入るようになった谷崎潤一郎が、「花嫁」の千萬子を溺愛し、おねだりされた当時の高価な衣装などを無分別に買い与える行動を取ります。そこにはまさに危険な(デンジャラス)人間関係があります。
千萬子の嫁ぎ先の家に、谷崎潤一郎は毎日、手紙を熱心に送ります。この行動に、「いもうと」の重子はあきれかえり、戸惑います。
この小説は、血縁関係がない妻の親族の女性に囲まれた谷崎潤一郎の一見、奇妙な行動を描いています。
なお、短歌の中に出てきた“センカン亭”は、京都市の下鴨神社を囲む糺すの森に建てられた、そこそこ広い日本建築の建屋です。
谷崎潤一郎は京都市内で、関西人として豊かな生活を送っています。実は、第二次大戦中は疎開先などで、食料確保などにかなりの苦労をしています。ひ弱・軟弱な小説家はいる所がなかったからです。
この新作小説「デンジャラス」は、文豪の谷崎潤一郎の第二次大戦直後の作家活動を支えた女系家族の物語です。
この小説「デンジャラス」は2017年6月10日に中央公論新社が発行されました。価格は1600円プラス消費税です。
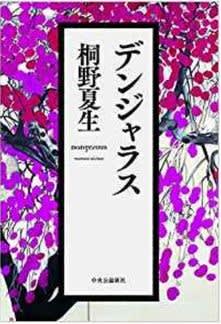
実は、一度は軽く眼を通したのですが、細部が分からない気がして、何回か読み返しました。
この小説の冒頭は、谷崎潤一郎が昭和26年(1951年)に詠んだ短歌から始まります。最愛の女性たちに囲まれた、君臨する主人として満足した私生活を送っていました。
その短歌は「つまいもうと娘花嫁われを囲むセンカン亭の夜のまどゐ哉」です。この“センカン亭”は、旧字の漢字なので、表示できません。
この短歌が詠まれた昭和26年(1951年)は、谷崎潤一郎が書いた小説「細雪」(ささめゆき)がヒット作となり、文化勲章を受章した時です。
第二次大戦時中は軟弱な女系家族の生活内容という中身から発禁扱いだった小説「細雪」が戦後になると読まれて、谷崎潤一郎が“文豪”と呼ばれ始めた時期でした。
この短歌の「つま」とは三番目の妻となった松子のことです。そして、「いもうと」とは松子のすぐ下の妹の重子(しげこ)を指しています。
「娘」とは、三番目の妻となった松子の連れ子の美恵子(みえこ)を指しています。「花嫁」とは、松子の連れ子の清一の嫁になった千萬子(ちまこ)を指しています。
この小説は、「いもうと」の重子の視点で描かれています。松子や重子は、小説「細雪」に描かれた四姉妹のモデルといわれています。そして、重子は「細雪」に描かれた三女の「雪子」のモデルとみなされています。
当時の谷崎潤一郎は血縁関係がない妻の親族の女性に囲まれた理想的な女系家庭をつくり、満足して暮らしていました。
この小説の後半部では、売れっ子小説家になり、多額の原稿料などが入るようになった谷崎潤一郎が、「花嫁」の千萬子を溺愛し、おねだりされた当時の高価な衣装などを無分別に買い与える行動を取ります。そこにはまさに危険な(デンジャラス)人間関係があります。
千萬子の嫁ぎ先の家に、谷崎潤一郎は毎日、手紙を熱心に送ります。この行動に、「いもうと」の重子はあきれかえり、戸惑います。
この小説は、血縁関係がない妻の親族の女性に囲まれた谷崎潤一郎の一見、奇妙な行動を描いています。
なお、短歌の中に出てきた“センカン亭”は、京都市の下鴨神社を囲む糺すの森に建てられた、そこそこ広い日本建築の建屋です。
谷崎潤一郎は京都市内で、関西人として豊かな生活を送っています。実は、第二次大戦中は疎開先などで、食料確保などにかなりの苦労をしています。ひ弱・軟弱な小説家はいる所がなかったからです。











































