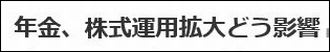長野県佐久市の東端にある佐久荒船高原は、ここ数日間は濃霧に包まれ、強風が吹き、雨がたくさん降りました。
台風10号が本州南側の太平洋上を比較的ゆっくりと北東方向に進んだ結果、関東甲信越地方に強風と雨をもたらしたからです。8月29日夜から30日正午までは、佐久市や北佐久郡軽井沢町などには、雷と大雨による洪水注意報が出ていたそうです。
30日の午後2時過ぎから、佐久荒船高原は台風一過の快晴になりました。
佐久荒船高原の南側にそびえている荒船山(標高1423メートル)の山頂部分をやっと望むことができました。


午後4時過ぎの西日が艫岩(ともいわ)に当たっています。まだ夏の夕日です。
ここ数日間は、濃霧に包まれ、荒船山はまったく見えませんでした。
佐久荒船高原の中心部にある“コスモスの丘”では、コスモスの背丈が1メートル程度まで育っています。

コスモスは、ここ数日間の強風や大雨にも耐え、ほとんど倒れていません。
コスモスは、ポツポツと花を咲かせ始めています。


佐久荒船高原の雑木林の斜面では、濃い桃色のツリフネソウ(釣船草)の花が咲いています。


ツリフネソウの近くには、キツリフネも咲いています。
ナンブアザミあるいはツクシアザミではないかと推測したアザミ系の花には、アブが来ています。

佐久荒船高原では、夏の山野草が花期を終え、秋の山野草に代替わりしています。
台風10号が本州南側の太平洋上を比較的ゆっくりと北東方向に進んだ結果、関東甲信越地方に強風と雨をもたらしたからです。8月29日夜から30日正午までは、佐久市や北佐久郡軽井沢町などには、雷と大雨による洪水注意報が出ていたそうです。
30日の午後2時過ぎから、佐久荒船高原は台風一過の快晴になりました。
佐久荒船高原の南側にそびえている荒船山(標高1423メートル)の山頂部分をやっと望むことができました。


午後4時過ぎの西日が艫岩(ともいわ)に当たっています。まだ夏の夕日です。
ここ数日間は、濃霧に包まれ、荒船山はまったく見えませんでした。
佐久荒船高原の中心部にある“コスモスの丘”では、コスモスの背丈が1メートル程度まで育っています。

コスモスは、ここ数日間の強風や大雨にも耐え、ほとんど倒れていません。
コスモスは、ポツポツと花を咲かせ始めています。


佐久荒船高原の雑木林の斜面では、濃い桃色のツリフネソウ(釣船草)の花が咲いています。


ツリフネソウの近くには、キツリフネも咲いています。
ナンブアザミあるいはツクシアザミではないかと推測したアザミ系の花には、アブが来ています。

佐久荒船高原では、夏の山野草が花期を終え、秋の山野草に代替わりしています。