今日はなんだかぼんやりしており、品物を入れたままスーパーのかごを家まで持って帰ってしまいました。
さて、先日の首都高料金に関するエントリー、特にETCの代替となる簡易無線機にかんしていくつかコメントをいただいている。
一方、首都高速道路㈱は距離別料金についてのプレスリリースを発表した。
距離別料金に関する懇談会からの提言及び意見募集の開始について
この中に「距離別料金の意見募集案」というPDFファイルがあり、その中、36ページにETCに変わる補完システムについての言及がある。
デポジット方式のETCパーソナルカード、というのは信用状況の関係でクレジットカードを作れないユーザーの救済措置であり、これはわかる。
次の、無線装置というのが問題だ。
・料金所で停止をして、電子マネーで上限額を前払いする。
・無線装置で入口・出口を把握する。
・前払い額と距離別料金の差額を電子マネーで返金する。
無線装置はETC車載器類似の装置で、簡便に自動車に装着できるものを想定している。
J氏からも指摘があり、私も2004年11月頃のエントリーで指摘しているが、これはシンガポールのEPRと同じような仕組みになるのではないか。
多分、技術的には入口でいったん停止をする必要はなく、単にETCと利便性に関して政治的に差別化を図る必要があるだけだと思う。
でも、結局のところ「ETCはこの程度のものでよかったのだ」というのが答えじゃないのか?
どうせDSRC商業利用などの発展もあまり期待できないんだから、今からでもいいから仕様を落として高速料金支払い専用の廉価バージョンをつくり、無償配布をするという選択肢だってあるのかもしれない。
さて、先日の首都高料金に関するエントリー、特にETCの代替となる簡易無線機にかんしていくつかコメントをいただいている。
一方、首都高速道路㈱は距離別料金についてのプレスリリースを発表した。
距離別料金に関する懇談会からの提言及び意見募集の開始について
この中に「距離別料金の意見募集案」というPDFファイルがあり、その中、36ページにETCに変わる補完システムについての言及がある。
デポジット方式のETCパーソナルカード、というのは信用状況の関係でクレジットカードを作れないユーザーの救済措置であり、これはわかる。
次の、無線装置というのが問題だ。
・料金所で停止をして、電子マネーで上限額を前払いする。
・無線装置で入口・出口を把握する。
・前払い額と距離別料金の差額を電子マネーで返金する。
無線装置はETC車載器類似の装置で、簡便に自動車に装着できるものを想定している。
J氏からも指摘があり、私も2004年11月頃のエントリーで指摘しているが、これはシンガポールのEPRと同じような仕組みになるのではないか。
多分、技術的には入口でいったん停止をする必要はなく、単にETCと利便性に関して政治的に差別化を図る必要があるだけだと思う。
でも、結局のところ「ETCはこの程度のものでよかったのだ」というのが答えじゃないのか?
どうせDSRC商業利用などの発展もあまり期待できないんだから、今からでもいいから仕様を落として高速料金支払い専用の廉価バージョンをつくり、無償配布をするという選択肢だってあるのかもしれない。
















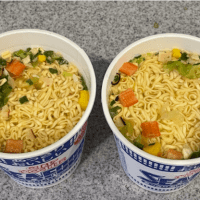
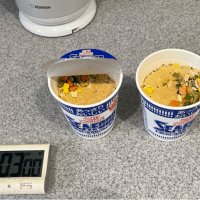


参宮橋カーブ実験ではDSRCを使うようです。「商業利用が期待できない」から、とにかくETCを普及させ、それをベースにDSRCを使う環境を無理やりつくろうとしているように感じます。
国家詐欺だし、こういうところでアメリカあたりがグローバルスタンダード論で、市場を開放せよ、というととたんに日本政府も、企業もガタガタと崩れる。そんな筋書きが見えるように思います。
日本政府は道路特定財源などという別ポケットを持ってるから、政府全体としては借金だらけなのに、道路関係事業でどこで金が使えるか、国土交通省道路局の役人はいつもそれを考えてるんじゃないかと思います。
ETCを使えばディスカウント、と仕組みにも道路特定財源がだいぶつかわれているんじゃないでしょうか?
(このこと、要確認ですが。)
研究は国土交通省国土交通政策総合研究所(国総研)と自動車メーカー、カーナビメーカーなど23社。大部の報告書で技術的なことも多いのでまだ読みきったわけではないのですが(言い訳です)、ETCでつかった5.8GHzDSRCが、ETCだけじゃなく、ITSの全体に使える、ということを強調するための報告書みたいなのです。
たとえば、この研究報告の第2章に
「本共同研究では、以下の3 つのサービスを実現させるため、設置するDSRC 路側無線装置及びITS車載器の機器仕様、両機器間の通信及びデータ仕様等を検討することを目的とする。」 とあり、「3つのサービス」のひとつが「(1)道路上における情報提供サービス 5.8GHzDSRC を用いて、音声・画像情報やアップリンク情報等により、分かりやすい情報や案内注意情報を提供し、安全・安心に寄与するためのサービス」
とあります。このサービスは参宮橋カーブ実験そのもののように思えます。
この研究の前提が、ETCが1100万台普及した、というところにあることが、第1章などからわかります。
すみません。技術音痴を助けることもかねて、お時間のおありのとき、この報告書、チラチラと見て、感想をお伝えいただけませんか?