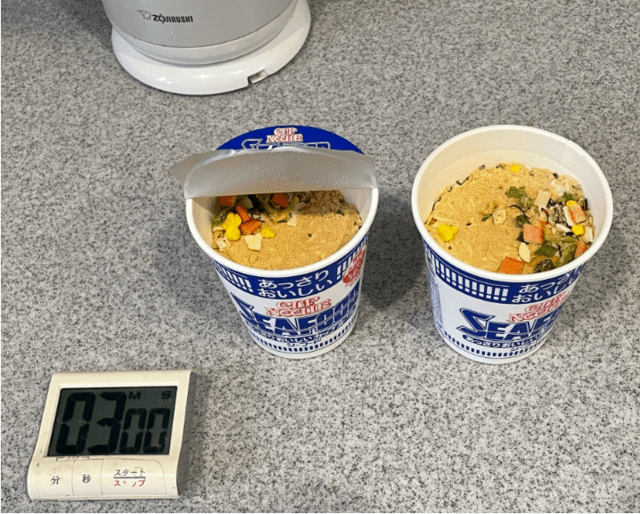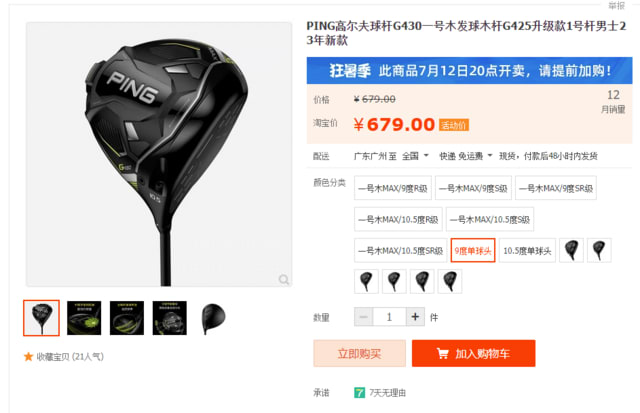HUAWEI(ファーウェイ) WATCH GT 4、ソフトウエアアップデートでゴルフナビ機能が追加になったということなので購入し使ってみた。

普通のクロノグラフに見える
時計自体の評価は別の機会に譲るが、一口で言えば
・コスパが良い。楽天のポイント還元含めて3万円で購入(グリーンバンド仕様)
・フェースデザインを選ぶと普通のクロノグラフのように見える。個人的には好み。
・バッテリ持ちはアップルウォッチとは比較にならないくらい良い
・母艦がiPhoneだとできることは最低限になる
さて、肝心のゴルフナビだが、先に長所短所を書いておく。
長所
・バッテリーを気にする必要なし。満充電からラウンド終了時で残量78%。アップルウォッチは通信環境にもよるが、昼休みを挟んでワンラウンドもたないことがある。
・ピンまでの距離は他のゴルフナビと変わらず普通に使える
・ウォッチ画面タップでレイアップ検討ができる(バンカー手前で50ヤード残しなら150ヤード打つ、など)
・(なんと)ショット検知機能がついているのでラウンド振り返りが可能。
・スコア入力は特にストレスなく可能。(ただし本人のみ)
・専用機ではなくスマートウォッチがゴルフナビなので無駄がない。
ショット感知はガーミンの売り物だが、この時計は搭載している。筆者はiPhone+Golfshotの有料サブスクでショット検知を利用しているが、Huawaiは標準搭載。
iPhone+Golfshotのショット検知は結構誤検知が多く、歩きながら無意識に素振り動作をするとそれで1打カウントしちゃうところがあるが、Huawaiはかなり正確。
ただしアプローチショットは検出されないことが多かった。
正確なショット検知はスイングとインパクト時の衝撃を感知しないとできないが、Huawaiの仕組みはどこにも記載がない。
邪推だがガーミンの特許との関係があるのかもしれない。
短所
・ショット検知はついているが、飛距離表示は実際のティーショット地点が基点ではなく、データ上のバックティーが基点らしい(多分)
ティーショットを打った直後に30ヤードとか表示される。なので後で見返して240ヤード飛んでても実際とは違うようだ。
またセカンドショット以降もショット検知はするが、飛距離表示は更新されないようだ。なお、スマホソフト上で軌跡という振り返り機能をつかうと
セカンド、サードショットの飛距離は表示される。
また前述のとおり、フルショットに近いショットじゃないと検知しない。30ヤード程度のアプローチは検知できていない模様。

スマホソフト上の軌跡画面。ティーショットの235ydは多分青ティーからの距離。グリーン周りでミスがありダボなんだけどそのアプローチは検出できていない
・スマホ側のソフトはあくまでHuaweiの健康管理ソフト「HUAWEIヘルス」の一項目なので、スマホ画面からはほぼ何もできない。
なので細かい設定などはできない。
・ゴルフナビのUIはお世辞にもいいとは言えない。
・コースデータのダウンロードとウォッチへの転送は結構時間がかかるので事前にWIFI環境でやっておいたほうが良い
・コースダウンロードの時点ではAグリーン、Bグリーンの選択はできず、デフォルトでAグリーンになっている。Bグリーンの時は毎ホール手動で修正が必要。
これは画面の右上にある小さなAという表示を押すことでBに切り替えが可能。ただしこの機能については一切説明されていない。
・主要ハザードまでの距離表示なし
・グリーンのフロントエッジ、バックエッジの距離表示なし
・今のところ国内専用
結論
残り距離の表示、コース図、レイアッププランの表示など基本は押さえられているが総合的な使い勝手は専用品のほうが良いと思う。
ただしショット検知がついているのは特筆出来る点。
ショット検知機能からの応用がまだ不十分だけど、これはソフトウエアアップデートを期待したい。