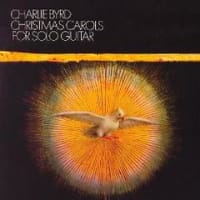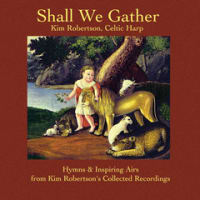”Nina de fuego”by Buika
黒人女性のフラメンコ歌手である、まあ雑にいえば。
アフリカはギニアをルーツに持ち、スペインの島嶼部に育つ、という出自を聞いてもあまり具体的なイメージが湧かない。これが北アフリカ出身の両親に連れられてフランスはパリで移民の子として育つ、とか言うなら、聞き覚えのある物語のいくつかは浮かんでくるのだが。
なにしろ赤道近くの土地から「ピレネー山脈を超えれば、そこはもうアフリカである」なんていわれもしたスペインの地に移動したなんてのは、夢想好きな野次馬であるワールドミュージック・ファンとしては、一幕の幻想から別の幻想に移動した、という感じで受け取ってしまう。
小さな女の子の手を引いた黒人の夫婦が、ダリやらキリコやらが描いたシュールで強烈なスペインの風土と色彩の中に悄然として立っている、なんてイメージが広がり、そしてそのまんまの音楽が、このCDからは聴こえてくる仕組みだ。あっと、これは Buika の3枚目のアルバム、2008年作。
定番のフラメンコ・ギターや手拍子のテンション高いパッセージも聴こえて来はするのだが、それより彼女の世界を印象的に構成するのは、ジャズの匂いを振りまくピアノやら、レイジーに揺れ動きリズムを穿つウッドベースの響きだ。時のむこうのアメリカ南部、綿畑の過酷な労働の思い出、安酒と博奕打ちの風景。などなどが遠くヨーロッパの地で育まれたジプシーの激情と無理やり同居している、そんな一幕が刺激的でたまられない。
音楽的越境を当たり前のようにする彼女だが、ラテン音楽の範疇のものは、スペインの音楽を根に持つ彼女に無理がない分、スリルには欠けるような気がする。だからそのような曲でも、間奏のジャズィなトランペットの響きの方に、つい耳を傾けてしまったりする。
フラメンコで鍛えたBuikaの錆びた声が鳴り響く。乾燥した土地の上をありえない砂嵐が駆け抜ける。
やっぱり彼女は時空を超えたシュールな絵の中の人で、ひび割れたスペイン窓の外はミシシッピーが流れ、遠く向こう岸に霞むアフリカ。まるでスロー・ブルースみたいな啖呵の切り方を見せる ”Volver,Volver ”なんか、相当にカッコ良い。