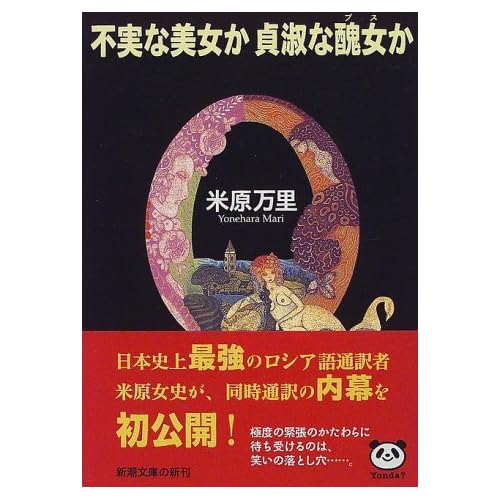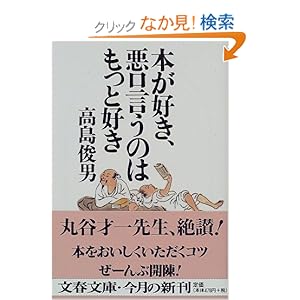
第11回講談社エッセイ賞受賞の評論集です。著者は、本書編集にたずさわった小宮久美子さんの力が甚大で、いいエッセイ集になったというようなことを書いています。
それはともあれ、著者は中国文学者で、1938年生まれ。本書からいろいろなことを学びました。
「欠伸」「呆然(茫然)」「専家」「降灰(コウカイ)」「子息」「指摘」「母語」などの蘊蓄。徹底的な字義詮索、コダワリを見せています。
書評も痛快で面白いです。(『狐の書評』本の雑誌社、みなもと太郎『風雲児たち①~⑳』潮出版社、奥本大三郎『虫のゐどころ』新潮社、若桑みどり『絵画を読む』日本出版協会、久保忠夫『三十五のことばに関する七つの章』大修館書店、長谷川真理子『オスとメス=性の不思議』講談社現代新書、高橋秀美『TOKYO外国人裁判』平凡社、石川英輔『泉光院江戸旅日記』講談社、向井敏『表現とは何か』文藝春秋)
「湖辺萬筆」の「つかまったのが何より証拠」は怖い話です。電車の切符を買うときのふとした出来事で、個室に連れ込まれ、尋問された状況が詳しく説明され、自白にともなう「冤罪」というのもこういうことで成立してしまうのかと戦慄を覚えます。
「ネアカ李白とナクラ杜甫」も両者の対照的な育ち、人格、生き方、しかしお互いに尊重しあっていたということが分り易く解説されていました。
「回やその楽を改めず」では碩学の狩野享吉の話ですが、露伴、漱石などとの人間関係が詳らかにされていて興味尽きません。
本書の白眉は、今では使われなくなってしまった「支那」という言葉がもともとは差別用語ではないことを論じた「『支那』は悪いことばだろうか」です。差別用語でないどころか、魯迅も、日本の代表的中国研究者であった吉川幸次郎も好んで使っていたことが明らかにされ、しかしある時からこの言葉に差別観が刷り込まれ、以来不幸な成行きに身をまかせ、死語になってしまったことが追跡されています。あわせて中国という言葉の曖昧さにも言及があります。
著者のように自由闊達に、権威から遠いところで仕事ができる人は羨ましいですね。