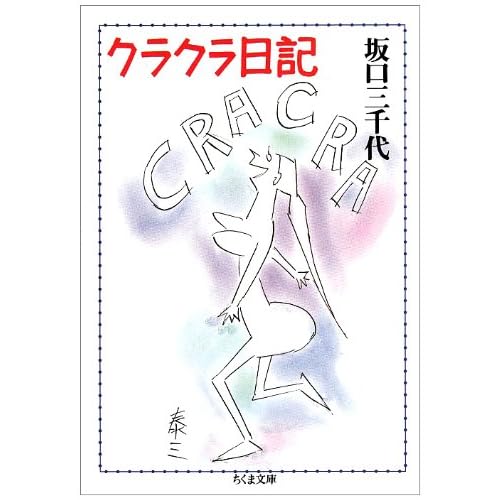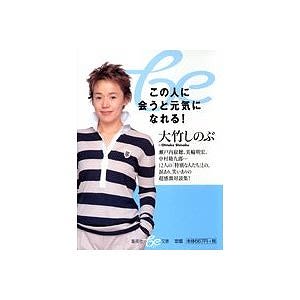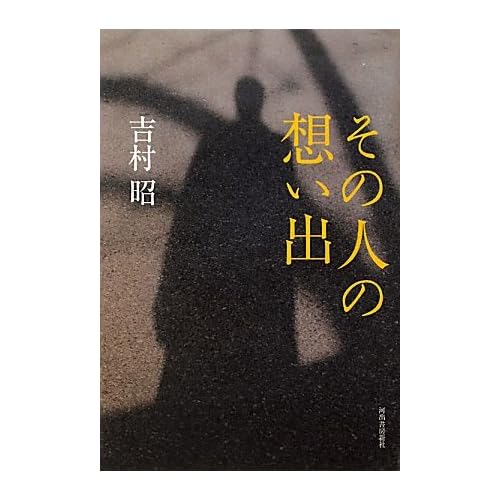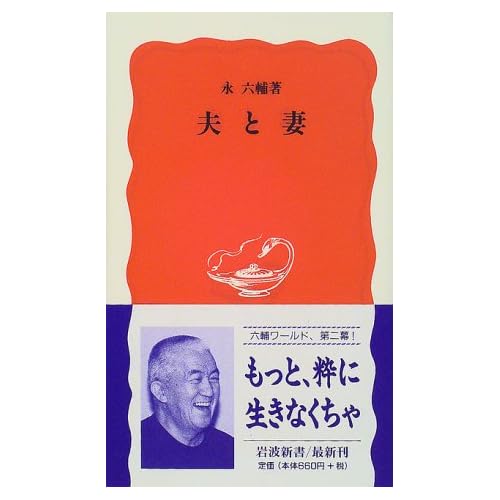大阪を描くことから、そして人間を描くことから小説が始まるそうです(人間を描くということでは、バルザックを目指している)。後者は作者が「社会派小説家」とみなされることに対する控えめな反論です。結果として社会問題を抉りだす小説をつくってきたので、社会派と呼ばれるのですが、その呼称は本意ではないようです。
「人間を描くこと」が最初で、社会や組織は後から構成されていくという小説作法とか。また、小説の構想を時間をくみたてることにかなりの時間を要し、ある程度、結論まで出来上がった段階で書き始めるとか。
著者は、取材が本当に好きと語っています。そのための予習は生半可ではありません。最初は素人で知識がなくとも、調べをしっかりして熱意で取材にあたるという方法論です。
『華麗なる一族』では、取材のおりにもらった名刺が250枚くらいと書かれていました。取材拒否にも相当遭遇したらしいです。『白い巨塔』では医学の世界でタブーであった誤診をとりあげたので、取材拒否にあいました。
とことん調べるその追求力はただものではく、いくつかその例があげられています。ひとつ、『女の勲章』で最後の部分でパリが舞台になるにもかかわらず、病気で行けなかったので、大きなパリの地図を壁にはって、イメージを広げたという裏話、もうひとつは「大阪格子」の語源が分らず文献資料もなかったので、船場の古老を探して聴き回り半年かかった話です。
そうした裏話も面白いですが、「第二章:あのひとやつしやな-大阪あれこれ」で上方文化をとりあげて話題にしているところが秀逸です。大阪の船場という特殊な家族制度、風習、風俗、言語、大阪弁などなど。「大阪女系分布図」では、女性の呼称にヴァラエティがあり(「嬢はん(いとはん)」「御寮人はん(ごりょんはん)」「お家はん(おえはん)」)、その由来が記されている。
著者はこうした上方文化をハワイ州立大学で客員教授だったときに、自らの小説をテキストに向こうの学生に講義し、理解してもらったようである(「上方文化ハワイに芽生える-プロフェッサー・ヤマサキの”ぼんち通信”」)。
全編、大阪文化が匂いたってくるエッセイの連続である。