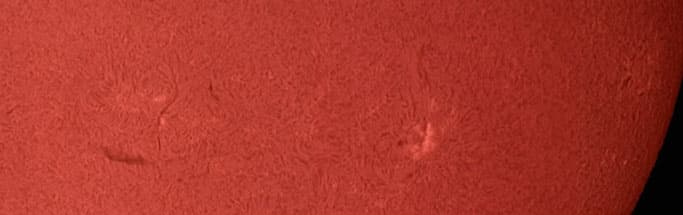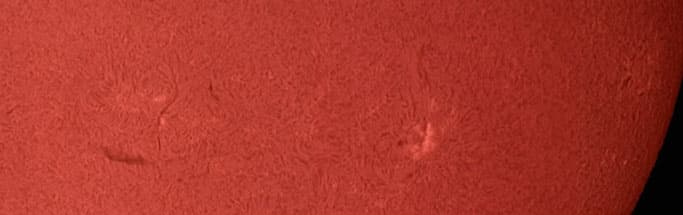某オークションでセレストロンSC235を落札してしまった。
前オーナーが2001年に新品で購入したものなのでそれほど旧式ではない。
入札前に少し調べたが、このSC235(C9,1/4)はKYOEYなどから発売されているC9とは色違いで仕様も若干違うのかもしれないが・・・。
VIXENから発売されたシリーズです。

シュミカセは光軸調整など若干難しいところもありますが、なんといっても魅力はコストパフォーマンス(中古なのでなおさらですが)が高いこととバックフォーカスにゆとりがあることとです。
将来的にAOなど光学補償系を使うこともできます。
高橋のμ-180も気に入っているのですが、バックフォーカスにゆとりが無く拡張性に欠ける。
去年の夏に使っていたC8-EXはなんとなくしっくりこなかった、光軸が狂っていたことも原因とおもいますが・・・。
このC9はC8より32mm口径が大きいだけであるが、ネットで見るとなかなか評判が良い。私の好きな○さんもC9はとてもいいと言っていた。
C8を使いこなせばいいのでしょうけど、いわゆる相性もあると思いますがC9は何となく気に入った。
下の黒いC8と比較した大きさです。

ミラーシフトはC8の富田式ミラーシフトロックを流用した。
今夜は星が出ているのでテストしたいのだが、まだ台の固定やらフードを作らなければならない。フードにはファンを取りつけようと思っている。