日馬富士が横綱になる際、横綱審議委員会は満場一致で推挙したが、「張り手やけたぐりは、禁じ手ではないが、自覚を促したい」「横綱の自覚を持って、張り手は慎んでほしい」といった前代未聞の注文が付いたそうだ。
これに関して、『Number Web』で「横綱・日馬富士は、張り手、けたぐりを自重すべきか?」というレポートを挙げている。
この記事で、自重すべきかのアンケートで、「自重すべきでない」が6割を占めていた。
①「張り手やけたぐりはルール上認められている技である。認められている技なのに、横綱だからと言って制限するのはおかしい」
②「横綱に品格を求めること自体がナンセンス」
③「張り手は日馬富士の闘志の表れで、非難されるものではない」
などが主な理由。
①については、論破するのはなかなか難しい。(明徳義塾の「4打席敬遠」を思い出すなあ)
これは、②にも関連するが、ここでは、「張り手・けたぐり」の技の性質のみを考えてみる。
まず、「張り手」だが、これは決まり手ではなく、技の一つ。「突っ張り」に類するものと考えられる。
顔をビンタすることにより怯ませ、それに乗じて、押し込んだり、まわしをつかむ「導入技(きっかけの技)」である。(張っておいて四つになることを「張り差し」という)
と言っても、大きな手で相当な腕力でビンタをするのだから、まともに食らったら、相当な衝撃であり、当たり所によっては、脳震盪や目や耳にも障害が出そうである。
よって、金的攻撃や髷をつかんでの攻撃と同様、禁止すべきだと考える。
張り手のデメリットとしては、「張り手を繰り出す瞬間、脇が空くので、そこをついて下から入られると体を起こされてしまう」が挙げられるが、これは立ち合いの時に繰り出す張り手の場合で、相撲の途中で繰り出される張り手は、これを交わすのは難しい。体力も消費しているので、張り手の機を突いて一気に寄り切るのはなかなか難しい。
本日の日馬富士×稀勢の里戦がその例で、動き回り足が止まり、体がやや離れ見合った直後、張り手を繰り出した。1、2発目はクリーンヒットしなかったが、それでも、目の付近にあたるので、稀勢の里の動きが止まる。さらに、2、3発繰り出す。そのうちの1発当たり、体が硬直する。それでも、稀勢の里は怯まず押しに出るが、目を瞑り気味に顔もそむけながら出るので、日馬富士の肩透かしを決められてしまった。
「張り手」は勝つために相当有効な技だと言える。
「けたぐり」はどうだろう。足を掛けることで、相手の体勢を大きく崩すことが目的であるが、この技だけで決まってしまうこともある(技であるが、「決まり手」にもなる)。
これで決められなくても、大きく体勢を崩させ、そこを一気に決めないと、逆に不利になるリスクの大きい技である。なぜなら、自分の足を出てきた相手に掛けるので、自分の足を前に大きく出さないと届かず、相当のけぞった体勢になり、失敗すると簡単に寄り倒されたり、突き倒されたりする。
技の熟練度やタイミングが必要で、成功率は低いので、地力が上の者が繰り出すメリットはない。下位のものが、一か八かで繰り出す技なので、規制する必要はない。
②と③については、「相撲そのものの品格」と、「態度の品格」と分けて考える。
横綱は相撲界の顔であり、強い横綱、熟練した技を期待される。基本給(賞金以外)も高いので、求められるのは当然と言える。
今場所6日目、日馬富士×栃煌山戦、結びの一番だった。
「はっけよ~」と行事が発した瞬間、日馬富士が左に飛んで引き技。一応、まわしを掴んで送り出し気味なので決まり手は「上手投げ」であるが、内容的には「はたき込み」や「引き落とし」に近い。
結びの一番である。わざわざ国技館に足を運び、最後まで残って、横綱の相撲を待っていたお客さんに見せる相撲ではない。そういえば、白鳳相手の優勝決定の大一番で、大きく体をかわして「はたき技」を決めたこともあったっけ…
確かに、横綱は強いことが第一だが、「勝てばいい」というものではない。
「汚い技」「卑怯な技」という表現を使って良いかは疑問はあるが、これでは、面白くない。魅力ゼロである。
「態度の品格」についても、横綱は求められるモノだと考える。日馬富士について言うと、とにかく「我を忘れやすい」。立ち合いで押し切れないと、もう反射的に手が顔に向かう。今、NHKのスポーツニュースでちょうど稀勢の里戦をやっていた。数えると、7~8回、日馬富士の手が稀勢の里の顔に当たっていた。闘志の延長というより、癖か単に頭に血が上っただけのように思える。(白鳳も時々ある。また、張り差しも時々する)
「頭に血が上った」と考えるのは、押し出しが決まった時、相手の体が絡まって離れない時があるが、そういう場合、日馬富士はその体を引きはがすため、必要以上に相手の体を突き飛ばすことが多い。「ダメを押す」力強さとも観ることができるが、そうは思えない。
6日目の結びの一番で、変化技を決めた時、お客さんは日馬富士をもっと野次るべきであった。
これに関して、『Number Web』で「横綱・日馬富士は、張り手、けたぐりを自重すべきか?」というレポートを挙げている。
この記事で、自重すべきかのアンケートで、「自重すべきでない」が6割を占めていた。
①「張り手やけたぐりはルール上認められている技である。認められている技なのに、横綱だからと言って制限するのはおかしい」
②「横綱に品格を求めること自体がナンセンス」
③「張り手は日馬富士の闘志の表れで、非難されるものではない」
などが主な理由。
①については、論破するのはなかなか難しい。(明徳義塾の「4打席敬遠」を思い出すなあ)
これは、②にも関連するが、ここでは、「張り手・けたぐり」の技の性質のみを考えてみる。
まず、「張り手」だが、これは決まり手ではなく、技の一つ。「突っ張り」に類するものと考えられる。
顔をビンタすることにより怯ませ、それに乗じて、押し込んだり、まわしをつかむ「導入技(きっかけの技)」である。(張っておいて四つになることを「張り差し」という)
と言っても、大きな手で相当な腕力でビンタをするのだから、まともに食らったら、相当な衝撃であり、当たり所によっては、脳震盪や目や耳にも障害が出そうである。
よって、金的攻撃や髷をつかんでの攻撃と同様、禁止すべきだと考える。
張り手のデメリットとしては、「張り手を繰り出す瞬間、脇が空くので、そこをついて下から入られると体を起こされてしまう」が挙げられるが、これは立ち合いの時に繰り出す張り手の場合で、相撲の途中で繰り出される張り手は、これを交わすのは難しい。体力も消費しているので、張り手の機を突いて一気に寄り切るのはなかなか難しい。
本日の日馬富士×稀勢の里戦がその例で、動き回り足が止まり、体がやや離れ見合った直後、張り手を繰り出した。1、2発目はクリーンヒットしなかったが、それでも、目の付近にあたるので、稀勢の里の動きが止まる。さらに、2、3発繰り出す。そのうちの1発当たり、体が硬直する。それでも、稀勢の里は怯まず押しに出るが、目を瞑り気味に顔もそむけながら出るので、日馬富士の肩透かしを決められてしまった。
「張り手」は勝つために相当有効な技だと言える。
「けたぐり」はどうだろう。足を掛けることで、相手の体勢を大きく崩すことが目的であるが、この技だけで決まってしまうこともある(技であるが、「決まり手」にもなる)。
これで決められなくても、大きく体勢を崩させ、そこを一気に決めないと、逆に不利になるリスクの大きい技である。なぜなら、自分の足を出てきた相手に掛けるので、自分の足を前に大きく出さないと届かず、相当のけぞった体勢になり、失敗すると簡単に寄り倒されたり、突き倒されたりする。
技の熟練度やタイミングが必要で、成功率は低いので、地力が上の者が繰り出すメリットはない。下位のものが、一か八かで繰り出す技なので、規制する必要はない。
②と③については、「相撲そのものの品格」と、「態度の品格」と分けて考える。
横綱は相撲界の顔であり、強い横綱、熟練した技を期待される。基本給(賞金以外)も高いので、求められるのは当然と言える。
今場所6日目、日馬富士×栃煌山戦、結びの一番だった。
「はっけよ~」と行事が発した瞬間、日馬富士が左に飛んで引き技。一応、まわしを掴んで送り出し気味なので決まり手は「上手投げ」であるが、内容的には「はたき込み」や「引き落とし」に近い。
結びの一番である。わざわざ国技館に足を運び、最後まで残って、横綱の相撲を待っていたお客さんに見せる相撲ではない。そういえば、白鳳相手の優勝決定の大一番で、大きく体をかわして「はたき技」を決めたこともあったっけ…
確かに、横綱は強いことが第一だが、「勝てばいい」というものではない。
「汚い技」「卑怯な技」という表現を使って良いかは疑問はあるが、これでは、面白くない。魅力ゼロである。
「態度の品格」についても、横綱は求められるモノだと考える。日馬富士について言うと、とにかく「我を忘れやすい」。立ち合いで押し切れないと、もう反射的に手が顔に向かう。今、NHKのスポーツニュースでちょうど稀勢の里戦をやっていた。数えると、7~8回、日馬富士の手が稀勢の里の顔に当たっていた。闘志の延長というより、癖か単に頭に血が上っただけのように思える。(白鳳も時々ある。また、張り差しも時々する)
「頭に血が上った」と考えるのは、押し出しが決まった時、相手の体が絡まって離れない時があるが、そういう場合、日馬富士はその体を引きはがすため、必要以上に相手の体を突き飛ばすことが多い。「ダメを押す」力強さとも観ることができるが、そうは思えない。
6日目の結びの一番で、変化技を決めた時、お客さんは日馬富士をもっと野次るべきであった。















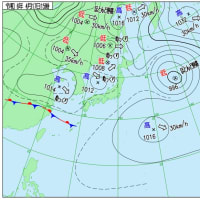
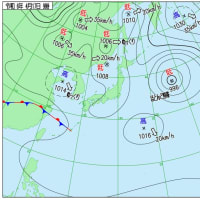
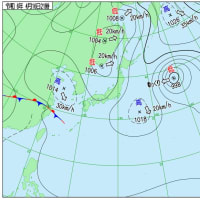
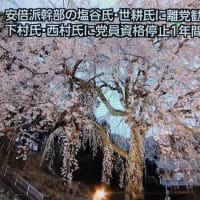
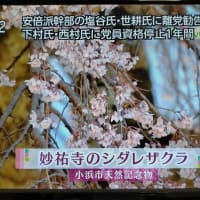






拳を握るのは禁じ手だと思うのですが(ルール調べてないけど見たことないし)それっていつ頃から? と思ってwikiで検索してみました。奈良時代の志賀清林という人が聖武天皇に云々の時、
「突く・殴る・蹴る」
を禁じ手としたという話があるい……。
突きというのは目を攻撃することなのでしょうか? それとも今の相撲とはルールが違うのか、張手は突きではないのか。
どうも突きは解禁されたみたいですが、女子相撲では禁止とのこと。
肩から手首までの関節を固めた掌底突きのようなものを立ち会いで使ったら、勝率は悪い(命中しなかったら関節を硬直させているところに相手の体当たりを受ける)でしょうが、命中した時は相当危険です。志賀清林が暴力を神事として提案する際に「突き」を禁じたが、スポーツとしては一応容認したということなのか。
しかし、横綱にあるまじき技云々というのは、突きに関しては「威力が高い」即ち危険ということなのでしょう。(けたぐりは見た目が悪いってことですかね)
しかし、横綱でなくとも使えば威力が高く危険ってことなら、ルール変更で禁止した方がいいのでは、と思います。
スポーツではなく宗教的民族的儀式なので
「Japanese Only」
とするか、ルールで禁止するかだと思います。
>日馬富士が左に飛んで引き技。一応、まわしを掴んで送り出し気味なので決まり手は「上手投げ」であるが、内容的には「はたき込み」や「引き落とし」に近い。
・・・・は、もはや美しさの欠片もない
残念な相撲のように、わたしには見えました。
ただ、じゃあ、『張り手』禁止?『けたぐり』禁止?
となると、「日馬富士に相撲をやるな」
って事に近いようなニュアンスの言い方に
なってしまうのかもしれない・・・・
とも、そんなに相撲を見ていないのにも
関わらず思いました。
となると、
横綱らしい品格のある力士じゃない力士
を推挙した、
『横綱審議委員会が悪い』
ということになります。
(現に小錦の時は、挙げなかったじゃないですか
・苦笑)
大相撲の悲劇は、一度横綱に
上がってしまえば、後は引退しか無い所。
負けてしまえば全ては終わりなのです。
これで品格と言われても・・・・。
果たして生活がかかっている場合、
どこまで品格を貫き通せるものかどうか・・・・?
『Number Web』のアンケートで、
「自重すべきでない」が6割もあったのは
横綱の特殊事情を知っているからこそ・・・・・
と思いたいこてくんでした。
まっ、でも『美しく』はないわな。
神事だったら(笑)
ではではっ。
(このわたしの文章もそんなに
美しくはないのですが・・・・)
なるほど、神事ですか。
で、検索してみました。
======================
相撲は人間の闘争本能の発露である力くらべや取っ組み合いから発生した伝統あるスポーツである。これによく似た形態のスポーツは古来世界各地で行われた。
我が国の相撲の起源としては、古事記(712年)や日本書紀(720年)の中にある力くらべの神話や、宿禰(すくね)・蹶速(けはや)の天覧勝負の伝説があげられる。
相撲はその年の農作物の収穫を占う祭りの儀式として、毎年行われてきた。これが後に宮廷の行事となり300年続くことなる。
戦国の力じまん .鎌倉時代から戦国時代にかけては武士の時代。武士の戦闘の訓練として盛んに相撲が行われた。織田信長は深く相撲を愛好し、元亀・天正年間(1570~92年)に近江の安土城などで各地から力士を集めて上覧相撲を催し、勝ち抜いた者を家臣として召し抱えた。
=====================
「力比べの余興」→「祭りの儀式」→「訓練」→「召抱えのテスト」ときて、江戸時代に「職業」となったようです。
そう言えば、二年前の大河ドラマ『平清盛』に天覧相撲のシーンがありました。(豊真将が出演していました)
私見ですが、力比べ、神事、鍛練、体力テストのどれを考えても、「張り手」はふさわしくないですね。
卑怯な技なので、禁止すべきです。
>、日本人がお互いの空気を読んで目に見えない強制力を働かせるという芸当が日本人同士にしか通用しない、所謂外国人にはできないように、「神事でスポーツ」というのはやはり無理でしょう。
相撲協会が「国技」と言っているので、新弟子の頃から精神を叩きこむべきです。
>「Japanese Only」
とするか、ルールで禁止するかだと思います。
わはは…。
>横綱らしい品格のある力士じゃない力士を推挙した、『横綱審議委員会が悪い』ということになります。
その通りです。
そもそも、条件を付けておいて「満場一致」というのが、中途半端です。ダメなのかOKなのか判断しなければだめです。
それに、条件を満たしていない現状なので、横綱剥奪しないと筋が通りません。
>『Number Web』のアンケートで、「自重すべきでない」が6割もあったのは
>横綱の特殊事情を知っているからこそ・・・・・
>と思いたいこてくんでした。
いえ、そこまで考えていないと思います。
「ルール内なら何をしても良い」というのが過半数を超えるという現状。いや~な世の中になったものです。
http://ssay.cocolog-nifty.com/blog/2010/02/post-57dc.html
品格を横綱に対して口煩く言う前に、
横審や理事会や他の親方衆、
あなたがたはどうなんだ?と言いたいです。
それとは別に「張り手」についてですが、
アマチュアでは禁じ手ですよね。
アマは駄目でプロはOKという、この理由を明確にする必要があると思います。
ぼく個人としては、プロでも張り手は禁止すべきだと思います。
(・・・って、すっかり大相撲を見なくなっているのに、何を語っちゃってんだ?)
理由は、余りにも危険な技だからです。
ぼくは、これも今ではすっかり関心外ですが、
昔プロレスや格闘技に多少興味があったので(あ、観るほうですよ、もちろん)、
お相撲さんの超ヘビー級のパンチがどれだけ凄まじい威力か、頭では理解できます。
拳でなく、手のひらで殴っても同じことです。
100%の力で張らないから相手もKOにならないだけで、
思いっきり殴ったら、下手すりゃ相手力士は死んじゃいますよ。
というより、打撃技は最早相撲とは呼べないでしょう。
大相撲は見てもストレスを感じるだけなので、やはり観ません。
観ないのに語ってしまい、申し訳ございませんでした。
怒涛の連続コメントですね。
>横綱の品格というテーマで以前書きました。
http://ssay.cocolog-nifty.com/blog/2010/02/post-57dc.html
読みました。
ほとんど同意します。
>品格を横綱に対して口煩く言う前に、横審や理事会や他の親方衆、あなたがたはどうなんだ?と言いたいです。
激しく同意です。
そもそも2場所しか審議対象にしないのが間違いです。ひと場所優勝(それと同等)の成績を上げたら、翌場所は昇進が話題なんて、緩すぎます。
日馬富士の際、「張り手を慎む」を条件に満場一致で推挙しましたが、条件を付けて満場一致というのも意味不明ですし、それで決めたのなら、張り手をした段階で横綱剥奪にしないと、「審議」の意味がなくなってしまいます。
張り手の危険性は全くその通りだと思います。なくても十分相撲の面白さは成立しますし、ない方がより良いものとなります。
>打撃技は最早相撲とは呼べないでしょう。
日馬富士の場合は、頭に血が昇って多発します。けんかです。