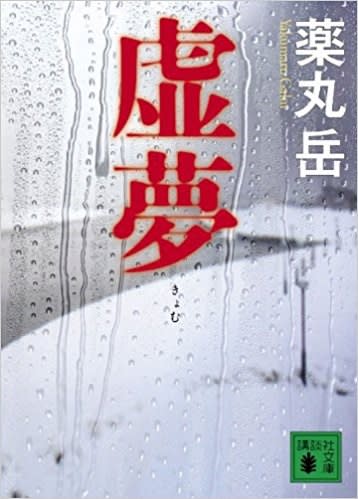今回のお気に入りは、生命史図譜です。
古生物の最新復元イラストをたっぷり鑑賞したくて「生命史図譜」を購入しました。
著者は、科学雑誌「ニュートン」のライターであり、「ザ・パーフェクト―日本初の恐竜全身骨格発掘記: ハドロサウルス発見から進化の謎まで」の著者である土屋健。
本を手に取って驚いたのはその重さ。
単行本より一回り大きいタテヨコに厚さ2.4cmならこれくらいの重さ、というのを5割増しでオーバーしています。
さすがフルカラーの図譜!
本を開く前に納得しました。
さて本書の感想を書く前にAMAZONの内容紹介を引用します。
=====
地質年代ごとに、古生物を化石写真と復元イラストで紹介してきた『生物ミステリーPRO 』古生物シリーズ。
エディアカラ紀からはじまった本シリーズは、足かけ4年余りをかけ、10冊目の第四紀をもって大団円を迎えました。
今回は、「古生物シリーズ」の総まとめ的な“別冊"をお届けします。
といっても、「この1冊でも楽しめる」仕様となっております。
もちろん、シリーズを1冊でもお持ちの方には、「もっとお役に立てる」工夫が満載です。
『生命史図譜』には、制作陣がぜひともチャレンジしてみたかったことが3つ詰まっています。
●図譜パート――古生物を「分類順」に再編纂
シリーズ第1~10巻に登場する復元イラスト付き生物を、分類ごとにまとめ直し、カタログ的に紹介しました。
時代をまたいでどんな近縁種がいたのか、分類単位の中でどのような進化があったのか、がとてもわかりやすくなっています。
同時に、このパートでは、書籍刊行後に発表された重大な研究成果も掲載。
古生物情報のアップデートや復元イラストの更新、新イラストの追加も行っています。
●シリーズ総索引パート――情報へのアクセス向上
古生物の研究者や愛好家は、書籍の「索引で情報を探す」ことをよくやります。
第1~10巻を個々に検索するのはタイヘンなので、「○巻の○ページ」という具合の総索引を作成しました。
シリーズ全体を、よりいっそう便利にお使いいただけます。
●国内の博物館パート――著者のプチガイド
日本各地には、古生物をあつかった素晴らしい博物館がたくさんあります。
本シリーズを読んで興味をもったら、ぜひ博物館を訪ねてみてください。
これまで以上に、化石が皆さまにとって身近なものになるでしょう。
このページをご覧いただいている皆さまに大きな感謝を。
本書が皆さまの“古生物ライフ"の助けになれば幸いです。
=====
サイエンスイラストレーターが描いた最新の復元イラストは、いったい何枚あったのでしょう?
これらは、内容紹介にもあった通り、足かけ4年余りをかけた古生物シリーズ全10巻のために描かれたもの。
昨年末に北斎漫画全巻を一気に鑑賞したときと同様、次から次へ出てくるイラストのボリューム感に圧倒されました。
前者は写実性・芸術性を追求し、後者は科学的正確性を追求している違いこそあれど、感動的なほどに見事な仕事です。
内容紹介にもある通り、例えばサメのご先祖がメガロドンに至るまでの進化を知ることができる構成は観ていて実に楽しい。
復元イラスト中心に必要最小限の解説文。
図鑑好きにはたまりません。
古生代カンブリア紀を代表するアノマノカリスに関するパートが一番興味深かったです。
アノマノカリスのご先祖から子孫までの多彩な系統が一目瞭然。
あの大きな触手をヒゲクジラのヒゲのようにプランクトンを濾し取るために発達させた種がいることや、三葉虫をかじるほどの力はなかったかもしれないこと。
面白すぎ!
惜しむらくは漢字に振り仮名がほとんど振られていないこと。
読者の対象を中学生以上と考えてのことでしょうが、本書の内容なら小学生も飛びつくはず。
自分もそんな小学生だったことを思い出しました。
(おまけ ~ 表紙の写真)
琥珀の中に閉じ込められているのは、何と「恐竜のしっぽ」!
映画ジュラシックパークは、琥珀の中に閉じ込められた蚊から取り出したDNAから恐竜を再生します。
表紙の化石があれば、そんなに回りくどいことをせずに恐竜のDNAを取り出せます。
これは大発見です。
ああ、誰か恐竜を再生してくれないかな?
古生物の最新復元イラストをたっぷり鑑賞したくて「生命史図譜」を購入しました。
著者は、科学雑誌「ニュートン」のライターであり、「ザ・パーフェクト―日本初の恐竜全身骨格発掘記: ハドロサウルス発見から進化の謎まで」の著者である土屋健。
本を手に取って驚いたのはその重さ。
単行本より一回り大きいタテヨコに厚さ2.4cmならこれくらいの重さ、というのを5割増しでオーバーしています。
さすがフルカラーの図譜!
本を開く前に納得しました。
さて本書の感想を書く前にAMAZONの内容紹介を引用します。
=====
地質年代ごとに、古生物を化石写真と復元イラストで紹介してきた『生物ミステリーPRO 』古生物シリーズ。
エディアカラ紀からはじまった本シリーズは、足かけ4年余りをかけ、10冊目の第四紀をもって大団円を迎えました。
今回は、「古生物シリーズ」の総まとめ的な“別冊"をお届けします。
といっても、「この1冊でも楽しめる」仕様となっております。
もちろん、シリーズを1冊でもお持ちの方には、「もっとお役に立てる」工夫が満載です。
『生命史図譜』には、制作陣がぜひともチャレンジしてみたかったことが3つ詰まっています。
●図譜パート――古生物を「分類順」に再編纂
シリーズ第1~10巻に登場する復元イラスト付き生物を、分類ごとにまとめ直し、カタログ的に紹介しました。
時代をまたいでどんな近縁種がいたのか、分類単位の中でどのような進化があったのか、がとてもわかりやすくなっています。
同時に、このパートでは、書籍刊行後に発表された重大な研究成果も掲載。
古生物情報のアップデートや復元イラストの更新、新イラストの追加も行っています。
●シリーズ総索引パート――情報へのアクセス向上
古生物の研究者や愛好家は、書籍の「索引で情報を探す」ことをよくやります。
第1~10巻を個々に検索するのはタイヘンなので、「○巻の○ページ」という具合の総索引を作成しました。
シリーズ全体を、よりいっそう便利にお使いいただけます。
●国内の博物館パート――著者のプチガイド
日本各地には、古生物をあつかった素晴らしい博物館がたくさんあります。
本シリーズを読んで興味をもったら、ぜひ博物館を訪ねてみてください。
これまで以上に、化石が皆さまにとって身近なものになるでしょう。
このページをご覧いただいている皆さまに大きな感謝を。
本書が皆さまの“古生物ライフ"の助けになれば幸いです。
=====
サイエンスイラストレーターが描いた最新の復元イラストは、いったい何枚あったのでしょう?
これらは、内容紹介にもあった通り、足かけ4年余りをかけた古生物シリーズ全10巻のために描かれたもの。
昨年末に北斎漫画全巻を一気に鑑賞したときと同様、次から次へ出てくるイラストのボリューム感に圧倒されました。
前者は写実性・芸術性を追求し、後者は科学的正確性を追求している違いこそあれど、感動的なほどに見事な仕事です。
内容紹介にもある通り、例えばサメのご先祖がメガロドンに至るまでの進化を知ることができる構成は観ていて実に楽しい。
復元イラスト中心に必要最小限の解説文。
図鑑好きにはたまりません。
古生代カンブリア紀を代表するアノマノカリスに関するパートが一番興味深かったです。
アノマノカリスのご先祖から子孫までの多彩な系統が一目瞭然。
あの大きな触手をヒゲクジラのヒゲのようにプランクトンを濾し取るために発達させた種がいることや、三葉虫をかじるほどの力はなかったかもしれないこと。
面白すぎ!
惜しむらくは漢字に振り仮名がほとんど振られていないこと。
読者の対象を中学生以上と考えてのことでしょうが、本書の内容なら小学生も飛びつくはず。
自分もそんな小学生だったことを思い出しました。
(おまけ ~ 表紙の写真)
琥珀の中に閉じ込められているのは、何と「恐竜のしっぽ」!
映画ジュラシックパークは、琥珀の中に閉じ込められた蚊から取り出したDNAから恐竜を再生します。
表紙の化石があれば、そんなに回りくどいことをせずに恐竜のDNAを取り出せます。
これは大発見です。
ああ、誰か恐竜を再生してくれないかな?