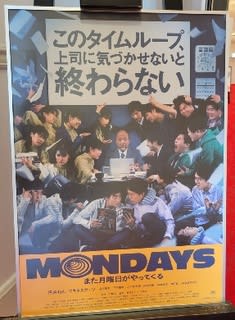(原題:BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER)とにかく長い。最近、ハリウッド製の娯楽編の上映時間が軒並み延びる傾向にあるが、本作もそのトレンド(?)の中にあるのかもしれない。もちろんいくら尺が長くても中身が充実していれば言うことはないのだが、この映画に関してはどうにも評価出来ない。ネタを詰め込んでいる割には料理の仕方がイマイチだ。まあ、これは前作の主演チャドウィック・ボーズマンの早すぎる退場が影を落としていることは確かだろう。
ワカンダの王であった超人ブランクパンサーことティ・チャラが病により命を落とし、彼の母であるラモンダが後を継ぐ。折しも国際社会はワカンダで産出される万能の鉱石ヴィブラニウムの保有を巡って紛糾し始めていた。欧米諸国はワカンダとは別に海底に埋蔵されているヴィブラニウムの採掘調査を開始するが、それが海の帝国タロカンの逆鱗に触れ、ワカンダおよび地上世界との紛争に発展する。ティ・チャラの妹シュリは、側近のオコエや若き科学者リリ・ウィリアムズらと共に事態の収拾に乗り出す。

タカロンの親玉エムバクはおそろしく強く、兵士たちも不死身に近い。腕力だけに限れば、たぶんワカンダと国際社会が束になっても敵わないだろう。だが、斯様な勢力が数百年も前から存在していたことを、今まで地上の誰も知らなかったというのは、明らかにおかしい。この作品世界にはワカンダだけではなくアベンジャーズやエターナルズもいるはずで、そんな“ぽっと出”の団体が入り込む余地は無いはずだ(笑)。
タカロンの連中はずっと海の中に潜んでいたためか(苦笑)、人質にはすぐに逃げられるし、陽動作戦には簡単に引っ掛かったりと、あまりスマートには見えない。そして何より、タカロンの造形が「アクアマン」や「アバター」の二番煎じに思えてしまうのは辛い。
ワカンダ側の対応も褒められたものではなく、二代目のブラックパンサーが登場するまでのゴタゴタはハッキリ言ってどうでもいい。C・ボースマンの存在感が大きかったため、すぐさま代役を立てることが出来ず、二代目が出てくるまでの辻褄を無理に合わせようとして、上映時間だけが長くなってしまった。MCUではお馴染みのエンドクレジット後のシークエンスも、蛇足としか思えない。
前回から続投のライアン・クーグラーの演出はパッとせず、アクション場面はハデな割に目を引くようなアイデアは見当たらない。レティーシャ・ライトにルピタ・ニョンゴ、ドミニク・ソーン、アンジェラ・バセット、そして敵役のウィンストン・デュークとキャストは皆健闘しているが、C・ボースマンの抜けた穴をカバーすることばかりに気を取られているようで愉快になれない。ルドウィグ・ゴランソンによる音楽は標準レベルだが、ラスト流れるリアーナの歌は良かった。
ワカンダの王であった超人ブランクパンサーことティ・チャラが病により命を落とし、彼の母であるラモンダが後を継ぐ。折しも国際社会はワカンダで産出される万能の鉱石ヴィブラニウムの保有を巡って紛糾し始めていた。欧米諸国はワカンダとは別に海底に埋蔵されているヴィブラニウムの採掘調査を開始するが、それが海の帝国タロカンの逆鱗に触れ、ワカンダおよび地上世界との紛争に発展する。ティ・チャラの妹シュリは、側近のオコエや若き科学者リリ・ウィリアムズらと共に事態の収拾に乗り出す。

タカロンの親玉エムバクはおそろしく強く、兵士たちも不死身に近い。腕力だけに限れば、たぶんワカンダと国際社会が束になっても敵わないだろう。だが、斯様な勢力が数百年も前から存在していたことを、今まで地上の誰も知らなかったというのは、明らかにおかしい。この作品世界にはワカンダだけではなくアベンジャーズやエターナルズもいるはずで、そんな“ぽっと出”の団体が入り込む余地は無いはずだ(笑)。
タカロンの連中はずっと海の中に潜んでいたためか(苦笑)、人質にはすぐに逃げられるし、陽動作戦には簡単に引っ掛かったりと、あまりスマートには見えない。そして何より、タカロンの造形が「アクアマン」や「アバター」の二番煎じに思えてしまうのは辛い。
ワカンダ側の対応も褒められたものではなく、二代目のブラックパンサーが登場するまでのゴタゴタはハッキリ言ってどうでもいい。C・ボースマンの存在感が大きかったため、すぐさま代役を立てることが出来ず、二代目が出てくるまでの辻褄を無理に合わせようとして、上映時間だけが長くなってしまった。MCUではお馴染みのエンドクレジット後のシークエンスも、蛇足としか思えない。
前回から続投のライアン・クーグラーの演出はパッとせず、アクション場面はハデな割に目を引くようなアイデアは見当たらない。レティーシャ・ライトにルピタ・ニョンゴ、ドミニク・ソーン、アンジェラ・バセット、そして敵役のウィンストン・デュークとキャストは皆健闘しているが、C・ボースマンの抜けた穴をカバーすることばかりに気を取られているようで愉快になれない。ルドウィグ・ゴランソンによる音楽は標準レベルだが、ラスト流れるリアーナの歌は良かった。