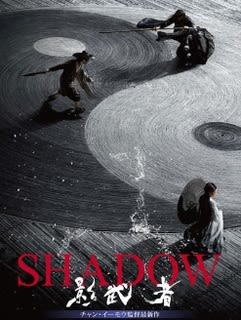伊坂幸太郎による原作は未読だが、彼の小説はすでに10回以上映画化されているものの、成功している例はあまりない。時制や舞台をランダムに配置して伏線を張りまくり、終盤で一気にそれらを回収するという“手口”は、映画にする上でストーリーの追尾だけに気を取られると、中身の薄い作品に終わってしまう。残念ながら、本作もその轍を踏んでいる。
仙台駅前の大型ビジョンの前には、パブリックビューイングとして映し出される日本人初のボクシング世界ヘビー級タイトルマッチを見るために多くの人々が集まっていた。その人混みの中、リサーチ会社で働く佐藤は街頭アンケートを取っていた。そこでアンケートに応じてくれたのが就活中の紗季で、後に偶然再会することになった2人はそのまま付き合うことになる。

それから10年が経ち、佐藤は意を決して紗季にプロポーズをするのだが、彼女は返事を保留したまま行方をくらましてしまう。一方、件の試合で世界チャンピオンになったものの間もなくタイトルを失ったウィンストン小野は、一時は引退状態に追いこまれていたが、妻の美奈子のサポートもあって6年ぶりに現役復帰する。
筋書きは原作通りなのかもしれないが、複数のパートが同時進行していく作劇は散漫な印象を受ける。ラストの伏線回収の部分も、カタルシスが得られない。ここは、佐藤と紗季のエピソードに絞った方がマシだったかもしれない。特に大きく上映時間が割かれたボクシングの話は、凡庸な試合場面も相まって、まるで盛り上がらない。
とはいえ、佐藤と紗季の関係も描き方が不十分だ。普通、10年間も付き合って進展せず会話も他人行儀なままのカップルがゴールインするとは考えられない。今さらラブコメらしいシチュエーションを提示したところで、無駄である。監督は今泉力哉だが、先日観た「愛がなんだ」に比べると大幅にヴォルテージが落ちる。やはり有名作家による原作の“縛り”があると、思うように仕事が出来ないのだろう。
三浦春馬に多部未華子、恒松祐里、萩原利久、矢本悠馬、森絵梨佳、貫地谷しほり、原田泰造と多彩なキャストを揃えてはいるが、複数パートを展開する必要があるためか、作劇の集中度が欠けて各人の真価が発揮出来ているとは思えない。ただ、斉藤和義による音楽だけは良かった。
仙台駅前の大型ビジョンの前には、パブリックビューイングとして映し出される日本人初のボクシング世界ヘビー級タイトルマッチを見るために多くの人々が集まっていた。その人混みの中、リサーチ会社で働く佐藤は街頭アンケートを取っていた。そこでアンケートに応じてくれたのが就活中の紗季で、後に偶然再会することになった2人はそのまま付き合うことになる。

それから10年が経ち、佐藤は意を決して紗季にプロポーズをするのだが、彼女は返事を保留したまま行方をくらましてしまう。一方、件の試合で世界チャンピオンになったものの間もなくタイトルを失ったウィンストン小野は、一時は引退状態に追いこまれていたが、妻の美奈子のサポートもあって6年ぶりに現役復帰する。
筋書きは原作通りなのかもしれないが、複数のパートが同時進行していく作劇は散漫な印象を受ける。ラストの伏線回収の部分も、カタルシスが得られない。ここは、佐藤と紗季のエピソードに絞った方がマシだったかもしれない。特に大きく上映時間が割かれたボクシングの話は、凡庸な試合場面も相まって、まるで盛り上がらない。
とはいえ、佐藤と紗季の関係も描き方が不十分だ。普通、10年間も付き合って進展せず会話も他人行儀なままのカップルがゴールインするとは考えられない。今さらラブコメらしいシチュエーションを提示したところで、無駄である。監督は今泉力哉だが、先日観た「愛がなんだ」に比べると大幅にヴォルテージが落ちる。やはり有名作家による原作の“縛り”があると、思うように仕事が出来ないのだろう。
三浦春馬に多部未華子、恒松祐里、萩原利久、矢本悠馬、森絵梨佳、貫地谷しほり、原田泰造と多彩なキャストを揃えてはいるが、複数パートを展開する必要があるためか、作劇の集中度が欠けて各人の真価が発揮出来ているとは思えない。ただ、斉藤和義による音楽だけは良かった。