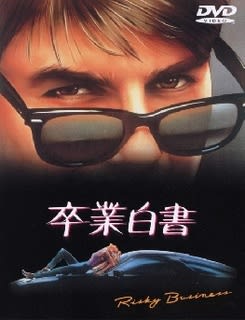(原題:STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER)前作「最後のジェダイ」(2017年)のレベルがあまりにも低かったせいか、今作は随分とマシに見える。もっとも、決して上出来ではなく、本国での評価が低いのも頷ける。それでも“何とか最終作としての体裁を整えた”という意味では存在価値はある。そして十代の頃から足かけ40年以上も(半ば義務感で)本シリーズをリアルタイムで追いかけてきた身としては、もうこれ以上観る必要は無いのだという、一種の安堵感を覚えてしまった(苦笑)。
祖父ダース・ベイダーのマスクの残骸を手にして、ニューオーダーの支配者となったカイロ・レンと、ルーク・スカイウォーカーの後継者と目されるレイとの最後の戦いを描く本作。このシリーズの共通モチーフであるフォースは、以前は使う者を最小限フォローする未知のパワーに過ぎなかったのたが、ここではテレキネシスやテレポーテーションなどの明らかな“超能力”として扱われる。

しかも、つい最近ジェダイになったばかりのレイが、長年修行してやっとフォースを手に入れたはずのヨーダやオビ=ワン・ケノービよりも遙かに強いパワーを使いこなすという不思議。前作の時点で消えたルークやハン・ソロ、そして消えるはずのレイアが亡霊じみた姿で何かとレイたちをバックアップするという御都合主義。さらにはポーやフィンといったレイの仲間達の存在感の小ささなど、作劇面やキャラクター設定に欠点が散見される。後半でレイの意外な生い立ちが紹介されるのだが、大したインパクトは無い。
肝心の活劇場面も、驚くようなアイデアも見当たらず漫然と流れて行くのみだ。しかし、前述のように何はともあれ終わらせたというのが、この映画の最大の長所である。思えば、このシリーズは本来エピソード6で完結していたはずだ。それが蛇足じみた三部作を始めてしまった。おかげで、当初から(興行成績は別にして)質的には期待出来ないものになったのは当然だろう。
J・J・エイブラムスの演出は、まあ無難にこなしている印象。レイ役のデイジー・リドリーをはじめ、オスカー・アイザックやジョン・ボヤーガ、ケリー・マリー・トランといった顔ぶれは魅力無し。カイロ・レンに扮したアダム・ドライバーは今や他の諸作品で確実に評価を上げているだけに、本作での役柄は余計なものに感じてしまう。なお、前作でちょっと気になったベニチオ・デル・トロは今回は不在。ひょっとしたら彼を主役にスピンオフ作品が出来るかもしれないが、私は観る予定は無い。
祖父ダース・ベイダーのマスクの残骸を手にして、ニューオーダーの支配者となったカイロ・レンと、ルーク・スカイウォーカーの後継者と目されるレイとの最後の戦いを描く本作。このシリーズの共通モチーフであるフォースは、以前は使う者を最小限フォローする未知のパワーに過ぎなかったのたが、ここではテレキネシスやテレポーテーションなどの明らかな“超能力”として扱われる。

しかも、つい最近ジェダイになったばかりのレイが、長年修行してやっとフォースを手に入れたはずのヨーダやオビ=ワン・ケノービよりも遙かに強いパワーを使いこなすという不思議。前作の時点で消えたルークやハン・ソロ、そして消えるはずのレイアが亡霊じみた姿で何かとレイたちをバックアップするという御都合主義。さらにはポーやフィンといったレイの仲間達の存在感の小ささなど、作劇面やキャラクター設定に欠点が散見される。後半でレイの意外な生い立ちが紹介されるのだが、大したインパクトは無い。
肝心の活劇場面も、驚くようなアイデアも見当たらず漫然と流れて行くのみだ。しかし、前述のように何はともあれ終わらせたというのが、この映画の最大の長所である。思えば、このシリーズは本来エピソード6で完結していたはずだ。それが蛇足じみた三部作を始めてしまった。おかげで、当初から(興行成績は別にして)質的には期待出来ないものになったのは当然だろう。
J・J・エイブラムスの演出は、まあ無難にこなしている印象。レイ役のデイジー・リドリーをはじめ、オスカー・アイザックやジョン・ボヤーガ、ケリー・マリー・トランといった顔ぶれは魅力無し。カイロ・レンに扮したアダム・ドライバーは今や他の諸作品で確実に評価を上げているだけに、本作での役柄は余計なものに感じてしまう。なお、前作でちょっと気になったベニチオ・デル・トロは今回は不在。ひょっとしたら彼を主役にスピンオフ作品が出来るかもしれないが、私は観る予定は無い。