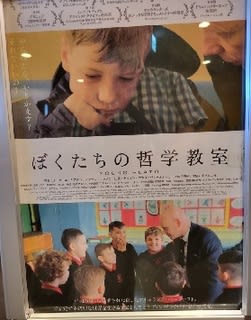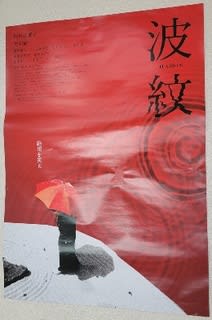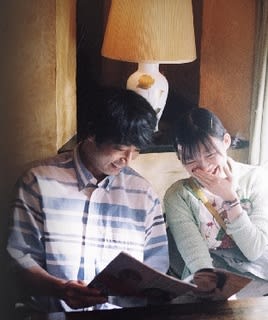(原題:Bird on a Wire)90年作品。当時すでに40歳を過ぎていたにも関わらず申し分のないプロポーションを維持していたゴールディ・ホーンと、その頃の「US」誌選出のセクシー男優のベストテンにランクインしたメル・ギブソンとの“セクシー共演”を鑑賞するシャシンだ(笑)。ハッキリ言って、それ以外にはあまり見どころは無い。ただし、ユニヴァーサル映画創立75周年記念作品ということで十分な予算はかけられており、チープさが無いのは救いである。
弁護士のマリアンヌ・グレーヴスは、偶然立ち寄った自動車修理工場で15年前に事故でこの世を去った恋人リック・ジャーミンにそっくりの男と出会う。他人のそら似だと思ったマリアンヌだが、実は相手はリック本人だった。彼は15年前にメキシコの麻薬カルテルに関する事件の証言をするためにFBIの証人保護リストに登録されていて、名前も職業も変えてひっそりと暮らしていたのだ。

彼女に勘付かれたと思ったリックはFBIの新しい担当者であるジョー・ウェイバーンに連絡するが、彼はすでにくだんの麻薬組織に買収されていた。ウェイバーンはリックの生存を組織に通報すると、早速殺し屋どもがリックを狙って押し寄せてくる。リックはマリアンヌを伴っての決死の逃避行を強いられる。
マリアンヌは敏腕弁護士という触れ込みだが、G・ホーンが演じると少しもそうは見えない。こんなに浮ついたギャルっぽい女が法廷でシッカリと仕事が出来るとは思えないのだ。リックに扮するM・ギブソンはいつも通りだが、何となくG・ホーンに押されて存在感は薄い。少なくとも「マッドマックス」や「リーサル・ウェポン」のシリーズのようなキャラの濃さは見受けられない。ただ、セクシー男優のメンツからか、上半身の裸はもちろんのこと、お尻のヌードまでも披露して主演女優に対抗しているのは御愛敬だ。
本作はコメディ仕立ての“トラプル巻き込まれ型サスペンス編”だが、お笑いが過ぎてサスペンスの方は盛り上がらない。しかも、筋書きは単純のようで無理筋であり、御都合主義が目立つ。クライマックスが動物園内の活劇という悪くないモチーフを提示はしているが、主要キャラであるはずの獣医のレイチェルがクローズアップされていないのも不満だ。
監督のジョン・バダムは80年代半ばまでは意欲的な仕事を手掛けていたが、この時期には並のプログラム・ピクチュアの演出家として落ち着いてしまったようだ。デイヴィッド・キャラダインにビル・デューク、スティーヴン・トボロウスキー、ジョーン・セベランスといった他の面子は可も無く不可も無し。音楽はハンス・ジマーが担当しているが、大して印象に残らない。
弁護士のマリアンヌ・グレーヴスは、偶然立ち寄った自動車修理工場で15年前に事故でこの世を去った恋人リック・ジャーミンにそっくりの男と出会う。他人のそら似だと思ったマリアンヌだが、実は相手はリック本人だった。彼は15年前にメキシコの麻薬カルテルに関する事件の証言をするためにFBIの証人保護リストに登録されていて、名前も職業も変えてひっそりと暮らしていたのだ。

彼女に勘付かれたと思ったリックはFBIの新しい担当者であるジョー・ウェイバーンに連絡するが、彼はすでにくだんの麻薬組織に買収されていた。ウェイバーンはリックの生存を組織に通報すると、早速殺し屋どもがリックを狙って押し寄せてくる。リックはマリアンヌを伴っての決死の逃避行を強いられる。
マリアンヌは敏腕弁護士という触れ込みだが、G・ホーンが演じると少しもそうは見えない。こんなに浮ついたギャルっぽい女が法廷でシッカリと仕事が出来るとは思えないのだ。リックに扮するM・ギブソンはいつも通りだが、何となくG・ホーンに押されて存在感は薄い。少なくとも「マッドマックス」や「リーサル・ウェポン」のシリーズのようなキャラの濃さは見受けられない。ただ、セクシー男優のメンツからか、上半身の裸はもちろんのこと、お尻のヌードまでも披露して主演女優に対抗しているのは御愛敬だ。
本作はコメディ仕立ての“トラプル巻き込まれ型サスペンス編”だが、お笑いが過ぎてサスペンスの方は盛り上がらない。しかも、筋書きは単純のようで無理筋であり、御都合主義が目立つ。クライマックスが動物園内の活劇という悪くないモチーフを提示はしているが、主要キャラであるはずの獣医のレイチェルがクローズアップされていないのも不満だ。
監督のジョン・バダムは80年代半ばまでは意欲的な仕事を手掛けていたが、この時期には並のプログラム・ピクチュアの演出家として落ち着いてしまったようだ。デイヴィッド・キャラダインにビル・デューク、スティーヴン・トボロウスキー、ジョーン・セベランスといった他の面子は可も無く不可も無し。音楽はハンス・ジマーが担当しているが、大して印象に残らない。