BYOT、ビヨット?それともバイヨット?
今日のNBCポッドキャストが伝えたアメリカの新しい教育トレンドのことだ。Bring Your Own Technology=自分の持っているITガジェットを授業で積極的に使おうというわけである。
スマートフォンの爆発的な人気で、今や大人のみならず子供たちも必携の携帯IT機器だが、これまで教室ではタブーだった、このいわば「電子おもちゃ」を教育機器として活用しようという動きがBYOTである。
アイパッド、キンドルファイア、ネットブック、からニンテンドーのゲームマシンまで、子供たちが持っているモバイル機器なら何を持ってきても良いと公認したのは、ジョージア州フォーサイス郡の小学校がその一例。これまでは教師や両親にはナイショで持ち歩いていたマシンが堂々と授業中に使えるというわけだ。
子供たちのマシンは、リサーチ用、教育ゲーム用、プレゼン用など様々な目的で使える。個人のマシンを持たない子供たちには、行政側が準備したラップトップPCを貸し出して対応するのだそうだ。ゲームマシンだからといってひとりで没入するというのではなく、「参加し互いに係わり合う」ことが求められ、子供たちは「同士の協力や教師との話し合い」の機会も増えるし、教師は「直接的な生徒へのフィードバックができる」のだとは、BYOTの担当者の言。
グループとしてITマシンのより効果的な利用方法を学ぶことで、従来の学習の幅が広がるのと同時に、それぞれのマシンを大切に扱おうとする新しい意識も生まれてくるので、個人が密かに覗いていた映像や、仲間とのメール交換も減少したというプラス効果もあるようだ。
プラス効果は子供たちだけでなく、教師にも、これまでないがしろにしてきたIT機器の効果的な使い方をよく考えて対応しようとする姿勢が生まれ、教育スタイルが変化してきているのだという。すなわち「教科書に従って教師の知識を子供たちに与える」のではなく、「学ぶ方向を示してファシリテートする」ことで、子供たちの学習意欲が向上したとも云う。
BYOTの導入時には、子供がゲームマシンを持って学校に行くことに反対する父兄も多かったが、実際にプログラムが走り出してみると、父兄の心配は杞憂で、子供たちはしっかり新システムになれていったという。学校側も、子供たちや父兄との確約書を取り(契約社会のアメリカらしい)、決められたルールを遵守してシステムを運用している。ネットにつなぐ場合は、フィルターがかかった学校側のネットワークを使用することしか許されない。子供たちがルール違反をした場合には、自分のマシンの持参は禁止となる。
2年前、7校で始まったフォーサイス郡のBYOTだが、今年は35校がすべて参加している。また、ジョージアのほかにも、テキサス、ミネソタ、オハイオの各州では、同様のBYOTが採用され始めている。フォーサイス郡のBYOTは他地域のパイロットプログラムとみなされているようだ。
さて、BYOTは日本の小学校にも適用されるのだろうか。頭の固い文部省や教育委員会の日頃の姿勢からすれば、積極賛同ということは100%なかろう。前例主義の役人たちだから、私学あたりの誰かが密かに始めたものが評判になって聞こえないかぎりは、自分達からまずやってみようなんてことは云うはずもない。
「子供たちは素晴らしいクリエイターで、大人には思いもよらない新しいマシンの使い方を思い浮かべることが出来る」とNBCの記事はまとめているが、こうしたBYOTがアメリカの初等教育システムとして定着してゆけば、これまでとはまた違ったクリティティブな若者を創造することが可能になるかもしれない。
ゆとり教育の反動からか、ふたたび知識詰め込み型に戻さねばイカンなどと考えているノーテンキな日本は、どうやら、「21世紀の初等教育をどう変革させるか」についてはあまり興味がなさそうに見える。
今日のNBCポッドキャストが伝えたアメリカの新しい教育トレンドのことだ。Bring Your Own Technology=自分の持っているITガジェットを授業で積極的に使おうというわけである。
スマートフォンの爆発的な人気で、今や大人のみならず子供たちも必携の携帯IT機器だが、これまで教室ではタブーだった、このいわば「電子おもちゃ」を教育機器として活用しようという動きがBYOTである。
アイパッド、キンドルファイア、ネットブック、からニンテンドーのゲームマシンまで、子供たちが持っているモバイル機器なら何を持ってきても良いと公認したのは、ジョージア州フォーサイス郡の小学校がその一例。これまでは教師や両親にはナイショで持ち歩いていたマシンが堂々と授業中に使えるというわけだ。
子供たちのマシンは、リサーチ用、教育ゲーム用、プレゼン用など様々な目的で使える。個人のマシンを持たない子供たちには、行政側が準備したラップトップPCを貸し出して対応するのだそうだ。ゲームマシンだからといってひとりで没入するというのではなく、「参加し互いに係わり合う」ことが求められ、子供たちは「同士の協力や教師との話し合い」の機会も増えるし、教師は「直接的な生徒へのフィードバックができる」のだとは、BYOTの担当者の言。
グループとしてITマシンのより効果的な利用方法を学ぶことで、従来の学習の幅が広がるのと同時に、それぞれのマシンを大切に扱おうとする新しい意識も生まれてくるので、個人が密かに覗いていた映像や、仲間とのメール交換も減少したというプラス効果もあるようだ。
プラス効果は子供たちだけでなく、教師にも、これまでないがしろにしてきたIT機器の効果的な使い方をよく考えて対応しようとする姿勢が生まれ、教育スタイルが変化してきているのだという。すなわち「教科書に従って教師の知識を子供たちに与える」のではなく、「学ぶ方向を示してファシリテートする」ことで、子供たちの学習意欲が向上したとも云う。
BYOTの導入時には、子供がゲームマシンを持って学校に行くことに反対する父兄も多かったが、実際にプログラムが走り出してみると、父兄の心配は杞憂で、子供たちはしっかり新システムになれていったという。学校側も、子供たちや父兄との確約書を取り(契約社会のアメリカらしい)、決められたルールを遵守してシステムを運用している。ネットにつなぐ場合は、フィルターがかかった学校側のネットワークを使用することしか許されない。子供たちがルール違反をした場合には、自分のマシンの持参は禁止となる。
2年前、7校で始まったフォーサイス郡のBYOTだが、今年は35校がすべて参加している。また、ジョージアのほかにも、テキサス、ミネソタ、オハイオの各州では、同様のBYOTが採用され始めている。フォーサイス郡のBYOTは他地域のパイロットプログラムとみなされているようだ。
さて、BYOTは日本の小学校にも適用されるのだろうか。頭の固い文部省や教育委員会の日頃の姿勢からすれば、積極賛同ということは100%なかろう。前例主義の役人たちだから、私学あたりの誰かが密かに始めたものが評判になって聞こえないかぎりは、自分達からまずやってみようなんてことは云うはずもない。
「子供たちは素晴らしいクリエイターで、大人には思いもよらない新しいマシンの使い方を思い浮かべることが出来る」とNBCの記事はまとめているが、こうしたBYOTがアメリカの初等教育システムとして定着してゆけば、これまでとはまた違ったクリティティブな若者を創造することが可能になるかもしれない。
ゆとり教育の反動からか、ふたたび知識詰め込み型に戻さねばイカンなどと考えているノーテンキな日本は、どうやら、「21世紀の初等教育をどう変革させるか」についてはあまり興味がなさそうに見える。











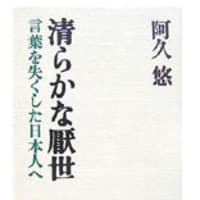






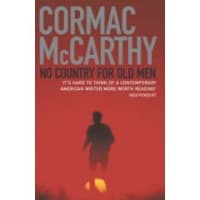
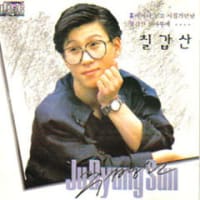
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます