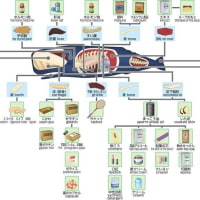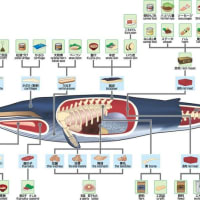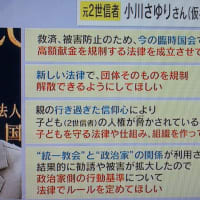1月21日(土):
朝日デジタル:(高橋源一郎の「歩きながら、考える」)皇居で手を振る、人権なき「象徴」
2017年1月19日05時00分
国家や社会の中で天皇をどう位置づけるのか。退位をめぐり、改めて問い直されています。作家・高橋源一郎さんが、皇居へ足を運んだうえで考察しました。寄稿をお届けします。
12月23日、わたしは朝から、天皇の一般参賀を待つ人たちの長い列の中にいた。観光客と思われる外国人の姿も多かった。定刻になると、係の警官たちに促されるように、わたしたちは、皇居の中に入っていった。皇居に入るのは初めての経験だった。
午前10時を過ぎて、広場に面した宮殿のベランダに、「その人」が現れた。一斉に、日の丸の小旗が振られたが、それは、もしかしたら、写真を撮るために向けられたスマートフォンの数よりも少なかったかもしれない。
「その人」は、小さな紙を取り出して、静かに読みあげた。
「誕生日にあたり寄せられた祝意に対し、深く感謝いたします。ニュースで伝えられたように、昨日は新潟で強風のなか、大きな火災がありました。多くの人が寒さのなか避難を余儀なくされており、健康に障りのないことを願っています。冬至が過ぎ、今年もあとわずかとなりましたが、来年が明るく、また穏やかな年となることを念じ、みなさんの健康と幸せを祈ります」
「その人」とその家族は、何度も手を振り、やがて、ベランダを背にした。その姿を見ながら、わたしは表現し難い感情を抱いた。そして、半世紀以上も前に書かれた、ある文章を思い出した。
1947年1月、「進歩派」の代表的な作家・中野重治は「五勺(しゃく)の酒」という文章を雑誌に発表し、大きな話題となった。中野は、憲法公布の日、それを告げる天皇の姿を皇居前で見たある中学校長の思い、という形でその文章を書いた。それは、奇妙な文章でもあった。天皇(制)批判が「進歩派」の普通の感覚であった時代に、中野はこう書いていたのだ。
「僕は天皇個人に同情を持っているのだ……あそこには家庭がない。家族もない。どこまで行っても政治的表現としてほかそれがないのだ。ほんとうに気の毒だ……個人が絶対に個人としてありえぬ。つまり全体主義が個を純粋に犠牲にした最も純粋な場合だ。どこに、おれは神でないと宣言せねばならぬほど蹂躙(じゅうりん)された個があっただろう」
個人の人権を尊重した憲法の公布を告知する天皇の姿に触れながら、誰も、その天皇自身の「人権」には思い至らない。その底の浅い理解の中に、中野は、民衆の傲慢(ごうまん)さと、「戦後民主主義」の薄っぺらさを感じとったのである。
わたしが、手を振る「その人」たちを見ながら感じた思いも、中野のそれに近いものだったのかもしれない。中野の指摘に、誰よりも敏感に反応したのは、実は、いまの明仁天皇だったのではないか。わたしには、そう思える。明仁天皇が、中野の文章を読んでいるのかどうかはわからないが。
明仁天皇は、天皇即位後、25万字にのぼる「おことば」を発表している。明仁天皇の、第一の「仕事」とは、「おことば」を発することなのだ。ここしばらく、わたしは、その、膨大な「おことば」を読んで過ごした。そこには、迷い、悩み、けれども愚直に世界とことばで対峙(たいじ)しようとしている個人がいるように思えた。
美智子妃と結婚する直前、皇太子時代に、こんなことを友人にしゃべった、と伝えられている。
――ぼくは天皇職業制を実現したい。毎日朝10時から夕方の6時までは天皇としての事務をとる。そのあとは家庭人としての幸福をつかむんだ――
その願いが完全に実現することはなかったが、少なくとも、中野が案じた「家庭」をつくることはできたのだ。
「天皇という立場にあることは、孤独とも思えるものですが、私は結婚により、私が大切にしたいと思うものを共に大切に思ってくれる伴侶を得ました」(2013年・80歳の誕生日会見)
では、その「孤独」と思える「天皇という立場」とは何なのだろうか。
昨年8月、明仁天皇は「象徴としてのお務め」に関しての「おことば」を出された。
「……天皇という立場上、現行の皇室制度に具体的に触れることは控えながら、私が個人として、これまでに考えて来たことを話したいと思います。即位以来、私は国事行為を行うと共に、日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方を、日々模索しつつ過ごして来ました」
憲法は天皇を、日本国と日本国民の統合の象徴としている。
では、「象徴」とは何だろうか。国旗や国歌がその国の象徴とされることは多い。だが、わたしたちの国のような形で生身の人間をその国の象徴と規定する例を、わたしは、ほかに知らない。そんな、個人が象徴の役割を務める、きわめて特異な制度の下にあって、その意味を、誰よりも真剣に、孤独に考えつづけてきたのが、当事者である明仁天皇本人だった。「個人」として、「象徴」の意味を考えつづけた明仁天皇がたどり着いた結論は、彼がしてきた行いと「おことば」の中に、はっきりした形で存在している。
「私はこれまで天皇の務めとして、何よりもまず国民の安寧と幸せを祈ることを大切に考えて来ましたが、同時に事にあたっては、時として人々の傍らに立ち、その声に耳を傾け、思いに寄り添うことも大切なことと考えて来ました」
「その人」が訪れるのは、たとえば被災地だ。そこを訪れ、被災者と同じ「目線」でしゃべることができるように、「その人」は跪(ひざまず)くのである。「その人」は、弱い立場の人たちのところに行って励まし、声をかける。それから、もっと大切にしている仕事がある。それは「慰霊」の旅だ。「その人」は、繰り返し、前の戦争で亡くなった人たちの「いる」場所に赴き、深い哀悼の意を示す。
弱者と死者への祈り。それこそが「象徴」の務めである、と「その人」は考えたのだ。
戦後71年。この国の人々は、過去を忘れようと、あるいは、都合のいいように記憶を改竄(かいざん)しようとしている。だが、健全な社会とは、過去を忘れず、弱者や死者の息吹を感じながら、慎(つつ)ましく、未来へ進んでゆくものではないのか。個人として振る舞うことを禁じられながら、それでも、「その人」は、ただひとりしか存在しない、この国の「象徴」の義務として、そのことを告げつづけている。だが、70年前、中野重治が悲哀をこめて書いたように、その天皇がほんとうには持つことのなかった「人権」について考えられることはいまも少ないのである。
◇
社会の様々な現場を高橋さんが訪ねる寄稿シリーズ「歩きながら、考える」(随時掲載)は今回、皇居を行き先に選びました。退位の意向をにじませる「おことば」を表明して初となる、天皇誕生日の一般参賀です。平成で最多の3万8千人が訪れました。
入場開始の1時間前に現地へ。写真は皇居前で撮りました。「その人」の声を聞き終えると高橋さんは「新潟の話が出たね」と言いました。すばやく前日の火災に触れたことが印象深かったようです。 (編集委員・塩倉裕)
朝日デジタル:(高橋源一郎の「歩きながら、考える」)皇居で手を振る、人権なき「象徴」
2017年1月19日05時00分
国家や社会の中で天皇をどう位置づけるのか。退位をめぐり、改めて問い直されています。作家・高橋源一郎さんが、皇居へ足を運んだうえで考察しました。寄稿をお届けします。
12月23日、わたしは朝から、天皇の一般参賀を待つ人たちの長い列の中にいた。観光客と思われる外国人の姿も多かった。定刻になると、係の警官たちに促されるように、わたしたちは、皇居の中に入っていった。皇居に入るのは初めての経験だった。
午前10時を過ぎて、広場に面した宮殿のベランダに、「その人」が現れた。一斉に、日の丸の小旗が振られたが、それは、もしかしたら、写真を撮るために向けられたスマートフォンの数よりも少なかったかもしれない。
「その人」は、小さな紙を取り出して、静かに読みあげた。
「誕生日にあたり寄せられた祝意に対し、深く感謝いたします。ニュースで伝えられたように、昨日は新潟で強風のなか、大きな火災がありました。多くの人が寒さのなか避難を余儀なくされており、健康に障りのないことを願っています。冬至が過ぎ、今年もあとわずかとなりましたが、来年が明るく、また穏やかな年となることを念じ、みなさんの健康と幸せを祈ります」
「その人」とその家族は、何度も手を振り、やがて、ベランダを背にした。その姿を見ながら、わたしは表現し難い感情を抱いた。そして、半世紀以上も前に書かれた、ある文章を思い出した。
1947年1月、「進歩派」の代表的な作家・中野重治は「五勺(しゃく)の酒」という文章を雑誌に発表し、大きな話題となった。中野は、憲法公布の日、それを告げる天皇の姿を皇居前で見たある中学校長の思い、という形でその文章を書いた。それは、奇妙な文章でもあった。天皇(制)批判が「進歩派」の普通の感覚であった時代に、中野はこう書いていたのだ。
「僕は天皇個人に同情を持っているのだ……あそこには家庭がない。家族もない。どこまで行っても政治的表現としてほかそれがないのだ。ほんとうに気の毒だ……個人が絶対に個人としてありえぬ。つまり全体主義が個を純粋に犠牲にした最も純粋な場合だ。どこに、おれは神でないと宣言せねばならぬほど蹂躙(じゅうりん)された個があっただろう」
個人の人権を尊重した憲法の公布を告知する天皇の姿に触れながら、誰も、その天皇自身の「人権」には思い至らない。その底の浅い理解の中に、中野は、民衆の傲慢(ごうまん)さと、「戦後民主主義」の薄っぺらさを感じとったのである。
わたしが、手を振る「その人」たちを見ながら感じた思いも、中野のそれに近いものだったのかもしれない。中野の指摘に、誰よりも敏感に反応したのは、実は、いまの明仁天皇だったのではないか。わたしには、そう思える。明仁天皇が、中野の文章を読んでいるのかどうかはわからないが。
明仁天皇は、天皇即位後、25万字にのぼる「おことば」を発表している。明仁天皇の、第一の「仕事」とは、「おことば」を発することなのだ。ここしばらく、わたしは、その、膨大な「おことば」を読んで過ごした。そこには、迷い、悩み、けれども愚直に世界とことばで対峙(たいじ)しようとしている個人がいるように思えた。
美智子妃と結婚する直前、皇太子時代に、こんなことを友人にしゃべった、と伝えられている。
――ぼくは天皇職業制を実現したい。毎日朝10時から夕方の6時までは天皇としての事務をとる。そのあとは家庭人としての幸福をつかむんだ――
その願いが完全に実現することはなかったが、少なくとも、中野が案じた「家庭」をつくることはできたのだ。
「天皇という立場にあることは、孤独とも思えるものですが、私は結婚により、私が大切にしたいと思うものを共に大切に思ってくれる伴侶を得ました」(2013年・80歳の誕生日会見)
では、その「孤独」と思える「天皇という立場」とは何なのだろうか。
昨年8月、明仁天皇は「象徴としてのお務め」に関しての「おことば」を出された。
「……天皇という立場上、現行の皇室制度に具体的に触れることは控えながら、私が個人として、これまでに考えて来たことを話したいと思います。即位以来、私は国事行為を行うと共に、日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方を、日々模索しつつ過ごして来ました」
憲法は天皇を、日本国と日本国民の統合の象徴としている。
では、「象徴」とは何だろうか。国旗や国歌がその国の象徴とされることは多い。だが、わたしたちの国のような形で生身の人間をその国の象徴と規定する例を、わたしは、ほかに知らない。そんな、個人が象徴の役割を務める、きわめて特異な制度の下にあって、その意味を、誰よりも真剣に、孤独に考えつづけてきたのが、当事者である明仁天皇本人だった。「個人」として、「象徴」の意味を考えつづけた明仁天皇がたどり着いた結論は、彼がしてきた行いと「おことば」の中に、はっきりした形で存在している。
「私はこれまで天皇の務めとして、何よりもまず国民の安寧と幸せを祈ることを大切に考えて来ましたが、同時に事にあたっては、時として人々の傍らに立ち、その声に耳を傾け、思いに寄り添うことも大切なことと考えて来ました」
「その人」が訪れるのは、たとえば被災地だ。そこを訪れ、被災者と同じ「目線」でしゃべることができるように、「その人」は跪(ひざまず)くのである。「その人」は、弱い立場の人たちのところに行って励まし、声をかける。それから、もっと大切にしている仕事がある。それは「慰霊」の旅だ。「その人」は、繰り返し、前の戦争で亡くなった人たちの「いる」場所に赴き、深い哀悼の意を示す。
弱者と死者への祈り。それこそが「象徴」の務めである、と「その人」は考えたのだ。
戦後71年。この国の人々は、過去を忘れようと、あるいは、都合のいいように記憶を改竄(かいざん)しようとしている。だが、健全な社会とは、過去を忘れず、弱者や死者の息吹を感じながら、慎(つつ)ましく、未来へ進んでゆくものではないのか。個人として振る舞うことを禁じられながら、それでも、「その人」は、ただひとりしか存在しない、この国の「象徴」の義務として、そのことを告げつづけている。だが、70年前、中野重治が悲哀をこめて書いたように、その天皇がほんとうには持つことのなかった「人権」について考えられることはいまも少ないのである。
◇
社会の様々な現場を高橋さんが訪ねる寄稿シリーズ「歩きながら、考える」(随時掲載)は今回、皇居を行き先に選びました。退位の意向をにじませる「おことば」を表明して初となる、天皇誕生日の一般参賀です。平成で最多の3万8千人が訪れました。
入場開始の1時間前に現地へ。写真は皇居前で撮りました。「その人」の声を聞き終えると高橋さんは「新潟の話が出たね」と言いました。すばやく前日の火災に触れたことが印象深かったようです。 (編集委員・塩倉裕)