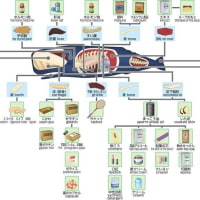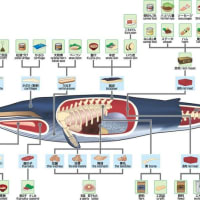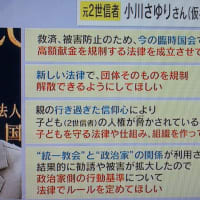6月14日(水):
サンデー毎日:大日本帝国を呼び戻す共謀罪は治安維持法の再来だ!=保阪正康 2017年5月31日
「共謀罪」が衆議院で可決されてしまった。市民生活を大幅に阻害し、社会を萎縮させる希代の悪法の強行を、現代史研究の第一人者は、「ファシストの所業」と喝破する。治安維持法によってもたらされた戦前・戦中のファシズムを検証しつつ、私たちの暗澹たる未来を照射する―。(一部敬称略)
どのような理由があって、この内閣は次々と問題法案を国会で成立させていくのだろうか。たとえば戦後も70年が過ぎたのだから、これまでの「戦後体制をご破算にする」というなら、そう主張すればいい。この国はこれまで国家意識が希薄であったから、「お国が第一」との発想を持ってもらうといって、安保関連法を通し、マイナンバー制度を導入し、少しでも犯罪のにおいをかぎつけたら市民的自由の制限など当たり前というのなら、その主張はファシズムそのものである。私は大反対ではあるが。
ところがこの政権は、どの方向に進むかの指示器も示さずに、ただひたすら結論ありきで突っ走っている。今回の共謀罪の委員会でのやりとり、国会審議の軽視、疑問がなんら解消しないままの法案成立を見ていて、今この国が向かっているのは、明らかに自省なき大日本帝国への回帰なんだ、と断定してかまわない。安倍首相は一言も口にしないが、自らの在任中に大日本帝国を再構築しようと企図していると考える以外にない。
共謀罪の審議でもっとも重要な点は、その条文やこの法律そのものの内容もさることながら、単純にこの法律によって私たちの健全な社会生活は著しく阻害されるということだ。共謀罪をテロ等準備罪と言い換えたところで、その内容は変わるわけではなく、社会が病理を抱えこむ時代になったという意味である。
「一般の人」論争などはその典型で、安倍首相はある集団が犯罪集団となったら、そこに関わっている人は「一般人であるわけがない」と屈託なく答えた。この無邪気な首相は実は恐るべきファシストなのである。ある集団が犯罪集団であるか否かは警察や検察が決めるというのであれば、一般人はどのような集団ともかかわらないでひたすら他者と関係を持たずに社会生活を営む以外になくなる。
「妄想」という弾圧する側の病理にとりつかれた
さて、こうしたことを前提に以下の論を進めることにしていきたい。
この法律が案として閣議決定(三月二十一日)する直前に、私は『毎日新聞』の取材に応じて「反対」の立場から次のように述べた(三月十九日付朝刊に「社会に病理を生む恐れ」との見出しがついている)。
「法は自己目的化することがある。戦前の治安維持法も、作られた当初は、天皇や私有財産を否定する団体を取り締まることが目的だった。しかし、徐々に取り締まりの対象が自由主義者、宗教、さらに国家主義者へと変わっていった。起訴率を高めるために取り調べに拷問も使われた。一般の人たちには関係のない法律だったはずが、考えられないほど増幅し、歯止めが利かなくなっていった。治安立法の怖さとはそういうものなのだ。(以下略)」
私はこの法律が国会に上程されるときからこのように考えていたが、結果的にこういう不安がむしろ当たり前になってしまった。
昭和史(とくにその前期)のファシズム体制を検証していて、治安維持法に基く捜査がどれほど社会生活を萎縮させるかはこれまで一貫して語られてきた。結局、この治安立法は、特高警察による自白を引き出すための拷問や、ごく一般人の社会生活も予防拘禁といった形で制限されたり、さらには特別要視察人として自らがたまたま入会していた文化サークルの中に一人の非社会的犯罪を夢想する者がいてその人物が逮捕されるなどすることで、一般人も一生監視されることにもなりかねない怖さを持ってきた。
そんな昭和の光景がこれからは日々繰り返される法的根拠ができあがっていく。それが「社会が病む」という状態であった。
昭和前期に特高警察に身を置いた刑事、治安維持法容疑で逮捕された宗教人、自由主義者、そしてごくふつうの市民(当時は臣民といったわけだが)など数十人に私は証言を求めてきた。それは結果的に社会が病むとはどういうことか、を知ることになったのだ。
まず初めに後藤田正晴、鈴木俊一などかつての内務省の官僚だった人物十人余に、大日本帝国下で内務省はどのような役割を果たしたのかを聞いていて、奇妙な言を何度か聞かされた。
それは「私は地方局育ちだから」という語である。内務省の地方局育ちは、ゆくゆくは官選知事になる。ありていにいうなら、ある県の県民の生活を守る、あるいはその環境を守ることを任務とする。しかし内務省育ちの人が、「地方局育ちだから」というときに、そこには警保局育ちで特高警察をフルに使って国民の弾圧に奔走した人たちとは肌が違う、との意味をこめていることに気づいたのだ。
「あの人は警保局育ちだから」というとき、そこには国民を弾圧するという発想しかないことを、いみじくも表しているのである。事実を言えば、同じ内務省にあっても、私は国民を、あるいは国民の思想を弾圧する側には与(くみ)さなかったと告白しているのである。
戦後の保守党の代議士の出身母体を見ていくとわかるが、内務省警保局出身の政治家は大体が右派グループに属し、常に治安維持を至上命令とし、そのための法律づくりに走り回っている。その言は、現実を見ているのではなく、国民がいつ共産主義者になるかわからない、反政府的分子になるかわからないとの妄想にも似た言を弄していたことが今は容易にわかる。
弾圧する側の病理にとりつかれてしまっているのだ。私は昭和のある事件の被害者がいかに特高警察に弾圧されたか、犯罪の意思などないのに拷問を何度も受け精神異常になった人たちの関係者の証言を聞いたのだが、そのことを当時の特高関係の責任者(戦後は自民党右派の議員)は一片の同情すら持っていないのに驚いた。
平気で拷問できるのが「有能な刑事」
思想犯の取り調べにあたった元特高警察の刑事たち(複数)にも、昭和四十年代に話を聞いたのだが、あえてそのときのメモをそのまま以下に紹介したい。
「我々ヒラ刑事もアカ(注・共産主義者のこと)の見分け方などの教育を受けたんだが、そんなことよりも疑いのある団体の連中を引っぱってきて強引に調べれば大体は我々の思いどおりに自白するよ。強引に調べればの意味? あのころは拷問は当たり前。といってもふつうの刑事はそんなに殴ったり蹴ったりできないよ。どこかで自制する気持ちもあるからね。しかしそんなことまったくかまわずに、女性でも少年でも棒で殴る、道端に連れていって叩(たた)きつける、小道具を使って痛めつける、細かくは言いたくないけどね。そして自白をとる。予審判事の覚えもよくなるから、そんな刑事ほど有能でできる奴(やつ)となったね。戦後は復讐(ふくしゅう)を恐れて姿を消した者もいる……」
こうした話を聞いていくと、特高警察の刑事たちの中では平気で拷問を続けることができるのが有能で、仕事のできる刑事、となるのだ。官僚機構の末端で、こうした汚れ役を担わされた拷問刑事は、思想犯として逮捕されるのを恐れている人たちや、やはり刑事仲間でも「超有名人」だったという。実際にこうした刑事に取り調べを受けた宗教家は、「おまえなんか非国民だから殺したっていいんだ」と言われ、その刑事のシナリオに合うように自白を強要されて拷問を受けたという。
「小柄な男で、ガラス玉のような感情のない目をしていた刑事で、その残酷さは有名でしたね」
そんな刑事たちは、T署のAとか、K署のBとかと、すぐに名指しされることに、私は驚いた。そういう刑事たちの名は、昭和二十年四月、五月から、警察署の名簿から消えていった。敗戦とともに、拷問を加えた容疑者たちからの復讐を恐れてのことという(戦後、実際にそういう刑事が探しだされて集団ですさまじいリンチを受けた事件が幾つかあったと証言する刑事もいる)。
これは原子物理学者の武谷三男から聞いた話だが、戦争末期にやはり治安維持法違反で逮捕されたというのだが、初めは拷問まがいの取り調べを受けたという。ところが敗戦が近くなると、刑事たちは「先生」と言いだし、それで署内で原子爆弾の説明を求められて、署員を前に講演したという。同志社大学の教授だった和田洋一(私の恩師なのだが)は、京都で新村出、中井正一、久野収らと同人誌「土曜日」を戦時下に細々と刊行した。和田は共産主義には批判的なクリスチャンだったが、特高刑事により治安維持法違反で逮捕されている。昭和十八年である。
その刑事は、「おまえは一日二十四時間のうち一分一秒でもいいから、共産主義はいいと思っただろう」と問われている。自分はこの思想には反対だというと、「そんなことはいい。一分一秒でもいいから思ったことあるだろう」とあまりにも執拗(しつよう)なので、「一秒ぐらいならあるかもしれない」と答えると、「それだよ。おまえは治安維持法違反なんだ」と言われた。この顛末(てんまつ)を和田は戦後になって『灰色のユーモア』という書の中で明かしている。
治安維持法の容疑者として逮捕され、その後釈放された者たちが一様に語っているが、戦争末期になると特高刑事たちは、そういう容疑者宅を回って、「俺はあんたを拷問していないよな。そのことを一筆書いてくれんか」と頼んで歩いたとのエピソードもある。
「あんた、俺を殴ったではないか」「いやあ一発二発ぐらいは大目に見ろよ」といった会話が交わされたというのである。
ファシズムは「行政独裁」と同義語
こうした話を幾つも集めていくと、治安維持法が暴走していくプロセスが、人間社会の思惑と計算をこめてのことであり、ひとたび弾圧機構が自己回転していくととんでもない形になることがわかる。
治安維持法は敗戦という事態でその醜悪な部分を露呈したのだが、共謀罪がもしこのような形で暴走するならば、歯止めはどのような形で収まるのだろうか。最低限度、共謀罪は取り調べの可視化が前提になるというのは当然のことであろう。
すでに多くの論者が指摘しているように、治安維持法は当初は共産主義系団体やその構成員を対象にしていた。しかし、昭和八年の鍋山貞親や佐野学ら指導部の転向声明を機に、実質的に共産主義者は存在しえない状態になった。そこで特高警察は機構を縮小していったか。
そんなことはない。むしろその体制を拡大して自由主義者、宗教家、文化人、労働者などのつくっている団体とそこに関係する「一般人」をターゲットにしていく。それを根絶やし状態にすると次は国家主義、民族主義陣営(いわゆる右翼)にとシフトしていく。
太平洋戦争下では、戦時立法とからませながら軍事に抗する人たちをも個の中に入れていく。その自己増殖の激しさは、驚くほどのスピードで進んでいくのだ。
昭和十八年一月一日、首相官邸でこの日の『朝日新聞』の朝刊の東方同志会・中野正剛による「戦時宰相論」を読んだ東條英機首相は、司法相の松阪広政にすぐに電話を入れ、中野の逮捕を命じている。中野は、検事による取り調べを受けるが、とくに該当する罪名はなく釈放。東條は憲兵隊に命じて中野の身柄を拘束して脅している。中野は「断」という一字を残して自決している。
軍事独裁といい、ファシズムという。しかしこれは何も特別の事態を意味するのではない。東條の例を見てもわかるとおり、行政独裁と同義語なのである。行政、立法、司法の三権は分立しているのではなく、行政の下に立法も司法も隷属していることを指している。
かつて安倍首相は「私は立法府の長である」と言って、あわてて取り消したというが、その心情は行政独裁国家にしますとの意思表示だったと考えれば、決して不思議ではない。しかも今回の共謀罪は統治主義から人治主義に変わる意味もある。この内閣の議会での答弁の、人を喰ったような内容は、行政独裁ならぬ「安倍独裁」との意味さえある。
テロ準備罪と名を変え、国連からの忠告も無視する動きを見ていくと、私たちの二十一世紀は暗澹(あんたん)とした気持ちになってくる。私たちは今、「昭和の怪物」よりはるかに凶々(まがまが)しい「平成の怪物」の下に身を置いているのかもしれない。
(この項、了) (ノンフィクション作家・評論家 保阪正康) (サンデー毎日6月11日号から) .
サンデー毎日:大日本帝国を呼び戻す共謀罪は治安維持法の再来だ!=保阪正康 2017年5月31日
「共謀罪」が衆議院で可決されてしまった。市民生活を大幅に阻害し、社会を萎縮させる希代の悪法の強行を、現代史研究の第一人者は、「ファシストの所業」と喝破する。治安維持法によってもたらされた戦前・戦中のファシズムを検証しつつ、私たちの暗澹たる未来を照射する―。(一部敬称略)
どのような理由があって、この内閣は次々と問題法案を国会で成立させていくのだろうか。たとえば戦後も70年が過ぎたのだから、これまでの「戦後体制をご破算にする」というなら、そう主張すればいい。この国はこれまで国家意識が希薄であったから、「お国が第一」との発想を持ってもらうといって、安保関連法を通し、マイナンバー制度を導入し、少しでも犯罪のにおいをかぎつけたら市民的自由の制限など当たり前というのなら、その主張はファシズムそのものである。私は大反対ではあるが。
ところがこの政権は、どの方向に進むかの指示器も示さずに、ただひたすら結論ありきで突っ走っている。今回の共謀罪の委員会でのやりとり、国会審議の軽視、疑問がなんら解消しないままの法案成立を見ていて、今この国が向かっているのは、明らかに自省なき大日本帝国への回帰なんだ、と断定してかまわない。安倍首相は一言も口にしないが、自らの在任中に大日本帝国を再構築しようと企図していると考える以外にない。
共謀罪の審議でもっとも重要な点は、その条文やこの法律そのものの内容もさることながら、単純にこの法律によって私たちの健全な社会生活は著しく阻害されるということだ。共謀罪をテロ等準備罪と言い換えたところで、その内容は変わるわけではなく、社会が病理を抱えこむ時代になったという意味である。
「一般の人」論争などはその典型で、安倍首相はある集団が犯罪集団となったら、そこに関わっている人は「一般人であるわけがない」と屈託なく答えた。この無邪気な首相は実は恐るべきファシストなのである。ある集団が犯罪集団であるか否かは警察や検察が決めるというのであれば、一般人はどのような集団ともかかわらないでひたすら他者と関係を持たずに社会生活を営む以外になくなる。
「妄想」という弾圧する側の病理にとりつかれた
さて、こうしたことを前提に以下の論を進めることにしていきたい。
この法律が案として閣議決定(三月二十一日)する直前に、私は『毎日新聞』の取材に応じて「反対」の立場から次のように述べた(三月十九日付朝刊に「社会に病理を生む恐れ」との見出しがついている)。
「法は自己目的化することがある。戦前の治安維持法も、作られた当初は、天皇や私有財産を否定する団体を取り締まることが目的だった。しかし、徐々に取り締まりの対象が自由主義者、宗教、さらに国家主義者へと変わっていった。起訴率を高めるために取り調べに拷問も使われた。一般の人たちには関係のない法律だったはずが、考えられないほど増幅し、歯止めが利かなくなっていった。治安立法の怖さとはそういうものなのだ。(以下略)」
私はこの法律が国会に上程されるときからこのように考えていたが、結果的にこういう不安がむしろ当たり前になってしまった。
昭和史(とくにその前期)のファシズム体制を検証していて、治安維持法に基く捜査がどれほど社会生活を萎縮させるかはこれまで一貫して語られてきた。結局、この治安立法は、特高警察による自白を引き出すための拷問や、ごく一般人の社会生活も予防拘禁といった形で制限されたり、さらには特別要視察人として自らがたまたま入会していた文化サークルの中に一人の非社会的犯罪を夢想する者がいてその人物が逮捕されるなどすることで、一般人も一生監視されることにもなりかねない怖さを持ってきた。
そんな昭和の光景がこれからは日々繰り返される法的根拠ができあがっていく。それが「社会が病む」という状態であった。
昭和前期に特高警察に身を置いた刑事、治安維持法容疑で逮捕された宗教人、自由主義者、そしてごくふつうの市民(当時は臣民といったわけだが)など数十人に私は証言を求めてきた。それは結果的に社会が病むとはどういうことか、を知ることになったのだ。
まず初めに後藤田正晴、鈴木俊一などかつての内務省の官僚だった人物十人余に、大日本帝国下で内務省はどのような役割を果たしたのかを聞いていて、奇妙な言を何度か聞かされた。
それは「私は地方局育ちだから」という語である。内務省の地方局育ちは、ゆくゆくは官選知事になる。ありていにいうなら、ある県の県民の生活を守る、あるいはその環境を守ることを任務とする。しかし内務省育ちの人が、「地方局育ちだから」というときに、そこには警保局育ちで特高警察をフルに使って国民の弾圧に奔走した人たちとは肌が違う、との意味をこめていることに気づいたのだ。
「あの人は警保局育ちだから」というとき、そこには国民を弾圧するという発想しかないことを、いみじくも表しているのである。事実を言えば、同じ内務省にあっても、私は国民を、あるいは国民の思想を弾圧する側には与(くみ)さなかったと告白しているのである。
戦後の保守党の代議士の出身母体を見ていくとわかるが、内務省警保局出身の政治家は大体が右派グループに属し、常に治安維持を至上命令とし、そのための法律づくりに走り回っている。その言は、現実を見ているのではなく、国民がいつ共産主義者になるかわからない、反政府的分子になるかわからないとの妄想にも似た言を弄していたことが今は容易にわかる。
弾圧する側の病理にとりつかれてしまっているのだ。私は昭和のある事件の被害者がいかに特高警察に弾圧されたか、犯罪の意思などないのに拷問を何度も受け精神異常になった人たちの関係者の証言を聞いたのだが、そのことを当時の特高関係の責任者(戦後は自民党右派の議員)は一片の同情すら持っていないのに驚いた。
平気で拷問できるのが「有能な刑事」
思想犯の取り調べにあたった元特高警察の刑事たち(複数)にも、昭和四十年代に話を聞いたのだが、あえてそのときのメモをそのまま以下に紹介したい。
「我々ヒラ刑事もアカ(注・共産主義者のこと)の見分け方などの教育を受けたんだが、そんなことよりも疑いのある団体の連中を引っぱってきて強引に調べれば大体は我々の思いどおりに自白するよ。強引に調べればの意味? あのころは拷問は当たり前。といってもふつうの刑事はそんなに殴ったり蹴ったりできないよ。どこかで自制する気持ちもあるからね。しかしそんなことまったくかまわずに、女性でも少年でも棒で殴る、道端に連れていって叩(たた)きつける、小道具を使って痛めつける、細かくは言いたくないけどね。そして自白をとる。予審判事の覚えもよくなるから、そんな刑事ほど有能でできる奴(やつ)となったね。戦後は復讐(ふくしゅう)を恐れて姿を消した者もいる……」
こうした話を聞いていくと、特高警察の刑事たちの中では平気で拷問を続けることができるのが有能で、仕事のできる刑事、となるのだ。官僚機構の末端で、こうした汚れ役を担わされた拷問刑事は、思想犯として逮捕されるのを恐れている人たちや、やはり刑事仲間でも「超有名人」だったという。実際にこうした刑事に取り調べを受けた宗教家は、「おまえなんか非国民だから殺したっていいんだ」と言われ、その刑事のシナリオに合うように自白を強要されて拷問を受けたという。
「小柄な男で、ガラス玉のような感情のない目をしていた刑事で、その残酷さは有名でしたね」
そんな刑事たちは、T署のAとか、K署のBとかと、すぐに名指しされることに、私は驚いた。そういう刑事たちの名は、昭和二十年四月、五月から、警察署の名簿から消えていった。敗戦とともに、拷問を加えた容疑者たちからの復讐を恐れてのことという(戦後、実際にそういう刑事が探しだされて集団ですさまじいリンチを受けた事件が幾つかあったと証言する刑事もいる)。
これは原子物理学者の武谷三男から聞いた話だが、戦争末期にやはり治安維持法違反で逮捕されたというのだが、初めは拷問まがいの取り調べを受けたという。ところが敗戦が近くなると、刑事たちは「先生」と言いだし、それで署内で原子爆弾の説明を求められて、署員を前に講演したという。同志社大学の教授だった和田洋一(私の恩師なのだが)は、京都で新村出、中井正一、久野収らと同人誌「土曜日」を戦時下に細々と刊行した。和田は共産主義には批判的なクリスチャンだったが、特高刑事により治安維持法違反で逮捕されている。昭和十八年である。
その刑事は、「おまえは一日二十四時間のうち一分一秒でもいいから、共産主義はいいと思っただろう」と問われている。自分はこの思想には反対だというと、「そんなことはいい。一分一秒でもいいから思ったことあるだろう」とあまりにも執拗(しつよう)なので、「一秒ぐらいならあるかもしれない」と答えると、「それだよ。おまえは治安維持法違反なんだ」と言われた。この顛末(てんまつ)を和田は戦後になって『灰色のユーモア』という書の中で明かしている。
治安維持法の容疑者として逮捕され、その後釈放された者たちが一様に語っているが、戦争末期になると特高刑事たちは、そういう容疑者宅を回って、「俺はあんたを拷問していないよな。そのことを一筆書いてくれんか」と頼んで歩いたとのエピソードもある。
「あんた、俺を殴ったではないか」「いやあ一発二発ぐらいは大目に見ろよ」といった会話が交わされたというのである。
ファシズムは「行政独裁」と同義語
こうした話を幾つも集めていくと、治安維持法が暴走していくプロセスが、人間社会の思惑と計算をこめてのことであり、ひとたび弾圧機構が自己回転していくととんでもない形になることがわかる。
治安維持法は敗戦という事態でその醜悪な部分を露呈したのだが、共謀罪がもしこのような形で暴走するならば、歯止めはどのような形で収まるのだろうか。最低限度、共謀罪は取り調べの可視化が前提になるというのは当然のことであろう。
すでに多くの論者が指摘しているように、治安維持法は当初は共産主義系団体やその構成員を対象にしていた。しかし、昭和八年の鍋山貞親や佐野学ら指導部の転向声明を機に、実質的に共産主義者は存在しえない状態になった。そこで特高警察は機構を縮小していったか。
そんなことはない。むしろその体制を拡大して自由主義者、宗教家、文化人、労働者などのつくっている団体とそこに関係する「一般人」をターゲットにしていく。それを根絶やし状態にすると次は国家主義、民族主義陣営(いわゆる右翼)にとシフトしていく。
太平洋戦争下では、戦時立法とからませながら軍事に抗する人たちをも個の中に入れていく。その自己増殖の激しさは、驚くほどのスピードで進んでいくのだ。
昭和十八年一月一日、首相官邸でこの日の『朝日新聞』の朝刊の東方同志会・中野正剛による「戦時宰相論」を読んだ東條英機首相は、司法相の松阪広政にすぐに電話を入れ、中野の逮捕を命じている。中野は、検事による取り調べを受けるが、とくに該当する罪名はなく釈放。東條は憲兵隊に命じて中野の身柄を拘束して脅している。中野は「断」という一字を残して自決している。
軍事独裁といい、ファシズムという。しかしこれは何も特別の事態を意味するのではない。東條の例を見てもわかるとおり、行政独裁と同義語なのである。行政、立法、司法の三権は分立しているのではなく、行政の下に立法も司法も隷属していることを指している。
かつて安倍首相は「私は立法府の長である」と言って、あわてて取り消したというが、その心情は行政独裁国家にしますとの意思表示だったと考えれば、決して不思議ではない。しかも今回の共謀罪は統治主義から人治主義に変わる意味もある。この内閣の議会での答弁の、人を喰ったような内容は、行政独裁ならぬ「安倍独裁」との意味さえある。
テロ準備罪と名を変え、国連からの忠告も無視する動きを見ていくと、私たちの二十一世紀は暗澹(あんたん)とした気持ちになってくる。私たちは今、「昭和の怪物」よりはるかに凶々(まがまが)しい「平成の怪物」の下に身を置いているのかもしれない。
(この項、了) (ノンフィクション作家・評論家 保阪正康) (サンデー毎日6月11日号から) .