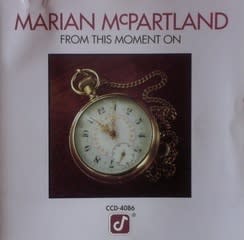Jazz Goes To The Movies / Manny Albam and His Orchestra
自分のリーダーアルバムで映画の主題曲を取り上げたのがジェロームリチャードソン。
「リチャードソンが映画の世界に・・」というタイトルでもあった。スタジオワークが多かったリチャードソンだが、ニューヨークを拠点にしていたので映画のサウンドトラックはそれほど多くは無かったかもしれないが。
ジャズプレーヤーが素材として映画の主題歌を採り上げることは多い。アルバムすべての曲を映画音楽から選ぶというものも何枚もある。
ここにもすべて映画の主題歌を採り上げたアルバムがある。
タイトルも「ジャズが映画に向かう」。名アレンジャー「マニーアルバム」の作品だ。
先日紹介したピーターソンのヴォーカルアルバムのアレンジも彼の手によるものであった。他にも自分が今まで紹介したアルバムにも良く登場している。
このマニーアルバム、実はサド・メルのデビューアルバムで有名な”Solid State”の設立に、ソニーレスターと一緒に加わった。当然だが、アレンジャーが加わったレーベルからはオーケストラのいい作品がよく生まれる。ゲーリー・マクファーランドの参加した「グリフォン」もそのひとつ。短命であったが結構自分のお気に入りであった。
このソリットステートではサド・メルが何と言っても一番であるが、マニーアルバム自身の作品も何枚か残されている。
このアルバムのライナーノーツの冒頭に、「音楽無しで映画を見ることは、悪い風邪をひいて味が分からないで食事をするようなものだ」と書かれている。
ジャズと映画の関係の歴史は古い。ベイシーも演奏を始めたのは無声映画の時代。カンサスシティーでの最初の仕事も、映画に合わせたピアノがベイシーの演奏暦の始まりだったとか。ホンキートンク風のピアノでも弾いていたのか。
スイング時代に生まれたジャズのスタンダードには、ミュージカルの主題歌いわゆるティンパンアレー物が多かった。映画の普及に合わせてミュージカルだけでなく映画の主題曲からも数多くのスタンダードが生まれていった。一方で、有名な「死刑台のエレベーター」のようなジャズをテーマにした作品も少なくない。映画とジャズは切っても切れない縁があるということだろう。
さて、映像に音楽がないと味わいが無いのと同様、映像無しでサウンドトラックの音楽だけを聴いても、演奏が平板に聴こえてしまう。もちろん実際に見たことのある映画だと「そのシーンを思い出しながら」という楽しみもあるのだが。サウンドトラックのアルバムを聴いて不満に思うのはこの点だ。
映画音楽の素材をオーケストラで表現するというのは、単調になりがちなサウンドトラックにもう一度飾りを施すようなもの。お馴染みのメロディーを音楽だけでも聴くに耐えうる作品に仕立て上げ直すという効果がある。
実際に映画音楽を作っている作曲家にとっては、観賞用のアレンジを別に用意するというのも楽しみの一つだと思う。ミッシェルルグランはその典型だと思うが、編曲に加えて自分の演奏まで加えて、映画を素材に作編曲、そして演奏と3点セットの作品が数多い。
このアルバムでは、まずは特徴ある映画音楽を素材に選び。有名なジャズプレーヤーを集め。曲に合わせてアレンジの曲想も変え。それに合わせてソロプレーの人選も考えるという凝った作りのジャズアルバムになっている。
編曲家、マニーアルバムの多彩な才能の本領発揮だ。
メンバーはオールスターであるが、その中に、ウッズとクイルの2人、クラークテリーとブルックマイヤーのコンビ、ビルクローとジムホール。どこかのグループでコンビを組んでいたメンバーが目立つ。それにエディーコスタも彼らとの共演が多い。気心が通じた普段コンボでも活躍していたソリストが集まって好演を繰り広げている。
結果は、ジャズ風の映画音楽というのではく、タイトルどおりジャズ作品として映画音楽に正面から向きあった一枚のアルバムだ。
これもインパルスの初期の作品。いいアルバムが多い。
1. Exodus Gold 5:10
2. High Noon (Do Not Forsake Me) Tiomkin, Washington 2:44
3. Paris Blues Ellington 2:42
4. La Dolce Vita Rota 2:40
5. Majority of One Steiner 2:05
6. Green Leaves of Summer Tiomkin, Webster 5:56
7. Guns of Navarone Tiomkin 3:26
8. El Cid Rozsa 2:25
9. Slowly Goell, Raksin 4:53
<Personnel>
Arranged & Conducted by Manny Albam
Produced by Bob Thiele
<8>
Al DeRisi, Bernie Glow, Nick Travis, Johnny Coles (tp)
Urbie Green, Bill Elton, Al Raph, Bill Dennis (tb)
Phil Woods (as)
Oliver Nelson (ts)
Jim Hall (g)
George Duvivier (b)
George Devens (per)
Gus Johnson (ds)
Recorded in NYC, January 12, 1962
<1>,<5>,<3>,<6>
John Bello, Johnny Coles, Al DeRisi, Joe Newman (tp)
Wayne Andre, Willie Dennis, Alan Raph (tb)
Bob Brookmeyer (vtb)
Gene Quill, Phil Woods (as)
Oliver Nelson, Frank Socolow (ts)
Gene Allen (bs)
Eddie Costa (p, vib)
Jim Hall (g)
Bill Crow (b)
Gus Johnson (d)
Recorded in NYC, January 25, 1962
<2>,<4>,<7>,<9>
Nick Travis (tp)
Clark Terry (tp, flh)
Bob Brookmeyer (vtb)
Julius Watkins (frh)
Harvey Phillips (tu)
Gene Quill (as)
Oliver Nelson (ts)
Gene Allen (bs)
Eddie Costa (p, vib)
Jimmy Raney (g)
Bill Crow (b)
Gus Johnson (d)
Pecorded in NYC, February 12, 1962
自分のリーダーアルバムで映画の主題曲を取り上げたのがジェロームリチャードソン。
「リチャードソンが映画の世界に・・」というタイトルでもあった。スタジオワークが多かったリチャードソンだが、ニューヨークを拠点にしていたので映画のサウンドトラックはそれほど多くは無かったかもしれないが。
ジャズプレーヤーが素材として映画の主題歌を採り上げることは多い。アルバムすべての曲を映画音楽から選ぶというものも何枚もある。
ここにもすべて映画の主題歌を採り上げたアルバムがある。
タイトルも「ジャズが映画に向かう」。名アレンジャー「マニーアルバム」の作品だ。
先日紹介したピーターソンのヴォーカルアルバムのアレンジも彼の手によるものであった。他にも自分が今まで紹介したアルバムにも良く登場している。
このマニーアルバム、実はサド・メルのデビューアルバムで有名な”Solid State”の設立に、ソニーレスターと一緒に加わった。当然だが、アレンジャーが加わったレーベルからはオーケストラのいい作品がよく生まれる。ゲーリー・マクファーランドの参加した「グリフォン」もそのひとつ。短命であったが結構自分のお気に入りであった。
このソリットステートではサド・メルが何と言っても一番であるが、マニーアルバム自身の作品も何枚か残されている。
このアルバムのライナーノーツの冒頭に、「音楽無しで映画を見ることは、悪い風邪をひいて味が分からないで食事をするようなものだ」と書かれている。
ジャズと映画の関係の歴史は古い。ベイシーも演奏を始めたのは無声映画の時代。カンサスシティーでの最初の仕事も、映画に合わせたピアノがベイシーの演奏暦の始まりだったとか。ホンキートンク風のピアノでも弾いていたのか。
スイング時代に生まれたジャズのスタンダードには、ミュージカルの主題歌いわゆるティンパンアレー物が多かった。映画の普及に合わせてミュージカルだけでなく映画の主題曲からも数多くのスタンダードが生まれていった。一方で、有名な「死刑台のエレベーター」のようなジャズをテーマにした作品も少なくない。映画とジャズは切っても切れない縁があるということだろう。
さて、映像に音楽がないと味わいが無いのと同様、映像無しでサウンドトラックの音楽だけを聴いても、演奏が平板に聴こえてしまう。もちろん実際に見たことのある映画だと「そのシーンを思い出しながら」という楽しみもあるのだが。サウンドトラックのアルバムを聴いて不満に思うのはこの点だ。
映画音楽の素材をオーケストラで表現するというのは、単調になりがちなサウンドトラックにもう一度飾りを施すようなもの。お馴染みのメロディーを音楽だけでも聴くに耐えうる作品に仕立て上げ直すという効果がある。
実際に映画音楽を作っている作曲家にとっては、観賞用のアレンジを別に用意するというのも楽しみの一つだと思う。ミッシェルルグランはその典型だと思うが、編曲に加えて自分の演奏まで加えて、映画を素材に作編曲、そして演奏と3点セットの作品が数多い。
このアルバムでは、まずは特徴ある映画音楽を素材に選び。有名なジャズプレーヤーを集め。曲に合わせてアレンジの曲想も変え。それに合わせてソロプレーの人選も考えるという凝った作りのジャズアルバムになっている。
編曲家、マニーアルバムの多彩な才能の本領発揮だ。
メンバーはオールスターであるが、その中に、ウッズとクイルの2人、クラークテリーとブルックマイヤーのコンビ、ビルクローとジムホール。どこかのグループでコンビを組んでいたメンバーが目立つ。それにエディーコスタも彼らとの共演が多い。気心が通じた普段コンボでも活躍していたソリストが集まって好演を繰り広げている。
結果は、ジャズ風の映画音楽というのではく、タイトルどおりジャズ作品として映画音楽に正面から向きあった一枚のアルバムだ。
これもインパルスの初期の作品。いいアルバムが多い。
1. Exodus Gold 5:10
2. High Noon (Do Not Forsake Me) Tiomkin, Washington 2:44
3. Paris Blues Ellington 2:42
4. La Dolce Vita Rota 2:40
5. Majority of One Steiner 2:05
6. Green Leaves of Summer Tiomkin, Webster 5:56
7. Guns of Navarone Tiomkin 3:26
8. El Cid Rozsa 2:25
9. Slowly Goell, Raksin 4:53
<Personnel>
Arranged & Conducted by Manny Albam
Produced by Bob Thiele
<8>
Al DeRisi, Bernie Glow, Nick Travis, Johnny Coles (tp)
Urbie Green, Bill Elton, Al Raph, Bill Dennis (tb)
Phil Woods (as)
Oliver Nelson (ts)
Jim Hall (g)
George Duvivier (b)
George Devens (per)
Gus Johnson (ds)
Recorded in NYC, January 12, 1962
<1>,<5>,<3>,<6>
John Bello, Johnny Coles, Al DeRisi, Joe Newman (tp)
Wayne Andre, Willie Dennis, Alan Raph (tb)
Bob Brookmeyer (vtb)
Gene Quill, Phil Woods (as)
Oliver Nelson, Frank Socolow (ts)
Gene Allen (bs)
Eddie Costa (p, vib)
Jim Hall (g)
Bill Crow (b)
Gus Johnson (d)
Recorded in NYC, January 25, 1962
<2>,<4>,<7>,<9>
Nick Travis (tp)
Clark Terry (tp, flh)
Bob Brookmeyer (vtb)
Julius Watkins (frh)
Harvey Phillips (tu)
Gene Quill (as)
Oliver Nelson (ts)
Gene Allen (bs)
Eddie Costa (p, vib)
Jimmy Raney (g)
Bill Crow (b)
Gus Johnson (d)
Pecorded in NYC, February 12, 1962