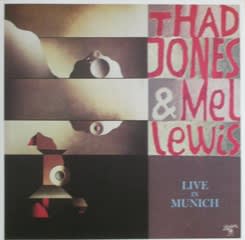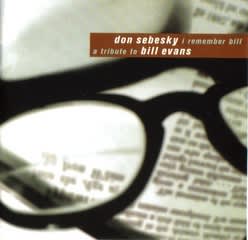BLUES GOING UP / GEORGE BARNES QUARTET
中学生の頃ベンチャーズなるグループが流行った。ある世代以上の方であれば知らない人はいないだろう。エレキブームを作った張本人であり、ビートルズに対抗してヒットチャートでトップを争っていたグループだ。
これまで売れたれレコードはミリオンどころではない。9000万枚を超えたとのこと。まだまだ現役なので一億枚も夢ではないかもしれない。
特徴は3本のギターにドラム。ピアノ(キーボード)レスでボーカルも無い。
ギターの技がすべてであり、あの「テケテケ」サウンドを作り出して一世を風靡した。
特にリードギターのノーキーエドワーズのギタースタイルはひとつの時代を作ったともいえる。
ジャズの世界ではギターだけのグループはあまり見かけない。
しかしConcordはアルバムづくりでギタープレーヤーを良く取り上げたので、ギターのDUOやトリオのアルバムも多い。
GEORGE BARNESのアルバムにこのカルテット編成がある。
ギターが2本にベースとドラムを加えたカルテットが、丁度ベンチャーズのジャズ版ともいえる編成である。
バーンズは、ジャズギターの世界でアンプ付きのギターでシングルトーンの演奏をした草分けの一人。あのチャーリークリスチャンが話題になるのに対してあまり評価されないのはスタジオ中心の仕事をしていたからであろう。
このアルバムは、このバーンズのカルテットが、サンフランシスコのクラブのサンデーマチネーに出演したものだ。
ライナーノーツに目を通すと、この演奏はジャズの歴史をさかのぼって1900年以前のジャズ発祥の地ニューオリンズの昼の街角を思い浮かべるようだと書かれている。
はたしてそれがどのようなものなのかは分からないが、アフリカンドラムのリズムに合わせたブルースギターの音色を想像すればよいのだろうか。その頃は洗濯板でさえ楽器の時代であった。
それに較べると非常に洗練されたサウンドだ。バーンズはひたすらシングルトーン中心。Ducan Jamesのリズムギターとのコンビネーションワークがすべてだ。
これは、「Jamセッションではなく、Jazzセッション」だとも書かれている。
ジャズの楽しみのひとつはジャムセッションだが、ある種MJQと同じような計算され尽くされたアンサンブルワークとその中の即興演奏もまた新鮮さを覚える。
最後のBLUES GOING UPは、アップテンポで普段あまり見せないコードワークを交えながらの彼のテクニックのすべてを見せるショーケース。アンコールに応えて、再度演奏を始めるあたりはライブならではの演奏だ。
ちょうど休日の昼下がり、この演奏が実際に行われたのと同じような時間にアルバムを聴けたのも「このライブの雰囲気」をいつもより実感できたのかもしれない。
この年、Barnesは9月に心臓発作で、地元Concordで他界している。この演奏で聴けるようにまだまだ50代のバリバリの現役であったのだが。
バーンズによるジャズの世界の「ベンチャーズ」は、ほとんど世に知られること無くこのアルバムが最後になった。
1. FASCINATING RHYTHM
2. WHY WAS I BORN
3. WHEN SUNNY GETS BLUES
4. SWEET GEORGEA BROWN
5. CHEERFUL LITTLE EARFUL
6. THE FLINSTONS THEME
7. PICK YOURSELF UP
8. ON GREEN DOLPHIN STREET
9. THREE LITTLE WORDS
10. I MAY BE WRONG BUT I THINK YOU’RE WONDERFUL
11. SWEET AND LOVELY
12. BLUES GOING UP
<Personnel>
George Barnes (g)
Duncan James (g)
Dean Reilly (b)
Benny Barth (ds)
Originally released on Concord CJ-43
Recorded live at Bimbo’s , San Francisco ,April 17 , 1977
中学生の頃ベンチャーズなるグループが流行った。ある世代以上の方であれば知らない人はいないだろう。エレキブームを作った張本人であり、ビートルズに対抗してヒットチャートでトップを争っていたグループだ。
これまで売れたれレコードはミリオンどころではない。9000万枚を超えたとのこと。まだまだ現役なので一億枚も夢ではないかもしれない。
特徴は3本のギターにドラム。ピアノ(キーボード)レスでボーカルも無い。
ギターの技がすべてであり、あの「テケテケ」サウンドを作り出して一世を風靡した。
特にリードギターのノーキーエドワーズのギタースタイルはひとつの時代を作ったともいえる。
ジャズの世界ではギターだけのグループはあまり見かけない。
しかしConcordはアルバムづくりでギタープレーヤーを良く取り上げたので、ギターのDUOやトリオのアルバムも多い。
GEORGE BARNESのアルバムにこのカルテット編成がある。
ギターが2本にベースとドラムを加えたカルテットが、丁度ベンチャーズのジャズ版ともいえる編成である。
バーンズは、ジャズギターの世界でアンプ付きのギターでシングルトーンの演奏をした草分けの一人。あのチャーリークリスチャンが話題になるのに対してあまり評価されないのはスタジオ中心の仕事をしていたからであろう。
このアルバムは、このバーンズのカルテットが、サンフランシスコのクラブのサンデーマチネーに出演したものだ。
ライナーノーツに目を通すと、この演奏はジャズの歴史をさかのぼって1900年以前のジャズ発祥の地ニューオリンズの昼の街角を思い浮かべるようだと書かれている。
はたしてそれがどのようなものなのかは分からないが、アフリカンドラムのリズムに合わせたブルースギターの音色を想像すればよいのだろうか。その頃は洗濯板でさえ楽器の時代であった。
それに較べると非常に洗練されたサウンドだ。バーンズはひたすらシングルトーン中心。Ducan Jamesのリズムギターとのコンビネーションワークがすべてだ。
これは、「Jamセッションではなく、Jazzセッション」だとも書かれている。
ジャズの楽しみのひとつはジャムセッションだが、ある種MJQと同じような計算され尽くされたアンサンブルワークとその中の即興演奏もまた新鮮さを覚える。
最後のBLUES GOING UPは、アップテンポで普段あまり見せないコードワークを交えながらの彼のテクニックのすべてを見せるショーケース。アンコールに応えて、再度演奏を始めるあたりはライブならではの演奏だ。
ちょうど休日の昼下がり、この演奏が実際に行われたのと同じような時間にアルバムを聴けたのも「このライブの雰囲気」をいつもより実感できたのかもしれない。
この年、Barnesは9月に心臓発作で、地元Concordで他界している。この演奏で聴けるようにまだまだ50代のバリバリの現役であったのだが。
バーンズによるジャズの世界の「ベンチャーズ」は、ほとんど世に知られること無くこのアルバムが最後になった。
1. FASCINATING RHYTHM
2. WHY WAS I BORN
3. WHEN SUNNY GETS BLUES
4. SWEET GEORGEA BROWN
5. CHEERFUL LITTLE EARFUL
6. THE FLINSTONS THEME
7. PICK YOURSELF UP
8. ON GREEN DOLPHIN STREET
9. THREE LITTLE WORDS
10. I MAY BE WRONG BUT I THINK YOU’RE WONDERFUL
11. SWEET AND LOVELY
12. BLUES GOING UP
<Personnel>
George Barnes (g)
Duncan James (g)
Dean Reilly (b)
Benny Barth (ds)
Originally released on Concord CJ-43
Recorded live at Bimbo’s , San Francisco ,April 17 , 1977