The Blues Hot and Cool + 7X Wilder / Bob Brookmeyer
ボブ・ブルックマイヤーが亡くなって3年経つ。晩年はアレンジャーとして活躍したがプレーヤーとしても息の長い活躍をした。レギュラーグループだとジェリーマリガンやクラークテリーとのコンビが有名だ。スタンゲッツともよくコンビを組んだが、誰と組んでも相手のプレーを引き立たせる名パートナーぶりを発揮する。
何の世界でも名脇役がいる。このブルックマイヤーも女房役として主役の引き立て役が似合うタイプだ。彼の楽器はトロンボーンでもバルブトロンボーン。ディキシー時代からトロンボーンは主役のトランペットの引き立て役であったが、バルブトロンボーン故の細かいフレーズワークは超低音のトランペットのよう。こんな絡み方を得意としていた。よくうたうプレーぶりだが、出身地のカンサスシティージャズのDNAを身に付けていたのかもしれない。
そのブルックマイヤーだが、ペッパーアダムスやズートシムスと同様、彼も50年代末から60年代初頭にかけて、821 6TH Ave.のロフトの常連だった。ニューヨークではスタジオワークの傍ら昔の相棒であったジェリーマリガンのコンサートバンドへ参加していたが、このロフトで繰り広げたコラボプレーを再現したようなアルバムを何枚か残している。
一番有名なのはビルエバンスとのピアノのコラボ”Ivory Hunter”だが、同じ時期にブルックマイヤーとしては珍しいワンホーンアルバムが2枚ある。その2枚がカップリングされて、CD化されているのがこのアルバム。どちらも、脇役から主役への変身が試されたアルバムとなった。

元のアルバムの一枚は”The Blues-Hot-And-Cool”.
ピアノのジミー・ロウルズが加わったトリオ。ベースはバディー・クラーク、ドラムはメル・ルイスだ。昔からのプレー仲間、主役ブルックマイヤーを引き立たせるバックとしては適任だ。
メル・ルイスも丁度ニューヨークに出てきたばかり。ブルックマイヤーと共にジェリーマリガンのコンサートビッグバンドに加わっていたが、メル・ルイスとブルックマイヤーのコンビはサドメルの立ち上げ時、さらにはサドジョーンズが去った後のメルルイスオーケストラでも深い関係がある。2人が最初にプレーをしたのは1952年、ブルックマイヤーがプロ活動を始めた頃すでに一緒にプレーをしている。ブルックマイヤーにとっては長い付き合いとなった一人だ。
ライナーノートに、発売当時のダウンビート評が載っている。「ブルックマイヤーのプレーはこれまでのアルバムではどれも”too lazy”、まるでベットで寝転がっているような感じであったが・・・」、「ところがこのアルバムは違う、エンジン全開でジャズの音節を取り込んでいる」と。
スタジオワークで色々なタイプの音楽に日々接している事、そしてLoftでのプレーの成果で演奏の幅が広がったのかもしれない。
ブルックマイヤーの好プレーを引き出した選曲もツボにはまっている。オリジナルのブルースの2曲が実にいい感じだ。他のポピュラーな曲の選曲もブルックマイヤーのメロディアスなプレーにはジャストフィット。
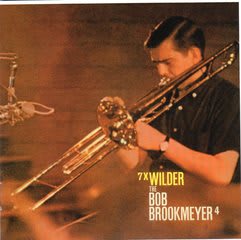
もう一枚は、”7x Wilder”。
こちらはギターのジムホールとのコラボになるが、ブルックマイヤーはトロンボーンだけでなくこのアルバムではピアノも弾いている。ビルエバンスとのアルバムも当初はトロンボーンで共演する予定だったのが急遽ピアノ同士のコラボになったといわれる。ブルックマイヤーは、デビューしてすぐのビッグバンド時代はピアニストとして参加したことも多かったようなので、ピアニストとしても一人前だ。
ジムホールとはジミージュフリーのグループで一緒だったが、Loftでのセッションでも良く一緒にプレーをしていたようだ。ベースはビル・クロウ、ドラムはこちらもメル・ルイス。このメンバーも、ジェリーマリガンのコンサートビッグバンドを含め良く一緒にプレーをしていた仲なので気心は通じ合った同士。
こちらのアルバムは、素材としてはAlec Wilderの作品集となっているが、ジムホールとのコラボプレーが聴きどころ。
この後、マリガンのバンドで一緒だったクラークテリーとレギュラーグループを組むことになったが、チームプレーが多かった中で、ブルックマイヤーの主役ぶりをたっぷり味わえる2枚のアルバムだ。
1. On the Sunny Side of the Street Dorothy Fields / Jimmy McHugh 6:04
2. Stoppin' at the Savoy Bob Brookmeyer 5:54
3. Languid Blues Bob Brookmeyer 7:21
4. I Got Rhythm George Gershwin / Ira Gershwin 4:53
5. Smoke Gets in Your Eyes Otto Harbach / Jerome Kern 5:48
6. Hot and Cold Blues Bob Brookmeyer 7:57
7. While We're Young Bill Engvick / Morty Palitz / Alec Wilder 6:09
8. That's the Way It Goes Sidney Robin / Alec Wilder 4:42
9. The Wrong Blue Bill Engvick / Alec Wilder 4:32
10. It's so Peaceful in the Country Alec Wilder 4:04
11. Blues for Alec Bob Brookmeyer 6:07
12. I'll Be Around Alec Wilder 4:28
13. Who Can I Turn To? Bill Engvick / Alec Wilder 4:26
1-6 The Blues Hot and Cool
Bob Brookmeyer (vtb)
Jimmy Rowles (p)
Buddy Clark (b)
Mel Lewis (ds)
Recorded in June 1960, New York
7-13 7 X Wilder
Bob Brookmeyer (vtb,p)
JimHall (g)
Bill Crow (b)
Mel Lewis (ds)
Recorded on June 29, New York
ボブ・ブルックマイヤーが亡くなって3年経つ。晩年はアレンジャーとして活躍したがプレーヤーとしても息の長い活躍をした。レギュラーグループだとジェリーマリガンやクラークテリーとのコンビが有名だ。スタンゲッツともよくコンビを組んだが、誰と組んでも相手のプレーを引き立たせる名パートナーぶりを発揮する。
何の世界でも名脇役がいる。このブルックマイヤーも女房役として主役の引き立て役が似合うタイプだ。彼の楽器はトロンボーンでもバルブトロンボーン。ディキシー時代からトロンボーンは主役のトランペットの引き立て役であったが、バルブトロンボーン故の細かいフレーズワークは超低音のトランペットのよう。こんな絡み方を得意としていた。よくうたうプレーぶりだが、出身地のカンサスシティージャズのDNAを身に付けていたのかもしれない。
そのブルックマイヤーだが、ペッパーアダムスやズートシムスと同様、彼も50年代末から60年代初頭にかけて、821 6TH Ave.のロフトの常連だった。ニューヨークではスタジオワークの傍ら昔の相棒であったジェリーマリガンのコンサートバンドへ参加していたが、このロフトで繰り広げたコラボプレーを再現したようなアルバムを何枚か残している。
一番有名なのはビルエバンスとのピアノのコラボ”Ivory Hunter”だが、同じ時期にブルックマイヤーとしては珍しいワンホーンアルバムが2枚ある。その2枚がカップリングされて、CD化されているのがこのアルバム。どちらも、脇役から主役への変身が試されたアルバムとなった。

元のアルバムの一枚は”The Blues-Hot-And-Cool”.
ピアノのジミー・ロウルズが加わったトリオ。ベースはバディー・クラーク、ドラムはメル・ルイスだ。昔からのプレー仲間、主役ブルックマイヤーを引き立たせるバックとしては適任だ。
メル・ルイスも丁度ニューヨークに出てきたばかり。ブルックマイヤーと共にジェリーマリガンのコンサートビッグバンドに加わっていたが、メル・ルイスとブルックマイヤーのコンビはサドメルの立ち上げ時、さらにはサドジョーンズが去った後のメルルイスオーケストラでも深い関係がある。2人が最初にプレーをしたのは1952年、ブルックマイヤーがプロ活動を始めた頃すでに一緒にプレーをしている。ブルックマイヤーにとっては長い付き合いとなった一人だ。
ライナーノートに、発売当時のダウンビート評が載っている。「ブルックマイヤーのプレーはこれまでのアルバムではどれも”too lazy”、まるでベットで寝転がっているような感じであったが・・・」、「ところがこのアルバムは違う、エンジン全開でジャズの音節を取り込んでいる」と。
スタジオワークで色々なタイプの音楽に日々接している事、そしてLoftでのプレーの成果で演奏の幅が広がったのかもしれない。
ブルックマイヤーの好プレーを引き出した選曲もツボにはまっている。オリジナルのブルースの2曲が実にいい感じだ。他のポピュラーな曲の選曲もブルックマイヤーのメロディアスなプレーにはジャストフィット。
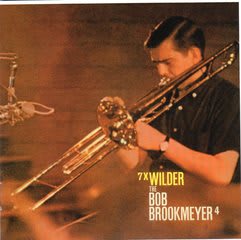
もう一枚は、”7x Wilder”。
こちらはギターのジムホールとのコラボになるが、ブルックマイヤーはトロンボーンだけでなくこのアルバムではピアノも弾いている。ビルエバンスとのアルバムも当初はトロンボーンで共演する予定だったのが急遽ピアノ同士のコラボになったといわれる。ブルックマイヤーは、デビューしてすぐのビッグバンド時代はピアニストとして参加したことも多かったようなので、ピアニストとしても一人前だ。
ジムホールとはジミージュフリーのグループで一緒だったが、Loftでのセッションでも良く一緒にプレーをしていたようだ。ベースはビル・クロウ、ドラムはこちらもメル・ルイス。このメンバーも、ジェリーマリガンのコンサートビッグバンドを含め良く一緒にプレーをしていた仲なので気心は通じ合った同士。
こちらのアルバムは、素材としてはAlec Wilderの作品集となっているが、ジムホールとのコラボプレーが聴きどころ。
この後、マリガンのバンドで一緒だったクラークテリーとレギュラーグループを組むことになったが、チームプレーが多かった中で、ブルックマイヤーの主役ぶりをたっぷり味わえる2枚のアルバムだ。
1. On the Sunny Side of the Street Dorothy Fields / Jimmy McHugh 6:04
2. Stoppin' at the Savoy Bob Brookmeyer 5:54
3. Languid Blues Bob Brookmeyer 7:21
4. I Got Rhythm George Gershwin / Ira Gershwin 4:53
5. Smoke Gets in Your Eyes Otto Harbach / Jerome Kern 5:48
6. Hot and Cold Blues Bob Brookmeyer 7:57
7. While We're Young Bill Engvick / Morty Palitz / Alec Wilder 6:09
8. That's the Way It Goes Sidney Robin / Alec Wilder 4:42
9. The Wrong Blue Bill Engvick / Alec Wilder 4:32
10. It's so Peaceful in the Country Alec Wilder 4:04
11. Blues for Alec Bob Brookmeyer 6:07
12. I'll Be Around Alec Wilder 4:28
13. Who Can I Turn To? Bill Engvick / Alec Wilder 4:26
1-6 The Blues Hot and Cool
Bob Brookmeyer (vtb)
Jimmy Rowles (p)
Buddy Clark (b)
Mel Lewis (ds)
Recorded in June 1960, New York
7-13 7 X Wilder
Bob Brookmeyer (vtb,p)
JimHall (g)
Bill Crow (b)
Mel Lewis (ds)
Recorded on June 29, New York
 | THE BLUES HOT AND COLD + 7 X WILDER |
| Bob Brookmeyer | |
| LONEHILLJAZZ |










































