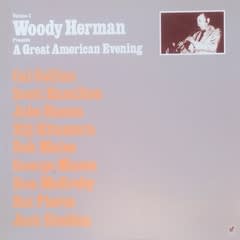Christmas Serenade in the Glenn Miller Style / Tex Benke, Ray Eberle,The Modernaires with Paula Kelly
寒さだけは一足先に12月の寒さだが、11月も25日を過ぎクリスマスまであと一ケ月。
ただでさえ時間が経つのが早いが、年末の慌ただしさの中、これからの時期はいつにも増してあっと言う間に時が過ぎゆく。クリスマスのアルバムもこの時期に聴かねばと思いつつ、聴きそびれてまた来年となってしまう。今年は早めに聴き始める事にしようと思う。
クリスマスのアルバムとなると曲は定番、歌や演奏はジャズ以外にも世の中には山ほどあるので、同じ曲を色々な演奏で聴き較べるには格好の素材だ。有名ミュージシャンは、一度はクリスマスアルバムを作っているので、好きな歌手やミュージシャンのアルバムを聴くのもひとつ。もう一つは、ミュージシャンではなく、普段聴かないジャンルを含めて、どんなスタイルのアルバムを選んでみようか悩むのも楽しいものだ。
あまりクリスマスとは結びつかないジャンルのアルバムも意外性があっていいが、まずはクリスマスにはお似合いのスイングスタイルから。
このアルバムはその代表格。タイトル通りグレンミラースタイルでのクリスマスだ。それもボーカル&コーラス付きで。タイトルに固有名詞が沢山並んでいるので、その関係も改めて整理しておくと。
昔のスイングオーケストラはコーラスやボーカルをメンバー従えていたが、オリジナルのグレンミラーオーケストラも例外ではなかった。そのミラーオーケストラの専属コーラスグループがModernaires。結成されたのは1934年男性のトリオでスタートするが、グレンミラーと契約したのは1940年。Make Believe Ballroom Timeがスタートであった。
この時の写真がこのYou Tubeにもあるが、Modernairesに加えて、2人のボーカリストがいる。
一人がこのアルバムのリーダーでもあるTex Benke。ここでは歌も歌っているが本業はサックス、この二刀流がその後のミュージシャン生活を悩ましたようだが。もう一人のボーカルがRay Eberle。
このアルバムに加わっているPaula Kellyはこの時まだメンバーではなく、彼女がミラーのバンドに加わったのは、映画“Sun Valley Serenade”に一緒に出演したのが始まり、1941年になってからだ。もっとも、彼女はこの時すでにModernairesのリーダーHal Dickenson夫人となっていたので、すでに身内であったと言ってもいいかも。
その後、ミラーのバンドで一緒に活動していたが、リーダーのグレンミラーは1942年に軍隊に加わるためにバンドを解散することに。そこで、ケリーはModernairesに加わって、女性一人、男性5人のコーラスグループが誕生した。
その後、KellyはKelly Jr.に代替わり、他のメンバーも入れ替わったが、今でもこのModernairesはスイングスタイルのコーラスグループとして活動しているようだ。
このアルバムが録音されたのは1965年。彼らが一緒に演奏していた時から25年近く経っていた。デビュー当時は彼らのスタイルが世の中の最先端であったが、ビートルズ時代の始まり、世の中ロックの波に洗われ音楽の流行や好みは大きく変っていた。しかし、彼らは何も動ぜず昔のスイングスタイルを守ってプレーを続けていた。
Tex Benke.もミラーが去った後、一時はグレンミラーオーケストラを引き継いだり、他の演奏をやりたくて辞めたりしていたようだが、結局、スイングスタイルのビッグバンドが彼の拠り所となっていた。
彼を中心にまさにオリジナルのミラーオーケストラのシンガー達が集まって、彼らの原点であるミラーサウンドを再現するのだからこれは本物だ。アレンジはアランコープランがやっているが、多少モダンに響く所もあり、珠玉のミラーサウンドを再現している。
はたして、オリジナルのグレンミラーのクリスマスソングの録音があるかどうかは寡聞にして知らないが、グレンミラーサウンドのクリスマスアルバムとしてはお勧め盤だ。
1. It Happened in Sun Valley Mack Gordon / Harry Warren 2:34
2. Have Yourself a Merry Little Christmas Ralph Blane / Hugh Martin 2:46
3. We Wish You the Merriest Les Brown 2:26
4. The Christmas Song Mel Tormé / Robert Wells 2:59
5. Rudolph the Red-Nosed Reindeer Johnny Marks 2:28
6. Snowfall Sandy Owen / Claude Thornhill 2:50
7. And the Bells Rang Glenn Miller 1:56
8. Merry Christmas, Baby Lou Baxter / Johnny Moore 2:28
9. Jingle Bells James Pierpont 2:59
10. Santa Claus Is Coming to Town J. Fred Coots / Haven Gillespie 2:28
11. Sleigh Ride Leroy Anderson / Mitchell Parish 3:00
12. White Christmas Irving Berlin 3:00
The Modernaires
Tex Benke (vol,ts)
Ray Eberle (vol)
Paul Kelly (vol)
Arranged by Alan Copeland
Recorded in 1965
寒さだけは一足先に12月の寒さだが、11月も25日を過ぎクリスマスまであと一ケ月。
ただでさえ時間が経つのが早いが、年末の慌ただしさの中、これからの時期はいつにも増してあっと言う間に時が過ぎゆく。クリスマスのアルバムもこの時期に聴かねばと思いつつ、聴きそびれてまた来年となってしまう。今年は早めに聴き始める事にしようと思う。
クリスマスのアルバムとなると曲は定番、歌や演奏はジャズ以外にも世の中には山ほどあるので、同じ曲を色々な演奏で聴き較べるには格好の素材だ。有名ミュージシャンは、一度はクリスマスアルバムを作っているので、好きな歌手やミュージシャンのアルバムを聴くのもひとつ。もう一つは、ミュージシャンではなく、普段聴かないジャンルを含めて、どんなスタイルのアルバムを選んでみようか悩むのも楽しいものだ。
あまりクリスマスとは結びつかないジャンルのアルバムも意外性があっていいが、まずはクリスマスにはお似合いのスイングスタイルから。
このアルバムはその代表格。タイトル通りグレンミラースタイルでのクリスマスだ。それもボーカル&コーラス付きで。タイトルに固有名詞が沢山並んでいるので、その関係も改めて整理しておくと。
昔のスイングオーケストラはコーラスやボーカルをメンバー従えていたが、オリジナルのグレンミラーオーケストラも例外ではなかった。そのミラーオーケストラの専属コーラスグループがModernaires。結成されたのは1934年男性のトリオでスタートするが、グレンミラーと契約したのは1940年。Make Believe Ballroom Timeがスタートであった。
この時の写真がこのYou Tubeにもあるが、Modernairesに加えて、2人のボーカリストがいる。
一人がこのアルバムのリーダーでもあるTex Benke。ここでは歌も歌っているが本業はサックス、この二刀流がその後のミュージシャン生活を悩ましたようだが。もう一人のボーカルがRay Eberle。
このアルバムに加わっているPaula Kellyはこの時まだメンバーではなく、彼女がミラーのバンドに加わったのは、映画“Sun Valley Serenade”に一緒に出演したのが始まり、1941年になってからだ。もっとも、彼女はこの時すでにModernairesのリーダーHal Dickenson夫人となっていたので、すでに身内であったと言ってもいいかも。
その後、ミラーのバンドで一緒に活動していたが、リーダーのグレンミラーは1942年に軍隊に加わるためにバンドを解散することに。そこで、ケリーはModernairesに加わって、女性一人、男性5人のコーラスグループが誕生した。
その後、KellyはKelly Jr.に代替わり、他のメンバーも入れ替わったが、今でもこのModernairesはスイングスタイルのコーラスグループとして活動しているようだ。
このアルバムが録音されたのは1965年。彼らが一緒に演奏していた時から25年近く経っていた。デビュー当時は彼らのスタイルが世の中の最先端であったが、ビートルズ時代の始まり、世の中ロックの波に洗われ音楽の流行や好みは大きく変っていた。しかし、彼らは何も動ぜず昔のスイングスタイルを守ってプレーを続けていた。
Tex Benke.もミラーが去った後、一時はグレンミラーオーケストラを引き継いだり、他の演奏をやりたくて辞めたりしていたようだが、結局、スイングスタイルのビッグバンドが彼の拠り所となっていた。
彼を中心にまさにオリジナルのミラーオーケストラのシンガー達が集まって、彼らの原点であるミラーサウンドを再現するのだからこれは本物だ。アレンジはアランコープランがやっているが、多少モダンに響く所もあり、珠玉のミラーサウンドを再現している。
はたして、オリジナルのグレンミラーのクリスマスソングの録音があるかどうかは寡聞にして知らないが、グレンミラーサウンドのクリスマスアルバムとしてはお勧め盤だ。
1. It Happened in Sun Valley Mack Gordon / Harry Warren 2:34
2. Have Yourself a Merry Little Christmas Ralph Blane / Hugh Martin 2:46
3. We Wish You the Merriest Les Brown 2:26
4. The Christmas Song Mel Tormé / Robert Wells 2:59
5. Rudolph the Red-Nosed Reindeer Johnny Marks 2:28
6. Snowfall Sandy Owen / Claude Thornhill 2:50
7. And the Bells Rang Glenn Miller 1:56
8. Merry Christmas, Baby Lou Baxter / Johnny Moore 2:28
9. Jingle Bells James Pierpont 2:59
10. Santa Claus Is Coming to Town J. Fred Coots / Haven Gillespie 2:28
11. Sleigh Ride Leroy Anderson / Mitchell Parish 3:00
12. White Christmas Irving Berlin 3:00
The Modernaires
Tex Benke (vol,ts)
Ray Eberle (vol)
Paul Kelly (vol)
Arranged by Alan Copeland
Recorded in 1965