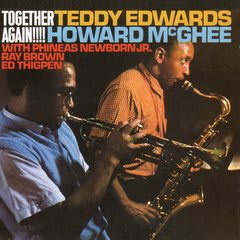American Jazz Institute Presents Ellington Saxophone Encounters
ジャズの演奏はある種の一期一会。そこで生まれる名演と全く同じものが再び演奏されることはない。だからこそ、過去の演奏が時代を経ても聴かれ続けるのだろう。中でも名手の名演といわれるものは、色々な形でカバーされることも多い。同じような編成だけでなく、時にはランバートヘンドリックス&ロスが試みたようにボーカライズされたり、スーパーサックスのようにアンサンブルにしたり。
名手の再演は何もソロだけでなくビッグバンドもある。ベイシーや、エリントンはそれそれぞれ独自のサウンドを作り出した。譜面のあるビッグバンドは、理屈上は同じ演奏も可能でオリジナルサウンドの再現も可能だが、本家のノリを出すのはそんない簡単ではない。譜面に表せない「何か」がある。新たなアレンジをしても、どこかオリジナルのイメージが残ってしまうものも不思議だ。
マーク・マスターズという西海岸出身のアレンジャーがいる。1957年生まれ、西海岸で音楽を学びトランペットも吹くマークが初めてアルバムを作ったのは84年、27歳の時だった。その後、アレンジだけでなく教育にも携わるようになり、97年にはAmerican Jazz Institute(AJI)というNPOを設立した。ジャズの伝承により力を入れるために。
ジャズの啓蒙や教育などを行うのに加えて、伝統ある過去の曲や新たな曲チャレンジをするレパートリーオーケストラを編成し、ラジオ局も持っている。このジャズの伝承を幅広く行う組織のプレジデントとして今でも活躍している。
このAJIが監修しているアルバムが何枚かある。すべてを聴いた訳ではないが、どれも拘りを感じるアルバムだ。
このマーク・マスターズが、バリトンサックスのゲイリースマリヤンに相談を持ち掛けて生まれたのがこのアルバムだ。サックス奏者が5人集まったアンサンブルチームだが、そのチームリーダーをスマリヤンに託した。スマリヤンもアルバムの主旨を聞いて快諾したそうだ。
「エリントンサックスエンカウンター」というタイトルにあるように、エリントンナンバーをサックスサンサンブルで再現してくれるのかと思ったら、もう一捻りしている。
エリントンオーケストラのサックスセクションにも代々名プレーヤーがいる、アルトのジョニーホッジスを始めとして、テナーではポールゴンザルベス、古くはベンウェブスター、クラリネットのジミーハミルトン、そしてバリトンはハーリーカーネイ。誰をとってもエリントンサウンドには不可欠な名手だ。
エリントンのオーケストラというとエリントン自作の曲が多いが、エリントンは彼らのソロの出番を常に考慮している。しかし、エリントン以外に彼らエリンニアンが作った曲もある。もちろん自分達をフィーチャーした演奏で。
このアルバムでは、そのようなサックスセクションのメンバーが作った曲を選び、さらに、それらをサックスのアンサンブルに仕立て上げている。パーカーの演奏を素材にして有名なスーパーサックスのエリントン版だが、エリントンオーケストラのサックスセクションのメンバーの曲と演奏を素材にしているという拘りに感心する。
アレンジを担当したのは、もちろんマークマスターズ。アレンジはエリントンサウンドを十分に意識している。スマリヤンもソロだけでなくアンサンブルでも大活躍。エリントンサウンドを支えたハーリーカーネイのバリトンの役割が大事であったことが再認識される。他のメンバーも、ピートクリストリーブ、ゲイリーフォスターなど西海岸の重鎮が並ぶ。サックス好きにはたまらないサウンド、さらにエリントンファンには一石二鳥だ。
このように過去の名演を伝承するには、単にカバーするだけでなくやり方次第で新たな名演を生み出すことができる。このように歴史的な遺産ともいえるジャズの演奏は、後継者たちによってきちんと残す努力が色々な形で行われている。このような地味な活動を支えられるのは、やはり本場アメリカだからか。日本でも同じような活動を試みるミュージシャンを支えるファンが育たねばと思うのだが。
1. Esquire Swank (Hodges-Ellington)
2. The Line Up (Paul Gonsalves)
3. LB Blues (Johnny Hodges)
4. We're In Love Again (Harry Carney)
5. Ultra Blue (Jimmy Hamilton)
6. Used To Be Duke (Johnny Hodges)
7. Jeep's Blues (Hodges-Ellington)
8. Get Ready (Jimmy Hamilton)
9. Love's Away (Ben Webster)
10. Rockin' In Rhythm (Carney-Ellington)
11. Peaches (Johnny Hodges)
12. The Happening (Paul Gonsalves)
Gary Smulyan (bs)
Gary Foster (as,cl)
Dan Shelton (as,cl)
Pete Christlieb (ts)
Gene Cipriano (ts)
Bill Cunliffe (p)
Tom Warrington (b)
Joe La Barbera (ds)
Produced by Mark Masters & Tom Burns
Arranged by Mark Masters
Recorded on January 15, 2012 at Tri Tone Studio
Engineer : Tally Sherwood
ジャズの演奏はある種の一期一会。そこで生まれる名演と全く同じものが再び演奏されることはない。だからこそ、過去の演奏が時代を経ても聴かれ続けるのだろう。中でも名手の名演といわれるものは、色々な形でカバーされることも多い。同じような編成だけでなく、時にはランバートヘンドリックス&ロスが試みたようにボーカライズされたり、スーパーサックスのようにアンサンブルにしたり。
名手の再演は何もソロだけでなくビッグバンドもある。ベイシーや、エリントンはそれそれぞれ独自のサウンドを作り出した。譜面のあるビッグバンドは、理屈上は同じ演奏も可能でオリジナルサウンドの再現も可能だが、本家のノリを出すのはそんない簡単ではない。譜面に表せない「何か」がある。新たなアレンジをしても、どこかオリジナルのイメージが残ってしまうものも不思議だ。
マーク・マスターズという西海岸出身のアレンジャーがいる。1957年生まれ、西海岸で音楽を学びトランペットも吹くマークが初めてアルバムを作ったのは84年、27歳の時だった。その後、アレンジだけでなく教育にも携わるようになり、97年にはAmerican Jazz Institute(AJI)というNPOを設立した。ジャズの伝承により力を入れるために。
ジャズの啓蒙や教育などを行うのに加えて、伝統ある過去の曲や新たな曲チャレンジをするレパートリーオーケストラを編成し、ラジオ局も持っている。このジャズの伝承を幅広く行う組織のプレジデントとして今でも活躍している。
このAJIが監修しているアルバムが何枚かある。すべてを聴いた訳ではないが、どれも拘りを感じるアルバムだ。
このマーク・マスターズが、バリトンサックスのゲイリースマリヤンに相談を持ち掛けて生まれたのがこのアルバムだ。サックス奏者が5人集まったアンサンブルチームだが、そのチームリーダーをスマリヤンに託した。スマリヤンもアルバムの主旨を聞いて快諾したそうだ。
「エリントンサックスエンカウンター」というタイトルにあるように、エリントンナンバーをサックスサンサンブルで再現してくれるのかと思ったら、もう一捻りしている。
エリントンオーケストラのサックスセクションにも代々名プレーヤーがいる、アルトのジョニーホッジスを始めとして、テナーではポールゴンザルベス、古くはベンウェブスター、クラリネットのジミーハミルトン、そしてバリトンはハーリーカーネイ。誰をとってもエリントンサウンドには不可欠な名手だ。
エリントンのオーケストラというとエリントン自作の曲が多いが、エリントンは彼らのソロの出番を常に考慮している。しかし、エリントン以外に彼らエリンニアンが作った曲もある。もちろん自分達をフィーチャーした演奏で。
このアルバムでは、そのようなサックスセクションのメンバーが作った曲を選び、さらに、それらをサックスのアンサンブルに仕立て上げている。パーカーの演奏を素材にして有名なスーパーサックスのエリントン版だが、エリントンオーケストラのサックスセクションのメンバーの曲と演奏を素材にしているという拘りに感心する。
アレンジを担当したのは、もちろんマークマスターズ。アレンジはエリントンサウンドを十分に意識している。スマリヤンもソロだけでなくアンサンブルでも大活躍。エリントンサウンドを支えたハーリーカーネイのバリトンの役割が大事であったことが再認識される。他のメンバーも、ピートクリストリーブ、ゲイリーフォスターなど西海岸の重鎮が並ぶ。サックス好きにはたまらないサウンド、さらにエリントンファンには一石二鳥だ。
このように過去の名演を伝承するには、単にカバーするだけでなくやり方次第で新たな名演を生み出すことができる。このように歴史的な遺産ともいえるジャズの演奏は、後継者たちによってきちんと残す努力が色々な形で行われている。このような地味な活動を支えられるのは、やはり本場アメリカだからか。日本でも同じような活動を試みるミュージシャンを支えるファンが育たねばと思うのだが。
1. Esquire Swank (Hodges-Ellington)
2. The Line Up (Paul Gonsalves)
3. LB Blues (Johnny Hodges)
4. We're In Love Again (Harry Carney)
5. Ultra Blue (Jimmy Hamilton)
6. Used To Be Duke (Johnny Hodges)
7. Jeep's Blues (Hodges-Ellington)
8. Get Ready (Jimmy Hamilton)
9. Love's Away (Ben Webster)
10. Rockin' In Rhythm (Carney-Ellington)
11. Peaches (Johnny Hodges)
12. The Happening (Paul Gonsalves)
Gary Smulyan (bs)
Gary Foster (as,cl)
Dan Shelton (as,cl)
Pete Christlieb (ts)
Gene Cipriano (ts)
Bill Cunliffe (p)
Tom Warrington (b)
Joe La Barbera (ds)
Produced by Mark Masters & Tom Burns
Arranged by Mark Masters
Recorded on January 15, 2012 at Tri Tone Studio
Engineer : Tally Sherwood
 | Ellington Saxophone Encounters |
| クリエーター情報なし | |
| Capri Records |