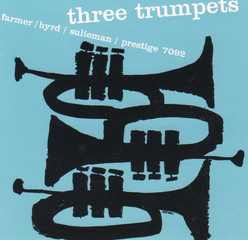年明けとともに、寒い日が続いていた。
ゴルフには寒さだけでなく、カチンカチンに凍ったグリーンはプレーしていても面白くない。ちょうどこの冬一番の冷え込みと言われた日、朝一番のスタートだったが、その前に支配人が一足先にスタートしていった。終わって風呂場で顔を合わせると、「グリーンのシートをもう少し大きくしないといけないな」と。元々プロだったその支配人、最近は集客と売上が優先される時代だけに、何事も自ら現場体験してお客の立場で改善していくというのはいいことだ。
という訳で、寒い日本を離れて先日グアムに遠征した。昔は、毎年ハワイ合宿をしたこともあったが、久々の海外ゴルフ。というよりは海外に出掛けること自体久しぶりだった。
今回は、日数も短く、ゴルフバッグを持参しなければならないので、空港まで車で行って預けることにした。最近、羽田空港は駐車場が満杯で、時間によっては駐車するのも大変と聞くので、成田の駐車場事情はどうかと調べたら、こちらは外部の駐車場も多く問題はなさそう。競争が激しくなっているのか、以前よりも安くなったような気もした。その中で一泊300円と激安のB-timesが目についた。
調べてみるとコインパーキングのTimesが最近力を入れている時間貸しではなく、日貸の駐車場。成田の場合、場所は系列のタイムスレンタカーの敷地の中。要はレンタカーを置いてあるパーキングスペースの有効利用ということだ。
当然利用者は空港利用者がほとんどだと思うが、空港までの送り迎えはレンタカーの送迎バスがあるので、これを利用すれば新たな投資は必要なし。在り物利用のサービスとしては良くできた仕組みだ。
もちろん、利用者にとっても同じサービスであれば安いのが一番。タイムスクラブのメンバー限定のサービスだが、たまたま自分は会員になっていたので、使う側も何も面倒な手続きいらずであった。実際に使ってみたが、利用できる台数も多くないので、個人サービスに近く、待ち時間もなく便利に使わせてもらった。次回もここを使うだろう
グアムでのゴルフは、スターツゴルフリゾートとマンギラオゴルフクラブ、どちらも日本の会社がオーナーでお客も大部分が日本人。グアムは今がトップシーズン、プレー料金もしっかりリゾート料金であった。特にマンギラオは全日$250、円安の昨今3万円に近い。今回の幹事役が色々伝手を探したが、ディスカウントは一切無いらしい。国内ではプレー代は安くなる一方だが、やはり価格は需給関係で決まるのだろう。
何を買っても、高く割に中身が期待外れだとがっかりするものだが、今回のコースは価格相応に満足。天気が良かったのも幸いだった。リゾートコースにしてはどちらも手入れが良く、特にグリーンが良い状態だった。マンギラオは、米国ゴルフダイジェスト誌の世界の100コースに選ばれているというだけあって、有名な海越えの12番ショート以外も全体のレイアウトが変化に富んでいて楽しめるコースだ。池が絡むホールが多いアウトと、崖を下って海沿いのインの対比も素晴らしい。


初めて廻るコースはどこに行ってもプレー以前に、OBはどこかとか、池やバンカーの在りかが気になる。更に、ここのようにリゾートコースで綺麗な景色が楽しめ、おまけに風が強いとなると、気になる事が多く、肝心のスコアはどうしても二の次になる。もう一度プレーに集中してチャレンジしてみたいコースだ。
暖かい南国でゴルフをすると、寒い日本ではしばらくゴルフはお休みかと思っていたが、ここ2,3日の暖かさにつられて昨日はホームコースへ。研修生がキャディーにつき、組み合わせで2サムだったので、こちらは見慣れた景色に見とれることもなく、プレーに集中できた。
前半はダボなしの41。後半もその調子と思ったら、出だしのロングホールで林に打ち込み大トラブル。最終のロングホールも同じミス。どちらも大叩きの9。他はなんとかまとめてまずまず90を切るスコア。
昨年末からパットの不調が続いていたが、グリップを変えたせいとばかり思っていた。先日忘れていたポイントを一つ思い出したらパットがしっくりきたのが大きい。周りの状況を気にしないだけでなく、体の動きも無意識に自然体で打てるとスイング全体がしっくりくるのだが、ゴルフというのはどうもその域に達するのは難しいようだ。プロが毎日のように練習しても体に覚え込ますのは大変なようだが、素人は身に付いたつもりでも一晩寝るとすぐに忘れてしまう。
ゴルフには寒さだけでなく、カチンカチンに凍ったグリーンはプレーしていても面白くない。ちょうどこの冬一番の冷え込みと言われた日、朝一番のスタートだったが、その前に支配人が一足先にスタートしていった。終わって風呂場で顔を合わせると、「グリーンのシートをもう少し大きくしないといけないな」と。元々プロだったその支配人、最近は集客と売上が優先される時代だけに、何事も自ら現場体験してお客の立場で改善していくというのはいいことだ。
という訳で、寒い日本を離れて先日グアムに遠征した。昔は、毎年ハワイ合宿をしたこともあったが、久々の海外ゴルフ。というよりは海外に出掛けること自体久しぶりだった。
今回は、日数も短く、ゴルフバッグを持参しなければならないので、空港まで車で行って預けることにした。最近、羽田空港は駐車場が満杯で、時間によっては駐車するのも大変と聞くので、成田の駐車場事情はどうかと調べたら、こちらは外部の駐車場も多く問題はなさそう。競争が激しくなっているのか、以前よりも安くなったような気もした。その中で一泊300円と激安のB-timesが目についた。
調べてみるとコインパーキングのTimesが最近力を入れている時間貸しではなく、日貸の駐車場。成田の場合、場所は系列のタイムスレンタカーの敷地の中。要はレンタカーを置いてあるパーキングスペースの有効利用ということだ。
当然利用者は空港利用者がほとんどだと思うが、空港までの送り迎えはレンタカーの送迎バスがあるので、これを利用すれば新たな投資は必要なし。在り物利用のサービスとしては良くできた仕組みだ。
もちろん、利用者にとっても同じサービスであれば安いのが一番。タイムスクラブのメンバー限定のサービスだが、たまたま自分は会員になっていたので、使う側も何も面倒な手続きいらずであった。実際に使ってみたが、利用できる台数も多くないので、個人サービスに近く、待ち時間もなく便利に使わせてもらった。次回もここを使うだろう
グアムでのゴルフは、スターツゴルフリゾートとマンギラオゴルフクラブ、どちらも日本の会社がオーナーでお客も大部分が日本人。グアムは今がトップシーズン、プレー料金もしっかりリゾート料金であった。特にマンギラオは全日$250、円安の昨今3万円に近い。今回の幹事役が色々伝手を探したが、ディスカウントは一切無いらしい。国内ではプレー代は安くなる一方だが、やはり価格は需給関係で決まるのだろう。
何を買っても、高く割に中身が期待外れだとがっかりするものだが、今回のコースは価格相応に満足。天気が良かったのも幸いだった。リゾートコースにしてはどちらも手入れが良く、特にグリーンが良い状態だった。マンギラオは、米国ゴルフダイジェスト誌の世界の100コースに選ばれているというだけあって、有名な海越えの12番ショート以外も全体のレイアウトが変化に富んでいて楽しめるコースだ。池が絡むホールが多いアウトと、崖を下って海沿いのインの対比も素晴らしい。


初めて廻るコースはどこに行ってもプレー以前に、OBはどこかとか、池やバンカーの在りかが気になる。更に、ここのようにリゾートコースで綺麗な景色が楽しめ、おまけに風が強いとなると、気になる事が多く、肝心のスコアはどうしても二の次になる。もう一度プレーに集中してチャレンジしてみたいコースだ。
暖かい南国でゴルフをすると、寒い日本ではしばらくゴルフはお休みかと思っていたが、ここ2,3日の暖かさにつられて昨日はホームコースへ。研修生がキャディーにつき、組み合わせで2サムだったので、こちらは見慣れた景色に見とれることもなく、プレーに集中できた。
前半はダボなしの41。後半もその調子と思ったら、出だしのロングホールで林に打ち込み大トラブル。最終のロングホールも同じミス。どちらも大叩きの9。他はなんとかまとめてまずまず90を切るスコア。
昨年末からパットの不調が続いていたが、グリップを変えたせいとばかり思っていた。先日忘れていたポイントを一つ思い出したらパットがしっくりきたのが大きい。周りの状況を気にしないだけでなく、体の動きも無意識に自然体で打てるとスイング全体がしっくりくるのだが、ゴルフというのはどうもその域に達するのは難しいようだ。プロが毎日のように練習しても体に覚え込ますのは大変なようだが、素人は身に付いたつもりでも一晩寝るとすぐに忘れてしまう。