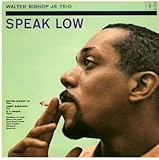Dizzy Gillespie Live At The Village Vanguard
ペッパーアダムスが久しぶりにドナルドバードとレコーディングを行ったのは1967年9月29日と10月5日の2回に分けて行われたが、その間の10月1日、日曜日の午後にビレッジバンガードでジャムセッションが行われた。そのジャムセッションを企画したのはソリッドステートレーベルの創設者のソニーレスターであった。
ジャズの世界でジャムセッションは50年代までは良く行われ、レギュラーの仕事が終わった後、早朝まで行われていたという。仲間同士の鍛錬の場であり、新人達にとっては修行の場でもあった。しかし、この録音が行われた1960年代の後半になると、ジャムセッションは下火となっていたという。
その一つの理由が、ミュージシャンユニオンの力が強くなり、”No Money, No Play”が組合の方針として掲げられ、無報酬での演奏が難しくなったからといわれている。これで、ファンにとっては、聴きたくてもステージ上でのジャムセッションを目にする(耳にできる)機会が少なくなったという訳だ。ミュージシャン達にとっても、ジャムセッションは決してお金のためだけではない楽しみと意義があったはずだが、その機会が減るという事は、自分の演奏を成長させる機会が減るという事になっていた。
そんな時代に、珍しくベテランから新人まで、普段一緒に演奏する機会が少ないメンバーが一同に集まっが、ソニーレスターが立ち上げたソリッドステートレーベルでアルバムを作ったミュージシャン達が中心だった。
ドラムのメルルイス、ベースのリチャードデイビス、ペッパーアダムス、ガーネットブラウンなど、サドメルのメンバーも多く参加した。
そして、若手代表でチックコリア、大事なセッションリーダーはディジーガレスピー御大が務めた。エリントンオーケストラで有名なレイナンスもバイオリンで加わった。
メンバーを見ただけで楽しそうなジャムセッションになりそうな気がする。
この模様を録音して、ソリッドステートからJazz For A Sunday Afternoon Vo.1 と Vol.2というタイトルでリリースされた。そのための、公開ライブのようなジャムセッションだったという訳である。


1968年8月8日のダウンビートでこのアルバムが紹介され、評点は5星半。もちろん、5星が満点なので、この五つ星半は初めてのことであった。それだけ、レビュアーの評価が高かったということになる。
丁度この頃は自分のジャズ喫茶通いが始まった頃。このアルバムを初めて聴いた時は、サドメルのメンバーはいるし、アルバムのデザインも聴いた雰囲気もすっかり気に入って、このシリーズは愛聴盤になった。
このセッションは、レスターは当初からシリーズ化を目論んでいたようだが、結局レーベル自体が長続きせず、Vol.4で終わってしまったのが残念だ。
Vol1.と2,の好評に応えて、当日の残りの未収録曲をDizzy Gillespie At The Village Vanguardというアルバムで続けてリリースした。ところが、ディジーズブルース以外は、すでにVol.1.2.に収められていた曲であったという、期待外れのアルバムであった。
日本盤のジャケットはこんな感じであった、

これは、その演奏。
結局、当日録音されていたのは、既にリリースされていた2枚のアルバムの6曲に、別テイクも無く、あと一曲だけだったという事が実態であったというのも、今になってディスコグラフィーを確認すると明らかだ。
このソリッドステートレーベルは、早々にブルーノート(リバティー)に売却されていたが、CD時代になって、マイケルカスクーナがこの録音の再発を手掛けた。
今回は、全7曲を当日のステージでの演奏順に並べ替えて。ライブ物はやはりその順序がいいと思う。そして、3曲はLPではソロやアンサンブルがカットされていた部分があったが、これを元の演奏のまま収め完全な形でのリリースとなった。
すると、必然的に最初の2曲だけがエルビンが参加し、後はメルルイスに替わったことも、一部ではレイナンスが参加していて、2部はガーネットブラウンという事も明確になる。
そして、ガレスピーのアルバムで最後に出された曲は、曲名自体も間違いであったというお粗末な結果も修正された完全盤となった。
そして再発に際しては、タイトルは当初のJazz for A Sunday Afternoonではなく、Dizzy Gillespie At The Village Vanguard featuring Chick Corea & Elvin Jonesとなった。一般受けするにはこのタイトルの方が良いと思ったのだろう。
ディジーガレスピーのアルバムは、ガレスピーの基本的に誘れれば断らないという性格なのか、超大作からつまらないアルバムまで千差万別ある。編成もコンボからビッグバンドまで幅広く、当たり外れが多いが、このアルバムは何といっても、ダウンビートで前代未聞の5星半を得たアルバム。ガレスピーも演奏だけでなく、このジャムセッションの雰囲気を味わえる好アルバムだ。特に、このCDでのカスクーナによる再発アルバムは、Jazz for A Sunday AfernoonのVol.1,Vol.2のオリジナルLPでカットされた部分を含む完全盤だ。
内容を正しく表せば、「Sunday Afternoon Jam Session At The Village Vanguard, Session Leaded by Dizzy Gillespie」ということになる。
そして、このセッションを成功させたのは、実はガレスピーに加えてペッパーアダムスの存在のような気がする。
ヘッドアレンジ風のイントロからテーマ設定、そして他のソロのオブリガード、さらに自らの豪快のソローパートすべてに登場する。気配り上手のアダムスが、マイペースのガレスピーを実に上手く補佐している。
この頃のアダムスは、ライブ活動はサドメルとデュークピアソンのビッグバンドが中心。そして、レコーディングは直前、直後のドナルドバードとのセッションを除けば、ソロはあってもバックのアンサンブルが多かった。
アダムスにとっても、久しぶりのジャムセッションの場であったのかもしれない。
アダムスのライブの生き生きとしたプレーを聴けるのも、このアルバムが魅力を増している。
1, Birks’ Works 17:57
2. Lullaby Of The Leaves 13:30
3. Lover Come Back To Me 19:15
4, Blues For Max 9:10
5. Tour De Force 11:51
6. On The trail 16:43
7. Sweet Georgia Brown 16;19
Dizzy Gillespie (tp)
Pepper Adams (bs)
Garnet Brown (tb)
Ray Nance (Violin)
Chick Corea (p)
Richard Davis (b)
Elvin Jones (ds) #1,2
Mel Lewis (ds) other Tracks
Recorded live at The Village Vanguard, New York
Prpduced by Sonny Lester
ペッパーアダムスが久しぶりにドナルドバードとレコーディングを行ったのは1967年9月29日と10月5日の2回に分けて行われたが、その間の10月1日、日曜日の午後にビレッジバンガードでジャムセッションが行われた。そのジャムセッションを企画したのはソリッドステートレーベルの創設者のソニーレスターであった。
ジャズの世界でジャムセッションは50年代までは良く行われ、レギュラーの仕事が終わった後、早朝まで行われていたという。仲間同士の鍛錬の場であり、新人達にとっては修行の場でもあった。しかし、この録音が行われた1960年代の後半になると、ジャムセッションは下火となっていたという。
その一つの理由が、ミュージシャンユニオンの力が強くなり、”No Money, No Play”が組合の方針として掲げられ、無報酬での演奏が難しくなったからといわれている。これで、ファンにとっては、聴きたくてもステージ上でのジャムセッションを目にする(耳にできる)機会が少なくなったという訳だ。ミュージシャン達にとっても、ジャムセッションは決してお金のためだけではない楽しみと意義があったはずだが、その機会が減るという事は、自分の演奏を成長させる機会が減るという事になっていた。
そんな時代に、珍しくベテランから新人まで、普段一緒に演奏する機会が少ないメンバーが一同に集まっが、ソニーレスターが立ち上げたソリッドステートレーベルでアルバムを作ったミュージシャン達が中心だった。
ドラムのメルルイス、ベースのリチャードデイビス、ペッパーアダムス、ガーネットブラウンなど、サドメルのメンバーも多く参加した。
そして、若手代表でチックコリア、大事なセッションリーダーはディジーガレスピー御大が務めた。エリントンオーケストラで有名なレイナンスもバイオリンで加わった。
メンバーを見ただけで楽しそうなジャムセッションになりそうな気がする。
この模様を録音して、ソリッドステートからJazz For A Sunday Afternoon Vo.1 と Vol.2というタイトルでリリースされた。そのための、公開ライブのようなジャムセッションだったという訳である。


1968年8月8日のダウンビートでこのアルバムが紹介され、評点は5星半。もちろん、5星が満点なので、この五つ星半は初めてのことであった。それだけ、レビュアーの評価が高かったということになる。
丁度この頃は自分のジャズ喫茶通いが始まった頃。このアルバムを初めて聴いた時は、サドメルのメンバーはいるし、アルバムのデザインも聴いた雰囲気もすっかり気に入って、このシリーズは愛聴盤になった。
このセッションは、レスターは当初からシリーズ化を目論んでいたようだが、結局レーベル自体が長続きせず、Vol.4で終わってしまったのが残念だ。
Vol1.と2,の好評に応えて、当日の残りの未収録曲をDizzy Gillespie At The Village Vanguardというアルバムで続けてリリースした。ところが、ディジーズブルース以外は、すでにVol.1.2.に収められていた曲であったという、期待外れのアルバムであった。
日本盤のジャケットはこんな感じであった、

これは、その演奏。
結局、当日録音されていたのは、既にリリースされていた2枚のアルバムの6曲に、別テイクも無く、あと一曲だけだったという事が実態であったというのも、今になってディスコグラフィーを確認すると明らかだ。
このソリッドステートレーベルは、早々にブルーノート(リバティー)に売却されていたが、CD時代になって、マイケルカスクーナがこの録音の再発を手掛けた。
今回は、全7曲を当日のステージでの演奏順に並べ替えて。ライブ物はやはりその順序がいいと思う。そして、3曲はLPではソロやアンサンブルがカットされていた部分があったが、これを元の演奏のまま収め完全な形でのリリースとなった。
すると、必然的に最初の2曲だけがエルビンが参加し、後はメルルイスに替わったことも、一部ではレイナンスが参加していて、2部はガーネットブラウンという事も明確になる。
そして、ガレスピーのアルバムで最後に出された曲は、曲名自体も間違いであったというお粗末な結果も修正された完全盤となった。
そして再発に際しては、タイトルは当初のJazz for A Sunday Afternoonではなく、Dizzy Gillespie At The Village Vanguard featuring Chick Corea & Elvin Jonesとなった。一般受けするにはこのタイトルの方が良いと思ったのだろう。
ディジーガレスピーのアルバムは、ガレスピーの基本的に誘れれば断らないという性格なのか、超大作からつまらないアルバムまで千差万別ある。編成もコンボからビッグバンドまで幅広く、当たり外れが多いが、このアルバムは何といっても、ダウンビートで前代未聞の5星半を得たアルバム。ガレスピーも演奏だけでなく、このジャムセッションの雰囲気を味わえる好アルバムだ。特に、このCDでのカスクーナによる再発アルバムは、Jazz for A Sunday AfernoonのVol.1,Vol.2のオリジナルLPでカットされた部分を含む完全盤だ。
内容を正しく表せば、「Sunday Afternoon Jam Session At The Village Vanguard, Session Leaded by Dizzy Gillespie」ということになる。
そして、このセッションを成功させたのは、実はガレスピーに加えてペッパーアダムスの存在のような気がする。
ヘッドアレンジ風のイントロからテーマ設定、そして他のソロのオブリガード、さらに自らの豪快のソローパートすべてに登場する。気配り上手のアダムスが、マイペースのガレスピーを実に上手く補佐している。
この頃のアダムスは、ライブ活動はサドメルとデュークピアソンのビッグバンドが中心。そして、レコーディングは直前、直後のドナルドバードとのセッションを除けば、ソロはあってもバックのアンサンブルが多かった。
アダムスにとっても、久しぶりのジャムセッションの場であったのかもしれない。
アダムスのライブの生き生きとしたプレーを聴けるのも、このアルバムが魅力を増している。
1, Birks’ Works 17:57
2. Lullaby Of The Leaves 13:30
3. Lover Come Back To Me 19:15
4, Blues For Max 9:10
5. Tour De Force 11:51
6. On The trail 16:43
7. Sweet Georgia Brown 16;19
Dizzy Gillespie (tp)
Pepper Adams (bs)
Garnet Brown (tb)
Ray Nance (Violin)
Chick Corea (p)
Richard Davis (b)
Elvin Jones (ds) #1,2
Mel Lewis (ds) other Tracks
Recorded live at The Village Vanguard, New York
Prpduced by Sonny Lester
 | Live at the Village Vanguard |
| Dizzy Gillepie | |
| Emd/Blue Note |