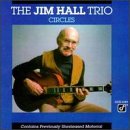Songs For Any Taste / Mel Torme
連休に入ったが、現役を退くとあまり連休のありがた味を感じない。どこかへ出かけるのであれば、混んでいる連休を外せばいいのでこの連休も予定を何も入れなかった。
ところがゴルフのように仲間のお誘いがあるものは断るわけにもいかず、結局何回かは予定が入ってしまう。それに夜はライブが続くので結局普段よりもなかなか時間がとれない毎日になってしまいそうだ。散らかったままの部屋やアルバム整理もまたしばらく先にお預けになってしまう。
ライブの方は、まずはマイクプライスオーケストラのエリントン特集の2回目にも行ってみた。前回と違って今回は客席の方も大勢駆けつけており盛況だった。演奏の方も2回目ということもあり、よりこなれていたように感じた。聴く方もファンの方が多かったせいか、ジャズのライブには珍しく緊張感のあるライブだった。また続けてほしい。
翌日は堀恵二のメロウサックスアンサンブル。いつもの演奏に加え、堀さんのトークも好調で、段々演奏もリラックスムードに。きっちりしたアンサンブルであっても、ライブの演奏となると多少お遊びも増えてくる。とはいうものの、やはりプロのアンサンブルは決まるところは流石。
ライブの良さとなると、ボーカルのライブ物もいい。特に歌い手がステージを盛り上げる術を持ち合わせていると尚更。
ジャズボーカルの世界は昔から男性に較べてどうしても女性優勢。唯でさえ少ない男性陣でステージを楽しませてくれるというと、メルトーメは外せないだろう。自分自身でドラムも叩くせいではないかもしれないが、バックの演奏とのコラボも実に上手い。聴衆とバックと一緒にステージを作り上げて盛り立てていけるライブはいつも圧巻だ。
メルトーメは息の長い歌手生活を送ったが、初期の名アルバム、特にライブ物といえばベツレヘムのアットクレッセントが有名だ。マティーペイチのピアノをバックに軽快に歌っている。よくよくメンバーを見るとドラムはメルルイス。ケントンオーケストラを離れて、ペッパーアダムス達と一緒に地元で活動を本格的に活動し始めた頃の57年2月の演奏だ。この年のメルルイスの活動は半端ではない。
この時の録音で、「アットクレッセント」のアルバムに収まりきれなかった残りの曲を集めたのがこのアルバム。残り物や別テイクといわれるものに中には「わざわざという気がしないでもない」という物が多いが、ライブの残りというのもはできが良くても悪くても「あるステージの再現」という点では意味があると思う。
このアルバムも決して残り物というものではなく、それぞれステージの雰囲気を含めていい曲ばかりだ。あえて纏まりが無いという意味では、タイトルの付け方も言いえて妙かも。最初のイッツオールライトウィズミーでは曲の途中で「ジェリコの戦い」のフレーズが入ったり、枯葉はフランス語で歌ったり、セカンドしてステージならではのパフォーマンスが楽しめる。バックもアコーディオン(弾いているのはラリーバンカー)があったりして楽しめる。
一曲だけ、パットモランのボーカルグループがバックの曲が入っている(#5)が、これは残りでアルバムを作るための埋め合わせのようで、特にアルバム全体への意味は無いように思うが。ライブ物はCDで再発される時はステージを再現してくれるような収め方が自分にはすっきりするのだだ、ジャズの場合はオリジナルのアルバムへの拘りもあるので難しい問題だ。
1. It's All Right With Me Porter 4:28
2. Manhattan Hart, Rodgers 3:14
3. Taking a Chance on Love Duke, Fetter, Latouche 2:28
4. Home by the Sea Fetter, Lewing 1:24
5. I Got Plenty O' Nuttin' Gershwin, Gershwin, Heyward 3:24
6. De-Lovely Porter 2:42
7, Tenderly Gross, Gruss Vom Schweizerland … 2:31
8. I Wish I Were in Love Again Hart, Rodgers 2:18
9. Autumn Leaves Kosma, Mercer, Prevert 1:32
10. Nobody's Heart Hart, Rodgers 2:21
Don Fagerquist (tp)
Larry Bunker (vib, accor, vib, cga, bgo)
Marty Paich (p)
Max Bennett (b)
Mel Lewis (d)
Mel Torme (vo)
Recorded live at "Crescendo Club", Los Angeles, CA, February 22, 1957
Only #5
Howard McGhee (tp)
Ralph Sharon (p)
Max Bennett (b)
Stan Levey (d)
Mel Torme (vo)
Pat Moran And Her Quartet (chorus)
Recorded Los Angeles, CA, 1957
連休に入ったが、現役を退くとあまり連休のありがた味を感じない。どこかへ出かけるのであれば、混んでいる連休を外せばいいのでこの連休も予定を何も入れなかった。
ところがゴルフのように仲間のお誘いがあるものは断るわけにもいかず、結局何回かは予定が入ってしまう。それに夜はライブが続くので結局普段よりもなかなか時間がとれない毎日になってしまいそうだ。散らかったままの部屋やアルバム整理もまたしばらく先にお預けになってしまう。
ライブの方は、まずはマイクプライスオーケストラのエリントン特集の2回目にも行ってみた。前回と違って今回は客席の方も大勢駆けつけており盛況だった。演奏の方も2回目ということもあり、よりこなれていたように感じた。聴く方もファンの方が多かったせいか、ジャズのライブには珍しく緊張感のあるライブだった。また続けてほしい。
翌日は堀恵二のメロウサックスアンサンブル。いつもの演奏に加え、堀さんのトークも好調で、段々演奏もリラックスムードに。きっちりしたアンサンブルであっても、ライブの演奏となると多少お遊びも増えてくる。とはいうものの、やはりプロのアンサンブルは決まるところは流石。
ライブの良さとなると、ボーカルのライブ物もいい。特に歌い手がステージを盛り上げる術を持ち合わせていると尚更。
ジャズボーカルの世界は昔から男性に較べてどうしても女性優勢。唯でさえ少ない男性陣でステージを楽しませてくれるというと、メルトーメは外せないだろう。自分自身でドラムも叩くせいではないかもしれないが、バックの演奏とのコラボも実に上手い。聴衆とバックと一緒にステージを作り上げて盛り立てていけるライブはいつも圧巻だ。
メルトーメは息の長い歌手生活を送ったが、初期の名アルバム、特にライブ物といえばベツレヘムのアットクレッセントが有名だ。マティーペイチのピアノをバックに軽快に歌っている。よくよくメンバーを見るとドラムはメルルイス。ケントンオーケストラを離れて、ペッパーアダムス達と一緒に地元で活動を本格的に活動し始めた頃の57年2月の演奏だ。この年のメルルイスの活動は半端ではない。
この時の録音で、「アットクレッセント」のアルバムに収まりきれなかった残りの曲を集めたのがこのアルバム。残り物や別テイクといわれるものに中には「わざわざという気がしないでもない」という物が多いが、ライブの残りというのもはできが良くても悪くても「あるステージの再現」という点では意味があると思う。
このアルバムも決して残り物というものではなく、それぞれステージの雰囲気を含めていい曲ばかりだ。あえて纏まりが無いという意味では、タイトルの付け方も言いえて妙かも。最初のイッツオールライトウィズミーでは曲の途中で「ジェリコの戦い」のフレーズが入ったり、枯葉はフランス語で歌ったり、セカンドしてステージならではのパフォーマンスが楽しめる。バックもアコーディオン(弾いているのはラリーバンカー)があったりして楽しめる。
一曲だけ、パットモランのボーカルグループがバックの曲が入っている(#5)が、これは残りでアルバムを作るための埋め合わせのようで、特にアルバム全体への意味は無いように思うが。ライブ物はCDで再発される時はステージを再現してくれるような収め方が自分にはすっきりするのだだ、ジャズの場合はオリジナルのアルバムへの拘りもあるので難しい問題だ。
1. It's All Right With Me Porter 4:28
2. Manhattan Hart, Rodgers 3:14
3. Taking a Chance on Love Duke, Fetter, Latouche 2:28
4. Home by the Sea Fetter, Lewing 1:24
5. I Got Plenty O' Nuttin' Gershwin, Gershwin, Heyward 3:24
6. De-Lovely Porter 2:42
7, Tenderly Gross, Gruss Vom Schweizerland … 2:31
8. I Wish I Were in Love Again Hart, Rodgers 2:18
9. Autumn Leaves Kosma, Mercer, Prevert 1:32
10. Nobody's Heart Hart, Rodgers 2:21
Don Fagerquist (tp)
Larry Bunker (vib, accor, vib, cga, bgo)
Marty Paich (p)
Max Bennett (b)
Mel Lewis (d)
Mel Torme (vo)
Recorded live at "Crescendo Club", Los Angeles, CA, February 22, 1957
Only #5
Howard McGhee (tp)
Ralph Sharon (p)
Max Bennett (b)
Stan Levey (d)
Mel Torme (vo)
Pat Moran And Her Quartet (chorus)
Recorded Los Angeles, CA, 1957
 | Songs for Any Taste |
| Mel Torme/td> | |
| Rhino / Wea |