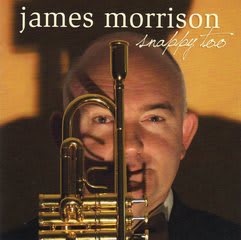Chambers‘Music / A Jazz Delegation From The East
ペッパーアダムスが続くが話の流れでついでにもう一枚。
カーチスフラーが復活宣言ともいえるアルバムにアダムスを招いたのはそれなりの付き合いがあったからだと思う。フラーとアダムスはニューヨークに出る前、デトロイトで一緒にプレーをした仲間同士。地元のクラブでは”Bones & Bari” とも言われるコンビで売り出していた旧知の仲であった。
アダムスの加わった初アルバムとしては、その仲間達と一緒の“Jazz Men Detroit”が有名だが、そのアルバムにはフラーは加わっていない。アダムスはそのアルバム以前にもいくつかのセッションに参加しているので、正式な初レコーディングとなるともう少し遡ることができる。ところが世に出ていないものであったり、サンプラーのための録音であったりでアルバム単位ではないのでなかなか聴く事はできないが、実はその中にフラーと一緒にプレーしたものがある。
1956年1月にアダムスはデトロイトからニューヨークへ出てくる、26歳の時であった。
ユニオンカードの移管手続中は仕事もできず、保険会社の事務をしながら出番を待っていた。オスカーペティフォードに連れられてケニークラークと出演していたカフェーボヘミアに出掛けたり、ジャムセッションに出たりしてニューヨーク生活には慣れていったようだが、そのような中で先述の4月30日のJazz Men Detroitの録音に誘われた。アダムスにとってはこれがニューヨークでの初レコーディングであったが、5月にはケントンオーケストラに加わったのですぐにニューヨークを離れることになるので、短いニューヨーク生活の思い出となったアルバムだ。
そのような中、この録音の直前4月20日にアダムスはフラーと共にボストンに出掛けている。広いアメリカ故ニューヨークとボストンは近そうでも400キロ近く離れている。4時間近くのドライブだ。わざわざボストンに行ったのは当然訳がある。
そこで待ち受けていたのは、丁度ボストンのジャズクラブ「ストリーヴィル」に出演していたマイルデイビスクインテットのメンバー達。中にはデトロイト時代の盟友ポールチェンバースもいた。コルトレーンも加わったマイルスのクインテットが編成された直後のツアーの途中であった。
わざわざボストンに出掛けたのはもうひとつそもそもの理由あった。
その当時はジャズのマイナーレーベルが雨後の筍のようにたくさんできたが、その一つTransitionというレーベルが55年にボストンで立ち上がっていた。このレーベルはこのフラーとアダムスのコンビに注目していたようで、それまでにも録音が企画されたり一部行われたりしたが、アルバム単位には完成していなかった。今回のセッションはこのTransitionにとっても今度こそといった録音機会であったようだ。
よくある話だが、有名グループのツアーの途中にリーダー除きで録音するというのは忙しいメンバーをブッキングするには好都合だ。マイルスグループがストリーヴィルに出演していたのは16日から30日まで、Transitionレーベルの地元ボストンというのも好都合であったのだろう。20日にマイルス除きのマイルスクインテットにフラーとアダムスが客演することで段取りが行われた。
ところがここでハップニング。アダムスが参加するレコーディングセッションでは何故かよく起こるが、当日ピアノのレッドガーランドがスタジオに現れない。時間も無かったのであろう、2曲はピアノレスで録音が進んだ。
このセッションが行われるのを聴きつけてスタジオに見学者がいた。地元バークレーでテナーサックスを学んでいたローランドアレキサンダーであった。事情を察してか、飛び入りでピアノを弾くことに。一曲のみであったがTrain’s Strainに参加している。
このアレキサンダーは後にはニューヨークに出てテナー奏者として活躍したようで、ハワードマギーのDusty Blueにも加わっていたが、ピアノでレコーディングに参加したのは後にも先にもこれだけであろう。
というわけで、今回も3曲だけの不完全な収録に終わり、”Bones& Bari”のアルバムは実現することなく構想倒れになった。ここでの演奏はTrane's Strainだけがサンプラーとして世に出て、Transition自体も短命に終わったため、残りの2曲は70年代になるまでお蔵入りしていたという曰くつきの演奏だ。という事情なので演奏自体は顔合わせジャムセッションに近い形なので可もなく不可もなく、記録としての価値以上の物は無い。
この3曲が、ポールチェンバースの初リーダーアルバムである、”Chamber’s Music”のボーナストラックとして加わってリリースされたのがこのアルバムだ。
アダムスの話で始めてしまったので、おまけの部分の説明が長くなってしまったが、本体のアルバムは、これも新興レーベルであるJazz Westに吹き込まれたチェンバースの初リーダーアルバム。当時の新興レーベルを含めて初物買の新人争奪戦が激しかった様子が窺われる。
メンバーはマイルスのグループに一緒に加わったコルトレーンとフィーリージョージョーンズに、ピアノがケニードリューというワンホーンでの演奏。チェンバースの特徴である図太いベースに加え、得意のアルコ奏法、オリジナル曲の提供と、初アルバムに必要なプレゼンテーションは無難に収められている。こちらの方が、その後のチェンバースの活躍を保証するできだが、なんといっても発展途上のコルトレーンの参加が価値を高めている気がする。
自分はオリジナル盤崇拝主義ではないので、形はどうあれ埋もれた演奏が世に出てくるのは大歓迎だ。特にこのような「規格品以外」の録音は丹念に発掘作業をしているプロデユーサーでないと見落としがちだ。このアルバムのようなカップリングは大歓迎。いずれにしても、マイルス、コルトレーンという両巨頭はこの当時からジャズ界全体の流れに枝葉の部分まで影響力を与えていたのが良く分かる。
1. Dexterity C.Parker 6:45
2. Stablemates B.Golson 5:53
3. Easy To Love C.Porter 3:52
4. Visitations P.Chambers 4:54
5. John Paul Jones D.Shaprio & D.Chanig 6:54
6. Eastbound K.Drew 4:21
John Coltrane (ts-1,2,5/7)
Kenny Drew (p)
Paul Chambers (b)
Philly Joe Jones (ds)
Recorded at United Western Recorders, Hollywood, CA, March 1 or 2, 1956
7. Trane's Strain
8, High Step
9. Nixon, Dixon And Yates Blues
Curtis Fuller (tb)
John Coltrane (ts)
Pepper Adams (bs)
Roland Alexander (p -7)
Paul Chambers (b)
Philly Joe Jones (ds)
Recorded in Boston, MA, April 20, 1956
Produced by Tom Wilson
ペッパーアダムスが続くが話の流れでついでにもう一枚。
カーチスフラーが復活宣言ともいえるアルバムにアダムスを招いたのはそれなりの付き合いがあったからだと思う。フラーとアダムスはニューヨークに出る前、デトロイトで一緒にプレーをした仲間同士。地元のクラブでは”Bones & Bari” とも言われるコンビで売り出していた旧知の仲であった。
アダムスの加わった初アルバムとしては、その仲間達と一緒の“Jazz Men Detroit”が有名だが、そのアルバムにはフラーは加わっていない。アダムスはそのアルバム以前にもいくつかのセッションに参加しているので、正式な初レコーディングとなるともう少し遡ることができる。ところが世に出ていないものであったり、サンプラーのための録音であったりでアルバム単位ではないのでなかなか聴く事はできないが、実はその中にフラーと一緒にプレーしたものがある。
1956年1月にアダムスはデトロイトからニューヨークへ出てくる、26歳の時であった。
ユニオンカードの移管手続中は仕事もできず、保険会社の事務をしながら出番を待っていた。オスカーペティフォードに連れられてケニークラークと出演していたカフェーボヘミアに出掛けたり、ジャムセッションに出たりしてニューヨーク生活には慣れていったようだが、そのような中で先述の4月30日のJazz Men Detroitの録音に誘われた。アダムスにとってはこれがニューヨークでの初レコーディングであったが、5月にはケントンオーケストラに加わったのですぐにニューヨークを離れることになるので、短いニューヨーク生活の思い出となったアルバムだ。
そのような中、この録音の直前4月20日にアダムスはフラーと共にボストンに出掛けている。広いアメリカ故ニューヨークとボストンは近そうでも400キロ近く離れている。4時間近くのドライブだ。わざわざボストンに行ったのは当然訳がある。
そこで待ち受けていたのは、丁度ボストンのジャズクラブ「ストリーヴィル」に出演していたマイルデイビスクインテットのメンバー達。中にはデトロイト時代の盟友ポールチェンバースもいた。コルトレーンも加わったマイルスのクインテットが編成された直後のツアーの途中であった。
わざわざボストンに出掛けたのはもうひとつそもそもの理由あった。
その当時はジャズのマイナーレーベルが雨後の筍のようにたくさんできたが、その一つTransitionというレーベルが55年にボストンで立ち上がっていた。このレーベルはこのフラーとアダムスのコンビに注目していたようで、それまでにも録音が企画されたり一部行われたりしたが、アルバム単位には完成していなかった。今回のセッションはこのTransitionにとっても今度こそといった録音機会であったようだ。
よくある話だが、有名グループのツアーの途中にリーダー除きで録音するというのは忙しいメンバーをブッキングするには好都合だ。マイルスグループがストリーヴィルに出演していたのは16日から30日まで、Transitionレーベルの地元ボストンというのも好都合であったのだろう。20日にマイルス除きのマイルスクインテットにフラーとアダムスが客演することで段取りが行われた。
ところがここでハップニング。アダムスが参加するレコーディングセッションでは何故かよく起こるが、当日ピアノのレッドガーランドがスタジオに現れない。時間も無かったのであろう、2曲はピアノレスで録音が進んだ。
このセッションが行われるのを聴きつけてスタジオに見学者がいた。地元バークレーでテナーサックスを学んでいたローランドアレキサンダーであった。事情を察してか、飛び入りでピアノを弾くことに。一曲のみであったがTrain’s Strainに参加している。
このアレキサンダーは後にはニューヨークに出てテナー奏者として活躍したようで、ハワードマギーのDusty Blueにも加わっていたが、ピアノでレコーディングに参加したのは後にも先にもこれだけであろう。
というわけで、今回も3曲だけの不完全な収録に終わり、”Bones& Bari”のアルバムは実現することなく構想倒れになった。ここでの演奏はTrane's Strainだけがサンプラーとして世に出て、Transition自体も短命に終わったため、残りの2曲は70年代になるまでお蔵入りしていたという曰くつきの演奏だ。という事情なので演奏自体は顔合わせジャムセッションに近い形なので可もなく不可もなく、記録としての価値以上の物は無い。
この3曲が、ポールチェンバースの初リーダーアルバムである、”Chamber’s Music”のボーナストラックとして加わってリリースされたのがこのアルバムだ。
アダムスの話で始めてしまったので、おまけの部分の説明が長くなってしまったが、本体のアルバムは、これも新興レーベルであるJazz Westに吹き込まれたチェンバースの初リーダーアルバム。当時の新興レーベルを含めて初物買の新人争奪戦が激しかった様子が窺われる。
メンバーはマイルスのグループに一緒に加わったコルトレーンとフィーリージョージョーンズに、ピアノがケニードリューというワンホーンでの演奏。チェンバースの特徴である図太いベースに加え、得意のアルコ奏法、オリジナル曲の提供と、初アルバムに必要なプレゼンテーションは無難に収められている。こちらの方が、その後のチェンバースの活躍を保証するできだが、なんといっても発展途上のコルトレーンの参加が価値を高めている気がする。
自分はオリジナル盤崇拝主義ではないので、形はどうあれ埋もれた演奏が世に出てくるのは大歓迎だ。特にこのような「規格品以外」の録音は丹念に発掘作業をしているプロデユーサーでないと見落としがちだ。このアルバムのようなカップリングは大歓迎。いずれにしても、マイルス、コルトレーンという両巨頭はこの当時からジャズ界全体の流れに枝葉の部分まで影響力を与えていたのが良く分かる。
1. Dexterity C.Parker 6:45
2. Stablemates B.Golson 5:53
3. Easy To Love C.Porter 3:52
4. Visitations P.Chambers 4:54
5. John Paul Jones D.Shaprio & D.Chanig 6:54
6. Eastbound K.Drew 4:21
John Coltrane (ts-1,2,5/7)
Kenny Drew (p)
Paul Chambers (b)
Philly Joe Jones (ds)
Recorded at United Western Recorders, Hollywood, CA, March 1 or 2, 1956
7. Trane's Strain
8, High Step
9. Nixon, Dixon And Yates Blues
Curtis Fuller (tb)
John Coltrane (ts)
Pepper Adams (bs)
Roland Alexander (p -7)
Paul Chambers (b)
Philly Joe Jones (ds)
Recorded in Boston, MA, April 20, 1956
Produced by Tom Wilson
 | Chambers' Music: a Jazz Delegation from the Eas |
| クリエーター情報なし | |
| Fresh Sounds Spain |