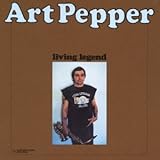Please Send Me Someone To Love / Phineas Newborn Jr.
誰でも一生の間、一度や二度は何らかの苦境に立つことがある。その時、頼りになる友がいるといないではその後の人生が大きく変る。
1968年アートペッパーが、長い療養の後、やっとバディーリッチのオーケストラに加わって復帰の第一歩を踏み出した矢先、胸の痛みで病院に担ぎ込まれた。その時、ペッパーがすぐに呼んだ名前はその後結婚するローリーと、コンテンポラリーレコードのオーナー、レスターケーニッヒであったという。
その時、直ちに手術が必要という状況であったが、保険に加入できず、手持ちのお金も無くすぐに手術を受けられなかったペッパーを救ったのはバディーリッチであった。
これで一命をとりとめたペッパーはその後無事心身ともに回復し、ケーニッヒの元で復帰アルバムを作ることになる。もしこの時に、誰か一人が欠けてもその後のペッパーの人生は大きく変ったかもしれない。
今の時代、すべてがお金優先になってしまった。物でも人でも使い物にならなくなるとすぐに捨てられる運命にある。昨今の業界事情には詳しくないが、金儲けを度外視してミュージシャンと信頼関係を築けているプロデューサーが果たして何人いるであろうか?特に、落ちぶれたミュージシャンをもう一度再起させる面倒を見続けられる人間が。ケーニッヒを始めとして、この時代のプロデューサーは、ジャズが好きで、ミュージシャンに惚れ込んでアルバム作りをしたプロデューサーが何人もいたように思う。
アートペッパーの復帰を支えたレスターケーニッヒは、もう一人大事なミュージシャンの復帰に手を貸している。自らのレーベルでもアルバムを出したピアノのフィニアスニューボーンJr.である。
ニューボーンは良く知られているように精神的な障害でプレーができなくなったという。天才肌で、テクニックも、表現力も、どれをとっても同時代のピアノの名手達と較べてもけっして引けを取らない。
他の多くのピアニストがバドパウエルの影響を受け右手中心のプレーをしたなかで、一人左手も重視するスタイルを引き継いでいた。だからといって、オールドスタイルをそのままという訳ではない。
本来であれば、ワンアンドオンリーのスタイルでもっと人気が出ても良かったはずだが、あまり脚光を浴びることはなかった。天才肌の人間というのは、どんな分野でもその時代には評価されず、後になって再評価されることが多いが、ニューボーンもそんな一人であったのだろう。
ダイナミックなプレーを聴くと、オスカーピーターソンのような堂々とした体格、そして風格を持ち合わせている印象を受けるが、実際には小柄な目立たたない風貌だったようだ。きっと性格的にも気が小さいタイプであったのだろう。そして、極端に潔癖症であったという。才能があるが故に評価されないということを、些細な事を気にして精神的に大きなプレッシャーを受けていたのかもしれない。
60年代に入って精神障害で療養を強いられる。地元に戻り半ば引退状態であったニューボーンに再びアルバム作りの場を用意したのがレスターケーニッヒであった。
1969年2月、久々にスタジオにメンバーの面々が集まった。ベースにはレイブラウン。そして、ドラムにはエルビンジョーンズ。
いつものエンジニア、ロイデュナンは都合がつかず、録音はケーニッヒ自身がやったそうだ。
特段何の打ち合わせも無く、ニューボーンのペースで録音は進んだという。大部分の曲は録り直しも無くtake1で終了、自然発生的な演奏であった。それができたのも、レイブラウンとエルビンを選んだケーニッヒの眼力と、それに応えた2人の力量のお蔭だ。2日間に渡った録音はアルバム2枚分になった。その中からとりあえずこのアルバムPlease Send Me Someone to Loveが発売され、残りの曲は後にHarlem Bluesで世に出た。
この録音の殆どがtake1で終えたという事は、あまり細かい事にはとらわれず、ニューボーンのピアノを中心に皆で思いの丈を出し合った演奏ということになる。どちらのアルバムがいいとか、どの曲がいいかは、あくまでも聴き手の主観でいいだろう。それよりこの2枚は2日間にわたるニューボーン復活のドキュメンタリーと考えるべきアルバムだと思う。何といっても、このアルバムの前後10年近くの間には他の演奏を聴く事はできないのだから。
その後もニューボーンの体調は一進一退を繰り返す。最後まで、ニューボーンを見守り、機会があるごとに演奏を再開することを促し、アドバイスしたのは、このセッションに参加したレイブラウンであった。そして5年近く経ってからのレコーディングにも付き合っている。ニューボーンが病気に苦しみながらも何度か復帰を試みられたのはレイブラウンのお蔭ということになる。
レイブラウンはピーターソンの元を離れてからは西海岸を拠点として、数多くのセッションやレコーディングに参加し、誰とでもオールマイティーな活躍をしてきた。引手数多で楽しくプレーをすることには何の不自由もなかった自分と、いつもきっかけを掴めず、せっかく掴んだきっかけをものにできずにいたニューボーンを比較すると、彼の事がいつも気に掛かっていたのだろう。
同じ天才でも2人の辿った道は大きく異なった。
1. Please Send Me Someone to Love Percy Mayfield 5:05
2. Rough Ridin' Ella Fitzgerald / Elvin Jones / William Tennyson 4:09
3. Come Sunday Duke Ellington 4:52
4. Brentwood Blues Phineas Newborn, Jr. 8:01
5. He's a Real Gone Guy Nellie Lutcher 4:39
6. Black Coffee Sonny Burke / Paul Francis Webster 7:03
7. Little Niles Randy Weston 4:20
8. Stay on It Tadd Dameron / Dizzy Gillespie 5:05
Phineas Newborn, Jr. (p)
Ray Brown (b)
Elvin Jones (ds)
Produced & Recorded by Lester Koenig
Recorded at Contemporary Studio in Los Angeles on February 12, 13 1969
誰でも一生の間、一度や二度は何らかの苦境に立つことがある。その時、頼りになる友がいるといないではその後の人生が大きく変る。
1968年アートペッパーが、長い療養の後、やっとバディーリッチのオーケストラに加わって復帰の第一歩を踏み出した矢先、胸の痛みで病院に担ぎ込まれた。その時、ペッパーがすぐに呼んだ名前はその後結婚するローリーと、コンテンポラリーレコードのオーナー、レスターケーニッヒであったという。
その時、直ちに手術が必要という状況であったが、保険に加入できず、手持ちのお金も無くすぐに手術を受けられなかったペッパーを救ったのはバディーリッチであった。
これで一命をとりとめたペッパーはその後無事心身ともに回復し、ケーニッヒの元で復帰アルバムを作ることになる。もしこの時に、誰か一人が欠けてもその後のペッパーの人生は大きく変ったかもしれない。
今の時代、すべてがお金優先になってしまった。物でも人でも使い物にならなくなるとすぐに捨てられる運命にある。昨今の業界事情には詳しくないが、金儲けを度外視してミュージシャンと信頼関係を築けているプロデューサーが果たして何人いるであろうか?特に、落ちぶれたミュージシャンをもう一度再起させる面倒を見続けられる人間が。ケーニッヒを始めとして、この時代のプロデューサーは、ジャズが好きで、ミュージシャンに惚れ込んでアルバム作りをしたプロデューサーが何人もいたように思う。
アートペッパーの復帰を支えたレスターケーニッヒは、もう一人大事なミュージシャンの復帰に手を貸している。自らのレーベルでもアルバムを出したピアノのフィニアスニューボーンJr.である。
ニューボーンは良く知られているように精神的な障害でプレーができなくなったという。天才肌で、テクニックも、表現力も、どれをとっても同時代のピアノの名手達と較べてもけっして引けを取らない。
他の多くのピアニストがバドパウエルの影響を受け右手中心のプレーをしたなかで、一人左手も重視するスタイルを引き継いでいた。だからといって、オールドスタイルをそのままという訳ではない。
本来であれば、ワンアンドオンリーのスタイルでもっと人気が出ても良かったはずだが、あまり脚光を浴びることはなかった。天才肌の人間というのは、どんな分野でもその時代には評価されず、後になって再評価されることが多いが、ニューボーンもそんな一人であったのだろう。
ダイナミックなプレーを聴くと、オスカーピーターソンのような堂々とした体格、そして風格を持ち合わせている印象を受けるが、実際には小柄な目立たたない風貌だったようだ。きっと性格的にも気が小さいタイプであったのだろう。そして、極端に潔癖症であったという。才能があるが故に評価されないということを、些細な事を気にして精神的に大きなプレッシャーを受けていたのかもしれない。
60年代に入って精神障害で療養を強いられる。地元に戻り半ば引退状態であったニューボーンに再びアルバム作りの場を用意したのがレスターケーニッヒであった。
1969年2月、久々にスタジオにメンバーの面々が集まった。ベースにはレイブラウン。そして、ドラムにはエルビンジョーンズ。
いつものエンジニア、ロイデュナンは都合がつかず、録音はケーニッヒ自身がやったそうだ。
特段何の打ち合わせも無く、ニューボーンのペースで録音は進んだという。大部分の曲は録り直しも無くtake1で終了、自然発生的な演奏であった。それができたのも、レイブラウンとエルビンを選んだケーニッヒの眼力と、それに応えた2人の力量のお蔭だ。2日間に渡った録音はアルバム2枚分になった。その中からとりあえずこのアルバムPlease Send Me Someone to Loveが発売され、残りの曲は後にHarlem Bluesで世に出た。
この録音の殆どがtake1で終えたという事は、あまり細かい事にはとらわれず、ニューボーンのピアノを中心に皆で思いの丈を出し合った演奏ということになる。どちらのアルバムがいいとか、どの曲がいいかは、あくまでも聴き手の主観でいいだろう。それよりこの2枚は2日間にわたるニューボーン復活のドキュメンタリーと考えるべきアルバムだと思う。何といっても、このアルバムの前後10年近くの間には他の演奏を聴く事はできないのだから。
その後もニューボーンの体調は一進一退を繰り返す。最後まで、ニューボーンを見守り、機会があるごとに演奏を再開することを促し、アドバイスしたのは、このセッションに参加したレイブラウンであった。そして5年近く経ってからのレコーディングにも付き合っている。ニューボーンが病気に苦しみながらも何度か復帰を試みられたのはレイブラウンのお蔭ということになる。
レイブラウンはピーターソンの元を離れてからは西海岸を拠点として、数多くのセッションやレコーディングに参加し、誰とでもオールマイティーな活躍をしてきた。引手数多で楽しくプレーをすることには何の不自由もなかった自分と、いつもきっかけを掴めず、せっかく掴んだきっかけをものにできずにいたニューボーンを比較すると、彼の事がいつも気に掛かっていたのだろう。
同じ天才でも2人の辿った道は大きく異なった。
1. Please Send Me Someone to Love Percy Mayfield 5:05
2. Rough Ridin' Ella Fitzgerald / Elvin Jones / William Tennyson 4:09
3. Come Sunday Duke Ellington 4:52
4. Brentwood Blues Phineas Newborn, Jr. 8:01
5. He's a Real Gone Guy Nellie Lutcher 4:39
6. Black Coffee Sonny Burke / Paul Francis Webster 7:03
7. Little Niles Randy Weston 4:20
8. Stay on It Tadd Dameron / Dizzy Gillespie 5:05
Phineas Newborn, Jr. (p)
Ray Brown (b)
Elvin Jones (ds)
Produced & Recorded by Lester Koenig
Recorded at Contemporary Studio in Los Angeles on February 12, 13 1969
 | Please Send Me Someone to Love |
| クリエーター情報なし | |
| Ojc |