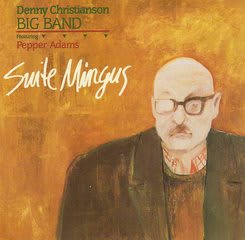Li'l Darlin' / Monty Alexsander
ドラムのデニスマクレルが加わったモンティーアレキサンダー、最近はレゲエのグループでの来日が多かったが今回はピアノトリオで。モンティーのラテンスタイルの演奏も魅力があるが、久々にピーターソンオリエンテッドなストレートアヘッドなピアノトリオを期待してライブに出掛けた。
会場でよくその日出演のミュージシャンのCDを売っているが、今回も入口に並んでいた。多くのアルバムを出しているモンティーだが、最近のアルバムを知らないのでどんなアルバムがあるのか覗いてみたら、プロモーターのオールアートプロモーションが監修したアルバムが。会場でのみ販売と書かれた「リトルダーリン」のタイトルに惹かれて手にとった。しかし、これは以前リリースされたアルバムといわれて、これは持っていたはずと思い出した。帰ってから確認したら、このアルバムがあった。ジャケットのデザインは違うがオールアートプロモーションの監修なので多分同じ内容だろう。
この日のライブは東京TUCでの2ステージ。普段のライブは2ステージ入れ替え無しだが、外タレだと入れ替えとなることが多い。ブルーノートなどは入れ替えが当たり前だが、この入れ替え前提のツーステージは曲者だ。時々ファーストとセカンドが同じ曲ということもある。今聴いたばかりの曲をもう一度聴くというのも普段なかなか経験できないが、やはりガッカリすることになる。クラシックのように事前に演目が分かっていれば嬉しいが、何か起こるか分からないのもジャズの楽しみの一つ。
この日のステージも入れ替え制であった。最初のステージが始まるが想像通りのスインギーなピアノトリオ。心地よさに思わず睡魔も訪れてしまった。ゲストというか、モンティー夫人のカテリーナ・ザッポーニもステージに上がったが、こちらも無難に。悪くは無いが、全体としてはモンティーのステージの割には平穏に終わった。
どのコンサートでも、大体セカンドステージの方が盛り上がりを見せるが、この日もセカンドステージになると一転して雰囲気が変った。今まで仲良く一緒にプレーをしていたトリオの3人がお互いに向き直した感じで、アグレッシブで雰囲気に変る。ソロの掛け合いも挑戦的で熱がこもる。アドリブの最中に色々な曲の引用が多いモンティーだが、次から次へ名曲のフレーズのオンパレードとなる。再びザッポーニも登場するが、こちらもエンジン始動。モンティーも一緒に歌い出すが、歌詞を覚えていないモンティーに彼女が耳元で歌詞を囁き、最後はスキャットでデュエットというおまけ付きもあった。久々にモンティーアレキサンダーのスインギー&ダイナミックな演奏を楽しめた。今回はセカンドステージまで残って正解であった。
さて、このアルバムに戻ると86年の日本での録音。コンコルドでお馴染みのピーターソントリオスタイルでよく演奏していた頃の録音。メンバーもコンコルド時代の仲間ジェフハミルトンのドラムにジョンクレイトンのベース。皆今では大御所だが、息の合った発展途上の実力者たちによる好演だ。
このアルバムの特徴は、エリントンとベイシーナンバーを特集していること。お馴染みのビッグバンドサウンドをピアノトリオで聴くとどうなるか?という嗜好だが、エリントンナンバーの方は、ビッグバンドだけでなく色々なスタイルで演奏されることが多い。ここでは一気に27分のメドレーで演奏している。
一曲、オリジナルのEleuthraを挟んで、ベイシーナンバーに移る。
こちらの方は、やはりベイシーサウンドがすぐに思いうかべてしまう。ということで、ベイシーナンバーのピアノトリオの演奏に興味が湧くが、分厚いサウンドでかつスインギーなベイシーサウンドには、モンティーのピアノスタイルはピッタリだ。
ラテンタッチのモンティーもいいが、このようなピーターソンスタイルのトリオ演奏も悪くない。今回のライブはこのアルバムのような演奏を久々に味わえたが、ライブならではのジャムセッション的な演奏も楽しめたのが大収穫。
1. Love You Madly Duke Ellington
2. Don't Get Around Much Anymore Duke Ellington / Bob Russell
3. Caravan Duke Ellington / Irving Mills / Juan Tizol
4. In a Mellow Tone Duke Ellington / Milt Gabler
5. Prelude to a Kiss Duke Ellington / Irving Gordon / Irving Mills
6. Come Sunday Duke Ellington
7. Rockin' in Rhythm Harry Carney / Duke Ellington / Irving Mills
8. Eleuthra Monty Alexander
9. Lil' Darlin' Neal Hefti
10. Shiny Stockings Frank Foster
11. April in Paris Vernon Duke / E.Y. "Yip" Harburg
12. Jumpin' at the Woodside Count Basie
Monty Alexander (p)
John Clayton (b)
Jeff Hamilton (ds)
Produced by Keiichiro Ebihara
Recording Engineer : Osamu Kasahara, Masayuki Makino
Recorded at Pioneeer Studio, Tokyo April 1 1986
ドラムのデニスマクレルが加わったモンティーアレキサンダー、最近はレゲエのグループでの来日が多かったが今回はピアノトリオで。モンティーのラテンスタイルの演奏も魅力があるが、久々にピーターソンオリエンテッドなストレートアヘッドなピアノトリオを期待してライブに出掛けた。
会場でよくその日出演のミュージシャンのCDを売っているが、今回も入口に並んでいた。多くのアルバムを出しているモンティーだが、最近のアルバムを知らないのでどんなアルバムがあるのか覗いてみたら、プロモーターのオールアートプロモーションが監修したアルバムが。会場でのみ販売と書かれた「リトルダーリン」のタイトルに惹かれて手にとった。しかし、これは以前リリースされたアルバムといわれて、これは持っていたはずと思い出した。帰ってから確認したら、このアルバムがあった。ジャケットのデザインは違うがオールアートプロモーションの監修なので多分同じ内容だろう。
この日のライブは東京TUCでの2ステージ。普段のライブは2ステージ入れ替え無しだが、外タレだと入れ替えとなることが多い。ブルーノートなどは入れ替えが当たり前だが、この入れ替え前提のツーステージは曲者だ。時々ファーストとセカンドが同じ曲ということもある。今聴いたばかりの曲をもう一度聴くというのも普段なかなか経験できないが、やはりガッカリすることになる。クラシックのように事前に演目が分かっていれば嬉しいが、何か起こるか分からないのもジャズの楽しみの一つ。
この日のステージも入れ替え制であった。最初のステージが始まるが想像通りのスインギーなピアノトリオ。心地よさに思わず睡魔も訪れてしまった。ゲストというか、モンティー夫人のカテリーナ・ザッポーニもステージに上がったが、こちらも無難に。悪くは無いが、全体としてはモンティーのステージの割には平穏に終わった。
どのコンサートでも、大体セカンドステージの方が盛り上がりを見せるが、この日もセカンドステージになると一転して雰囲気が変った。今まで仲良く一緒にプレーをしていたトリオの3人がお互いに向き直した感じで、アグレッシブで雰囲気に変る。ソロの掛け合いも挑戦的で熱がこもる。アドリブの最中に色々な曲の引用が多いモンティーだが、次から次へ名曲のフレーズのオンパレードとなる。再びザッポーニも登場するが、こちらもエンジン始動。モンティーも一緒に歌い出すが、歌詞を覚えていないモンティーに彼女が耳元で歌詞を囁き、最後はスキャットでデュエットというおまけ付きもあった。久々にモンティーアレキサンダーのスインギー&ダイナミックな演奏を楽しめた。今回はセカンドステージまで残って正解であった。
さて、このアルバムに戻ると86年の日本での録音。コンコルドでお馴染みのピーターソントリオスタイルでよく演奏していた頃の録音。メンバーもコンコルド時代の仲間ジェフハミルトンのドラムにジョンクレイトンのベース。皆今では大御所だが、息の合った発展途上の実力者たちによる好演だ。
このアルバムの特徴は、エリントンとベイシーナンバーを特集していること。お馴染みのビッグバンドサウンドをピアノトリオで聴くとどうなるか?という嗜好だが、エリントンナンバーの方は、ビッグバンドだけでなく色々なスタイルで演奏されることが多い。ここでは一気に27分のメドレーで演奏している。
一曲、オリジナルのEleuthraを挟んで、ベイシーナンバーに移る。
こちらの方は、やはりベイシーサウンドがすぐに思いうかべてしまう。ということで、ベイシーナンバーのピアノトリオの演奏に興味が湧くが、分厚いサウンドでかつスインギーなベイシーサウンドには、モンティーのピアノスタイルはピッタリだ。
ラテンタッチのモンティーもいいが、このようなピーターソンスタイルのトリオ演奏も悪くない。今回のライブはこのアルバムのような演奏を久々に味わえたが、ライブならではのジャムセッション的な演奏も楽しめたのが大収穫。
1. Love You Madly Duke Ellington
2. Don't Get Around Much Anymore Duke Ellington / Bob Russell
3. Caravan Duke Ellington / Irving Mills / Juan Tizol
4. In a Mellow Tone Duke Ellington / Milt Gabler
5. Prelude to a Kiss Duke Ellington / Irving Gordon / Irving Mills
6. Come Sunday Duke Ellington
7. Rockin' in Rhythm Harry Carney / Duke Ellington / Irving Mills
8. Eleuthra Monty Alexander
9. Lil' Darlin' Neal Hefti
10. Shiny Stockings Frank Foster
11. April in Paris Vernon Duke / E.Y. "Yip" Harburg
12. Jumpin' at the Woodside Count Basie
Monty Alexander (p)
John Clayton (b)
Jeff Hamilton (ds)
Produced by Keiichiro Ebihara
Recording Engineer : Osamu Kasahara, Masayuki Makino
Recorded at Pioneeer Studio, Tokyo April 1 1986
 | リル・ダーリン |
| クリエーター情報なし | |
| アブソードミュージックジャパン |